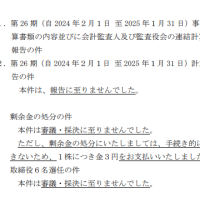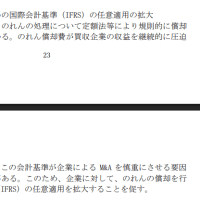インボイス導入の大混乱を招いた「三悪人」は、官僚と国会議員とマスメディアだ
インボイス制度導入をめぐる混乱の原因は何かを論じたコラム的な記事(メルマガの転載)。
「制度が変わる時は、いつもそうなのですが、国会に制度改定が提案されて論戦が行われる際には、国民に対して詳細は説明されません。その代わりに、実際に法案が可決して制度が実施される時になって大騒ぎになるのです。
例えばですが、監督官庁は広告代理店に多額の税金を払って「ご存知ですか?」というキャンペーンをやったりします。また、同時にマスコミもこの時点になって「混乱だ」とか「困る人が出る」などと騒ぐのです。
ここ20年、いや40年ぐらい同じことの繰り返しと言っても良いと思います。消費税の導入、後期高齢者保険、子育て制度、そして軽減税率に今回のインボイス、いつもそうです。法律を審議している時は、世論を刺激するような報道は伏せられて、法案が可決成立し実施段階になって「ご存知ですか?」キャンペーンを行う、こればっかりです。
主権者をナメているというのもそうですが、これでは民主主義の利点である決定への全員参加による合意形成ということが成り立っていないと思います。」
概ね、この観察の通りだと思います。
特に税制の場合は、与党の税制調査会の段階で、ほぼ決まってしまいます。それは、密室の中で決定されており、そもそも、政党の政策案にすぎないので、国民に見える形で議論されることはありません。形式的には、その後、国民が選挙で選んだ政権が承認した法律案が国会に提出され、国会では国民の代表である国会議員がそれを議論する、議論の内容はマスコミが報じて、国民も何が問題なのかを理解するということになっているのでしょう。しかし、税制改正は、毎年、予算といっしょに、急いで審議され、国民(特にその改正で影響を受ける人たち)が詳細まで理解する時間はありません。
法律改正から何年もたっているのに、今さら反対だといって騒ぐのはおかしいという見方も、特に専門家の間ではあるようですが、影響を受ける人たちにあえて知らせないようにしていたのですから、しかたがないでしょう。
記事で挙げている三悪人の筆頭は...
「1番目は中央官庁の官僚です。彼らは独自の正義感と優越感から、自分たちが立案した新しい制度は「国のためになる」と信じて疑っていません。ですから、野党議員がいちいち自分たちの提案した法律案にイチャモンを付けたりするのは面倒であり、サッサと法案を通して欲しいと思っているのです。
さらに言えば、中央官庁の官僚は制度を管理するのが仕事であり、実際に制度変更が実施される場合に困る現場、つまり各自治体や官庁の窓口の人々がどう困るのかなどには、そんなに関心はないと思います。
また今回のインボイス問題について言えば、財務省としてはそもそも「軽減税率」などやりたくなかったはずです。それを公明党などがねじ込んできて、10%に統一すればいいのに8%も残って税率が複数になったわけです。
財務省としては、それで実務が面倒になるなど「知ったこっちゃない」という感覚もあるでしょうし、さらに言えば「8%に削減されて減った税収を、捕捉強化で取り戻す」ことも考えたに違いありません。」
インボイスに関しては、単なる企業間でやりとりされる書類の問題であるかのように、キャンペーンされていて、むしろ、電帳法とからめて、企業のデジタル化推進に役立つみたいなことをマスコミに書かせています。しかし、実際は、仕入税額控除の要件を厳しくする増税であり、その影響は、免税業者や免税業者と取引している先に集中的に表れるということを、なるべく隠そうとしていたようです。
官僚以外で挙げているのは、野党議員とメディアです。それもそうかなと思います。しかし、与党や内閣も、導入後の今になって、対策を立てろといっている(ポーズかもしれませんが)のですから、同罪でしょう。
記事の結論は...
「とにかく、日本というのは制度が現実に追いついておらず、様々な制度改定が必要な国です。中には規制を思い切って緩和することもあれば、財源がないが必要な施策には受益者に不利益変更をお願いすることも多々あるはずです。そのような場合に、コソコソ法案を通すのではなく、法案審議の段階で徹底的に有権者に説明し、実務的な観点から「実現可能な代案」を野党は提出して、公明正大に決定をする、その決定には世論も、つまり有権者も参加する、そのようにしなければ、社会は前へ進みません。」