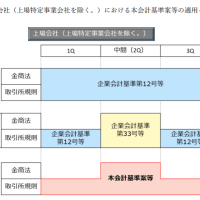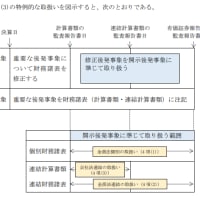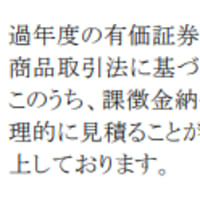5月に公表された「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」へのコメントが、企業会計基準委員会のサイトに掲載されました。22件のコメントが寄せられています。
コメントを論点別にまとめた資料が、いずれ公表されると思われますので、ここでは、明確な対立点となっている、利益剰余金か損益か(資本直入されるものについては、その他包括利益累計額かその他包括利益か)という変更時の差額の会計処理についてのコメントを見てみます(個人や実質的に個人と思われるコメントは除く)。なお、公開草案は、PLやその他の包括利益を通さずに利益剰余金等に直接加減という処理です。
<同意する意見>
日本公認会計士協会
・同意する。
・繰延税金資産の見積りの方法について、本公開草案においては、第 21 項、第 24項、第 28 項及び第 29 項など、現行の実務で行われている方法と異なる方法が定められており、かつ、異なる会計処理が定められている。したがって、繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の見積りの修正には該当しない・・・
株式会社プロネクサス プロネクサス総合研究所
・同意する。
有限責任あずさ監査法人
・同意する。
PwCあらた監査法人
・同意する。
・本公開草案は、繰延税金資産の回収可能性を判断する上での会計処理の原則及び手続の変更を伴うものである。
有限責任監査法人トーマツ
・同意する。
・(分類2)におけるスケジューリング不能な一時差異の取り扱いや、(分類3)や(分類4)の反証規定などが規定されており、現行実務と異なる会計処理が規定されているため、会計上の見積りの変更ではないと考えられる。また、今回の変更は企業を取り巻く環境の変化に対応して行われるものではないため、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合にも該当しないと考えられる。そのため、当期の損益に影響させるものではなく、会計方針の変更として期首利益剰余金で処理するべきと考える。
<同意しない意見>(おおむね同意含む)
一般社団法人日本貿易会
・概ね同意
・損益に計上する方が適切との意見も聞かれた。
・これまで硬直化していた繰延税金資産の回収可能性の判断の見直しがなされたものであるため、実質的には会計方針の変更ではなく、見積りの変更に該当すると考えられる側面もある。
一般社団法人日本経済団体連合会
・同意しない。
・(1)繰延税金資産の算定は見積りをベースとしており、(2)本適用指針は 66 号の内容を全体として引き継いで明確化や改善を図ったのみであり、(3)繰延税金資産の計上後に税負担が発生した場合には損益を経由して繰延税金資産を取り崩すので、計上段階で損益を経由しない場合には、計上と取り崩しとで会計処理に明らかな不整合が生じることから、適用初年度の影響額は、「損益」として取り扱うべきであると考える。
・24 号の「会計方針の変更」と「見積りの変更」の定義からは、今回の適用指針の開発は、やむなく「会計方針の変更」に相当するものと考えられる。したがって、24 号 6 項(1)の規定にしたがって、特定の経過的な取扱い(一時の損益として取り扱う)を定めるべきと考える。
(ほかにも理由を挙げていますが省略)
一般社団法人全国銀行協会
・同意しない。
・適用による期首時点の影響額は、「会計方針の変更」として利益剰余金に加減するのではなく、「見積りの変更」として当期の損益に計上すべきである。(理由は経団連とほぼ同じ)
宝印刷株式会社 総合ディスクロージャー&IR研究所
・同意しません。
・本適用指針の適用は、新たな適用指針の適用となりますが、本適用指針の適用によっても、繰延税金資産の計上に関する基本的な考え方に変更は生じない点、及び、企業の分類の考え方は、監査委員会報告の規定において既に存在した考え方を一部拡張するものであり、今までの繰延税金資産の計上に対する考え方に若干の変更を加えるものである点を勘案し、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合(企業会計基準第24 号第19 項)に類似していると考えられるため、本適用指針の適用を会計上の見積りの変更と同様に取り扱うことが適切であると考えます。
これ以外の論点では、会社分類に「経常的な利益(損益)」でなく、「臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得」を使うことや、今後の注記事項の追加の要否などについて、コメントが多かったように思います。
当サイトの関連記事(公開草案について)
最近の「企業会計基準委員会」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事