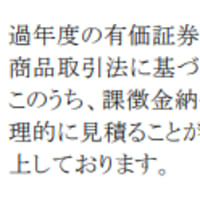租税法の中央大学商学部・酒井克彦教授へのインタビュー記事。一般向け。
まず、税制改正の進め方に問題があると言っています。
「――税制の決定プロセスにどのような問題があるのでしょうか。
いま税制改正論議は、政府税制調査会の力が弱くなり与党主導になっています。それにより、理念・大義が後回しになってしまっているように見受けられる部分があります。...
安倍首相の後押しがありますから、政治主導で歪んだ利権構造に手を付けることへの期待もありますが、一方で、政治主導により理念が後回しになることへの懸念もあります。」
「課税ベース(課税する範囲)の適正化はずっと言われていることですが、政治も絡み財界の要望を反映していくと、なかなか課税ベースの拡大を行えない。そうした背景もあって法人税法の本来の立脚ポイントが見えづらくなっていて、法人税法の屋台骨がだいぶ歪んでいるとの感触を持っています。」
そういえば、日本会計士協会は、自民党らの税制改正大綱にはコメントを出しながら、閣議決定された政府税調の大綱は無視していました。
租税特別措置については...
「――「租税特別措置法」(租特、何らかの政策目的を実現するために特定の条件を満たした個人・企業に税負担の軽減・加重を行う措置)で、企業の税負担が軽減されていると聞きます。どのようなものでしょうか。
「租税特別措置法」とは、例えば環境保全のためCO2を減らさなければいけないとの問題があったとします。そこで、産廃業者がCO2が出ない施設を作ろうとする時に、施設の減価償却を早く認めるといった税制上のメリットを与えることで、CO2削減を推進するというように、特定の政策目的のために導入する法律が租税特別措置法です。
問題なのは、作ったら作り放しでなかなか期限切れせず、既得権益化してしまうことが多々あるという現状です。たとえ時限立法(例えば2年間限定といった制度設計)としていても延長に次ぐ延長になって、枠組み自体の廃止が難しい。政治目的で入れたのであれば、その政策を終わらせる決断は政治にあるはずです。...」
税金は国対大企業の戦いになってきているそうです。
「――国際協調といえば、法人税率も日本だけの話ではなくなってきているという話もあります。
国同士の税のダンピング化などと言われていた時期もありましたが、 OECDという大きな枠組みの中で協調を取ろうという議論が始まっています。ダンピング化と言われるような状況を解消していこうという努力が始まってきていると思います。
税金の取り方が、少し乱暴に言うと国と国との取り合いから、国と大企業との戦いになってきています。国同士が手を取り合って、GAFA(Google、Amazon、Facebook、Appleに代表される多国籍企業)と対峙する、という構造に変わってきました。日本でも、ソフトバンクグループが、2018年3月期に巨額の税務上の欠損金を計上し、日本国内で法人税を払わないという「租税回避」が話題になりました。」
「とはいえ、政府としては自国の産業を守らないといけない。国と大企業の対峙とは言いましたが、他方で、国が自国企業を保護すべき面もあることは事実です。この点、最近一番注目されているのが「5G」の議論ですね。5G関連機器については、中国が我が国の国内市場を席巻するおそれがあり、安全保障上の喫緊の重大問題となっています。...
国は租税回避の面では大企業と喧嘩して、かたや経済安保の面では協力関係を保たなければならないという難しい舵取りが、この5G促進税制に見て取れるわけですね。」