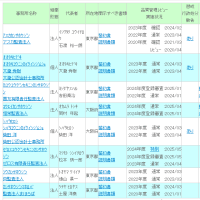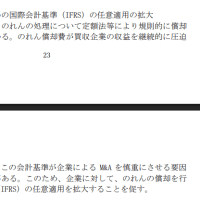「不祥事は国民性もガバナンスも超越する」というコラム記事。
VW社の排ガス不正、1990年代の日本の金融機関による会計操作、米国のエンロン社、ワールドコム社などの大規模な会計粉飾などを例に挙げて、「日本企業・日本人、米国企業・米国人だけでなく、ドイツ企業あるいはドイツ人も十分汚いことをするのだという事実には、社会的には歓迎できないことながら、人間とビジネスの普遍性を感じて、ある種の感慨を覚える」とのことです。
ガバナンスについても・・・
「・・・日本型、米国型、欧州型、いずれのコーポレートガバナンス(企業統治)も、不祥事の誘惑の前には無力だったということは覚えておきたい。また、こちらも問題が現在進行形だが、我が国の東芝は、現在の先進的とされる日本型企業ガバナンスでもやはり無力であったという事例を付け加えている。」
日本の金融機関では・・・
「例えば、1980年代の末期にかけて、信託銀行ではファンドトラストと呼ばれる運用商品(信託銀行が顧客から資金を預かって運用する仕組みの商品)で、本来違法な「握り」と呼ばれる利回り保証を付ける営業が広まっていた。加えて、保証利回りを達成するために、資産運用の部署(「受託資産運用部」といった名称)にあっては、顧客の口座間で利益の付け替えを大規模に行っていた。
営業から、運用に至るまで、多くの行員が関わっていたが、個々の行員は本来違法な行為であることを知りつつも、自分は銀行員として関わっているだけだという理解の下で、罪の意識は希薄だったように思う。」
筆者が勤めていた山一證券では・・・
「山一證券が自主廃業せざるを得なくなった直接の原因は、3000億円近い「飛ばし」(損失の意図的隠蔽)が発覚したことだった。「飛ばし」は、重要顧客に対する利回り保証付き運用の補填から発生したが、何年にもわたってこれが水面下に存在するにあたっては、当然飛ばしの面倒を見る担当者がいたはずだ。
しかし、彼らは、違法だと思いつつも、「会社のためにやらねばならない」という重圧の下で、飛ばしを継続していたはずだ。
一方で、関係する担当者も経営者も、「会社のためだ」あるいは「日本の証券市場・証券行政のためだ」といった理屈の下に、飛ばしを続けることに関して、個人的な罪の意識は希薄だったのではないか。山一が飛ばしを認めると、当時の大蔵省の証券行政にとっても大変な問題だ、という意識もあった。」
「自主廃業発表の直前まで、社員にとっては「大手証券だから潰れまい」(当時「四大証券」という懐かしい言葉があった)、「準大手証券など他社の方が先に潰れるだろう。当社はまだ大丈夫だろう」といった考えにリアリティがあった。当時の筆者の上司(本社の部長)は、「ウチに例の問題があるのは、ご存じの通りだが、もふ(「MOF」、当時の大蔵省の通称)もご存じなのだから、あいつらはウチを絶対に潰せないよ」と話していた。」
「いずれも、「今日まで続いてきた会社が、明日も続くだろう」と、悪い可能性を十分に探ることなく楽観していたにすぎない。」
東芝のケースも、会社が破たんする前に粉飾にストップがかかったという意味では、よかったのかもしれません。
 | しんがり 山一證券最後の12人 (講談社+α文庫) 清武 英利 講談社 2015-08-21 by G-Tools |