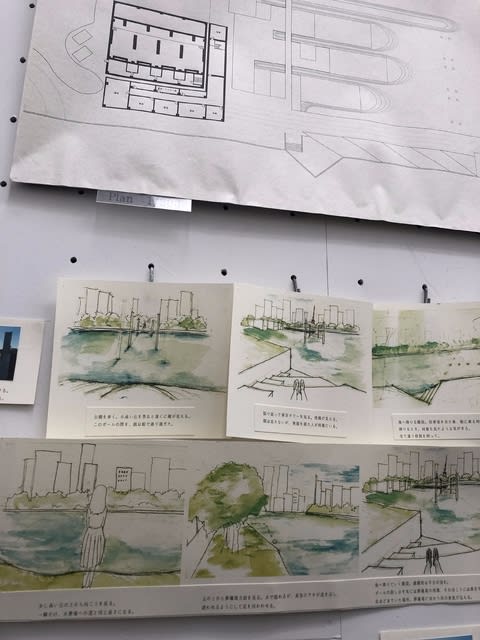移動の途中、東京ステーションギャラリー「メスキータ」展へ。
アムステルダムに生まれたポルトガル系ユダヤ人で、建築を学んだ後、木版画、エッチング、テキスタイル制作、ドローイング、水彩、油彩など多くの作品を制作するとともに応用美術学校で美術を教える。教え子の一人が、あのエッシャーだ。
75歳で、ナチスにより家族とともにアウシュビッツに送られて殺される。メスキータ逮捕を知ったエッシャーら教え子たちが、命をかけてメスキータの作品を運び出し、守ったという。
今回は日本で初めての、メスキータの回顧展である。今年は没後75年に当たる。本日初日。
メスキータの正確な描写力、コントラストによる画面構成、しかも彫刻刀の彫り方使い方による陰影や立体感の描き方など、圧倒された。アムステルダムの動物園に足しげく通って制作したという、動植物の生き生きとした、それでいてどこか神秘的な、単純な線での浮き立たせ方が素晴らしい。
当時発行されていた芸術芸術総合雑誌「ウェンディンゲン」、今あったら定期購読するのになあ。
「メスキータ」展、見応えがあった。
東京駅(丸の内)に来られる機会があればぜひ。