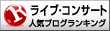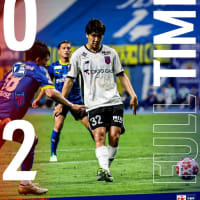ビラル流絢爛絵巻で魅せた濃厚な100分。
米・フィラデルフィア出身のシンガー・ソングライター、ビラルが約10年ぶりに来日(おそらく単独では初)。クエストラヴ(ザ・ルーツ)やディアンジェロ、コモンらに見出され、気鋭の音楽集団“ソウルクエリアンズ”へ参加。2001年のアルバム・デビュー以来決してリリースが多いとはいえないが(むしろソロとしては寡作)、その卓越した音楽性によって客演やプロデュースは枚挙に暇がないことで知られる鬼才だ。近年はロバート・グラスパー(元来、学生時代からの盟友であったとのことだが)との交流やケンドリック・ラマー作品へ顔を出すなど、日に日に注目度が増しているなかでの待望のステージとなった。東京・ビルボードライブ公演の2日目、2ndショウ。
ステージは左奥にギターのランディ・ルニオン、中央にドラムのジョー・ブラックス、ベースのコンリー・“トーン”・ウィットフィールドを挟んで右端にキーボードのデヴォン・ディクソン・ジュニアが控え、前列左にバック・ヴォーカルのマイカー・ロビンソンといった配置。キーボードのデヴォン・ディクソン・ジュニアがコズミックかつスピリチュアルな鍵盤を鳴らし、バック・ヴォーカルのマイカー・ロビンソンがハイトーンのファルセットを被せて舞台の世界観を整えると、主役のビラルが登場。現時点での最新作『イン・アナザー・ライフ』からの楽曲を主軸にしながら、ジワジワと濃厚な音世界を創生していく。

序盤は比較的ファンク・ロック的なタイトな音鳴りが強調されていたよう。また、レゲエ的な面影もチラリ。ヘアスタイルと顔立ちから一瞥するとモーリス・ホワイトのようだったが、歌唱では時折プリンスを想起させる歌い回しやシャウトを見せる(意図的ではないだろうが、紫色のスポットライトが多めに発光していたのも、その思いを強くさせたかもしれない)。楽曲が進むに連れて、ロビンソンとのスキャット競演ややや語気を強めてのポエトリーリーディング風、苛立ちを吐き捨てるような独白風グロウル、ピュアなソウルフル・ヴォーカルとさまざまなスタイルを繰り広げていく。しかも、ヴォーカルが尖ったように前面に出てくるのではなく、楽曲のムードや色彩に合わせて別人格が乗り移っていくような憑依的な佇まいゆえ、口寄せにより人を降ろす“イタコ”的な感じさえも醸し出していた。
そう強く感じさせたのはバンド・サウンドにも依拠するところがあった。ディクソン・ジュニアが鳴らすレトロフューチャーなシンセ・サウンド、ブラックスのグルーヴィなドラムと漆黒のベースの組み合わせは、一瞬ジョージア・アン・マルドロウやジェシー・ボイキンス3世&メロー・X『ズールー・グールー』あたりの宇宙に曼荼羅を展開するような実験的なソウル/ファンクに触れていたということもあるだろう。とはいえ、決してそのままどっぷりとスピリチュアル側へと傾くことはなく、モダンなレトロフューチャー像を構築しているゆえ、眉間に皺を寄せるような難解さは感じない。グルーヴという小宇宙を漂流している感覚に浸っているといった方がいいか。

前半はそう思いながら見ていたのだが、次第にその“憑依”という概念はやや的を外しているかもと思えてきた。声色や歌唱法を変えることでアクセントをつけるというよりは、深層心理を豊かな表情を持って吐露する演者として存在しているのではないかと。時に詩人、時に哲学者としてアゴラ(広場)に集うギリシアの賢者というか、古代のギリシアの戯曲を演じているアクターと考えると、ストンと腑に落ちた気がした。それぞれの楽曲の世界に内包される悲劇、喜劇、サテュロス(悲喜劇)を、レトロフューチャーな音の装飾を配しながら歌い演じる演者と言えばいいか。ビラル流の戯曲、壮大なソウル絵巻をドラマティックに描出している人生劇とすれば、処々に見せる声色や表情の違いは人間が持つ喜怒哀楽を集約したものとしてピタリと当てはまる。特にギリシアと限定する必要はないのだが、そのように脳裏を過ぎったのは、やはりヴォーカルやバンドが奏でる音色に人間味が溢れていたから。オリンポスに集うギリシア神話の神々は怠惰であったり嫉妬に激しかったりと人間性豊かなことで知られるが、そういった欲望や葛藤など人間が持つ本質的なものが、ビラルの声や一挙手一投足から感じられたゆえだろう。

元来属すとされるネオソウル路線では衒いないヴォーカルで聴かせ、終盤は即興的なラップなども組み込みながらヒップホップへ重心を寄せたビートからジャズ・セッション的なアプローチへと進行。ジャンルという概念などを過去に葬り去り、無限なビラル流小宇宙を縦横無尽に浮遊する幻想的でエキセントリックなステージ。それでも闇雲に自由奔放という訳ではなく、あくまでもモダンなコズミック感から脱することのない、彼の音楽的美学を貫いた上でのディープな世界観が見事に構築されていた。終盤のジャズとの親和性を深めたステージングは、なるほどロバート・グラスパーが盟友として長く親交を深めるのも頷ける才が満ち溢れていた(ビラルもグラスパー同様、ジャズを音楽への入り口であり最も興味を注ぐものだと感じていたようだ)。当初は客演やプロデュース的役割の多さから、ソロ・アクトとしてはバイプレイヤー的な存在を逸しないくらいに思っていたのだが、その考えはあっさりと覆された。特に押して主張するよりも引きながらも訴求力を高める美学が見事で、さまざまなジャンルのアーティストから客演に招かれるのも合点がいく。
本編が終了しても鳴りやまない拍手がフロアにこだますると、それほど間を待たずにバンド・メンバーとビラルが再登場。ラストは圧巻の「オール・マター」で幕。“愛とは何か”(So what is love? What is it?)のフレーズがリフレインする哲学的なステージ。シンプルに音や歌声に心酔しながらも、“愛とは”“人生とは”といった尽きることのない命題を掲げられたような気になった100分であった。

◇◇◇
<SET LIST>
Introduction
Star Now
Sirens II
The Flow
Pleasure Toy
West Side Girl
Don't Stop The Music(Original by Yarbrough & Peoples)
Hollywood
For You
Sometimes
Love Child
Levels
Who Are You
Never Be The Same
Back To Love
≪ENCORE≫
All Matter
<MEMBER>
Bilal(vo)
Micah Robinson(back vo)
Devon Dixon Jr.(key)
Randall Runyon(g)
Conley“Tone”Whitfield(b)
Joe Blaxx(ds)

◇◇◇