前書き
本日投稿分からそれまで問題点の多かった画像レイアウトを改善します。
(主要画像は最初から少し拡大して表示させることで拡大時のクリック動作を不要としました。)
では本題です。今日、私は友人などの5人と共にで京都市内を徒歩で観光してきました。
(かなりの距離を休まずに歩いた為に今でも足が痛い位です。)

清水寺などを観光した私達は「ある列車」に乗車するべく少し急いで河原町駅に向いました。
そして今回、河原町駅から阪急梅田駅まで乗車する列車がこちらです。


「電車から`京旅`気分」という事をテーマに6300系を改装した「京とれいん」(種別:快速特急)です。
先頭部分にはヘッドマークが装備され、車体側面には扇子のエンブレムが描かれています。
それでは車内の様子を紹介します。まずは標準的な内装をした1・2号車と5・6号車の車内の様子です。



1・2号車は赤系の転換式クロスシート、5・6号車には緑系の転換式クロスシートが使用されています。
またこれらの座席には折り返し時の手間を省く為の電動転換機能が装備されています。
(この辺りは「まぁこんな感じか。」という風に軽く流して下さい。)
続いて「京とれいん」化の際に最も大掛かりな改装を施された3・4号車の様子です。
普通乗車券のみで乗車出来る列車の中では恐らく「最強の設備」を備えていると言っても良いでしょう。
それではその全貌をご覧下さい。(知らなかった方は是非ともこの機会に覚えて下さい。)





デッキ部分と車内共に木目調や和紙風の模様が描かれ、落ち着いた雰囲気を演出しています。
車内には木材と畳の使用された固定式ボックスシートが2列+1列配置で個室風に設置されています。
付帯設備においても「妥協」という雰囲気は一切感じられません。




カーテンは和紙風の物が採用され、荷物棚には木目調の物が採用されています。
そして座布団部分(4枚目)などには凝った模様が描かれ上部には半透明の仕切り(5枚目)が設置されています。
午後03時01分。定刻通りに河原町駅を出発しました。





流れ行く車窓は古都の雰囲気が残る京都から高層ビルが軒を連ねる大都会までと変化に富んでいます。
そして列車は途中の淡路駅を出ると途中の十三駅までノンストップで運転されます。
河原町駅から乗車すること約45分。終点の阪急梅田駅に到着しました。


そして当駅からは阪急神戸線に乗り換えて阪急三宮駅に向いました。
では乗車後の私の感想です。大人しく100点満点を差し上げたいところですが少々気になった点が1つか存在します。
車内放送についてですが欲を言えば数秒でも良いので車内チャイムがあっても良かったのではと思いました。
また4ヵ国語(特に韓国語と中国語)ははっきり言って邪魔です。折角の落ち着いた雰囲気が壊れてしまいます。
最後におまけです。これは地下鉄三宮駅に設置されていた広告です。

まだ1日4往復(土日・休日限定)と本数が乏しい為、今後は更なる増発を期待します。
↑見られた方は上の画像をクリックして下さい。(鉄道コムのページへ移動します。)
もうかなり前の話ですが今日は久々に旅行記を書いてみました。
(段々と記憶が薄れつつあります。)
それでは本題です。前回は富山駅から美濃赤坂駅までの行程をご紹介しました。
今回は美濃太田駅から最終目的地である宝殿駅までの行程を公開します。
午後3時43分。日暮れの迫る美濃赤坂駅を後にします。

先程の折り返し列車で大垣駅に戻ります。
さて列車は程良い速度で美濃赤坂駅を後にします。


荒尾駅まではローカル線特有の雰囲気が広がります。
そして本線と合流すると車窓にも徐々に建物などが見えて来ます。
そして大垣駅からは向かい側のホームに停車していた列車に乗車します。
313系を使用した特別快速です。
この列車で乗換駅の岐阜駅を目指します。
乗り換えたと同時に列車は大垣駅を後にしました。

列車は途中駅に停車しますがほぼトップスピードで岐阜駅まで向います。
(この時点からはカメラのバッテリーの残りが危なかったので撮影が少々いい加減になります。)
岐阜駅からは残りの「あの区間」に乗車すべくこの列車に乗車します。

683系2000番台を使用した特急しらさぎです。
この列車で「あの区間」を経由して米原駅を目指します。
列車は大垣駅を出ると関ヶ原駅までは下り線から分離して「あの区間」に入ります。



「あの区間」とは戦前に勾配緩和を目的として設けられた迂回線の事です。
かつては蒸気機関車列車が走行していましたが現在は主に特急列車などが走行しています。
岐阜駅から約30分。乗換駅である米原駅に到着しました。
(同時に東海道本線[旅客線]を全線制覇しました。)
残り少ない行程をこの列車で一気に飛ばします。
223系1000番台を使用した新快速です。
この列車で最後の乗換駅である加古川駅を目指します。
そして日も暮れかかる米原駅を後にします。


列車はそれまでの田園地帯を抜けて灯りの溢れる夜の大都会に入ります。
漆黒の闇の中を列車は全速力で駆け抜けます。
米原駅から約2時間。最後の乗り換え駅である加古川駅に到着しました。
もう既に駅周辺は日も完全に暮れて「夜陰の街」と化していました。
いよいよ最後に列車する列車がこちらです。

223系1000番台を使用した普通列車です。
この列車で本旅行記の最終目的地である宝殿駅を目指します。
午後7時半頃。ついに最終目的地である宝殿駅に到着しました。


かくして私の3日間に渡る旅行記は幕を下しました。
これは今回の旅行記(3日目)の結果です。
・新規走破路線…高山本線、東海道本線
・新規乗車距離…217.3km
・乗車達成率…20.064%→22.092%
(JR6社管内)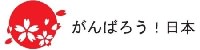


↑見られた方は上の画像をクリックして下さい。(鉄道コムのページへ移動します。)
今回は3日目の行程を公開します。(2回に分けての公開です。)
3日目は定刻通りであれば氷見線と高山本線、東海道本線の残り区間を乗車するはずでした。
(これは昨夜に乗車した日本海が大幅に遅延した為、富山駅で下車したからです。)
朝7時15分。本来の開始駅でなかった富山駅に到着しました。(理由は先述)


少々未練が残りますが気を取り直して途中駅から本日の工程を開始します。
本日1番目に乗車する列車はこの列車です。
キハ120系気動車を使用した普通列車です。
この列車で猪谷駅を目指します。
午前8時14分。列車は富山駅を後にしました。


富山駅を出て暫くの間は車窓からも北陸新幹線の高架橋が見えます。
その後はこの先の区間程ではありませんが山や川が広がって来ます。
富山駅から約1時間。白銀の中の猪谷駅に到着しました。

そして先頭に停車していた列車に乗り換えます。
ちなみに次に乗車する列車がこちらです。
キハ40系を使用した普通列車です。
この列車で太多線との接続駅である美濃太田駅を目指します。
そこそこの乗客を乗せた後、列車は駅を後にしました。


車窓左側には悠大な渓流と山々が広がります。
程良い積雪と川の流れが生みだす絶景は見る者を圧巻させます。
そしてその絶景を見ながら駅弁を食します。


源(株)から発売されている「ますのすし」(1300円)です。
大きさはそれ程大きくありませんが1人で完食すればかなりの満腹感を感じます。
猪谷駅から乗車すること約1時間。途中駅の高山駅に到着しました。


長時間停車を行う駅であったので駅弁と軽食類を調達します。
高山駅を出ると列車は集落の中を走ります。



高山駅から暫くの間は雪景色ですが下呂駅に近付くにつれて徐々に雪は消えてゆきます。
ちなみに途中の下呂駅にはこんな変わった物が存在しました。



このオブジェ(!?)からは泉の様に温泉が湧き出ています。
(効果効能は写真4枚目の石版に書かれている通りです。)
猪谷駅から乗車すること約4時間。終点の美濃太田駅に到着しました。


約4時間における長時間乗車でしたが私自身は全く疲労を感じませんでした。
そして後続の普通列車で岐阜駅に向いました。(割愛します。)
美濃太田駅から乗車すること約40分。ついに高山本線の終点である岐阜駅に到着しました。

この駅は高山本線と東海道本線の接続駅と言うこともあり大勢の乗客が下車します。
そして駅のホームの椅子で最後の食事を取ります。


金亀館(株)から発売されている「飛騨牛ほう葉みそ弁当」(1050円)です。
この地方の郷土料理である朴葉味噌を手軽に味わう事の出来る面白い駅弁です。
さて食事を取り終えて暫くした後、私は次の列車に乗車しました。
313系を使用した新快速(各駅停車)です。
この列車で大垣駅を目指します。
そして10分程度で大垣駅に到着しました。

ここからは東海道本線に2つ存在する「あの区間」の1つに乗車します。
この駅から乗車する列車はこの列車です。

313系(2両編成)を使用した普通列車です。
この列車で1つ目の「あの区間」の終点である美濃赤坂駅に向います。
そして列車は大垣駅を後にします。


大垣駅を出ると列車は車両基地の付近(1枚目)を走行します。
そして荒尾駅を出ると列車は完全に田舎の中を走ります。
そして僅か10分程度で終点の美濃赤坂駅に到着しました。





今回はここまでです。次回は当駅から宝殿駅までの様子を紹介します。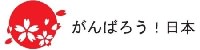


↑見られた方は上の画像をクリックして下さい。(鉄道コムのページへ移動します。)
今回は私が3日間に渡って行った全線乗車旅行記の2日目の様子を紹介します。
(あえて2日目からの公開です。)
午前10時20分。少々遅れた寝台特急を下車して青森駅に到着しました。


ここで駅弁と少量の手土産を購入して早速、2日目の行程に移ります。
本日1番目に乗車する列車はこの列車です。


HB-E300系を使用した快速リゾートあすなろ号です。
この列車で大湊線の終着駅である大湊駅を目指します。
それでは車内の様子をご紹介します。




車内には床部分や荷物棚を中心に木目が描かれ温かみを演出しています。
なお出入り口付近には大型の液晶モニターが設置されています。
続いて装備されている座席の様子です。




背面テーブル(4枚目)とインアームテーブル(5枚目)を装備した回転式リクライニングシートが採用されています。
座席間隔も非常に広々としている為、足をかなり伸ばしても前方の座席に当たりません。
ちなみに先頭部分には展望スペースが設けられています。


運転席の直ぐ真後ろには簡易式の椅子(2枚目)が設置されており前面展望を堪能する事が出来ます。
そしてこの前面展望は各車両に設置された液晶モニター(先述)にて生中継されます。
3号車には車椅子対応の大型トイレが設置されています。



外部と内部共に木目が描かれています。また非常に広々とした点が特徴です。
午前11時05分。快晴の下の青森駅を定刻通りに出発します。



列車は当駅から野辺地駅まで青い森鉄道線を走行します。
そして速度制限区間を抜けると一気に最高速度まで加速します。
そして列車は途中の野辺地駅から進行方向を変えます。


野辺地駅を出ると進行方向右側(A席)には主に森林が広がります。
乗車すること約100分。終点の大湊駅に到着しました。


駅構内にはみどりの窓口と待合所が設けられています。
(駅舎は約1年前に改築されたばかりです。)
そして折り返しの快速リゾートあすなろ号で青森駅に向います。
先程よりは乗客の数も少なめでした。
大湊駅を出ると進行方向右側(D席)には陸奥湾が広がります。


晴天の下を列車は程良い速さで快走します。
そして絶景を眺めながら駅弁を頂きます。

吉田屋(株)から発売されている八戸いいとこどり弁当(1100円)です。
(「景色も最高かつ駅弁も旨い」…正に言う事無しです。)
列車は野辺地駅を出ると再び青い森鉄道線に入ります。


JR線内とは異なり列車はかなりの速度で青い森鉄道線を疾走します。
そして高架橋を降りると列車は青森駅に差し掛かります。
乗車すること約100分。青森駅に到着しました。

再び手土産を購入して次に乗車する列車のホームに向かいます。
続いて乗車する列車この列車です。

キハ40系気動車を使用した普通列車です。
この列車で津軽線の終着駅である三厩駅を目指します。
列車は少々遅れて青森駅を後にしました。


青森駅から中小国駅間は単線ですが電化区間を走行します。
しかしこの区間を過ぎると完全に景色は山の中となります。
乗車すること約90分。終着駅の三厩駅に到着しました。




駅周辺は雪で覆われ、軒下には氷柱が立っています。
また1日に発着する列車が僅か5往復と非常に乏しい点も大きな特徴です。
午後5時43分。折り返し列車は大雪の中の三厩駅を出発しました。


殆ど車内に乗客のいない状態で終点の蟹田駅まで列車は走りました。
乗車すること約50分。終点の蟹田駅に到着しました。
ここからは特急スーパー白鳥号で終点の青森駅に向いました。(割愛します。)
午後6時55分。2日目の旅行記の最終目的地である青森駅に到着しました。


ここからは寝台特急日本海に乗車して富山駅(本来は高岡駅)に向いました。
(Continue to this page.)
これは今回の旅行記(2日目)の結果です。

・新規走破路線…大湊線、津軽線
・新規乗車距離…114.2km
・乗車達成率…12.483%⇒14.028% 19.493%→20.064%
(JR東日本管内) (JR6社管内)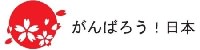


↑見られた方は上の画像をクリックして下さい。(鉄道コムのページへ移動します。)
先日に述べた様に「みずほ」と直通「さくら」は来年3月のダイヤ改正で増発されます。
今回は「みずほ」が1往復、直通「さくら」が7往復増発される予定です。
ちなみに私は今年の2月頃から増発の方法を考えていました。
私の予想では「ひかり」+完結「さくら」が一本化されて直通「さくら」に変わると推定していました。
また同時に極端に停車本数の乏しかった姫路駅、徳山駅、新下関駅の状況も改善されると考えていました。
予想はほぼ(!?)的中しました。先行公開された時刻表を見た時、私は「ああ…やはりな(納得)」と思いました。
各駅の増発後の停車本数は以下の通りです。
基本停車駅…上り18本[11]、下り18本[11]の計36本[22]
姫路駅…上り10本[3]、下り11本[5]の計21本[8]
徳山駅…上り4本[1]、下り6本[1]の計10本[2]
新山口駅…上り8本[7]、下り7本[6]の計15本[13]
新下関駅…上り4本[4]、下り4本[3]の計8本[7]
最大の変化点は姫路駅と徳山駅の停車本数が爆発的に増加する点です。
また新八代駅、新水俣駅、出水駅の停車本数も増加する予定です。
上記から停車本数は最大で6倍、最低でも1.3倍は増加する事が分かります。
しかしこの程度の本数は最初から停車させておくべきだったのではと私は思います。
(姫路駅は本数が約10往復、新山口駅は約7往復になりましたがそれが普通です。)
停車本数が増加する事を喜ぶが「でもまだ物足りない」と思う方は多く存在するはずです。
やはり今後も利用状況によっては更なる増発が行われる事も十分に考えられるので目が離せません。
↑見られた方は上の画像をクリックして下さい。(鉄道コムのページへ移動します。)
リニア鉄道館の訪問を終えて名古屋駅へ戻る時に「ある事」が私の頭の中に浮かびました。
それは「指定列車(近鉄特急)に乗車まではまだ3時間もあるので非常に暇だ。」という事です。
ということで私は空き時間を利用して中部国際空港方面へ行く事にしました。
(勝手な独断で寄り道や行き先を変更出来る事は1人旅の最大の魅力でもあります。)
そして名古屋駅から乗車する列車こちらです。


2000系を使用した全車特別車の快速特急「ミュースカイ」です。
この列車で目的地である中部国際空港駅を目指します。
それでは早速、車内に入ります。

車内には2+2列配置で回転式リクライニングシートが装備されています。
また空港特急という観点から座席は海をイメージした色の物が採用されています。
続いて装備されている座席の様子です。



座席は写真2枚目の様にリクライニングに連動して座面が沈み込む「座面チルト機能」を搭載しています。
また背面テーブルの留め具部分にはチケットホルダーが設けられています。
ちなみに客室ドア上部にはLCDディスプレイが搭載されています。


LCDディスプレイでは降車駅案内の他に展望映像(写真3枚目)などが放映されます。
そしてデッキ部分と洗面所・化粧室の様子です。


基本的にデッキ部分などを含めて化粧版は青系の物で統一されています。
また洗面台(写真2枚目)は非常に凝ったデザインの物が採用されています。
やがて列車は名古屋駅を後にします。



列車は途中、金山駅と神宮前駅に停車すると終点の中部国際空港駅までノンストップで運転されます。
また曲線区間が多い常滑線内でも列車は速度を殆ど落とす事無く高速で駆け抜けます。
そして常滑線と空港線の接続駅である常滑駅を通過すると到着放送が流れます。
(この動画は720pハイビジョン画質で再生可能です。)
到着放送では車内チャイムの他に専用BGMが流される事が特徴です。
名古屋駅から約28分。終点の中部国際空港駅に到着しました。




平成17年3月から行われた「愛・地球博」に合わせて開業した当駅は現代的な駅構造をしています。
特に「到着ホームから出発・到着ロビーまで段差無しで接続する。」など徹底したバリアフリーが図られています。
そして帰りの特別車両券を購入した後、再びホームに戻ってきました。 

ホームに戻ってきた時に丁度、列車が入線して来ました。
その入線して来た列車がこちらです。



2200系を使用した一部特別車の特急です。
この列車を利用して近鉄線の乗換駅である名古屋駅を目指します。
それでは早速、車内に入ります。(一部特別車ですが特別車を利用しました。)

特別車の車内には2000系と同様に回転式リクライニングシートが配置されています。
ちなみに一般車は転換式クロスシートとロングシートを組み合わせた配置です。
続いて装備されている座席の様子です。



座席自体は2000系に装備されている物と全く同じです。
(強いて言うなら背面テーブルの車両案内[写真3枚目]が異なる程度です。)
また客室ドア上部には2000系と同様にLCDディスプレイが搭載されています。

「展望映像が放映されない」点を除けば2000系に搭載されている物と大差ありません。
やがて列車は中部国際空港駅を後にしました。



行きに乗車したミュースカイとは異なりこの列車は途中、結構な数の駅に停車します。
また神宮前駅などを除いて途中駅から特別車に乗車する客は殆どいませんでした。
ちなみにデッキ部分には写真左のような注意文が貼られていました。

注意文では「この列車は前方の4両が一般車両で後方の2両が特別車」という事を意味しています。
(これは非常に賢い特急列車の運転方法だと思います。)
そして列車は常滑線から名古屋本線の線路に合流して名古屋駅に向います。
(この動画は720pハイビジョン画質で再生可能です。)
神宮前駅から名鉄名古屋駅の区間はJR東海道線や東海道新幹線の列車と並走します。
中部国際空港駅から約37分。乗換駅の名古屋駅に到着しました。

この後、私は売店で土産を購入した後に大阪難波行きの近鉄特急に乗車しました。
(Continue to there.)
↑見られた方は上の画像をクリックして下さい。(鉄道コムのページへ移動します。)
さて先日、私は修学旅行で北海道(主に富良野と小樽方面)に行っていました。
今回は最終日の自由行動の時の一部始終の様子を紹介します。
集合写真を撮影した小樽運河を後に小樽市内を観光します。


余談ですがこの時から集合時間まで私は単独で行動していました。
(決して単独で行動した事を虚しいとは思っていません。)
観光を始めてから約30分後。偶然見つけたラーメン屋に入ることにしました。

そして数ある品の中から味噌ラーメンを注文しました。
また昼食時という事もあり店内は比較的、賑わっていました。
勘定を払った後に私は小樽駅に向いました。

ここから今回の旅行が始まります。(と言っても僅か一駅間だけですが…。)
乗車券を購入する為に駅構内に入ります。

駅舎には小樽運河を思わせる独特の気品と風格が漂っています。
また高い天井まで続く大きな窓が解放感を演出しています。
購入した切符を自動改札に通し、ホームに上がります。



ホームには琺瑯看板やランプなど旅情を演出させる様々な工夫が施されています。
やはりこの様な駅には電車よりも夜行列車などの姿が似合います。
ちなみに4・5番線ホームの端にはこんな物が設置されていました。



かつて小樽市内に住んでいた石原裕次郎の面影を残す「メモリアルオブジェ」です。
小樽市を代表する有名人という事あって地元では大きく知られています。
お待たせしました。ようやく乗車する列車が入線してきました。

721系を使用した「快速エアポート134号」です。
この列車で一つ隣の南小樽駅を目指します。
それでは早速、車内に入ります。



普通車自由席(一般車)の車内には転換式クロスシートが配置されています。
また普通車指定席(Uシート車)の車内には回転式リクライニングシートが配置されています。
やがて午後1時04分。列車は小樽駅を出発しました。



列車は晴天の下の白銀の中を順調に駆け抜けます。
(雪とは全く無縁の地域に住んでいる私にとっては神秘的な光景でした。)
そして小樽駅から約3分。目的地の南小樽駅に到着しました。



小樽駅と同様に屋根の無い部分は膨大な量の雪で覆われています。
やがて列車は札幌方面に向って発車して行きました。


この後、私は集合場所で仲間と合流して新千歳空港に向いました。
前回は奈良駅から敦賀駅までの様子を紹介しました。
そして最後の今回は敦賀駅から大阪駅までの様子を紹介します。
特急列車を降りた時、私はある車両が停車していることに気付きました。



今年の3月を最後に引退する419系電車です。
国鉄末期に583系を近郊型車両に改造して誕生した車両です。
その時、別のホームには北陸本線の次期主力になると思われる車両が停車していました。

2006年の新快速の敦賀延伸とほぼ同時に登場した車両です。
また今年の3月には2両編成×20本が新たに投入されます。
(つまり415系や419系を置換えるという意味です。)
一抹の寂しさを感じた私は駅舎の外に出ることにしました。

現在、駅舎は福井県の整備事業に基づいて改装工事が行われています。
また駅舎の近くには「北陸新幹線の早期開通」を促す看板が立っていました。
そして午後16時53分。今回の旅行の最後を飾る列車がやって来ました。

今年の3月に営業運転を終える485系を使用した「特急雷鳥92号」です。
この列車で今回の旅の最終目的地の大阪駅を目指します。
大変長らくお待たせしました。往年の特急車両の車内の様子です。



車内には晩年の大改造で交換されたフリーストップ式のリクライニングシートが配置されています。
また指定席用の車両には座席間隔と窓割が合っていない座席がかなり存在します。
(自由席用の車両は座席間隔と窓割は合っています。)
続いて普通車の座席の様子です。



座席は現代の特急車両とは異なり、リクライニング角度が大きい点が特徴です。
また座席の後部には足置きと思われる「蹴り込み」部分が存在します。
またサニータリ―スペースも改造時期と場所によっては多くの相違点が存在します。


こういった微妙な違いを観察する事もまた面白いものです。
その他の車内設備も晩年の大改造で大きな変化が表れています。



改造に改造を重ねた結果、古典的な物から最新型の物までが入り混ざる結果となりました。
やがて列車は敦賀駅を後にしました。



太陽も完全に暮れた夜陰の中の湖西線を列車は高速で疾走します。
(写真1枚目と2枚目は敦賀駅~近江塩津の区間の様子です。)
そして列車は京都駅、新大阪駅と停車していきます。

両駅共に新幹線の乗り換え駅ということもあり、大半の乗客が下車します。
(終点まで乗車していた乗客は座席定員の約4割程度でした。)
午後18時20分。あと数分で終点の大阪駅に到着する事を告げる車内放送が流れます。
(この動画はハイビジョン画質で再生可能です。)
車内放送の前後に鉄道唱歌が流れている点も見所です。
車内放送から約3分後の午後18時23分。ついに最終目的地の大阪駅に到着しました。
約13時間に渡る長旅が間も無く幕を下ろします。
そして列車が到着した途端に撮影大会が始まりました。

大勢の撮り鉄が特徴的な先頭部分を写真に収めようとしています。
やはり約半世紀に渡って活躍した列車だけに引退に「物淋しさ」を感じます。
その後、私は雷鳥号(回送列車)の出発を見送った後に後続の新快速と快速で宝殿駅を目指しました。(割愛)
(余談ですがこの日の晩飯は米原駅で購入した駅弁です。)
最後に今回の旅行の結果は以下の通りです。
・新規走破路線…阪和線、関西空港線、和歌山線、桜井線、湖西線
・新規乗車距離…276.1㎞
・乗車達成率…21.571%⇒27.103%
(JR西日本管内)
前回は橋本駅~奈良駅までの様子を紹介します。
そして今回は奈良駅~敦賀駅の様子を紹介します。
桜井線の列車を降りた後、私は2番線ホームに向いました。

この駅は近年の大改装で駅全体が劇的に変化しました。
そして次に乗車する列車がやって来ました。
221系を使用したみやこ路快速です。
この列車で次の乗り換え駅の京都駅を目指します。
やがて列車は劇的に変化した奈良駅を駅を後にしました。



単線区間とは思えない程の速さで列車は田園の中を疾走します。
また京都駅に近付くと徐々に京阪や近鉄の線路が見えてきます。
奈良駅から約1時間。京都駅に到着しました。
この駅からは短区間ですが東海道新幹線を利用します。
(新幹線は今回の切符とは別に乗車券と新幹線特急券が必要になります。)
その次に乗車する列車がこちらです。


700系新幹線を使用した「こだま666号」です。
この列車で北陸本線の始発駅の米原駅を目指します。
それでは早速、車内に入ります。(勿論、自由席利用です。)

客室内には2列+3列でフリーストップ式のリクライニングシートが配置されています。
またUターンラッシュと重なった点から、自由席の座席の殆どは埋まっています。
(中には幼児に1人で座席を使わせる親がいますがこれは好ましくない行為です。)
しかし京都駅を発車する時点ではまだ若干の空席が残っていました。

今回、私は2人掛けの座席(D・E席)の方を選びました。
写真を撮影している間に列車は京都駅を後にしました。



列車は薄曇りの中の東海道を、これまでの列車とは桁違いの速さで激走します。
また景色も米原駅が近付くにつれて雪景色が広がっていきます。
午後15時25分。雪の中の米原駅に到着しました。

余談ですが新幹線ホームでは現在も「反転フラップ式表示板」が使われています。
(山陽新幹線では2007年に新岩国駅を最後に姿を消しました。)
しかし駅構内は大改装で近代的な造りへと変わっていました。

最早、薄暗い駅舎だった頃の面影は全く残っていません。
駅構内の写真を撮り終えた後、駅弁(晩飯用)を購入して在来線ホームに向いました。



やはりホームも車窓と同じく雪景色をしています。
そして午後15時45分。次に乗車予定の列車が入線してきました。


683系2000番台を使用した「特急しらさぎ57号」です。
この列車で小浜線の接続駅である敦賀駅を目指します。
毎回の様に客室に入る前に写真を撮影します。



客室には2列+2列でフリーストップ式のリクライニングシートが配置されています。
ちなみに偶数号車は黒色、奇数号車は赤色の座席が採用されています。
続いて座席の様子です。



座席はキハ189系などに採用されている物と同等の物が採用されています。
また最前列と最後尾の座席には大型テーブル(写真右)と100vコンセントが設けられています。
やがて列車は米原駅を後にします。



余呉駅を通過すると列車は湖西線の線路と合流します。(写真3枚目参照)
また新疋田駅を通過すると車窓には上り線(米原方面)のループ線が見えてきます。
米原駅から約30分。敦賀駅に到着しました。

今回はここまでです。次回は敦賀駅~大阪駅までの様子を紹介する予定です。
(主に「特急雷鳥92号」の乗車レポートを中心に書く方針です。)
前回は関西空港駅~橋本駅までの様子を紹介しました。
それでは今回は橋本駅~奈良までの様子を紹介します。
ホーム上を散策した後、先程の電車の車内に戻ってきました。
ここから次の長時間停車駅である五条駅を目指します。
そして列車は長閑な風景の中をのんびりと走ります。

やはり景色はの殆どは田圃と畑で構成されています。
橋本駅から約30分。五条駅に到着しました。

同様に駅看板と列車の先頭部分を撮影します。
ここでも時間に余裕があったので駅の外に出てみました。


駅舎はコンクリート製ですが一抹の古めかしさを感じます。
また駅構内には駅弁屋と思われる売店も設けられています。
約10分間の停車時間を終え、列車は再び高田方面に向い始めました。



北宇治駅付近にはかつて当線を支えていた「スイッチバック」の名残が残されています。
(勿論、架線や線路、枕木などは取り外されています。)
和歌山駅から約2時間。ついに高田駅に到着しました。
やはり長時間乗車の疲れは半端ではありません。
そして高田駅からはこの列車に乗車します。

221系を使用した快速列車です。
この列車で和歌山線の終着駅である王寺駅を目指します。
列車は比較的、空いていたので車内で駅弁を食すことにしました。

数時間前に和歌山駅の駅弁屋で購入した駅弁です。
(販売価格も約700円とまた手頃です。)
駅弁を食べ終えた後にはもう列車は王寺駅のホームに差し掛かっていました。

ホーム付近の分岐点で関西本線(大和路線)の線路と合流します。
高田駅から約20分。王寺駅に到着しました。
この駅は近鉄線が乗り入れていることで知られています。
王寺駅を降りて待つ事、約30分…。次の列車がやって来ました。
先程の列車と同じ221系を使用した快速列車です。
この列車で高田駅を目指します。
やがて列車は王寺駅を後にしました。



列車は住宅地の中を高速で駆け抜けます。
(単調だった車窓に大きな変化が加わりました。)
王寺駅から約20分。先程の高田駅に戻ってきました。
既に反対側には次に乗車予定の列車(看板の奥の車両)が停車していました。
その次に乗車予定の列車がこちらです。
105系を使用した普通列車です。
この列車で桜井線の終着駅の奈良駅を目指します。
そして列車は高田駅を後にしました。



奈良駅に近付くにつれて住宅街の規模が徐々に増していきます。
またこの区間では1時間あたり2~3本の列車が運転されています。
高田駅から約1時間。ようやく奈良駅に到着しました。
今回はここまでです。次回は奈良駅~敦賀駅までの様子を紹介する予定です。









