奨学金制度 真の拡充を望む
ここ数年、長引く不況を背景に
会社倒産やリストラなどによる保護者の失職のため、
奨学金に関する相談が急増している。
そんな中、日本育英会は
「きぼう21プラン奨学金」をスタートさせた。
わが国の奨学金制度は、日本育英金奨学金として、
無利子の第一種奨学金と有利子の第2種奨学金がある。
「きぼう21」は第2種奨学金に代わるもので、
「希望する者すべてに奨学金を貸与することを目標に
有利子貸与制度の抜本的拡充を図り、
学生が安心して自立した生活ができるよう援助するとともに、
教育に機会均等の実現に資する」
という趣旨をうたっている。
当初から、予想していたが、この「きぼう21」に対し、
日本育英会の割り当てを充足するだけの希望者はいない。
先日、関東と関西の私立大学の懇談会があったが、
9つの大学が割り当てを消化できないでいた。
それにもかかわらず、日本育英会のほうから
追加割り当ての要請があり、各大学とも対応に苦慮している。
入学時や、海外留学など、まとまった費用が必要な学生に
貸与するなどの柔軟な対応がなければ、消化しきれない。
大学で奨学金を担当するものとして、
この新制度導入を機に抜本的問題について3つの提言をしたい。
第一は、返還の必要がない「給付」制度の導入
奨学金は受けたいが、返還のことを考えると、迷うという学生は多い。
第二に、無利子の第1種奨学金を根幹として制度にすべきである。
第三に、教育の機会均等を確保するため、国・公立大学と
私立大学との格差是正が必要である。
日本の将来を担う高等教育を受ける者が等しく、
安心して勉学に取り組めるよう、開かれた奨学金制度に
することが望まれる。
(朝日新聞 1999年7月2日 論壇 羽田 紀男氏 一部抜粋)
ノリ自身、奨学金を借りている者なので、すごく助けられている。
アパートの隣人も、今年から大学院生になり、昨年よりも、
奨学金を多くもらっているため、助かっているという。
文系の学生は、忙しいといっても、それでもまだ時間のやりくりは
出来る気がする。
一方で、理系の学生は、実験や共同研究、また自宅では出来ることが
少なく、もっぱら研究室に通わなければいけないと行っている。
そんな中で、やはりアルバイトをしながら研究となると
大変であることは間違いない。
奨学金で、聞いたことのある話は、
昔、奨学金を借りたとしても、例えば教師になったとしたら、
返還する義務がなくなるといった話を聞いたことがある。
大学で身に着けた学問を生かして、先生となり、
地域社会に、未来に貢献するならば良しとするものだろう。
一方で、返還の義務が強くなったのは、
昔、奨学金を借りていたものが、返還する義務を怠ったものが
多くいたため、今では厳しくなったと聞いたことがある。
名称は、「奨学金」といっても、
いってみれば、「借金」と何ら変わらない。
今、奨学金で楽をしているといっても、
それは未来の自分からの借用である。
今のがんばりが、未来につながるようでなければいけない。
10年後の自分が、あの時は楽しんだから、
今はちょっと我慢するか、といっている自分を想像するノリでした。
ここ数年、長引く不況を背景に
会社倒産やリストラなどによる保護者の失職のため、
奨学金に関する相談が急増している。
そんな中、日本育英会は
「きぼう21プラン奨学金」をスタートさせた。
わが国の奨学金制度は、日本育英金奨学金として、
無利子の第一種奨学金と有利子の第2種奨学金がある。
「きぼう21」は第2種奨学金に代わるもので、
「希望する者すべてに奨学金を貸与することを目標に
有利子貸与制度の抜本的拡充を図り、
学生が安心して自立した生活ができるよう援助するとともに、
教育に機会均等の実現に資する」
という趣旨をうたっている。
当初から、予想していたが、この「きぼう21」に対し、
日本育英会の割り当てを充足するだけの希望者はいない。
先日、関東と関西の私立大学の懇談会があったが、
9つの大学が割り当てを消化できないでいた。
それにもかかわらず、日本育英会のほうから
追加割り当ての要請があり、各大学とも対応に苦慮している。
入学時や、海外留学など、まとまった費用が必要な学生に
貸与するなどの柔軟な対応がなければ、消化しきれない。
大学で奨学金を担当するものとして、
この新制度導入を機に抜本的問題について3つの提言をしたい。
第一は、返還の必要がない「給付」制度の導入
奨学金は受けたいが、返還のことを考えると、迷うという学生は多い。
第二に、無利子の第1種奨学金を根幹として制度にすべきである。
第三に、教育の機会均等を確保するため、国・公立大学と
私立大学との格差是正が必要である。
日本の将来を担う高等教育を受ける者が等しく、
安心して勉学に取り組めるよう、開かれた奨学金制度に
することが望まれる。
(朝日新聞 1999年7月2日 論壇 羽田 紀男氏 一部抜粋)
ノリ自身、奨学金を借りている者なので、すごく助けられている。
アパートの隣人も、今年から大学院生になり、昨年よりも、
奨学金を多くもらっているため、助かっているという。
文系の学生は、忙しいといっても、それでもまだ時間のやりくりは
出来る気がする。
一方で、理系の学生は、実験や共同研究、また自宅では出来ることが
少なく、もっぱら研究室に通わなければいけないと行っている。
そんな中で、やはりアルバイトをしながら研究となると
大変であることは間違いない。
奨学金で、聞いたことのある話は、
昔、奨学金を借りたとしても、例えば教師になったとしたら、
返還する義務がなくなるといった話を聞いたことがある。
大学で身に着けた学問を生かして、先生となり、
地域社会に、未来に貢献するならば良しとするものだろう。
一方で、返還の義務が強くなったのは、
昔、奨学金を借りていたものが、返還する義務を怠ったものが
多くいたため、今では厳しくなったと聞いたことがある。
名称は、「奨学金」といっても、
いってみれば、「借金」と何ら変わらない。
今、奨学金で楽をしているといっても、
それは未来の自分からの借用である。
今のがんばりが、未来につながるようでなければいけない。
10年後の自分が、あの時は楽しんだから、
今はちょっと我慢するか、といっている自分を想像するノリでした。










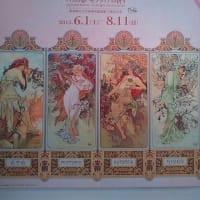









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます