本のタイトルに惹かれ、読んでみた。
メンタルが強い子どもに育てる13の習慣
エイミー・モーリン
メンタルが強い子どもに育てる13の習慣
エイミー・モーリン
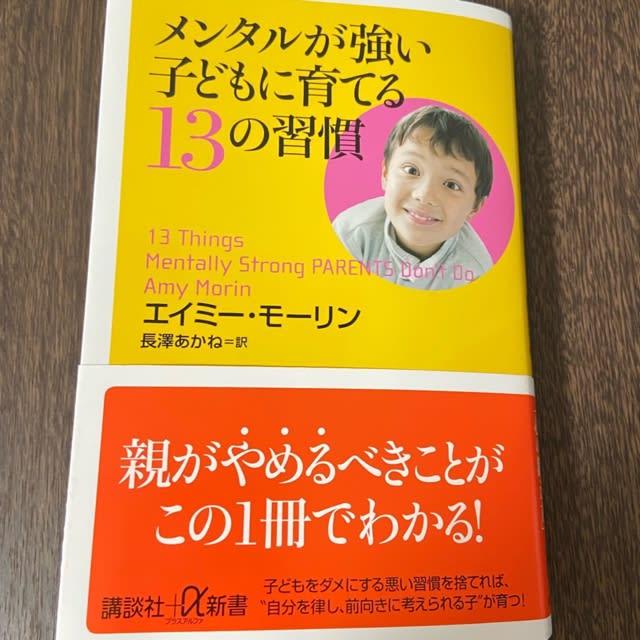
☆印象に残ったフレーズたち☆
・メンタルの力は、問題と真正面から向き合い、自分の能力を信じ、失敗から学ぶ勇気をくれる
・メンタルが強い人たちは、自分を哀れんだりしない
・自分を哀れむような悪い習慣が、メンタルの力を奪うのだ
・「成功できない」という思い込みは、どんな壁や障がいや才能のなさよりも本人の足を引っ張るだろう
・多くの場合、被害者意識は自己暗示に変わる。「私は被害者だ」と思っている子は、安全を確保したり、状況を改善する対策を講じないから、被害を受けるリスクが高まる
・人生で完璧な手札を配られる人間はいない
・親は子どもに教えなくてはならない。「人生に試練はつきものだけど、あなたにはそれに対処する力がある」と
・あなたがもらす不満が、子どもの世界観に影響を及ぼしている。ネガティブな言葉より、ポジティブな言葉を使うこと
・イヤな思いをぶちまけるのは聞き手にも話し手にも害のほうが大きい。感情を処理するというよい面もあるが、毎日のようにネガティブな思いを吐き出さないように気をつけること
・親切な行動を取り、ほかの人たちを助けよう。「誰もが世の中をよくする力を持っている」とわが子に教えること
・子どもがどんな問題を抱えていようと、本人に何とかできることは必ずある
・困難な状況は、明るい面を探す練習をする絶好のチャンスでもある
・親が間違いを犯したときは、子どもに謝ろう。関係を修復する、よいお手本になるから
・罪悪感のせいで、実りのない行動を取る必要はない
・子どもたちに危害が及ばないよう、親が一生守ってやることはできない。「私が必ず守る」と決意するよりも、危険に対処する力を本人につけさせたほうがいい
・打たれ強さは、健全で責任感のある大人になるのに不可欠
・わが子に何かを許せば、ほとんどの場合、一定のリスクを伴う。でも、やらせない場合にどんなリスクがあるかを考えることも大切
・人間関係のリスクを避けると人生が小さくまとまってしまう
・子育てに心配はつきもの
・メンタルが強い人たちは、リスクがあっても挑戦することを恐れない
・「怖いことにも挑戦できる」という自信がある子どもは、能力をフルに発揮できる
・子どもを力づけることと、権限を与えすぎることは大違い
・ルールを設けて罰を与える方法を知らずに、権威ある親にはなれない
・子どもに何でも打ち明けていると、親子の境界線があいまいになる
・権限を与えすぎると子どもの発育によくない
・世間の「標準」が絶対値ではない
・子どもが輝くチャンスはいくらでもある
・腹が立つのは、期待が大きすぎるサインかもしれない
・誰に頼まれなくてもさっと責任を引き受け、正しいことをする姿をわが子に見せよう
・幼い子どもは、お手伝いを通して能力を養い、自立し、自尊心を高める
・子どもが失敗したら説明を求めよう。ただし無責任な行動の言い訳を許してはいけない
・言い訳とは、ほかの人や環境のせいにすること。説明とは、自分の責任を引き受けること
・子どもが頑張っているのにうまくいかないときは、努力はムダになっていない、と安心させてあげること
・一度も苦しみを味わったことがない子どもは、喜びも感じられない。最高の喜びを知るために、人は時折、苦しみを経験しなくてはいけない
・つらい出来事が人生の大事な教訓に変わることもある、と子どもに伝えよう
・ほかの人を思い通りに動かそうとするのではなく、もっと自分の感情の手綱を握る努力をすべきだ
・メンタルが強い人たちは、自分ではどうしようもないことにムダなエネルギーを注がない
・親は多くを要求し、あら探しに精を出す監督ではなく、導き、支える上司になることもできるのだ
・わが子に、「失敗は避けられない」と教えよう。失敗して報いを受けることもあるけれど、どんな結果も学びのチャンスをくれる、と
・慌ててアドバイスをすると、子どもは問題を解決する方法を学べない。自分で解決策をいくつか見つけさせること
・「私は1万回の失敗をしたんじゃない。うまくいかない1万通りの方法を発見するのに成功したんだ」
・たたくと、子どもはさらに攻撃的になる
・たたくと、IQが低くなる
・新しい状況に足を踏み入れるときは、親が何を期待しているか、前もって明らかにしておくこと。
「図書館では走っちゃいけないし、おしゃべりはひそひそ声でしなくちゃダメよ」
・メンタルが強い人は、過去を引きずらない。過去から学ぶために振り返ることはあるが、過去の失敗で自分を罰さない。常に次はもっとうまくやることに、目を向けているからだ
・自分をいたわることで、子育てのガソリンタンクを満タンにしよう
・子どもは親の言葉より、行動からはるかに多くを学ぶ
・子育てにまつわるほとんどの決断には、正解も不正解もない。それぞれの親が、わが子にどんな人生の教訓を学ばせたいかによって、判断すべきだからだ
・親が自分の価値観をわかっていなければ、それを子どもに教えることはできない。そして、自分にとって何が一番大切かがはっきりすれば、子育ての難しい選択も、ずっと楽になるはずだ
・子どもの人生は子ども自身のもの、親の一番の仕事は信じて見守ること
・メンタルが強い人たちは、自分を哀れんだりしない
・自分を哀れむような悪い習慣が、メンタルの力を奪うのだ
・「成功できない」という思い込みは、どんな壁や障がいや才能のなさよりも本人の足を引っ張るだろう
・多くの場合、被害者意識は自己暗示に変わる。「私は被害者だ」と思っている子は、安全を確保したり、状況を改善する対策を講じないから、被害を受けるリスクが高まる
・人生で完璧な手札を配られる人間はいない
・親は子どもに教えなくてはならない。「人生に試練はつきものだけど、あなたにはそれに対処する力がある」と
・あなたがもらす不満が、子どもの世界観に影響を及ぼしている。ネガティブな言葉より、ポジティブな言葉を使うこと
・イヤな思いをぶちまけるのは聞き手にも話し手にも害のほうが大きい。感情を処理するというよい面もあるが、毎日のようにネガティブな思いを吐き出さないように気をつけること
・親切な行動を取り、ほかの人たちを助けよう。「誰もが世の中をよくする力を持っている」とわが子に教えること
・子どもがどんな問題を抱えていようと、本人に何とかできることは必ずある
・困難な状況は、明るい面を探す練習をする絶好のチャンスでもある
・親が間違いを犯したときは、子どもに謝ろう。関係を修復する、よいお手本になるから
・罪悪感のせいで、実りのない行動を取る必要はない
・子どもたちに危害が及ばないよう、親が一生守ってやることはできない。「私が必ず守る」と決意するよりも、危険に対処する力を本人につけさせたほうがいい
・打たれ強さは、健全で責任感のある大人になるのに不可欠
・わが子に何かを許せば、ほとんどの場合、一定のリスクを伴う。でも、やらせない場合にどんなリスクがあるかを考えることも大切
・人間関係のリスクを避けると人生が小さくまとまってしまう
・子育てに心配はつきもの
・メンタルが強い人たちは、リスクがあっても挑戦することを恐れない
・「怖いことにも挑戦できる」という自信がある子どもは、能力をフルに発揮できる
・子どもを力づけることと、権限を与えすぎることは大違い
・ルールを設けて罰を与える方法を知らずに、権威ある親にはなれない
・子どもに何でも打ち明けていると、親子の境界線があいまいになる
・権限を与えすぎると子どもの発育によくない
・世間の「標準」が絶対値ではない
・子どもが輝くチャンスはいくらでもある
・腹が立つのは、期待が大きすぎるサインかもしれない
・誰に頼まれなくてもさっと責任を引き受け、正しいことをする姿をわが子に見せよう
・幼い子どもは、お手伝いを通して能力を養い、自立し、自尊心を高める
・子どもが失敗したら説明を求めよう。ただし無責任な行動の言い訳を許してはいけない
・言い訳とは、ほかの人や環境のせいにすること。説明とは、自分の責任を引き受けること
・子どもが頑張っているのにうまくいかないときは、努力はムダになっていない、と安心させてあげること
・一度も苦しみを味わったことがない子どもは、喜びも感じられない。最高の喜びを知るために、人は時折、苦しみを経験しなくてはいけない
・つらい出来事が人生の大事な教訓に変わることもある、と子どもに伝えよう
・ほかの人を思い通りに動かそうとするのではなく、もっと自分の感情の手綱を握る努力をすべきだ
・メンタルが強い人たちは、自分ではどうしようもないことにムダなエネルギーを注がない
・親は多くを要求し、あら探しに精を出す監督ではなく、導き、支える上司になることもできるのだ
・わが子に、「失敗は避けられない」と教えよう。失敗して報いを受けることもあるけれど、どんな結果も学びのチャンスをくれる、と
・慌ててアドバイスをすると、子どもは問題を解決する方法を学べない。自分で解決策をいくつか見つけさせること
・「私は1万回の失敗をしたんじゃない。うまくいかない1万通りの方法を発見するのに成功したんだ」
・たたくと、子どもはさらに攻撃的になる
・たたくと、IQが低くなる
・新しい状況に足を踏み入れるときは、親が何を期待しているか、前もって明らかにしておくこと。
「図書館では走っちゃいけないし、おしゃべりはひそひそ声でしなくちゃダメよ」
・メンタルが強い人は、過去を引きずらない。過去から学ぶために振り返ることはあるが、過去の失敗で自分を罰さない。常に次はもっとうまくやることに、目を向けているからだ
・自分をいたわることで、子育てのガソリンタンクを満タンにしよう
・子どもは親の言葉より、行動からはるかに多くを学ぶ
・子育てにまつわるほとんどの決断には、正解も不正解もない。それぞれの親が、わが子にどんな人生の教訓を学ばせたいかによって、判断すべきだからだ
・親が自分の価値観をわかっていなければ、それを子どもに教えることはできない。そして、自分にとって何が一番大切かがはっきりすれば、子育ての難しい選択も、ずっと楽になるはずだ
・子どもの人生は子ども自身のもの、親の一番の仕事は信じて見守ること
子育てって奥が深い。
未知の世界だからどうしたらいいかわからない。知識がないよりはあった方が何かといいと思って、気になる本は読むようにしてる。
思うようにいかないことばかりだと思うけど、まずは何でもやってみようと思う。

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます