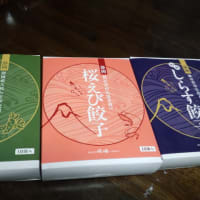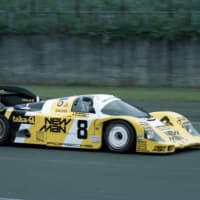ニジマスも外来魚で本来日本にはいない魚です。
これを河川に放流することは、ブラックバスと同じはずです。
ではなぜニジマスは許されるのでしょう。
地域によって違うと思いますが、静岡の場合、山奥の渓流にはニジマスは放流されていません。
岩魚の種類、ヤマメ、アマゴの問題を除いては、在来種を守る意識があります。
もう少し下流になると、渓流魚は釣り切られている状態です。ここにニジマスは放流されます。
しかし支流には放流していません。
アクセスが容易で釣り人の数が多い場所ではアマゴに加えてコストの安いニジマスを放流して遊漁の対象魚にしているわけです。そしてほぼ釣り切られる現状。もし越年しても極少数、もちろん繁殖できないという条件です。繁殖できないのですから、漁協が放流しなければ、ニジマスの姿を消すことができます。問題になってもわざわざ駆除する必要がありません。
ただし北海道ではBlogなどを見ている限り、釣り人のエゴで放流されているような印象を受けました。要は釣って楽しいからニジマスを放流しろと、在来の魚種はどうでもって感じが見受けられます。もちろん繁殖もしていますし、生態系を問題にしている人もいます。またブラウンだけを悪者にしたてあげている感もあります。(実際は詳しくないのでわかりません。日ごろblogなどをかいつまんで見ていての感想です)
さてここからはあまり地域の差がないと思われる点=なぜ問題にされないのか
「ニジマスって普通に昔から日本にいるんだよね。」多分詳しくない人はそう思っていませんか?
ブラックバスはもともと日本にいたと思っている人はほとんどいませんよね。
そして姿がまあ綺麗で悪者に見えない。申し訳ないですがブラックバスの姿は悪者に見えます。
フィッシュイーターには見えない。在来魚が脅かされているなんて想像もできませんよね。
普通に食べることができる、ポピュラーな存在。スーパーでも売ってますし。
総合して外来魚=悪者のイメージに当てはまらないのでマスコミが煽らない。
日本人の大好きな水戸黄門的な正義と悪の図式にはならないので、世間の興味は引けない。したがってマスコミはネタにしない。ブラックバス問題の真実はさておき(詳しくないので)ブラックバスは悪代官って非常にわかりやすいですからね。世間に流すのは簡単です。
そんなわけで、世間ではほとんど問題にされていないのが現状だと思います。
で、自分はどう思っているか
生態系うんぬん言い出したら人間がいなくなるのが一番ですから、人間の欲求を満たすためにどこで妥協するかが問題です。
自分は今の静岡の現状は良しだと思います。(他の地域はわかりません)
場所を選んで釣り人のためにニジマス放流、従来の生態系にはいない魚ですが、釣り人のエゴが許される範囲。もちろんほぼ釣り切る&繁殖しないのが条件ですし、鮎には時期も場所もかぶらないようになっています。また他の魚種(ウグイとかオイカワとか・・・)への影響も限定的と考えられるレベルだと思います。釣られやすいニジマスをうまく使って釣り人の欲求を満足させてくれる、現状にあったバランスの取れたやり方だと思います。
※この外来魚のニジマスを放流できる大義名分を表明している所もありました、自分が勝手に想像しているのではないことが確認できて良かったです。
長野県水産試験場
ところが、天竜川漁協は今年この大義名分を破りました。
前回は、いままでの釣り人を裏切って一部の人の利益が得られる行為をしたことを述べました。
まあそれが漁協の方針であると言われれば仕方がないですが。
しかし、問題はそれだけではありません。
ニジマスを本流に放流したことで、釣りきるのは無理になりました。ニジマスがどこで何をするのかわからない状態にしたということです。
そして鮎の遡上の時期に完全にバッティングします。影響があるかどうかはわかりません。しかし影響ないと根拠がない限り、放流すべきではないと思います。
もし、今年のデータで鮎への影響はわかるなんて言い出したら、それも大きな勘違いです。鮎の遡上数は毎年一定ではないですし、その増減の理由も定かではないのですから、そう簡単にわかるわけはないのです。
外来魚が問題視されているのに、平気でニジマスを全く管理できない環境に放流して、それを「チャンと放流」と漁協の理事が言ってのけるとは!本当に驚きました。
いくら法律でニジマスの放流が義務付けられているとはいえ、前述の大義名分は、これからもニジマス釣りを楽しむために最低限必要なことだと思います。
これを河川に放流することは、ブラックバスと同じはずです。
ではなぜニジマスは許されるのでしょう。
地域によって違うと思いますが、静岡の場合、山奥の渓流にはニジマスは放流されていません。
岩魚の種類、ヤマメ、アマゴの問題を除いては、在来種を守る意識があります。
もう少し下流になると、渓流魚は釣り切られている状態です。ここにニジマスは放流されます。
しかし支流には放流していません。
アクセスが容易で釣り人の数が多い場所ではアマゴに加えてコストの安いニジマスを放流して遊漁の対象魚にしているわけです。そしてほぼ釣り切られる現状。もし越年しても極少数、もちろん繁殖できないという条件です。繁殖できないのですから、漁協が放流しなければ、ニジマスの姿を消すことができます。問題になってもわざわざ駆除する必要がありません。
ただし北海道ではBlogなどを見ている限り、釣り人のエゴで放流されているような印象を受けました。要は釣って楽しいからニジマスを放流しろと、在来の魚種はどうでもって感じが見受けられます。もちろん繁殖もしていますし、生態系を問題にしている人もいます。またブラウンだけを悪者にしたてあげている感もあります。(実際は詳しくないのでわかりません。日ごろblogなどをかいつまんで見ていての感想です)
さてここからはあまり地域の差がないと思われる点=なぜ問題にされないのか
「ニジマスって普通に昔から日本にいるんだよね。」多分詳しくない人はそう思っていませんか?
ブラックバスはもともと日本にいたと思っている人はほとんどいませんよね。
そして姿がまあ綺麗で悪者に見えない。申し訳ないですがブラックバスの姿は悪者に見えます。
フィッシュイーターには見えない。在来魚が脅かされているなんて想像もできませんよね。
普通に食べることができる、ポピュラーな存在。スーパーでも売ってますし。
総合して外来魚=悪者のイメージに当てはまらないのでマスコミが煽らない。
日本人の大好きな水戸黄門的な正義と悪の図式にはならないので、世間の興味は引けない。したがってマスコミはネタにしない。ブラックバス問題の真実はさておき(詳しくないので)ブラックバスは悪代官って非常にわかりやすいですからね。世間に流すのは簡単です。
そんなわけで、世間ではほとんど問題にされていないのが現状だと思います。
で、自分はどう思っているか
生態系うんぬん言い出したら人間がいなくなるのが一番ですから、人間の欲求を満たすためにどこで妥協するかが問題です。
自分は今の静岡の現状は良しだと思います。(他の地域はわかりません)
場所を選んで釣り人のためにニジマス放流、従来の生態系にはいない魚ですが、釣り人のエゴが許される範囲。もちろんほぼ釣り切る&繁殖しないのが条件ですし、鮎には時期も場所もかぶらないようになっています。また他の魚種(ウグイとかオイカワとか・・・)への影響も限定的と考えられるレベルだと思います。釣られやすいニジマスをうまく使って釣り人の欲求を満足させてくれる、現状にあったバランスの取れたやり方だと思います。
※この外来魚のニジマスを放流できる大義名分を表明している所もありました、自分が勝手に想像しているのではないことが確認できて良かったです。
長野県水産試験場
ところが、天竜川漁協は今年この大義名分を破りました。
前回は、いままでの釣り人を裏切って一部の人の利益が得られる行為をしたことを述べました。
まあそれが漁協の方針であると言われれば仕方がないですが。
しかし、問題はそれだけではありません。
ニジマスを本流に放流したことで、釣りきるのは無理になりました。ニジマスがどこで何をするのかわからない状態にしたということです。
そして鮎の遡上の時期に完全にバッティングします。影響があるかどうかはわかりません。しかし影響ないと根拠がない限り、放流すべきではないと思います。
もし、今年のデータで鮎への影響はわかるなんて言い出したら、それも大きな勘違いです。鮎の遡上数は毎年一定ではないですし、その増減の理由も定かではないのですから、そう簡単にわかるわけはないのです。
外来魚が問題視されているのに、平気でニジマスを全く管理できない環境に放流して、それを「チャンと放流」と漁協の理事が言ってのけるとは!本当に驚きました。
いくら法律でニジマスの放流が義務付けられているとはいえ、前述の大義名分は、これからもニジマス釣りを楽しむために最低限必要なことだと思います。