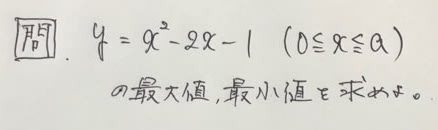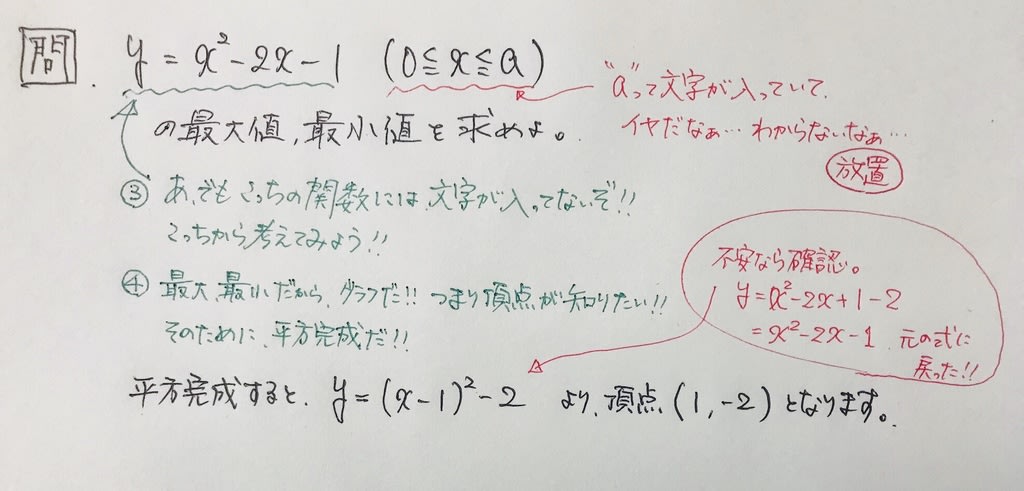今日は夏休み前の学年集会がありました。
私、進路指導係として、毎回学年集会で話をしています。
学年200人くらいの前で話すので楽しいです!
ちょっとプレッシャーなのは、学年の先生方がみんな見ていること。
私まだ、学年の中で若い方から2番目なんです・・・笑
200人以上の前で話すので、事前の準備はちゃんとします。
今日も何を話そうかなーと、通勤の車の中で。
今の勤務校で気を遣うのは、普通科以外の学科もあること。
大学、専門学校への進学以外に、就職する生徒も数十名。
自分自身は大学受験をするのが当たり前の環境だったから、
油断するとどうしても大学受験寄りの話し方になってしまう。
だから就職する生徒のことは強めに意識。
ここで問題です。
私は今日、どんな話をしたでしょうか。
さて、今日の話の内容。
直前に学年主任から「進路に向かって苦しもう」という話があったので、
それを使わせてもらおう!
と思い立ち、少しだけ用意していた話を変更。
このあたりの対応力もだいぶ板についてきた。笑
①苦しんだ分だけ、自分の進路に価値が出る
なんの苦労もしないで手に入れたものに、価値を感じる人は少ない。
同じ進路でも、苦労した末に手に入れたものは、自分の中で価値が高まる。
今までの人生だって、そうだったでしょ??
私は大学受験、本気でやりました。今も苦労して良かったと思っているよ。
みんなも自分の人生、自分の選択に価値を見出したいなら、苦労して勝ち取ろう!!
②自分の求める就職先、進学先から、求められる人材になる
「私はこの企業に就職したい!」「俺はこの大学に行きたい!」
そう思うのは自由ですが、採用したり合格を出すのは、企業や進学先です。
自分が相手に求める条件を考える時に、
逆に相手が自分に求めることは何なのか。それを考えてみましょう。
自分勝手な片思いにならないように。
③自分に必要な情報は、自分で集める
コロナの影響もあり、オープンキャンパスや企業見学ができない状況になっています。
「だから何もわからない」じゃなくて、情報は自分で集めよう。
Webでたくさん情報を発信してくれています。受け取るも受け取らないも自分次第。
担任の先生が30人以上の進学先や就職、進学の試験内容、日程について、完璧に覚えていることはできません。
自分で把握しよう。自分が損をせぬよう。
自分の人生、今まではレールを敷いてもらってきたかもしれないけれど、
これからは自分のレールは自分で敷くこと。
将来的には、他人のレールを敷く手助けができるようになるように。
さあ、夏休み、思い切り苦しんで。
自分にとって最高に価値ある進路をつかみ取りましょう!!
今日は制限時間4分をうまく使えた。
頭の中で言いたいことがクリアになっていたから、
話す前から、うまく話せるビジョンが見えた。
いつもこういう感じでありたい。
そんな教員11年目の夏。