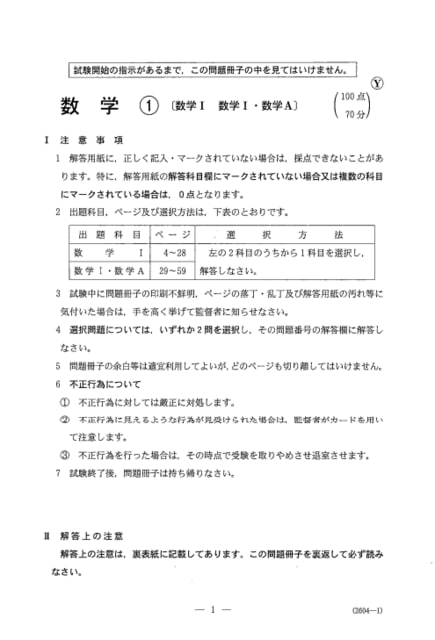「今年1年、大学院で学びます!」
って、周りの人に言うと、反応が分かれます。
あなたは、どちらでしょうか?
①「いいなあ、学べて」
②「今から学ぼうとするのってすごい」
これはおそらく、「学び」の捉え方を反映しています。
①を選んだ人は学ぶことを楽しんできた人。
学習に対して問題意識を持っていて、今も何かしら学ぼうとしているのではないでしょうか。
答えのない問いを好む人が多い気がします。
②を選んだ人は学ぶことを強いられてきた人。
きっと学習することに対する義務感が強くて、学ぶことに良い思い出があまりないのでは?
「学ぶ=正解を出すこと」って考えてる人が多そう。だから正解が出ないとイヤになっちゃう?
①の反応の人が増えたら、教育に関わる者としては嬉しいんですよね。
でも、きっとそんなに多くはない。学ぶって楽しいのに。
自分が知らないことが、世の中にはたくさんあって、知れば知るほど自分のちっぽけさを知る。
だけど確実に知識は増え、人生が豊かになっていく。
それが学びの楽しさだと思うんですよね。
ここで、ひとつ問題提起を。
小学生から「何のために勉強するの?」と聞かれたら、あなたは何と答えますか?
中学生から「何のために勉強するの?」と聞かれたら?
高校生から聞かれたら?
3つとも同じでは困りますよ。
小学生なら、小学生に伝わるように。
中学生なら、中学生に伝わるように。
高校生なら、高校生に伝わるように、しっかり理由をつけて答えられるでしょうか?
これができる大人が増えてほしい。
とか言っておきながら、僕も自信がありません。
普段、高校生には学習する意義を伝えていますが、小学生や中学生には同じ言い方では伝わらない。
彼らの感覚になって、どんな切り口で、どんな言葉を使って届ければ響くのか、そこまで考えないとならないですもんね。
きっと、それができる大人が増えたら、もっともっと学びに前向きな、学びに意義を見出そうとする子どもが増えるのではないでしょうか。
ちなみに、高校生に対して学習の意義を説くとき、
「受験に使うから」とか「試験に出るから」
というのは、上中下で言うと下な回答だと思っています。
もちろんそういう側面もありますよ、でも、でも、学びの「意義」ですから。
もっと希望に満ちた、前向きになれる回答を探してあげてください。
きっとみなさんも、これまでの人生で経験してきているはず。
試験に合格するためだけの、大学に行くためだけの学習になることほど、つまらないものはありませんからね。
身近にいる大人の考えって、子どもにすごく大きな影響を与えます。
逆に言うと、子どもは大人の考え方にすごく影響されます。
あなたが学ぶことに価値を感じていなければ、それは子どもに伝わっています。
子どもが学ぼうとするかどうかは、あなたが学ぼうとしているかどうかです。
学ぶことが好きな大人であってください。
そして楽しそうに学んでください。
それができない人は、せめて「学ぶことにも意義があるらしいぞ」ってことを、伝えてあげてください。
僕も今年1年、「なぜ学ぶのか」について、より深い答えを求めて学び続けます。
って、周りの人に言うと、反応が分かれます。
あなたは、どちらでしょうか?
①「いいなあ、学べて」
②「今から学ぼうとするのってすごい」
これはおそらく、「学び」の捉え方を反映しています。
①を選んだ人は学ぶことを楽しんできた人。
学習に対して問題意識を持っていて、今も何かしら学ぼうとしているのではないでしょうか。
答えのない問いを好む人が多い気がします。
②を選んだ人は学ぶことを強いられてきた人。
きっと学習することに対する義務感が強くて、学ぶことに良い思い出があまりないのでは?
「学ぶ=正解を出すこと」って考えてる人が多そう。だから正解が出ないとイヤになっちゃう?
①の反応の人が増えたら、教育に関わる者としては嬉しいんですよね。
でも、きっとそんなに多くはない。学ぶって楽しいのに。
自分が知らないことが、世の中にはたくさんあって、知れば知るほど自分のちっぽけさを知る。
だけど確実に知識は増え、人生が豊かになっていく。
それが学びの楽しさだと思うんですよね。
ここで、ひとつ問題提起を。
小学生から「何のために勉強するの?」と聞かれたら、あなたは何と答えますか?
中学生から「何のために勉強するの?」と聞かれたら?
高校生から聞かれたら?
3つとも同じでは困りますよ。
小学生なら、小学生に伝わるように。
中学生なら、中学生に伝わるように。
高校生なら、高校生に伝わるように、しっかり理由をつけて答えられるでしょうか?
これができる大人が増えてほしい。
とか言っておきながら、僕も自信がありません。
普段、高校生には学習する意義を伝えていますが、小学生や中学生には同じ言い方では伝わらない。
彼らの感覚になって、どんな切り口で、どんな言葉を使って届ければ響くのか、そこまで考えないとならないですもんね。
きっと、それができる大人が増えたら、もっともっと学びに前向きな、学びに意義を見出そうとする子どもが増えるのではないでしょうか。
ちなみに、高校生に対して学習の意義を説くとき、
「受験に使うから」とか「試験に出るから」
というのは、上中下で言うと下な回答だと思っています。
もちろんそういう側面もありますよ、でも、でも、学びの「意義」ですから。
もっと希望に満ちた、前向きになれる回答を探してあげてください。
きっとみなさんも、これまでの人生で経験してきているはず。
試験に合格するためだけの、大学に行くためだけの学習になることほど、つまらないものはありませんからね。
身近にいる大人の考えって、子どもにすごく大きな影響を与えます。
逆に言うと、子どもは大人の考え方にすごく影響されます。
あなたが学ぶことに価値を感じていなければ、それは子どもに伝わっています。
子どもが学ぼうとするかどうかは、あなたが学ぼうとしているかどうかです。
学ぶことが好きな大人であってください。
そして楽しそうに学んでください。
それができない人は、せめて「学ぶことにも意義があるらしいぞ」ってことを、伝えてあげてください。
僕も今年1年、「なぜ学ぶのか」について、より深い答えを求めて学び続けます。