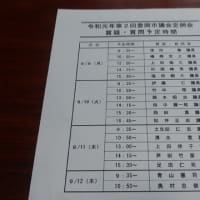19日から2泊3日で浦添市・那覇市に出かけました。浦添市では子供の貧困対策について学びました。沖縄県は全国に比べ生活保護率は高く、年間所得200万円未満世帯率も高く、非正規就業者率、就学援助率も高い状況です。親の貧困は早婚・低年齢出産・若者の離婚・経済的貧困が要因と言われています。子供の貧困は学力低下・多い不登校・低い進学率・中途退学へと繋がります。子供の貧困対策では、子供の居場所づくり運営支援を行われています。食事の提供週3回程度、生活指導(衛生保持、整理整頓、生活習慣や対人関係)、学習支援、進学支援などを行われています。平成30年度実績は、17団体が行い利用者数は34,886人です。この他にも子供の貧困対策支援員(てだこ未来応援隊11人)の配置では、アシスタントマネージャー1人・各中学校区内に2人(10人)配置され、更にCSW10人(民生委員、自治会、児童センター、保護者)が連携され、問題を抱えた子供に対して必要な支援、機関につなげる支援が行われています。平成30年度実績で219人に対し、子供の居場所・行政・学校・教育委員会つなぐ活動が行われました。「てぃーだこども食堂」の取り組みでは、冬にタンクトップで震えながら授業を受けている。給食しか食事がない子がいた。靴もない。PTAで支援を行いたいと考え衣服の支援から始め、服を特定されないように自校で集めた服は他校へ、他校で集めた服を該当子供に配る。2013年から現在も行われています。次に2015年度から給食がない日にご飯を食べられない子供を何とかしたいと、てぃーだこども食堂を立ち上げた。平日毎日晩ご飯を作り、長期休暇期間又は土曜日は昼・おやつ・夜ご飯を作って食べさせていた。3年が経過し反省点として、子供の自助力が育ちにくく、厚生も進まない。甘える親、過剰なサービス提供を当たり前として要求してくる。現在は週3回程度に抑えているとの事でした。長期間支援を続けますと当たり前となり、甘える子供、甘える親が出てきます。自立出来ない親が出てきます。支援の難しさを感じさせられました。
那覇市では、議会のICT化タブレット端末導入についてお聞きしました。平成26年から視察等導入に向けた協議を初め、平成28年4月運用開始されています。導入したメリットとして法令や計画等をその場で確認でき、効率的に役に立っている。事業や予算等が市民にわかりやすく速やかに説明することができる。議案書など重い紙資料をタブレット納められ検索も便利。ペーパレス化でコストの削減につながる。豊岡市議会も検討中ですが早く実現すべきだと感じました。