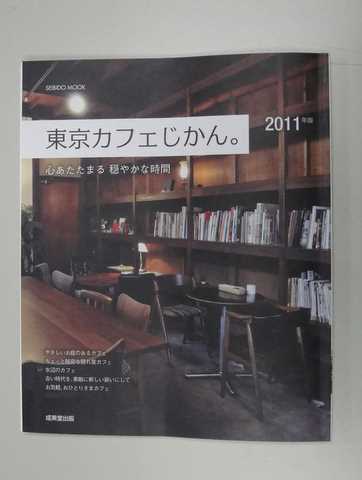そろそろ近郊の紅葉も見頃だろうと思い、東武線にある「国営武蔵丘陵森林公園」に行ってみた。
この公園は埼玉県の滑川町にあり、東西約1km南北約4kmのこの敷地は東京ドームの約65倍
ほどの広さ(面積304ha)がある広大な自然公園である。前回行った茨城の「ひたち海浜公園
(153ha)」立川の「昭和記念公園(148ha)」の倍の広さがあり、歩きごたえのある公園である。
この公園、森林公園とうたっているだけあり、遊技施設等は少なく敷地の90%以上が林である。
林間を縦横に走る小路をたどると、所々に紅葉した木々が混じり合って見える。今年は寒暖の差
が大きく、紅葉も色鮮やかという報道もあるが、私が見た限りは猛暑による葉っぱの痛みが激しく
全体としてはあまりパットしない紅葉のように思ってしまう。
歩き疲れて公園のベンチに座り、ふと空を見上げた時、真っ青な空に点々と雲がたなびいているの
が目にとまる。その雲をじーっと見つめると、ほんのわずかづつ右から左へ流れて行くのがわかる。
雲は高い空にあるのだろう、その動きは止まっているように見えるものの、しかし少しづつ形を変え
ながら確実に流れていっている。その雲を見ながら子供の頃を思いだした。
昔は幼稚園が少なく、希望者はクジ引きであった。私はそのクジに外れ幼稚園には行けなかった。
近所の友達はみな幼稚園に行ってしまい、兄は小学校へ通う。母は弟の面倒を見ることに忙しく、
私一人が取り残されてしまったようで、誰とも遊ぶことができず、独り遊びの日々だったように思う。
そんな時、縁側に寝転んでよく雲の流れるのを見ていた。抜けるような青空、何と広いのだろう?
この空のさらに上はやはり空なのだろうか?雲が流れてやがて太陽を覆い隠す。太陽が雲に隠れ
てもその所在はぼんやりと分かる。雲が流れるから、もう少し待っていれば又太陽が顔をだはずだ。
そんなことを思いながら飽きることなく雲を見つめていた。
小学校の何年生の時だっただろうか、夏休みの自由研究に「雲の観察」をテーマにしたことがある。
夏の空を眺め、特徴的な雲を見つけると、それをスケッチし、図鑑で雲の名前を調べて日記風に
仕立てる。しかし観察し始めると、いつも同じような雲で、特徴的な雲はなかなか現れてくれない。
しかも、雲には正式な分類名(巻雲、乱層雲、積乱雲等)と、俗称(すじ雲、さば雲、入道雲等)
があり、どちらも種類が多くないのである(せいぜい10種)。自分としてはなかなか良いテーマだと
思ったっのだが、毎日々同じような雲を描くしかなかった。途中でテーマを変更することも出来ず、
内容の貧弱な見劣りするレポートになってしまったことを憶えている。
そんなことがあったからか、大人になっても雲を眺めることは多かった。散歩をしていて風景の中に
雲が美しいと思うと、ついつい写真を撮っている。(下の写真は散歩の時々に撮った写真である)
雲は空高くにあると、空をどこまでも高く大きなものに感じさせてくれる。空の低くに、たなびく雲は
刻々と形を変えて流れていき、大気の流れの速さを感じさせてくれる。雲の呼び名は少なくても、
雲の形はどれ一つ同じものはなく、一瞬たりとも留まることもない。
私にとっての雲は「自然」を感じるさせてくれる最も身近な存在のものように思う。今、自分が生活
している周りは、人の手が加わった人工物に囲まれている。庭木も公園も近隣の山々でさえ人の
管理下にあり、人の意思で変更可能な存在である。どこにも自然を感じさせてくれるものが無い。
この日本と言う国の中で、この狭い東京の中で、しかも多くの人に関わらなければいけない社会の
中で生活していると、しばしば自由を奪われているように感じ、発狂しそうになってしまいそうである。
そんな時、誰の意思にも関わらない自由な一人になりたい時もある。そんな時、何にも束縛されない
自然に接してみたくなるのである。私にとっての自然とは人のコントロールが不可能な世界である。
それは「海」であり「雲」なのであろう。誰もいない海岸で、岩に打ち寄せる波を見ていると、その
膨大なエネルギーと恐ろしいような奥深さを感じる。広く澄み渡った空を見上げ、雲の流れを見て
いると、自然の雄大さと果てしなさい広がりの中に、ちっぽけな自分を感じ、その中に包まれている
「私」を思うのである。そんな海や雲を見ていると、自分の心が洗われるように感じて、癒しを感じる
のであろうか。暖かな小春日和の昼下がり河原の土手に寝転がり、日がな一日雲を眺めて過ごす、
そんなシュチュエーションが、自分にとっての至福の時なのではないだろうかと思うこともある。





















この公園は埼玉県の滑川町にあり、東西約1km南北約4kmのこの敷地は東京ドームの約65倍
ほどの広さ(面積304ha)がある広大な自然公園である。前回行った茨城の「ひたち海浜公園
(153ha)」立川の「昭和記念公園(148ha)」の倍の広さがあり、歩きごたえのある公園である。
この公園、森林公園とうたっているだけあり、遊技施設等は少なく敷地の90%以上が林である。
林間を縦横に走る小路をたどると、所々に紅葉した木々が混じり合って見える。今年は寒暖の差
が大きく、紅葉も色鮮やかという報道もあるが、私が見た限りは猛暑による葉っぱの痛みが激しく
全体としてはあまりパットしない紅葉のように思ってしまう。
歩き疲れて公園のベンチに座り、ふと空を見上げた時、真っ青な空に点々と雲がたなびいているの
が目にとまる。その雲をじーっと見つめると、ほんのわずかづつ右から左へ流れて行くのがわかる。
雲は高い空にあるのだろう、その動きは止まっているように見えるものの、しかし少しづつ形を変え
ながら確実に流れていっている。その雲を見ながら子供の頃を思いだした。
昔は幼稚園が少なく、希望者はクジ引きであった。私はそのクジに外れ幼稚園には行けなかった。
近所の友達はみな幼稚園に行ってしまい、兄は小学校へ通う。母は弟の面倒を見ることに忙しく、
私一人が取り残されてしまったようで、誰とも遊ぶことができず、独り遊びの日々だったように思う。
そんな時、縁側に寝転んでよく雲の流れるのを見ていた。抜けるような青空、何と広いのだろう?
この空のさらに上はやはり空なのだろうか?雲が流れてやがて太陽を覆い隠す。太陽が雲に隠れ
てもその所在はぼんやりと分かる。雲が流れるから、もう少し待っていれば又太陽が顔をだはずだ。
そんなことを思いながら飽きることなく雲を見つめていた。
小学校の何年生の時だっただろうか、夏休みの自由研究に「雲の観察」をテーマにしたことがある。
夏の空を眺め、特徴的な雲を見つけると、それをスケッチし、図鑑で雲の名前を調べて日記風に
仕立てる。しかし観察し始めると、いつも同じような雲で、特徴的な雲はなかなか現れてくれない。
しかも、雲には正式な分類名(巻雲、乱層雲、積乱雲等)と、俗称(すじ雲、さば雲、入道雲等)
があり、どちらも種類が多くないのである(せいぜい10種)。自分としてはなかなか良いテーマだと
思ったっのだが、毎日々同じような雲を描くしかなかった。途中でテーマを変更することも出来ず、
内容の貧弱な見劣りするレポートになってしまったことを憶えている。
そんなことがあったからか、大人になっても雲を眺めることは多かった。散歩をしていて風景の中に
雲が美しいと思うと、ついつい写真を撮っている。(下の写真は散歩の時々に撮った写真である)
雲は空高くにあると、空をどこまでも高く大きなものに感じさせてくれる。空の低くに、たなびく雲は
刻々と形を変えて流れていき、大気の流れの速さを感じさせてくれる。雲の呼び名は少なくても、
雲の形はどれ一つ同じものはなく、一瞬たりとも留まることもない。
私にとっての雲は「自然」を感じるさせてくれる最も身近な存在のものように思う。今、自分が生活
している周りは、人の手が加わった人工物に囲まれている。庭木も公園も近隣の山々でさえ人の
管理下にあり、人の意思で変更可能な存在である。どこにも自然を感じさせてくれるものが無い。
この日本と言う国の中で、この狭い東京の中で、しかも多くの人に関わらなければいけない社会の
中で生活していると、しばしば自由を奪われているように感じ、発狂しそうになってしまいそうである。
そんな時、誰の意思にも関わらない自由な一人になりたい時もある。そんな時、何にも束縛されない
自然に接してみたくなるのである。私にとっての自然とは人のコントロールが不可能な世界である。
それは「海」であり「雲」なのであろう。誰もいない海岸で、岩に打ち寄せる波を見ていると、その
膨大なエネルギーと恐ろしいような奥深さを感じる。広く澄み渡った空を見上げ、雲の流れを見て
いると、自然の雄大さと果てしなさい広がりの中に、ちっぽけな自分を感じ、その中に包まれている
「私」を思うのである。そんな海や雲を見ていると、自分の心が洗われるように感じて、癒しを感じる
のであろうか。暖かな小春日和の昼下がり河原の土手に寝転がり、日がな一日雲を眺めて過ごす、
そんなシュチュエーションが、自分にとっての至福の時なのではないだろうかと思うこともある。