
初めて俳優として好きになったのは官僚の夏だったと思います。通産省職員の生き様の内容と堺さんの活躍が好きでした・・・
それからはジョカーでもなかなか~はまっていました!!
1973年宮崎県生まれ。早稲田大学第一文学部入学後、劇団「東京オレンジ」の旗揚げに参加。数々の舞台を踏むと同時に、95年『ハートにS「休刊日」』でドラマデビュー。『オードリー』(00年)などで人気を博し、04年の大河ドラマ『新選組!』の山南敬助役でブレイク。08年の大河ドラマ『篤姫』の徳川家定役も好評を得る。『クライマーズ・ハイ』(08年)の鬼気迫る記者・佐山役や、『南極料理人』(09年)の飄々とした西村役など、映画でも活躍。待機作に『日輪の遺産』(2011年公開予定)がある。『武士の家計簿』オフィシャルサイトは www.bushikake.jp
微笑んでいる。
役や時代の背景を踏まえて答えてくれる。
ときにうつむいたり腕組みしたり天を仰ぐ。
自分がどう考えているのかを探ってる(ように見える)。
ひとつひとつの事柄に姿勢が真摯だ。
インタビューへの回答はもちろん、仕事への取り組み方も。
ガチガチではない。飄々である。
ガチガチだった時代から、徐々に抜けたらしい。
「細かいテクニックはぼく自身興味がないのと、主婦の方に言うのは『釈迦に説法』なので何とも言えないんです」と、堺 雅人は答える。
「何とも言えない」ので、普通はここで終わる。でも面白いのはこれからだ。
何らかの答えが出てくるのだ。それらがことごとく、よくできた短いコラムを読んでいるみたいに面白い。
映画『武士の家計簿』のインタビューでの話である。
映画は、幕末の加賀藩で、代々藩の経理係をつとめた猪山家三代の物語。“そろばんバカ”と呼ばれた下級武士・猪山直之が、家財道具を処分し倹約し、借金の返済を試みる…だけでなく藩の財政をも切り盛りする姿を描く。堺 雅人が“そろばんバカ”その人だ。
そしてこの取材の現場、少し変わっていて、まず映画に関する取材は5誌合同。冒頭のひとことに「主婦」という言葉が出ているのは、これが主婦向け雑誌の質問に対する回答だから。
問いはこうだ。
「作中に出てくる節約法で、現代の主婦が応用できそうなものは?」
「家で女性にこんなことをされると“ヤラレタ!”と思うようなシーンが作中にあれば教えてください」
人の価値観ではなく、自分で考えた自分の価値観
「何とも言えない」のは節約テクニックに関して。「ヤラレタ」については、意外な答えが得られることになる。
猪山家の3人の女性(祖母:草笛光子・母:松坂慶子・妻:仲間由紀恵)に関する話である。
「どんとした存在感というんですかね。その家にいてすべてを見守って、受け入れてくれている。隣に仲間さんがいらっしゃるだけで安心するところがあって。直之自身はすぐ視野が狭くなってまっすぐにものを見たがるところがあるんですが、それを優しく包み込む松坂さんの視線、草笛さんの存在…生き物としてのあったかさっていうのかな。“お母さん”“奥さん”っていう人たちは、ご自身が思ってる以上にご主人から頼りにされてるような気がするんですよ。ただそこにいるだけで『ヤラレタ』って思うときもあるんですね」
物語に息づく、“清貧の思想”や“慎ましさ”といった考え方には「実はあんまり興味がない」と笑う。猪山直之が家財道具を売り払って一家の借金を返すということは、こと武士道に照らし合わせると非常にかっこ悪い行いだ。「ぼくは、正しいかどうかわからないし、ダメだったらちゃんと責任を取るけれども、人の価値観ではなく自分で考えた自分の価値観で、“ウチはこうなんだ”って言い切る強さ、がかっこいいと思いました」
称えるだけではない。一方で「相当食えない男」だとも評する。
「だから“現実的な動機”もひとつ置いておく。子どもをしつけるシーンでも、当時の親子ってプライベート100%ではなくてどこかオフィシャルな部分もあったと思うんですよ。同じ主君に仕える同僚という意識において。だから子どもに(そろばんを)早く仕込めば仕込むほど、お国にとってはプラスなわけです。実際に直之は息子の成之に、年をごまかして早めに就職させるんですけど、当時の武家社会は年功序列の終身雇用ですから、先に就職した方が得なんですよ。算術なんて遺伝する才能じゃないので、ダメとわかれば早めに見切って養子に出してあげないといけない」
己の決めたルールに己で責任を持って従うには違いないが、それに殉ずるわけではない、ということだ。
「『武士は食わねど高楊枝』的な、地に足がついてないようなところで役を作りがちなんですけど、もうちょっと懐勘定的なことも含めて、現実の動機も混ぜるっていうことで、食えないヤツということは意識してみました」
…という部分をアタマのどこかにとどめ置いて映画を観ると、確実に役柄の印象が変わる。
合同取材の最後に堺 雅人は例の主婦向け雑誌を手にして言った。
「これいただいていっていいですか?“フォンデュ鍋”っていう特集がどうも気になっちゃって」
人の価値観ではなく、自分で考えた自分の価値観
「何とも言えない」のは節約テクニックに関して。「ヤラレタ」については、意外な答えが得られることになる。
猪山家の3人の女性(祖母:草笛光子・母:松坂慶子・妻:仲間由紀恵)に関する話である。
「どんとした存在感というんですかね。その家にいてすべてを見守って、受け入れてくれている。隣に仲間さんがいらっしゃるだけで安心するところがあって。直之自身はすぐ視野が狭くなってまっすぐにものを見たがるところがあるんですが、それを優しく包み込む松坂さんの視線、草笛さんの存在…生き物としてのあったかさっていうのかな。“お母さん”“奥さん”っていう人たちは、ご自身が思ってる以上にご主人から頼りにされてるような気がするんですよ。ただそこにいるだけで『ヤラレタ』って思うときもあるんですね」
物語に息づく、“清貧の思想”や“慎ましさ”といった考え方には「実はあんまり興味がない」と笑う。猪山直之が家財道具を売り払って一家の借金を返すということは、こと武士道に照らし合わせると非常にかっこ悪い行いだ。「ぼくは、正しいかどうかわからないし、ダメだったらちゃんと責任を取るけれども、人の価値観ではなく自分で考えた自分の価値観で、“ウチはこうなんだ”って言い切る強さ、がかっこいいと思いました」
称えるだけではない。一方で「相当食えない男」だとも評する。
「だから“現実的な動機”もひとつ置いておく。子どもをしつけるシーンでも、当時の親子ってプライベート100%ではなくてどこかオフィシャルな部分もあったと思うんですよ。同じ主君に仕える同僚という意識において。だから子どもに(そろばんを)早く仕込めば仕込むほど、お国にとってはプラスなわけです。実際に直之は息子の成之に、年をごまかして早めに就職させるんですけど、当時の武家社会は年功序列の終身雇用ですから、先に就職した方が得なんですよ。算術なんて遺伝する才能じゃないので、ダメとわかれば早めに見切って養子に出してあげないといけない」
己の決めたルールに己で責任を持って従うには違いないが、それに殉ずるわけではない、ということだ。
「『武士は食わねど高楊枝』的な、地に足がついてないようなところで役を作りがちなんですけど、もうちょっと懐勘定的なことも含めて、現実の動機も混ぜるっていうことで、食えないヤツということは意識してみました」
…という部分をアタマのどこかにとどめ置いて映画を観ると、確実に役柄の印象が変わる。
合同取材の最後に堺 雅人は例の主婦向け雑誌を手にして言った。
「これいただいていっていいですか?“フォンデュ鍋”っていう特集がどうも気になっちゃって」
理論とか理念とかより、目の前の問題をどうするか
監督の森田芳光と中村雅俊と一緒に取材を受けたとき「“そろばんバカ”の主人公と似ている部分は?」という質問を何度か受け、「全然似てません」と答えるたび、2人から「そんなことねえよ!(笑)」と突っ込まれたという。
「“不器用だな、そろばんバカだな”と思いながら演じてたんです(笑)。そういうぼくが“役者バカ”みたいに見えてたのかもしれないですね。森田さんと雅俊さんに言われるのはいやなことではないです。自分の姿は自分じゃ見えないのかもしれませんね」
猪山直之はそろばんに頼り、自身のルールを定めた。同じような“よって立つところ”は…俳優・堺 雅人には…「ないですないです」と、笑う。
「ただ、この映画って“武士はこうなるべき”っていうだいたいのルールは決まってて、“背に腹は代えられぬ”思いでそれを逸脱しちゃうストーリーなんですよね。そこは堺 雅人という俳優にもあると思います。ルールの逸脱が面白いんじゃないかな。自分のなかのルールを『この現場で、この状況だからちょっと変えまーす!』っていう。たとえば、ホントなら半日かけて撮るカットなのに、急に雨が降ってきて変更になる。手持ちのものだと完全にはできないけれども、やることになるのなら『これでいきます!』という変わり身。それが一番大切な気がします」
そろばんに比べると、なかなかにグニャグニャした地盤だ。
高校の演劇部から考えると俳優としてのキャリアは22年にわたる。最初はもっとカッチリキッチリしていたのではないだろうか。
「役者として“こうあらねばならない”ってことを一番考えていたのは、ぼくの場合でいうと、大学に入って劇団に入ったころですね。お客様からお金をいただくということで “自分はいっぱしの俳優だ”って意識を持つんです」
宮崎県の進学校から早稲田大学に進み、『劇団東京オレンジ』の旗揚げに参加。後に“早稲田のプリンス”として舞台はもちろん、比較的早い時期からドラマにも出演する。
「仕事も何もなくて、それを裏付ける技術が何もないときに“一番いいお芝居をしなきゃいけないのだ!”っていう思いを持つんですね。いいお芝居がなんなのかはまったくわからないのに、プロの俳優とは、“何かものすごいことをやっていかなきゃいけないのだ!”っていう思いにとらわれるだけで」
解くべき問題がないのに、解き方を一所懸命考えている状態だった。
「でも実際に仕事が入って、現場でやることが決まってくると、目に見えた形而下の問題になるので、理論とか理念とかあんまりいらないんですよね。できるかできないか、やれるかやれないかっていうだけ。どんなに不格好でもいいからひとつの形を出し続けるしか、たぶんやり方はないんですよ。どんなに高尚な志を持っていても、形にならなければゼロ。どんなにいびつになっても答えを出し、それには自分で責任を取っていかなくちゃならない。“仕事にする”っていうのは、たぶんそういうことだと思うんです」
“仕事にする”を最初に意識したのも、劇団に入ったとき。
「大学でお芝居始めるときには2カ月ぐらい悩みました。やるからには中退もするだろうなって思っていて。半ば出家するような気持ちでしたね。というのも“プロとして!”ってガッチガチに肩に力が入ってたから。そこからゆ~っくり、“俳優になろう”という気持ちが薄れていったんです」
大切なのは、その意識ではないのだ。「なろうと思うかどうかは関係なく、仕事をしていくことでしか俳優にはなれないんですよ。自分が“俳優だ!”って言い張っても、目の前のセリフがしゃべれなければ、俳優ではない。すべては後づけ、ぼく以外の人が決めることなんだなって、ゆっくりと気づいて、今も続けてるんですけど」
なろうと思わず、自然になりながら、楽しみもじわじわと広がっている。
「みんなでワイワイものを作っていく文化祭的な喜びは、高校時代からありました。自分の感情を表現する喜びというのも、高校の演劇部レベルでも感じられる楽しみだったし。それがお客さんに伝わって喜んでもらえる喜びが得られるようになったのは、ずいぶん最近のことのような気がします。演じることでお金をいただくようになって社会的な責任も感じるようになって、そういう部分に付随するいろんな喜びをまた今、少しずつ教わってるような感じがしてますね」
野望も目標もない。共演したい俳優も、仕事をしたい監督もいない。
「もっとうまくやりたいっていう欲ははありますけど、この役やりたいという欲はないですねえ」
欲しいものは「次の役(笑)」。
共演者も監督も役柄もそこに全部載っている。オファーがあればまた新たなルールで取り組むのだろう。
趣味を尋ねると「うーん、とくに…」とニコニコ笑っている。幸せですね、と言ったら「確かに」と破顔一笑した。
宮崎県屈指の進学校で演劇部に所属。「膨大な情報を効率よく覚えていくということを3年間やらなきゃいけないわけです。それに息が詰まっちゃって。しっかりした指導者と先輩がいなくて、やることのあんまり決まっていない文化部でのんびりしたかったんです。そこで自分が何をしたいのかをゆっくり考えようと…あ、でも当時はせいぜい“誰も威張ってる人がいないところがいいなあ”程度の理由です(笑)」…という、R25ならぬR15時代
それからはジョカーでもなかなか~はまっていました!!
堺 雅人
さかい・まさと
2010.11.18Vol.276 - Page1
「ルールの逸脱が面白い」
さかい・まさと
2010.11.18Vol.276 - Page1
「ルールの逸脱が面白い」
1973年宮崎県生まれ。早稲田大学第一文学部入学後、劇団「東京オレンジ」の旗揚げに参加。数々の舞台を踏むと同時に、95年『ハートにS「休刊日」』でドラマデビュー。『オードリー』(00年)などで人気を博し、04年の大河ドラマ『新選組!』の山南敬助役でブレイク。08年の大河ドラマ『篤姫』の徳川家定役も好評を得る。『クライマーズ・ハイ』(08年)の鬼気迫る記者・佐山役や、『南極料理人』(09年)の飄々とした西村役など、映画でも活躍。待機作に『日輪の遺産』(2011年公開予定)がある。『武士の家計簿』オフィシャルサイトは www.bushikake.jp
微笑んでいる。
役や時代の背景を踏まえて答えてくれる。
ときにうつむいたり腕組みしたり天を仰ぐ。
自分がどう考えているのかを探ってる(ように見える)。
ひとつひとつの事柄に姿勢が真摯だ。
インタビューへの回答はもちろん、仕事への取り組み方も。
ガチガチではない。飄々である。
ガチガチだった時代から、徐々に抜けたらしい。
「細かいテクニックはぼく自身興味がないのと、主婦の方に言うのは『釈迦に説法』なので何とも言えないんです」と、堺 雅人は答える。
「何とも言えない」ので、普通はここで終わる。でも面白いのはこれからだ。
何らかの答えが出てくるのだ。それらがことごとく、よくできた短いコラムを読んでいるみたいに面白い。
映画『武士の家計簿』のインタビューでの話である。
映画は、幕末の加賀藩で、代々藩の経理係をつとめた猪山家三代の物語。“そろばんバカ”と呼ばれた下級武士・猪山直之が、家財道具を処分し倹約し、借金の返済を試みる…だけでなく藩の財政をも切り盛りする姿を描く。堺 雅人が“そろばんバカ”その人だ。
そしてこの取材の現場、少し変わっていて、まず映画に関する取材は5誌合同。冒頭のひとことに「主婦」という言葉が出ているのは、これが主婦向け雑誌の質問に対する回答だから。
問いはこうだ。
「作中に出てくる節約法で、現代の主婦が応用できそうなものは?」
「家で女性にこんなことをされると“ヤラレタ!”と思うようなシーンが作中にあれば教えてください」
人の価値観ではなく、自分で考えた自分の価値観
「何とも言えない」のは節約テクニックに関して。「ヤラレタ」については、意外な答えが得られることになる。
猪山家の3人の女性(祖母:草笛光子・母:松坂慶子・妻:仲間由紀恵)に関する話である。
「どんとした存在感というんですかね。その家にいてすべてを見守って、受け入れてくれている。隣に仲間さんがいらっしゃるだけで安心するところがあって。直之自身はすぐ視野が狭くなってまっすぐにものを見たがるところがあるんですが、それを優しく包み込む松坂さんの視線、草笛さんの存在…生き物としてのあったかさっていうのかな。“お母さん”“奥さん”っていう人たちは、ご自身が思ってる以上にご主人から頼りにされてるような気がするんですよ。ただそこにいるだけで『ヤラレタ』って思うときもあるんですね」
物語に息づく、“清貧の思想”や“慎ましさ”といった考え方には「実はあんまり興味がない」と笑う。猪山直之が家財道具を売り払って一家の借金を返すということは、こと武士道に照らし合わせると非常にかっこ悪い行いだ。「ぼくは、正しいかどうかわからないし、ダメだったらちゃんと責任を取るけれども、人の価値観ではなく自分で考えた自分の価値観で、“ウチはこうなんだ”って言い切る強さ、がかっこいいと思いました」
称えるだけではない。一方で「相当食えない男」だとも評する。
「だから“現実的な動機”もひとつ置いておく。子どもをしつけるシーンでも、当時の親子ってプライベート100%ではなくてどこかオフィシャルな部分もあったと思うんですよ。同じ主君に仕える同僚という意識において。だから子どもに(そろばんを)早く仕込めば仕込むほど、お国にとってはプラスなわけです。実際に直之は息子の成之に、年をごまかして早めに就職させるんですけど、当時の武家社会は年功序列の終身雇用ですから、先に就職した方が得なんですよ。算術なんて遺伝する才能じゃないので、ダメとわかれば早めに見切って養子に出してあげないといけない」
己の決めたルールに己で責任を持って従うには違いないが、それに殉ずるわけではない、ということだ。
「『武士は食わねど高楊枝』的な、地に足がついてないようなところで役を作りがちなんですけど、もうちょっと懐勘定的なことも含めて、現実の動機も混ぜるっていうことで、食えないヤツということは意識してみました」
…という部分をアタマのどこかにとどめ置いて映画を観ると、確実に役柄の印象が変わる。
合同取材の最後に堺 雅人は例の主婦向け雑誌を手にして言った。
「これいただいていっていいですか?“フォンデュ鍋”っていう特集がどうも気になっちゃって」
人の価値観ではなく、自分で考えた自分の価値観
「何とも言えない」のは節約テクニックに関して。「ヤラレタ」については、意外な答えが得られることになる。
猪山家の3人の女性(祖母:草笛光子・母:松坂慶子・妻:仲間由紀恵)に関する話である。
「どんとした存在感というんですかね。その家にいてすべてを見守って、受け入れてくれている。隣に仲間さんがいらっしゃるだけで安心するところがあって。直之自身はすぐ視野が狭くなってまっすぐにものを見たがるところがあるんですが、それを優しく包み込む松坂さんの視線、草笛さんの存在…生き物としてのあったかさっていうのかな。“お母さん”“奥さん”っていう人たちは、ご自身が思ってる以上にご主人から頼りにされてるような気がするんですよ。ただそこにいるだけで『ヤラレタ』って思うときもあるんですね」
物語に息づく、“清貧の思想”や“慎ましさ”といった考え方には「実はあんまり興味がない」と笑う。猪山直之が家財道具を売り払って一家の借金を返すということは、こと武士道に照らし合わせると非常にかっこ悪い行いだ。「ぼくは、正しいかどうかわからないし、ダメだったらちゃんと責任を取るけれども、人の価値観ではなく自分で考えた自分の価値観で、“ウチはこうなんだ”って言い切る強さ、がかっこいいと思いました」
称えるだけではない。一方で「相当食えない男」だとも評する。
「だから“現実的な動機”もひとつ置いておく。子どもをしつけるシーンでも、当時の親子ってプライベート100%ではなくてどこかオフィシャルな部分もあったと思うんですよ。同じ主君に仕える同僚という意識において。だから子どもに(そろばんを)早く仕込めば仕込むほど、お国にとってはプラスなわけです。実際に直之は息子の成之に、年をごまかして早めに就職させるんですけど、当時の武家社会は年功序列の終身雇用ですから、先に就職した方が得なんですよ。算術なんて遺伝する才能じゃないので、ダメとわかれば早めに見切って養子に出してあげないといけない」
己の決めたルールに己で責任を持って従うには違いないが、それに殉ずるわけではない、ということだ。
「『武士は食わねど高楊枝』的な、地に足がついてないようなところで役を作りがちなんですけど、もうちょっと懐勘定的なことも含めて、現実の動機も混ぜるっていうことで、食えないヤツということは意識してみました」
…という部分をアタマのどこかにとどめ置いて映画を観ると、確実に役柄の印象が変わる。
合同取材の最後に堺 雅人は例の主婦向け雑誌を手にして言った。
「これいただいていっていいですか?“フォンデュ鍋”っていう特集がどうも気になっちゃって」
理論とか理念とかより、目の前の問題をどうするか
監督の森田芳光と中村雅俊と一緒に取材を受けたとき「“そろばんバカ”の主人公と似ている部分は?」という質問を何度か受け、「全然似てません」と答えるたび、2人から「そんなことねえよ!(笑)」と突っ込まれたという。
「“不器用だな、そろばんバカだな”と思いながら演じてたんです(笑)。そういうぼくが“役者バカ”みたいに見えてたのかもしれないですね。森田さんと雅俊さんに言われるのはいやなことではないです。自分の姿は自分じゃ見えないのかもしれませんね」
猪山直之はそろばんに頼り、自身のルールを定めた。同じような“よって立つところ”は…俳優・堺 雅人には…「ないですないです」と、笑う。
「ただ、この映画って“武士はこうなるべき”っていうだいたいのルールは決まってて、“背に腹は代えられぬ”思いでそれを逸脱しちゃうストーリーなんですよね。そこは堺 雅人という俳優にもあると思います。ルールの逸脱が面白いんじゃないかな。自分のなかのルールを『この現場で、この状況だからちょっと変えまーす!』っていう。たとえば、ホントなら半日かけて撮るカットなのに、急に雨が降ってきて変更になる。手持ちのものだと完全にはできないけれども、やることになるのなら『これでいきます!』という変わり身。それが一番大切な気がします」
そろばんに比べると、なかなかにグニャグニャした地盤だ。
高校の演劇部から考えると俳優としてのキャリアは22年にわたる。最初はもっとカッチリキッチリしていたのではないだろうか。
「役者として“こうあらねばならない”ってことを一番考えていたのは、ぼくの場合でいうと、大学に入って劇団に入ったころですね。お客様からお金をいただくということで “自分はいっぱしの俳優だ”って意識を持つんです」
宮崎県の進学校から早稲田大学に進み、『劇団東京オレンジ』の旗揚げに参加。後に“早稲田のプリンス”として舞台はもちろん、比較的早い時期からドラマにも出演する。
「仕事も何もなくて、それを裏付ける技術が何もないときに“一番いいお芝居をしなきゃいけないのだ!”っていう思いを持つんですね。いいお芝居がなんなのかはまったくわからないのに、プロの俳優とは、“何かものすごいことをやっていかなきゃいけないのだ!”っていう思いにとらわれるだけで」
解くべき問題がないのに、解き方を一所懸命考えている状態だった。
「でも実際に仕事が入って、現場でやることが決まってくると、目に見えた形而下の問題になるので、理論とか理念とかあんまりいらないんですよね。できるかできないか、やれるかやれないかっていうだけ。どんなに不格好でもいいからひとつの形を出し続けるしか、たぶんやり方はないんですよ。どんなに高尚な志を持っていても、形にならなければゼロ。どんなにいびつになっても答えを出し、それには自分で責任を取っていかなくちゃならない。“仕事にする”っていうのは、たぶんそういうことだと思うんです」
“仕事にする”を最初に意識したのも、劇団に入ったとき。
「大学でお芝居始めるときには2カ月ぐらい悩みました。やるからには中退もするだろうなって思っていて。半ば出家するような気持ちでしたね。というのも“プロとして!”ってガッチガチに肩に力が入ってたから。そこからゆ~っくり、“俳優になろう”という気持ちが薄れていったんです」
大切なのは、その意識ではないのだ。「なろうと思うかどうかは関係なく、仕事をしていくことでしか俳優にはなれないんですよ。自分が“俳優だ!”って言い張っても、目の前のセリフがしゃべれなければ、俳優ではない。すべては後づけ、ぼく以外の人が決めることなんだなって、ゆっくりと気づいて、今も続けてるんですけど」
なろうと思わず、自然になりながら、楽しみもじわじわと広がっている。
「みんなでワイワイものを作っていく文化祭的な喜びは、高校時代からありました。自分の感情を表現する喜びというのも、高校の演劇部レベルでも感じられる楽しみだったし。それがお客さんに伝わって喜んでもらえる喜びが得られるようになったのは、ずいぶん最近のことのような気がします。演じることでお金をいただくようになって社会的な責任も感じるようになって、そういう部分に付随するいろんな喜びをまた今、少しずつ教わってるような感じがしてますね」
野望も目標もない。共演したい俳優も、仕事をしたい監督もいない。
「もっとうまくやりたいっていう欲ははありますけど、この役やりたいという欲はないですねえ」
欲しいものは「次の役(笑)」。
共演者も監督も役柄もそこに全部載っている。オファーがあればまた新たなルールで取り組むのだろう。
趣味を尋ねると「うーん、とくに…」とニコニコ笑っている。幸せですね、と言ったら「確かに」と破顔一笑した。
宮崎県屈指の進学校で演劇部に所属。「膨大な情報を効率よく覚えていくということを3年間やらなきゃいけないわけです。それに息が詰まっちゃって。しっかりした指導者と先輩がいなくて、やることのあんまり決まっていない文化部でのんびりしたかったんです。そこで自分が何をしたいのかをゆっくり考えようと…あ、でも当時はせいぜい“誰も威張ってる人がいないところがいいなあ”程度の理由です(笑)」…という、R25ならぬR15時代













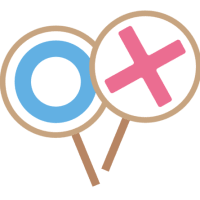






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます