先日、家族で動物園に行ったとき、車内でふと、旦那が「そういえば、六月ってなんていうんだっけ?」と尋ねてきたので、「水無月」と答えました。
旦那の疑問符を取り払うべく、念のため携帯で確かめたことが発端の、出雲神話紀行のはじまりはじまり~(笑)。
「水無月」と検索すると、六月の意味のほかに、和菓子の名前だったり、駆逐艦の名前だったりします。
梅雨の時期で、尚且つ田植えのために田んぼに水はる時期なのに水のない月とはこれいかに。
「水無月」の「無」とは、ない、という意味ではないのでした。
「無」とはひらがなの「の」の当て字。古来ではそういう使い方もよくあったようです。
ですから、「水無月」は「水のない月」ではなく「水の月」だったわけです。
では「神無月」は?
私の頭に疑問が浮かびました。
出雲の神事で十月は「神在月」であり、他の地域では「神無月」というと聞いたことがあるけど、ほんとは「神の月」なの??
「神無月」には諸説ありますが、一応「神のいない月」というのも俗説通りでありのようです。
その場合。
出雲のほかに、諏訪大社も「神在月」なんだとか。
諏訪大社の祭神が、あんまり体の大きい神なので、他の神が遠慮して「君は出雲に来なくてもいいよ、大変そうだから」といい、十月も神がいるので、諏訪も「神在月」なんだとか。
では、神のいない他の地域はどうなっているの??
「神無月」のほかの地域は、そのひと月だけ守護神のいないことになります。
留守を預かるのは恵比寿神が多いようで、それで恵比寿講を行う地域が多いんだとか。
でも、なんで恵比寿さん??
恵比寿神について調べてみました。
恵比寿さんは七福神の一人ですが、鯛を抱えて釣竿持ってるのでわかるように、漁業の神様です。
海に関係の深い神様なわけですね。
恵比寿さんについては諸説ありますが、とくに注目したのが、海から漂着したものを祀る神様だということ。
クジラやイルカなども漂着すれば先人はみな食して感謝したわけですね。
そういうものを祀る。疎かにすると祟るものだったわけですかね?漂着物というものは。
無論、海で遭難したり、津波などで攫われたものもあるのでしょうね…。
祀る気持ちがわかります。
そして、恵比寿さんを祭る神社でしばしば合祀されている神がヒルコ神と事代主命。
ヒルコ神はイザナミイザナギの最初の子と言われ、不具だったため海に流されてしまいます。
漂着物の神となるため、恵比寿神と同一視されるわけですね。
また、事代主命。
出雲の主神大国主命の息子であり、彼の鶴の一声で国津神である出雲系の神から大和系である天津神の神へと国譲りが行われるわけですね。
国譲りの是非を問われた時、事代主命は、漁をしている最中でした。
恵比寿神の、鯛を抱えて釣竿を持っている姿は、この事代主命の時事にちなんだものだったのです。
神無月の神事は、父の所に参集する神々の留守を、その息子が預かる、という機構も含んでいたんですね。
ふと、いろいろ調べ物をすると面白過ぎて止まらなくなります(^^)。










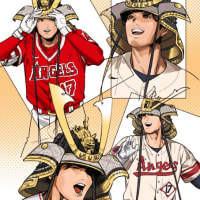









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます