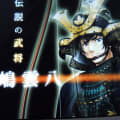もう15年前のこと、マリさんという方と
こんなを話をしたことを思い出しました。
「”お月見どろぼう”って知ってますか…?
十五夜の夜、お月さまに供えたお団子を
近くに住む子供たちが、みんなで順番に
各家庭を回って、もらいにいく風習…。
私、ここに嫁いで来て初めて知りました。」

「それは面白い…!私も初めて聞きました。
日本版ハロウィンみたいで楽しそうですね。」
「いや、さすがに仮装はしませんよ~。
そしてね。
そして今の時代、芋やお団子を供えません。
個包装してあるお菓子、”じゃがりこ”や
”うまい棒”、”きのこの山”など供えます。」
「夜になるとやってくる子ども達のために、
お菓子をいっぱい用意しておきます。」
「なるほど…。面白い風習ですね。」
”お月見どろぼう”の風習、私は子供時代から
一度も体験したことはありませんでした。
この話を聞いて、初めて知りました。
どうやらその風習は、ある特定の地域で
古くから伝わっているもののようですね。
都市部では廃れてしまって、郊外だけに
残されている風習だとも言われています。
今年になって9月21日、お月見の日に
また”お月見どろぼう”の話を聞きました。

「今日は”お月見どろぼう”の日ですね。
お月さまにお供えするお菓子をお土産に
持って来ました。栗蒸しようかんです。」
「これ、中津川で人気のお店のものです。
大人用の上等なお菓子だから、お供えの後、
近所の子供たちにあげちゃわないでね。」
「今日は子供時代に戻って、”お月見泥棒”
思い出して、お菓子を味わいましょう。」

この日は、また別の方からもお土産の
お菓子、”抹茶あんみつ”を頂きました。
「これ、地元で人気のお店のものです。
わかりにくい場所にあるお店なのですが、
なんと今日、JR駅の”ベルマート”でも
売っていました。食べてみてね~。」
「今日は、”お月見どろぼう”の日なので、
大人もお菓子を味わいましょうね。」
抹茶あんみつ、上品な味わいでした。
子供時代に”お月見どろぼう”を体験した方、
この地区には案外多いみたいですね。
では”お月見どろぼう”、その起源は…?
どの地区で残っているのかしら…?

”十五夜の月見芋”という民話集によると、
この話は、西暦444年の天皇暗殺による
皇位継承のトラブルに由来するそうです。
皇位への野望を抱いていたものにより、
皇位継承の有力候補だった、市辺押盤王
(いちべのおしはおう)は殺害されました。
さらにその2人の皇子、億計王(おけおう)と
弘計王(をけおう)を殺害しようとする
動きがあり、幼い皇子は家臣と共に
追手から逃れ、尾張の地を目指しました。
奈良の都から持ってきた食料は、
逃亡の旅で段々と乏しくなりました。
途中、皇子たち一行が食べ物に困っていると
地元の村人が教えてくれました。
「この地では、十五夜の夜、お月さまに
お供えした月見芋は、誰でも自由に
食べてもいいという風習があります。」
それは村人が、困っている皇子たち一行を
助けようとして、とっさについた嘘でした。
この地にそんな習慣はなかったのです。
さっそく皇子たちはお供えの芋を食べて、
尾張の国の真清田神社を目指しました。
それからこの辺り一帯では、「十五夜の
お月見のお供えは、誰でも食べていい。」
風習ができました。”お月見どろぼう”として
各地に広まっていったそうです。
さて、2人の皇子は、無事に追っ手を逃れ
第23代、第24代天皇になったそうです。
気が遠くなるほど昔の話ですねぇ~。
すると…、”お月見どろぼう”の風習も
気が遠くなるほど長い間、この地に
伝承されているのですね。
9月21日、お月見の夜はお天気が悪く、
お月さまは眺められませんでしたが、
おいしいお菓子をいただきました。