新潟県は雪氷熱を活用したデータセンター(DC)で、首都圏などの関連企業誘致に乗り出すそうです。コンピューターのデータセンターはコンピューター機器の放熱で、大量の熱を出します。この冷却に、県内に大量にある雪氷を活用。雪氷熱の冷風をデータセンターへ逆にデータセンターから出る排熱をハウス栽培(植物工場)の暖房に利用したりなどで熱エネルギーを有効利用、関連コストを削減する。データセンターの冷房代を抑えられること、県が首都圏の反対側にあるので首都圏で地震や津波など大災害が起きた場合に備えたデータのバックアップとしてデータセンターの利点を訴えて、企業の誘致に活用するそうです。
冬期に降り積もった雪や、凍結した氷などを、冷熱を必要とする季節まで保管し、冷熱源としてその冷気や溶けた冷水を利用する雪氷熱システムは現在も上越市や南魚沼市周辺の豪雪地帯を中心に、コメや日本酒の貯蔵、ワイナリーなどに活用されています。実例
こうした大雪という地域性を生かしたエネルギー創出は大切です。柏崎刈羽原発には、広大な敷地、港、送電網がありますから、ここの火力発電所を建設すればよいと思います。データセンターと同じく首都圏で地震や津波など大災害が起きた場合にも生き残ります。
東京電力の福島県の原発は、シビアアクシデント(過酷事故)をおこしました。
「何故もっと怒らないのかと避難先でよく問われる」と、友人が言う。私はいつも思う。『もし、原発事故が他で起きていたなら、他県の人々はどうだっただろう?』と。怒りには相当な力が要る。だが、理不尽は想像以上にその力を削ぐ。「今は生活だけで精一杯だ」と言い、友人は避難先へ帰った。
先回の7/8は、「技術委員会でみた、原子力ムラの人間喜劇」でお伝えしました。
全国市民オンブズマン連絡会議の「原発審議会委員寄付調査について」(8/20)で明らかになった昨年の3.11後も電事連の企業や原発関連メーカーから寄付を頂いていた専門家リストに名前の挙がっている委員がお一人、橋爪秀利氏(東北大学大学院工学研究科教授)は欠席でしたが、相変わらずの原子力ムラの人間喜劇がありました。

耐震性について次のようなやり取りがありました。
国会事故調は、
新耐震指針(2006年決定)によるバックチェックが終了していない。7設備については2008~2009年に中間報告されたが、他はまだである。1Fは1970年代前半に265ガルで設計された。新耐震指針でSsは600ガルになったが、265で設計された設備・機器が600でもつのか、耐力はあったのかチェックされないまま3.11となった。
事故の直接原因が全て津波か、地震が関わっていないかどうか検証されねばならない。
1号機A系の非常用発電機は、津波が発電所の取水口のある海岸に到達した時刻より前に、15時35~36分頃に停止している。
この非常用発電機については、鈴木元衛委員が「日本では非常用発電機の耐震テストは、多度津の加振台で40秒ほど揺らしただけである。どのくらいもつのか、実験が必要である。地震で損傷した可能性はある。」

国会事故調は、
原子炉内配管の地震での破損があった可能性がある。
1号機の地震後の原子炉の圧力や水位の変化から1号機では漏えい(地震で配管が破損してもれる)面積が0.3?以下の小破口の冷却材(炉水)喪失事故の可能性を否定できない。
そのような小規模な漏洩があると、原子炉の圧力は低下するが、
1号機IC(非常用復水器)を運転員は「運転員3人で止めた。急激に原子炉圧力が下がってきたので、どこか漏れているのではないか、一度止めてみたいと思い、上司に確認しOKもとり、止めた」と言っている。
中央制御室のホワイトボードにタービン建屋1階の原子炉側の通路(通称「松の廊下」)で「シューシュー音」と記載がある。
逆に、漏洩がなければ原子炉圧力は上昇します、その圧力を逃すSR弁(主蒸気逃し安全弁)作動の音が、「2、3号機では、SR弁が開くごとに大きな音がしたが、1号機は非常に静かだった。」
これに対し、鈴木元衛委員は「確かな証拠はなく、結論はだせない。どちらもありうる。可能性を入れて考えるべきというのが国会事故調の考えだと思う。1号機のSR弁が作動音はしなかったけれど開いたとするなら、原子力安全基盤機構(JNES・保安院の外郭団体)も東電も、きちんと説明すべきだ。」とコメントしました。
香山委員
が、先回7/8にも東電擁護になる発言を繰り返した香山晃氏(室蘭工業大学・教授)は、専門用語をつらね重箱の隅を突く様な質問を繰り返し「報告害の表現が断定的だ」とか「推定で書いている」「論理も証拠もない。」「論文は事実が正しいか、論理が正しいか審査される。」「査読を受ける論文ですと出版されない。」と批判しました。
国会事故調側は「その査読を受ける学術論文、学会の活動を通じて積み上げてきた原子力に関する知見があったのに、事故は起こったんです。」「事故の調査委員会の報告書が複数でるのは当たり前。学術論文とは異なった事故報告書が、世界の中で次の事故を防いだ、という事実があります。」「報告書が、どんな書き方であろうと教訓を得ようとする姿勢がないと。」と応じました。
香山委員は「論理のすり替えだ」などと学会ルールに固執し、教訓を得ようとする姿勢をしませんでした。
この耐震性の問題は、新耐震指針(2006年決定)の見直し、そして全国の原発の地震での危険性の再評価に直結します。「1Fは1970年代前半に265ガルで設計された。新耐震指針でSsは600ガルになったが、265で設計された設備・機器が600でもつのか、耐力はあったのかチェックされないまま3.11となった。」この事態を繰り返すわけには行きません。それだけに想定外をなくす努力が必要なのに、香山委員はそれが見られません。
全国の17の原子力発電所、50機の原子炉の運転再開や廃炉に直結します。香山委員は、先回と同じく眼前に座る東京電力の幹部社員に配慮したのでしょうか?
そして、7/8でも笑わせてくれた衣笠善博委員は、「(国会事故調報告書の)修正版を作る予定はあるのか?いつ作るのか?このまま固定化すると、これは何だということになる。」と質問しました。

この方は、通産省の工業技術院・地質調査所(現・産業技術総合研究所)で地震地質課長や主席研究官の研究職の技官で、退官後は東京工業大学 教授を務め、現在は東京工業大学名誉教授。彼は柏崎刈羽原発をはじめ日本中のほとんどすべての原発の審査に関わっています。
中国電力が島根原発3号機の原子炉設置許可申請前に実施した活断層調査で中電に対して技術指導を行い、その一方、中電からの申請を審査する経済産業省の原子力安全・保安院の委員も兼ねて、島根原発の安全審査を実施した際、保安院の委員として国の審査をおこなう、こういう形で日本中のほとんどすべての原発の審査に関わっています。
島根原発の活断層は、彼の指導と審査ではて最大 8km で、それで地震の大きさを設定して島根原発は建設されています。その後の掘削調査で22kmと判明しています。活断層が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
志賀原発の審査でもひとつながりの活断層を3つに分けて評価し、想定地震規模を小さくしています。このため、'07年の能登半島地震では、志賀原発は〝想定外〟の揺れに襲われました。柏崎刈羽原発では、原発から20km以内に活断層はないとしていますが、中越沖地震は14km離れた断層です。 動画
福島第一原発の耐震性の再評価(バックチェック)2009年では大地震・大津波の可能性を指摘する声を無視し、周辺の断層の長さを〝値切る〟ことに終始し、津波は論議さえしていません。
衣笠委員は、3.11に関して業務上過失致死傷罪で、東京地検に告発されています。 告発状
ですから、3.11で大地震で原発に破損が生じた可能性を指摘する公文書の国会事故調報告書は、潰しておきたいものです。それで「(国会事故調報告書の)修正版を作る予定はあるのか?いつ作るのか?このまま固定化すると、これは何だということになる。」
国会事故調側は「報告書を出してから法の定めで委員会は解散したので、報告書を書き直すことはない。」
何故、このような人たちが選ばれたのでしょうか。検討のための専門家委員会の人事案の原案は県の原子力安全対策課が作り、東電の了解を得て知事が任命する仕組みとの未確認情報があります。
電事連の企業や原発関連メーカーから寄付を頂戴していた方や県民のために教訓を得ようとする姿勢がない方、これまで柏崎刈羽原発の国の審査に関わって利益相反する方は委員を辞めるべきではないでしょうか?














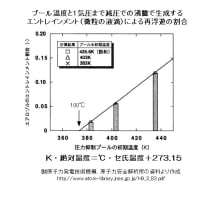





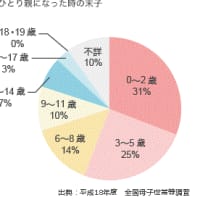
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます