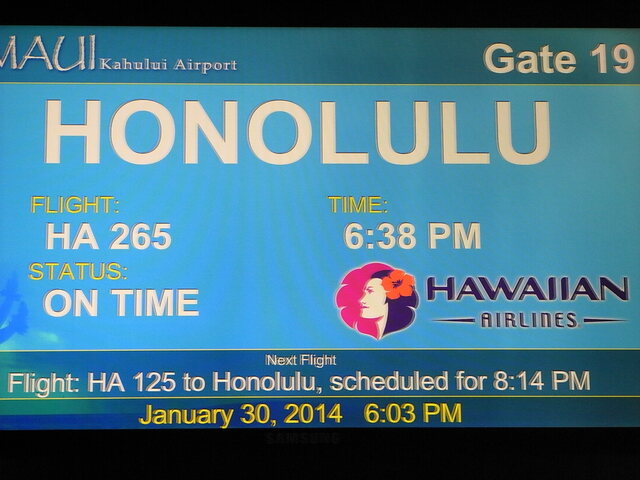2021年初旬、みずほ銀行はシステム障害が起きやすい銀行というイメージをさらに強固なものとした。個々の障害には技術的説明が付けられるだろうが、本質的な問題は人間組織として未だに「One」になれていないということではないか。巨大なコンピューターシステムの裏側には、常に泥臭い人間模様があるのだ。そしてこういったパターンは、種類や規模を超えて日本のいろんな大組織にあるような気がする。
銀行とはコンピューターシステムである
今日の銀行や金融機関といったものの実体(実態)は、ほぼイコール「コンピューターシステム」である。お金というものが多くの人間たちの共同幻想によって成り立っていると言うことをよく表しているが、つまり今日の銀行を語るには、それを駆動しているコンピューターシステムについて、ある程度の理解は必要と言うことになる。銀行の3大業務は「預金」「融資」「為替」であるが、システム的な捉え方では「〇〇系システム」というふうに大別する。
銀行のシステムを語るときによく「勘定系システム」とか「情報系システム」といった言葉が出てくる。銀行を駆動しているシステムは、なにも預金残高の管理をするものだけではない。ざっと列挙すると①勘定系、②情報系、③証券系、④国際系、⑤営業店系、といったところだろうか。
勘定系はまさに口座、資金決済、入出金などを管理しており、それはつまりATMやネットバンキングもこのシステムに接続されているということである。また情報系は銀行の内部管理システムと言え、一般社会にとっては縁がない。
これらのうちもっとも大規模で重要なのはもちろん「勘定系」である。ただし「勘定系システム」といっても具体的にどの範囲を指すのかは、言う人によっても状況によっても変わってくる。じつはその道の技術者と呼ばれる人物でも、よくわからないまま使っていることも少なくない。
ちなみにこういった銀行のシステムは、一般の我々が日常的に目にするようなパソコンだとか会社の情報処理部門にあるようなサーバーなどとは全く次元が違うコンピューターで処理される。また本番系と待機系といって、そっくり同じ大規模システムを常時稼働させており、たとえデータセンターが大震災で壊滅しようとも、短時間で待機系に切り替えて運用を継続できるようになっている。これに比べれば「おもちゃのようにいい加減な」パソコンやPCサーバーなどで世の中の預金管理をすることなど考えられない。
コンピューターシステム以前の問題
30代以上の方なら、みずほ銀行が複数の銀行の合併によって出来上がったことはよくご存じのはずだ。御多分に洩れず銀行業界も「〇〇ホールディングス」などという持ち株組織を作ったりするものだから経緯を描くとややこしくなるが、要は「富士銀行」、「第一勧業銀行」、「日本興業銀行」がひとつになって「みずほ銀行」と名乗っている、と理解すればわかりやすい。ということは、それまでバラバラだったコンピューターシステムを何らかの形で統合する必要があったわけだ。
すなわち富士銀行が使っていたIBM製のシステム、第一勧業銀行が使っていた富士通製のシステム、そして日本興業銀行が使っていた日立製のシステムを統合すると言うことだ(いずれも勘定系システムに限っての話)。
ただし、2021年現在の勘定系システムは「MINORI」と呼ばれる(いちおう)一から作り直したもので「旧みずほ銀行」「旧みずほコーポレート銀行」「旧みずほ信託銀行」のシステムを統合したものである。
通常なら、既存のどれかひとつのシステムにまとめてしまう「片寄せ」を行うのだが、メガバンク級のシステムを一から構築していくというのはおそらく前例がないチャレンジであった。ただこのシステムも記憶のいい方ならご承知のとおり、運用開始を再三延期してきた経緯がある。
さて「システム統合」といっても話は容易ではない。Androidスマホで人気が出たアプリをiPhoneでも使えるようにしようなどといった技術レベルとはまるで話が異なる。
それだけではない。そもそも銀行という仕事における言葉の使い方やその意味、概念すら出身銀行によって違うのだ。すなわちコンピューター云々の前に「これが銀行業界用語」と思いこんでいたものが、「自分たちローカル用語」だった、というレベルから話が始まるのである。
「おなじ大手都市銀行だし、そもそもガッチリ法規制がある業界だから、似たような仕事してんじゃないの?」というイメージが強いかもしれない。しかし実際は、それぞれの銀行ごとに非常に閉鎖的な職人集団のようになっている。いうなれば、それぞれの「金貸し」としての論理や哲学、世の中の見え方、整理のしかたが全く異なるのである。
じつは筆者は、この複数銀行それぞれの業界用語、専門用語を取りまとめるプロジェクトの端くれとして働いていた時期がある。本来「MINORI」の開発が完了するはずだった2016年頃のことである。もちろん派遣社員として月単位契約で働いていた立場であり、辞書整備のプロジェクト全体が見える立場にいたわけではない。
しかし「これ(銀行システム統合)はある意味、無理々々プロジェクトではないか」と感じていたのである。「一事が万事」と言うつもりはないが、少なくとも現場(隣接する現場も含めて)の一体感は皆無であったし、自分たちはいったいどこへ向けて努力しているのかもわからない状況だった。つまり「One」などという空気はおよそ感じられなかったのである。
言葉を言葉で説明する
辞書整備の仕事はほとんど「ICT」というより、いわば「国語審議会」とでもいうような感じになる。
これはいま筆者がテキトーに造った語だが、「期日前解約当座貸越仮勘定」みたいなわけのわからない言葉があったとする。そしてこれがいかなる定義やイメージをもって理解されるかが、出身銀行によって違っていたり、「なんじゃそりゃぁ?」といった反応となったりするわけである。もちろんこれでは仕事にならないから、いわば「みずほの国語辞典」を作らねばならないと言うことになる。
そしてこのような作業を金融・銀行業界の経験もない、そして文学部卒でもない、筆者のような単なる「ICT労務者」が集まって議論していたりするのである。金田一先生に怒鳴られそうである。
いちど筆者は、「この解説文の読点の位置だと係り受けの誤解が生じるのではないか」といったことをリーダーに進言したことがあった。即刻却下されたが、そのリーダーはなぜ自信をもってそう断言するのかを説明できなかった。そうしてその優れたリーダーの判断がすべてという状況下で、用語と解説文がギッシリ並んだエクセルシートと格闘する日々が続いた。
のちに周囲の人たちやリーダー本人から聞いたところによれば、「自分は小説を人並外れてたくさん読んでいるから文章がわかるのだ」という説明であった。筆者は一気に勤労意欲をそがれてしまったことを鮮明に覚えている。
もちろん、最終的にチェックしたり責任を持って判断したりする役割の人物・組織もどこかに存在するのだろうと思っていたのだが、それについて聞かされたことは一度もない。
さらに強烈な疑問を持ったのは、ひとつに統合されているかに見えていたシステムが、じつはIBM、富士通、日立の各システムが独立して動作している上位に、あたかもひとつのシステムであるかのように見せるための、いわば「表皮システム」をかぶせているだけだと明かされた時だ。
統合システムの地底には、しっかりと旧IBM、旧富士通、旧日立のそれぞれのシステムが息づいていたのである。
ただ、この時の「システム」が具体的にどんなもので、何と関連していたかは書かない。加えて2021年現在でそれがどう変わっているか、それとも変わっていないかもわからない(当然だが守秘義務契約もある)。
これもまた前世紀型リーダーシップなのか
去る2019年7月、みずほ銀行はようやく勘定系システムの完全な刷新を完了した(すべての既存データの移行完了)。「MINORI」と命名されている。「瑞穂の実り」ということなのだろか。
しかし、みずほ銀行で働く(働いてきた)現場の人々、システム統合・開発に携わってきた人々は、三行合併が発表された1999年夏ごろから、まさに組織の論理の中で仕事や人生を翻弄されてきたといえるのかもしれない。
かつて「One」という単語をキャッチコピーなどに取り入れる大企業が散見される時代があった。それは組織の統廃合や事業売却などで、人間組織としての一体感が失われた企業が、自分たち自身への掛け声として使っていたような気がする。
なぜなら、短い期間に組織の組み直しを繰り返したために、そこに所属する構成員の一体感が急速に失われていったからだ。
しかし組織のリーダー層も、変化が激しく先の見えない社会状況において、次に何をすればよいかわからないというのが偽らざるところなのではないか。
たとえば「日本」という言葉を冠する名前の大組織はたくさんあるが、そういった大規模な組織ほど自分たちの組織をとらえきることが出来ず、ある意味コントロール不能な状況になっているのではないか。
正社員や派遣社員といった雇用形態に関係なく、あるいは組織内のポジションに関係なく、大組織に所属している構成員たちは集団主義の兵隊ではない。
いつまでも20世紀の発想、高度成長期の成功体験がこびりついたままのリーダー、オーナーの下(もと)では、構成員一人ひとりの幸福度を上げ、より良い価値を社会に生み出していくなどということは無理な時代になっているのではないだろうか。