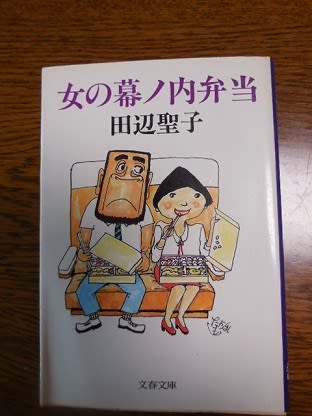
2002年(平成14年)
・1月20日(日)
今日、初七日だが、法要は葬式の時に併せて済んでいる。
近来はどこも、そのようになさるよしである。
十五日が通夜、十六日が葬式、
日記なんて書いてるひまはなかった。
自宅と西宮山手会館、あとはタクシー、
そして来て下さった方々への挨拶ばかりで、
埋め尽くされた時間。
十五日の新聞に死亡記事が出たので、どっと弔電が届く。
二百八十通あまり。なつかしい名もあった。
彼と共通の古なじみの名もあって、
「パパ、見て見て、〇〇ちゃんから来た!」と言いたくなり、
怱忙の中、笑いたくなった。
笑う、といえば、葬儀社との打ち合わせで、
決めないといけないことがあった。
葬儀のスタイルや飾りつけのクラス、
式の間じゅう流すBGM、
これは小学唱歌の「おぼろ月夜」「ふるさと」「冬景色」、
の三曲をメドレーで、などは指定してあったが、
祭壇に飾る写真がまだだった。
私は、あるパーティに際し、彼が呵々大笑している写真を選んだ。
自分が笑うのも、人が笑うのを見るのも好きな男だった。
いちばん小さなミッコに、
「お父ちゃんの好きなのは、笑い声」と教えた彼。
しかし、その笑いは、嘲笑や憫笑ではない。
優越感からでもなく、苦笑、冷笑でもないのは無論である。
赤と黒の格子のシャツ、青いセーターという若者風のいでたち。
彼は年相応の格好が似合わない男で、
ヨーロッパ紳士よりもアメリカ青年風で決めた方がぴったり。
着るものはみな、私が見立てている。
老来、いよいよ寛闊な身なりを好むようになり、
ネクタイなどは無用の長物となりはてた。
仕事も辞めてからは、腕時計、ライターなど、
ブランド品であれ何であれ、欲しがる人にみな与えてしまう。
そんな彼には、人生のしめくくりに、
格子縞のシャツと空色セーター、なんて軽装がぴったりだ。
五分刈りの短髪、太いまゆ、
ふだんはどんぐり眼が、大笑いしているので細められて、
口が大きく開いて、上下の白い歯といい配色。
こんな写真を葬式の祭壇に飾るなんて。
私も、世外人だから、いいか。
世捨て人ではなく、世間の決まりの外で生きてるもんな。
ミド嬢も弟もこの写真に賛成してくれた。
「義兄さんらしい」と弟も言う。
通夜に東京から出版社の重役さんがたが見え、恐縮した。
「明日、十六日は芥川賞、直木賞の選考会なので、
申し訳ありませんが、お葬式には参れません。
せめてお通夜に、と」
とねんごろなご挨拶。
「私こそ、直木賞選考委員の一人なのに、欠席になってしまって」
とお詫びする。仕事がらみの話も出て忙しい。
通夜は七時に終わり、二階で身内一同食事をとる。
宿泊施設になっているので、遠方のチュウやミッコは泊るという。
明日もあるから、と皆に言われて帰宅。
老母についていてくれるTさんが玄関を開けてくれ、
「お疲れさまですね。
おばあちゃまはもうお寝みです」
老母は疲れを案じて葬式に出席させないつもり。
(そうだ、喪主挨拶をしなきゃいけない)と思い出した。
葬儀社の人に、どのくらいの時間しゃべるのですか、
と聞くと、二十分くらいですね、と、そりゃ長い。
イスが足りなくて起っている人もいるだろうし、
短い方がいい。
まあ、何にせよ、呵々大笑の写真を掲げる以上は、
彼の懐抱する人生観くらいはしゃべらないと。
といっても、同業の医師(せんせい)や学友たちも、
来て下さるかもしれないから、あまりおふざけがすぎては、
(物書きはあんなものか)と思われ、
日本文芸家協会の品位を汚す、というものである。
「何を話すかなあ、おっちゃん」
私は葬儀場の棺の中の彼に言う。
「こら~。ちゃんと笑いとれよ~っ。
ワシの葬式じゃ。笑うてナンボ、ちゅう奴よ。
笑わしたらんかい」と彼。
笑わしたらんかい、というのは、
笑わせてやれの命令形を大阪弁風におちょくったもの。
「死者(死んだもん)がナニ言うとんねん!」
「うらやましかったら、早よ、来んかい」
ベッドで思い出したのは一茶の句だった。
<露ちるや むさいこの世に 用なしと>
まるでおっちゃんの心境じゃないか。
<生きのこり 生きのこりたる 寒さかな>
これは私のことを言ったみたいな一茶の句。
そして私の句は、司馬遼太郎さんに捧げた句。
<男みな なに死に急ぐ 菜の花忌>



(次回へ)
























