皮膚のカサカサは・・皮膚の脂・油が足りないからではなく・・セラミドの欠乏による変化ですので・・誤解のないように・・くれぐれも油や脂の摂取にはご注意下さい・・逆効果です。女性のばあいは・・本当にツルツルになるまでは・・セラミド配合の化粧品などがいいかも。
22年も前の話です・・日本食の大御所:故:湯木貞一さん(日本料理“吉兆”創業者)の手に直接触れる機会がありましたが、94歳の男の手にしては・・白くて繊細で・・上品で艶があり・・美しいこと・・非常に驚いた記憶があります ・・・今頃やっとその謎が解けました。
RAP食なら・・お肌もツルツルになる・・理由がお判りだと思います。信じて続行下さい。
2017年2月18日追記
<プラークを治したい方・・トコロテンは・・常用摂取を心がけましょう>
2月の診察室で、プラークの改善が鈍化する症例が多いのですが、そのような場合には「トコロテンを夏の間は食べていましたが・・冬は冷たいので・・」という会話が非常にしばしばであるのに気付きました。
逆に、年末・年始のセレモニーを過ごしても、プラーク改善が継続している場合は「トコロテンは毎日食べています・・」という会話になっているのに・・気付きました。
現在、8カ所の血管エコーが5000例を軽く突破し、データを解析中ですが、野菜パワーに驚いています。プラーク改善に関係する因子として、人間の「心理・心構え」以外に、「マクロファージ活性」「血管内皮の状態」「食品内成分」の“4本の矢”がありますが、野菜の多食には「血管内皮の状態」「食品内成分」の状態を改善させる働きがある・・と考えるのが妥当な結果が得られました。
考えてみれば、海藻は海の野菜です。野菜の値が高騰した昨年の夏~秋・冬もトコロテン(オーガニック栽培)を食べていれば「お得」で良かったのです。
日本人の昼食は野菜不足になりがちです。私は昼にトコロテンを食べています・・冬もです。
「冬でも職場で冷たくないトコロテンを美味しく食べる方法」を伝授します。
1) トコロテンのパックから密封シール外し、ざるで水洗してパックに戻し、さらに水切り。
2) タレを入れ、ポットの熱湯をパックへ注ぎます(溢れる寸前まで)
3) よくかき混ぜていただきます・・冷たくないはずです
夏は熱湯の代わりに冷水を入れます。先入観は捨てるべきですね・・何でも実験結果が優先します。 (先入観があると科学は進歩しません。「動脈硬化を食い止めるために・・スタチン剤が必要」などがいい例です)
トコロテンを食べるとお腹いっぱいで・・・と言われる方がいますが、「ところてん」=「無農薬の煮野菜」なのですが・・。
2017年5月1日追記
<トコロテンがなぜ?プラーク改善に必須アイテムか>
この9年間のプラークと食品との関係の研究で、プラークを溜めやすい食品の研究は終わりに近づいています。・・3~4カ月単位の非常に時間のかかる確認作業でした・・。
これからは、プラークが改善しやすい食品に研究をシフトします。
2017年2月~4月にかけて・・100分の1mmの精度でプラークの肥厚を測定するたびに、しばしば「トコロテンの有り難さ」を確認出来ました。
動脈硬化改善のための必須推奨食品として、第1位はトコロテンです。
量と頻度の問題もあるでしょうが・・時々、モズクやメカブ、おきゅうと、ワカメなどの海藻を食する程度ではプラーク改善の実感がありません。
プラークを治す必要がある人は、毎日(週に6回以上は)トコロテン(最低150g)をいただきましょう。リスクレベル3~4の人で肥満の人は特に、毎日300g食べる努力をしましょう。その上で上記の海藻などを摂取するように心がけましょう。「継続は力なり」ですが、間違ったことを継続すると大変なことになります。
トコロテンや寒天などを「週に1~2回食べている・・」では・・効果を実感していません。
私は40年も前から肝がん治療を専門としていますが、肝がんの患者さんには10年前からトコロテンを1日に2個(300g)食べていただく様に指導しています(癌結節が縮小する症例を多く経験)。現在はLMF研究会(低分子フコイダン研究会)の世話人でもありますが、フコイダンの飲用が必要である患者さんには必ずRAP食を勧めています。さらにトコロテンは必須アイテムとして追加でお勧めしています。モズク(多糖類であるフコイダンの原料)とテングサ(多糖類であるトコロテンの原料)は異なる種類の海藻ですから、成分も異なるのでしょう(モズク成分は水溶性、トコロテンのプルプル成分は非水溶性)。
なぜトコロテンがいいのでしょう? あのプルプルした中に未知なる成分が含有されているのでしょうが、水溶性ではないので実験しにくいのでしょうね。私の経験ではプラークを改善させますので、ところてんにも同じ多糖類であるフコイダンと同様のガンのアポトーシスを引き起こす有益成分が含まれているかもしれません。
とにかく、健康に良い食品とは・・「神様=マクロファージ」へのお供え物なのです。プラークが溜まっている人は、冷たいから・・とか、寒いから・とか、好きではないから・・とか、言えないはずです。 命を狙う敵は「冬でも・寒くても・・攻めてきます」
<脳出血やくも膜下出血の根本原因は・・96.7%がプラークです・・その実態に迫る>
血管をしなやかにする研究をしてほしい・・などのご希望がありますが、血管内のゴミ(プラーク)が減らなければ、血管が広がる方法を考えても間に合いません。そのうえ、血管のゴミがあるままで脳血管が広がると頭痛や片頭痛の原因にもなりますし、脳細胞が圧迫されて認知症の原因にもなります。
私が経験した症例の頭蓋内出血例30例(脳内出血12例、くも膜下出血18例)中29例(96.7%)は脳梗塞リスクレベル=2以上の、いわゆるプラークが根本原因と考えられる事例でした。プラークを脳梗塞・心筋梗塞リスクレベル1以内に収めておけば、かなり安心していいのです。
脳出血予防・くも膜下出血予防も・・脳梗塞・心筋梗塞・認知症予防と同じで、脳動脈・頭蓋内動脈にプラークを溜めないことなのです。(詳細は今後掲載予定)
「血管をしなやかにする方策」は「プラークを減らす方策」が存在しなかった時代には重要な方策ですが、奇跡とも思える「プラークを減らす方策」を伝授していますので、その方策を理解できた方は・・「血管をしなやかにする方策」は優先順位が低い旧式の作戦とお考えください。
血管の壁にプラークが少ない血管は・・血管劣化が少なく・・普通の食習慣では簡単に切れません!。
(2017年10月追記 :最近40代の方で、プラークは順調に退縮していましたが、血圧はまだやや高めのままで、ビールを毎日1000cc飲まれていた方が、朝の起床時に頭痛もなく脳出血となり(手で掴んだ物を落とす症状のみ)、緊急に血腫除去を受け、後遺症なく経過している方がおられます。LDLが低い人が脳出血になりやすいのですが、この方のLDLは低くはありません。血圧が高めの方は、くれぐれもアルコールには気をつけましょう。高血圧の方で、アルコールを多めに飲まざるを得ない方は、降圧剤での管理を少し厳しくしておいた方が無難です。ストレッチや指圧などで血圧が一時的に低下しても、担当医の同意なく降圧剤の服用を中止してはいけません。アルコールを多く飲んだ翌日に脳出血になりやすいですから。)
<植物油と健康に関しての再確認です>
テレビで説明を受けて、血管にいいとか・・血液をサラサラにするから・・などと・・毎日・・エゴマ油・他の植物油を生でも摂取するのはプラークが増える可能性があるので危険です。
ω3脂肪酸なら、魚から食事として摂取できるので、わざわざエゴマ油を買い求める必要はありません。
プラークを増やさないで、血液を安全にサラサラにしたいなら、高純度のEPA製剤、EPA+DHA製剤などがありますので「かかりつけ医」にご相談ください。その際は、くれぐれもコレステロールを下げる薬であるスタチン剤はご遠慮ください。
2017年7月18日追記
<RAP食を自分で行う場合に、ストイックに砂糖制限+脂質制限をしないように>
RAP食は糖質制限食ではありませんし、肉禁止でもありません。RAP食は日進月歩で進化しています。
脂質制限も、魚介類や肉類、およびそれらの加工品に関してのみ、保存料・人工甘味料などの添加がなく、脂質量が少ない食材を適量摂取するように指導しています。
肥満の人はRAP食で普通に痩せますが、元々肥満ではない女性の方が痩せすぎで心配される場合があります。
その様な場合は、
糖分を増やすためにバナナ以外の果物を通常の感覚よりも多めに毎日摂取してください。そして、主食(白米)を多く食べていただきます。同時にデンプン質のカボチャ、ジャガイモ、里芋などを味噌汁などに多用し、サツマイモなども時々いただく様にしましょう。
その上で、全卵で毎日1個と、卵白のみ2個分を追加で摂取(脂肪ゼロの蛋白質=脂肪ゼロの鶏肉として、卵白は重宝)をお勧めします。
さらに、骨や軟骨や全身の組織のためにも、塩無添加煮干し(真水でボイルした商品)を毎日40匹(長さ4~5cmの品なら)程度、数分水に浸して柔らかくしていただきましょう。煮干しに含まれるナイアシン(ビタミンB3)はプラークの蓄積抑制効果があるとの研究があります。
さらに、筋肉を付けるために、皮なしの鶏のモモ肉(3.5g)、鶏のムネ肉(1.5g)、鶏のササミ(0.8g)、ブタのヒレ肉(1.9g)、魚のタラ(0.2g)などを多めに(過去の自分より)いただき、運動しましょう。(**g)は100g当たりの脂質の量です。
これらのことで、体重減少がストップし、筋力もアップし、健康的に体力が向上するでしょう。
<“コンビニおにぎり” “コンビニ弁当のごはん”には注意が必要です>
ネット情報によれば、“コンビニのおにぎり”には植物油が混ぜられているようです。「コンビニおにぎり、油」で検索下さい。実際に実験してみました。“植物油添加の記載がない”コンビニおにぎりの角のひとつまみをコップに入れて、水を注いで良くかき混ぜます。すぐに表面に油滴が浮いてきました。また、一晩おいてコップを指で洗ってみると、コップに油がついているのを確認できました。
RAP食を守り、「白米はOKだから・・」と、“コンビニおにぎり”を普段よりも頻繁に食している方がいれば、そのおにぎりをコップで実験してから食べていただく様にお願い致します。
老人の一人暮らしで、健康に良い品を揃えた“ごはん付き弁当”を配達してもらっている方も、その“ごはん”や“おにぎり”は専門の工場で炊飯油を添加されて製品化されている品かもしれません。
弁当の“ごはん”でも実験しました。「コンビニの野菜炒め弁当」には調味油添加の記載がありますが、ご飯には(国産米)とだけ記載があります。この弁当の“白ごはん”で実験すると、“おにぎり”と全く同様に油滴が浮いてきました。
“コンビニおにぎりの多食”が、RAP食を守りながらのプラーク増加に関与かも?・・、と思われる40代の男性の症例もあります。
仕事の配置換えなどで、外食やコンビニ弁当を食べる機会が増えた方などはプラークの増加や高血圧、頭痛などの健康変化にご注意下さい。
現代社会では外で“ごはん”や“おにぎり”を食べる際も、一応は心に留めておきましょう。
2017年7月20日
<記事の削除について>
今回の想定外の“ごはん”“おにぎり”の記事内容を受けて、サプリの症例に関する事実関係の確認が必要になりました。プラークを悪化させる要因は複合的であり、確認作業は慎重であるべきとの観点から、サプリに関するコメントの記事、掲載症例を順次削除または修正します。
2018年1月29日 追記-------緊急安全情報
<納豆・豆乳ヨーグルトの過食はNGです>
「納豆・豆乳ヨーグルトとプラークとの事実関係・・実例に学ぶ」
Case1:「毎日:豆乳ヨーグルト600g+毎日:納豆3パック+毎日:枝豆をどんぶり1パイ」食べた人が、こんな習慣にしてからプラークが激しく悪化しました。
Case2:「豆乳800g+豆乳ヨーグルト200g(合計で1000g)+納豆2パック+豆腐0.7丁+枝豆70g」これらを毎日食べていた人のプラークが激しく悪化しました。(以前、糖質制限食の経験ある方)
Case3:「豆乳300g+豆乳ヨーグルト500g(合計で800g)+豆腐0.5丁+納豆1個+きなこ:大さじ2-3杯」・・・これらを毎日食べていた人のプラークが明らかに悪化しました。
Case4:「豆乳400g+豆乳ヨーグルト400gを(合計で800g)+豆腐1日置きに0.7丁」を毎日食べていた人のプラークが明らかに悪化しました。
(2017年10月からの臨床経験順)
**2017年の10月から、たて続けに4名の大豆・大豆加工製品の過食が原因と思われる症例に気付きました。
改めて「超音波装置による精密な観察」が無かったら・・・と、想像するだけでゾッとします。
また、一つの健康常識を覆せました。まだ隠された誤った健康常識があるかもしれません。












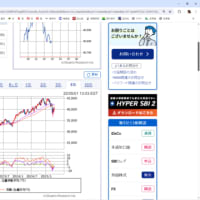














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます