朝から雨
雨が降ると暖かく、止むと途端に冷えてくる…
ところで早速小澤征爾が指揮をするオペラのチケットを買いに、駅のそばのチケットオフィスに行った。
行く前からチケットの値段はネットで買ってもTeatro comunaleで買っても、ここで買っても同じか?という疑問は有ったのだが…
窓口へ行って「一番安いチケットが欲しい」というと
空きを教えてくれたのだが、最低35ユーロの席しかないという。
ん???
昨日うちで調べた時は25ユーロというのが有ったのに?
「これが一番安いの?」と確認すると、「26歳以下なら有るけど?」
「いえいえ…」「じゃあこれが一番安い」とお姉さん。
確かに画面上にも空きがない
ちょっと納得行かないけど、まぁいいか
で、38.5ユーロ…
ん???
手数料取られてる!?
坂本龍一の時は手数料なかったからここに来たのに~
しかし、発券してしまったから遅いのだ…
く~これからしばらく何を切り詰めたらいいのやら…
まぁそれでも日本円で4000円強
有りえない、有りえないと自分を納得させるしかないのである。
さてさて、パンフレットは見ていたのに全然気付かなかったのは、所謂典型的なオペラではなかったから。
LA PICCOLA VOLPE ASTUTA

日本名は歌劇「利口な女狐の物語」
こちらにスポニチの記事を抜粋
小澤征爾が総監督を務め、毎年長野県松本市で開催されるサイトウ・キネン・フェスティバル。今年のオペラ公演はチェコの作曲家ヤナーチェクの「利口な女狐(めぎつね)の物語」を取り上げる。演出はフランスを中心に活躍を続けるロラン・ペリー。「利口な女狐の物語」は新聞に連載された動物が登場する絵物語をオペラ化した異色作だ。ヤナーチェクが70歳を前にして作ったオペラだけに彼の死生観が色濃く反映されている。主人公である女狐ビストロウシカの成長と死を軸に森の生き物の様子や自然のうつろいが生き生きとしたタッチで描き出されているが、これらを通じてヤナーチェクは東洋の輪廻転生思想にも似た「死と再生」という考え方を強いメッセージとして見る者に訴えかけている。森の中には生と死が常に同居しており、時が経過し人や生き物は老いるがその傍らにはいつも若い生命の息吹が存在している。
こうした考え方をイメージ化し、オペラの中で子供の合唱やバレエ・ダンサー、パントマイムなどを活用しながら巧みに表現しているのは注目ポイントだ。
小澤によるヤナーチェクのオペラといえば、01年のサイトウ・キネン・フェスティバルで上演した「イエヌーファ」(演出ロバート・カーセン)の名演が今も多くのファンの記憶に鮮烈に残っている。小澤の緻密で丁寧な音楽作りはヤナーチェクの繊細な世界と見事にマッチしていたことに加えて、登場人物の内面を掘り下げたカーセンの演出と相まって観客を圧倒的な感動に誘った。その後、小澤は別の演出でウィーン国立歌劇場でも「イエヌーファ」を上演し大成功を収めている。彼にとってヤナーチェクは最も相性の良い作曲家のひとりということができよう。その意味では今回の「利口な女狐の物語」には、「イエヌーファ」を超える名演への期待が膨らむ。
というのもここ数年、小澤のオペラに対するアプローチの充実ぶりは多くの専門家、ファンが認めるところだからだ。ウィーン国立歌劇場音楽監督という重責は、小澤の肉体に少なからぬダメージを与えたことは度重なる体調不良・休養からも明らかだが、その一方でオペラ上演の際に見せる深い呼吸感や柔軟な旋律運びは、監督就任数年を経て顕著に見られるようになったことも事実。昨年の「東京のオペラの森」で上演したワーグナーの「タンホイザー」(演出ロバート・カーセン)と先月、小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトで取り上げたヨハン・シュトラウスⅡの「こうもり」(演出デイヴィッド・ニース)はその好例。前者では深い呼吸感をもってワーグナー独特の深遠な世界を創り出すことに成功。休養からの復帰ということで周囲を心配させた先月の「こうもり」では、肩の力が抜けたような自然体の指揮ぶりでウィーン風の洒脱な旋律運びを披露。03年に同プロジェクトで「こうもり」を上演した時に比べると軽妙さや優雅さが格段に増している今年の演奏は、小澤が70歳を超えた今もなお、進化を続けていることを実感させるものだった。それこそが小澤征爾という指揮者の凄さであり、ここからの約10年間が芸術家としての円熟を深めていく「最良の時期」であることは間違いないだろう。だからこそ、今年の「利口な女狐の物語」は見逃せないステージといえる。
ということです。
以前「こうもり」を見たんだよなぁ(確か?)
あの時は小澤征爾とMaggio fiorentino(Teatro comunaleのオーケストラ)の結びつきに感動。お客の鳴りやまない拍手に感動。
同じ日本人として本当に誇りに思ったんだったよなぁ
Firenzeでは初上演になるとか。演出家も同じ。
チケットはまだ若干残っているようですので
11月8日、11日、13日、15日の4日間のみ。
Teatro comunaleに直接行くか、Biglietteria onlineで買うことをお勧めします
何事も勉強、勉強…とほほ
こんなチャンスめったにないからね
何を言っても楽しみ、楽しみ
Un evento attesissimo, da non perdere.
お見逃しなく!

雨が降ると暖かく、止むと途端に冷えてくる…
ところで早速小澤征爾が指揮をするオペラのチケットを買いに、駅のそばのチケットオフィスに行った。
行く前からチケットの値段はネットで買ってもTeatro comunaleで買っても、ここで買っても同じか?という疑問は有ったのだが…
窓口へ行って「一番安いチケットが欲しい」というと
空きを教えてくれたのだが、最低35ユーロの席しかないという。
ん???
昨日うちで調べた時は25ユーロというのが有ったのに?
「これが一番安いの?」と確認すると、「26歳以下なら有るけど?」
「いえいえ…」「じゃあこれが一番安い」とお姉さん。
確かに画面上にも空きがない
ちょっと納得行かないけど、まぁいいか
で、38.5ユーロ…
ん???
手数料取られてる!?
坂本龍一の時は手数料なかったからここに来たのに~
しかし、発券してしまったから遅いのだ…

く~これからしばらく何を切り詰めたらいいのやら…
まぁそれでも日本円で4000円強
有りえない、有りえないと自分を納得させるしかないのである。
さてさて、パンフレットは見ていたのに全然気付かなかったのは、所謂典型的なオペラではなかったから。
LA PICCOLA VOLPE ASTUTA

日本名は歌劇「利口な女狐の物語」
こちらにスポニチの記事を抜粋
小澤征爾が総監督を務め、毎年長野県松本市で開催されるサイトウ・キネン・フェスティバル。今年のオペラ公演はチェコの作曲家ヤナーチェクの「利口な女狐(めぎつね)の物語」を取り上げる。演出はフランスを中心に活躍を続けるロラン・ペリー。「利口な女狐の物語」は新聞に連載された動物が登場する絵物語をオペラ化した異色作だ。ヤナーチェクが70歳を前にして作ったオペラだけに彼の死生観が色濃く反映されている。主人公である女狐ビストロウシカの成長と死を軸に森の生き物の様子や自然のうつろいが生き生きとしたタッチで描き出されているが、これらを通じてヤナーチェクは東洋の輪廻転生思想にも似た「死と再生」という考え方を強いメッセージとして見る者に訴えかけている。森の中には生と死が常に同居しており、時が経過し人や生き物は老いるがその傍らにはいつも若い生命の息吹が存在している。
こうした考え方をイメージ化し、オペラの中で子供の合唱やバレエ・ダンサー、パントマイムなどを活用しながら巧みに表現しているのは注目ポイントだ。
小澤によるヤナーチェクのオペラといえば、01年のサイトウ・キネン・フェスティバルで上演した「イエヌーファ」(演出ロバート・カーセン)の名演が今も多くのファンの記憶に鮮烈に残っている。小澤の緻密で丁寧な音楽作りはヤナーチェクの繊細な世界と見事にマッチしていたことに加えて、登場人物の内面を掘り下げたカーセンの演出と相まって観客を圧倒的な感動に誘った。その後、小澤は別の演出でウィーン国立歌劇場でも「イエヌーファ」を上演し大成功を収めている。彼にとってヤナーチェクは最も相性の良い作曲家のひとりということができよう。その意味では今回の「利口な女狐の物語」には、「イエヌーファ」を超える名演への期待が膨らむ。
というのもここ数年、小澤のオペラに対するアプローチの充実ぶりは多くの専門家、ファンが認めるところだからだ。ウィーン国立歌劇場音楽監督という重責は、小澤の肉体に少なからぬダメージを与えたことは度重なる体調不良・休養からも明らかだが、その一方でオペラ上演の際に見せる深い呼吸感や柔軟な旋律運びは、監督就任数年を経て顕著に見られるようになったことも事実。昨年の「東京のオペラの森」で上演したワーグナーの「タンホイザー」(演出ロバート・カーセン)と先月、小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトで取り上げたヨハン・シュトラウスⅡの「こうもり」(演出デイヴィッド・ニース)はその好例。前者では深い呼吸感をもってワーグナー独特の深遠な世界を創り出すことに成功。休養からの復帰ということで周囲を心配させた先月の「こうもり」では、肩の力が抜けたような自然体の指揮ぶりでウィーン風の洒脱な旋律運びを披露。03年に同プロジェクトで「こうもり」を上演した時に比べると軽妙さや優雅さが格段に増している今年の演奏は、小澤が70歳を超えた今もなお、進化を続けていることを実感させるものだった。それこそが小澤征爾という指揮者の凄さであり、ここからの約10年間が芸術家としての円熟を深めていく「最良の時期」であることは間違いないだろう。だからこそ、今年の「利口な女狐の物語」は見逃せないステージといえる。
ということです。
以前「こうもり」を見たんだよなぁ(確か?)
あの時は小澤征爾とMaggio fiorentino(Teatro comunaleのオーケストラ)の結びつきに感動。お客の鳴りやまない拍手に感動。
同じ日本人として本当に誇りに思ったんだったよなぁ
Firenzeでは初上演になるとか。演出家も同じ。
チケットはまだ若干残っているようですので
11月8日、11日、13日、15日の4日間のみ。
Teatro comunaleに直接行くか、Biglietteria onlineで買うことをお勧めします

何事も勉強、勉強…とほほ
こんなチャンスめったにないからね
何を言っても楽しみ、楽しみ
Un evento attesissimo, da non perdere.
お見逃しなく!














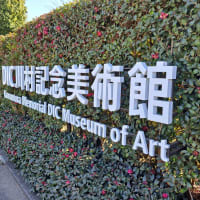





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます