実は昨日これを書こうと思っていたのに、軌道がずれてしまったのにタイトルを直すのを忘れてアップしてしまいました。
ということで今日こそ「リモージュボックス」のお話です。
「リモージュボックス」ってご存知ですか?
画像:https://www.wako.co.jp/exhibitions/379より拝借
こういう小さな箱のことで、陶器のことを色々調べていてその実態を知りました。
勿論実物はイタリアでも見たことが有るのですが、この手のものは小さいくせに高いんだろうな、ということで意図的に無視していました。自分の性格上、こういうものにはまりやすいんですよ…
リモージュボックスとは、ボワット・ド・リモージュ( Boîtes de Limoges)というのが正式名称で、フランスの南西部のリモージュで生まれた磁器製の蓋の付いた小箱を指します。
もともとは香料や白粉、紅といった化粧品や薬、砂糖菓子などをポケットに忍ばせて持ち歩くために作られましたが、この小箱が芸術品とも呼べるレベルにまで成長したのは、18世紀フランスを中心にヨーロッパの貴族の間で広まった「嗅ぎ煙草」の流行によるものでした。
「嗅ぎ煙草」とは
”火を着けず、煙ではなく直接その香りを楽しむ煙草の形式で、最も古い煙草の形態の一つ。
タバコの粉末を鼻から吸い込み、鼻腔粘膜などからニコチンを摂取する。”(引用)タイプの煙草で、この容器に葉っぱが入れられていたということですね。
ちょっと話は逸れますが、私の卒論のテーマである「金唐革」も日本では煙草入れとしてリサイクルされていました。
夏目漱石が金唐革の煙草ケースが当時流行していたことを小説に書き記しています。
今と違って煙草を吸うこと時代が”格好良かった”時代の話ですね。
リモージュボックスは18世紀中頃ロココの影響のもと、芸術の粋を集めた素晴らしい作品が生まれます。
その頃は煙草だけではなく「つけぼくろ入れ」としても活躍していたようです。
その後フランス革命の影響で貴族文化が崩壊したことで、一時期リモージュボックスも衰退します。
ところが贅沢を好んだナポレオン1世や、雅な生活にあこがれたブルジョア階級の台頭によって、19世紀中頃までには再びよみがえります。
しかしその後はパイプ煙草やシガレットの普及で19世紀末にはまた廃れてしまいます。
ところが20世紀に入ると、芸術品ともいえる18-19世紀をコレクションする人たちが増えたり、王家のコレクションを公開する美術館や博物館が現れると同時に、それらをお手本にした様々なモデルが作られるようになり、現在ではピルケースや乳歯入れなどの思い出の品を保管する宝箱として利用されています。
このリモージュボックスが1点、「ヘレンド展」に出展されていました。
写真:ヘレンド展カタログより拝借
およそ7×5×2cmしかありません。
1847-48年の作品でヘレンド窯の熱心な支援者であったカーロイ・エステルハージ伯爵への献上品だそうです。
その旨が金彩で書かれています。
外(蓋の部分)と内側は旧約聖書が題材になっていて、「エリエザルとリベカの出会いとエリエザルがリベカに贈り物をする」場面と「イサクとリベカの出会い」が描かれています。
この作品のように、内側に何かしらのメッセージや肖像画や細密画などが描かれた作品が多く、秘密のメッセージが込められていたようです。
なお現代では中に陶器製のミニチュアが収められているものも多くあります。
ということで、またまた危険なものを発見してしまった感じですが、忘れないように一応ご紹介しておきます。
最新の画像[もっと見る]
-
 今日いち-2025年4月21日
1ヶ月前
今日いち-2025年4月21日
1ヶ月前
-
 DIC 川村記念美術館
2ヶ月前
DIC 川村記念美術館
2ヶ月前
-
 DIC 川村記念美術館
2ヶ月前
DIC 川村記念美術館
2ヶ月前
-
 DIC 川村記念美術館
2ヶ月前
DIC 川村記念美術館
2ヶ月前
-
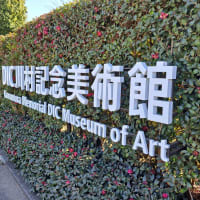 DIC 川村記念美術館
2ヶ月前
DIC 川村記念美術館
2ヶ月前
-
 2024年の終わりに
5ヶ月前
2024年の終わりに
5ヶ月前
-
 お札に描かれた人物ー国立公文書館
9ヶ月前
お札に描かれた人物ー国立公文書館
9ヶ月前
-
 お札に描かれた人物ー国立公文書館
9ヶ月前
お札に描かれた人物ー国立公文書館
9ヶ月前
-
 お札に描かれた人物ー国立公文書館
9ヶ月前
お札に描かれた人物ー国立公文書館
9ヶ月前
-
 お札に描かれた人物ー国立公文書館
9ヶ月前
お札に描かれた人物ー国立公文書館
9ヶ月前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます