イタリアに戻って数日、なんとなく時差ぼけなのか、夏の疲労が溜まっていたのか、変な時間に眠くなったり。
お昼寝していないのに、朝方早く目が覚めたり。
でもしばらくすると寒くて起きられなくなるから、今のうちは早寝早起きしておきましょう。
残念なことに、6時に目が覚めてもまだ暗いし、夕方も7時過ぎには暗くなってしまい、確実に秋は近づいている今日この頃です。
さて、今年日本に戻って色々考えることがありました。
いや~毎年同じこと考えているのですが、この先どうするのか?
まだすぐに卒業、という感じではないですが、いづれ卒業したら私はいったいどうするのか?
まぁほぼ日本に戻る気でいるわけですが、帰ってどうするか?
この不景気、この年齢・・・
ただ日本は不景気だといいながらも、選ばなければまだ仕事はある。
しかし、ここまでイタリアで培ったもの、何も生かせずに生きてゆくのかぁ???
ということで、少しずつ準備をせねば、ってなことで、周りにも「どんなことが出来るか?」聞いてみたりしております。
そんなこんなで簡単なイタリア語講座をやってみたりしていたわけですが、
実は「来年はこういうことが聞きたい」、という具体的なリクエストが友人からありました。
そうかぁ~そういうことを聞きたいのか・・・ということで今年は出来るだけ素材集めをしようと、今は心に決めております。
今年の意気込みをここで宣言したところで、更に具体的な今年の課題として、
・イタリア語の復習(人に教えるために)
・住んでるからこそ、の情報をもっとお知らせしたいと・・・なんて大きなこと言って大丈夫かな?
ということで、早起きした今日は早速昨日目にした記事から。
こんなことを知っていると街歩きが更に楽しくなる・・・というネタを1つご紹介。
フィレンツェには piazza della Passeraという広場があります。
ここ、私もかつて何度か紹介していますが、通称”美食広場”(私が勝手にネーミングしたんだけど)
この広場にあるレストランなどなどどこも外れなし!!
しかし、このPasseraがどういう意味かなんて、昨日この記事を読むまで気にしたことなかった。
ちょっとここに書くにははばかられるので、気になる人は辞書を引いてみてください。
トスカーナ方言になるのかと・・・
何でこんな名前が付いたのかというと、昔このあたりに遊郭があったから、とか。
何でも1348年約半数の市民を死に至らしめたペストがなんとこのあたりから発症したといわれているとか。
実際今ピンと来たけど、この近くにボカッチョの記念碑があるなぁ。
これに関係しているのかな?
今度確認してみますね。
他にも via delle Belle Donne, via dell'Amorinoなどなど、この手の意味深な名前の広場や通りの名前は結構あるそうです。
そして他にもフィレンツェらしい名前の通りがあるんです。
実はそちらをメインで紹介したかったのですが、まぁ前の話も知っていて損はないでしょう?
この広場のレストランに入ったら、ちょっと思い出してみたりして。
さて、次はvia della Vigna Vecchia、 via della Vigna Nova
ワイン好きのフィレンツェ人ならではの名前。
今のフィレンツェの中心街からはちょっと考えにくいですが、昔は”田舎”がもっと身近にあったし、お屋敷の中でワインを作っていた人もいたんですよ。
それが証拠に、フィレンツェの街中でこんなものを見かけたこと、ありませんか?
これ。
これは貴族が家で作っていたワインを、旅人に売るための窓口だったんです。
1500年代に遡ります。
その頃フィレンツェは毛織業が不況になっていました。
その穴を埋めるべく、ワインを売り出したのがことの始まり、とか。
ワイン屋さん(当時はオステリアでワインを販売していたようですが)を通さず、ダイレクトに生産者から購入することにより、購入する方も節約できたそうです。
私は以前、「一般にワインの販売は禁止されていたのでこの窓口を使って闇取引をしていた」と理解していました。
もう少し読み進めてみると、ちょっと誤解があったみたい。
ワインの販売が禁止されていたわけではなく、ワイン販売の厳しい決まりがあったようです。
ワインを売る時は、購入者にグラスで販売するか規制された容器を使うこと。喉の渇きをもよおす必要以上に塩気の多いパンを販売してはいけない、日没以降の販売も禁止だったようです。
フィレンツェの街中では本当に数多くみられます。
ちょっと目に留めてみてはいかがでしょう。
なんかお腹空いてきた。
最新の画像[もっと見る]
-
 今日いち-2025年4月21日
5ヶ月前
今日いち-2025年4月21日
5ヶ月前
-
 DIC 川村記念美術館
6ヶ月前
DIC 川村記念美術館
6ヶ月前
-
 DIC 川村記念美術館
6ヶ月前
DIC 川村記念美術館
6ヶ月前
-
 DIC 川村記念美術館
6ヶ月前
DIC 川村記念美術館
6ヶ月前
-
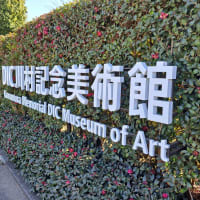 DIC 川村記念美術館
6ヶ月前
DIC 川村記念美術館
6ヶ月前
-
 2024年の終わりに
8ヶ月前
2024年の終わりに
8ヶ月前
-
 お札に描かれた人物ー国立公文書館
1年前
お札に描かれた人物ー国立公文書館
1年前
-
 お札に描かれた人物ー国立公文書館
1年前
お札に描かれた人物ー国立公文書館
1年前
-
 お札に描かれた人物ー国立公文書館
1年前
お札に描かれた人物ー国立公文書館
1年前
-
 お札に描かれた人物ー国立公文書館
1年前
お札に描かれた人物ー国立公文書館
1年前










食いしん坊のフィレンツェとか何とかいうタイトルで。
レストランのガイドだけではなく、食に関する習慣や歴史も楽しいものがあるはずです。
このワインの窓口だって知る人ぞ知る。
私が本の購入者第一号です。
次回そちらに行くことがあったら、この窓を探してみます。
読んでいて、遊郭…ペスト…中世…というと、ベネチアが舞台でしたが、映画「娼婦ベロニカ」を思い出してしまいました(;´∀`)(何でも映画に結びついてしまう)
今更何を言ってる…という感じですが、500年も前の建物の中で普段の現代の生活しているって改めて思うと凄いな…。
こういう小話(?)って本当に面白いですよね。大学でもこういう話をしてくれた先生が結構います。この手のことは覚えてられるんだけど、肝心なことは忘れちゃうんですよね。(笑)
こっちに戻ってきて、久々に本屋に行ったら、こういうミステリー(?)を集めた面白そうな本があったので、早速購入しました。少しずつ紹介して行きますね。
よん太郎さん>私もあの映画好きだわ。ベネチアにも昔遊郭だった場所があって・・・そうそう、これ書いてたときは思い出せなかったのに、記憶が繋がった。Ponte delle Tette(おっぱい橋)という名前がついています。なんでもこの橋の上で女性が胸を出して客引きしていたとか。こういう話って本当に面白いし、こういうことを知るとまた一段と街歩きが楽しくなるし、映画に結びつけても面白いよね。
頑張って紹介して行くぞ~!(^^)!
15世紀のVeneziaでは同性愛が流行っていて、国も対策に困っていたようです。”自然”に反するということで、数多くの人がサンマルコ広場の海側に立っている2本の塔で縛り首になったり、焼かれたりしていました。この同性愛撲滅の為の手段がこの遊郭だったそうです。(確か国の公認だったはず)そして遊郭の窓辺に立ち、胸を見せたり、足を見せたり、しまいにはヌードで客を引かなければならなかったのは、当時島の住民15万人に対して、11654人の遊女がいたことが記録に残っていて(1509年)客取り合戦が激しかったようです。^_^;