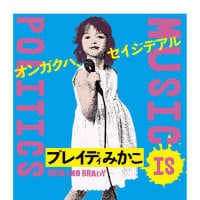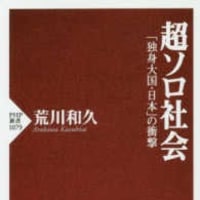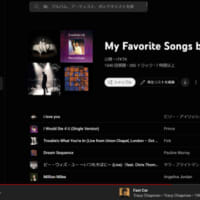掛札悠子,1992,「レズビアン」である、ということ,河出書房新社.(5.20.24)
突如、彗星のごとく現れ、数年後、なんの痕跡も残さず去って行った、伝説上の人物、それが掛札悠子さんだ。
自分が親密な関係を望む特定の相手が、異性ではなく同性であること、掛札さんがカミングアウトするのは、その事実だけである。
結局、「レズビアンである」と言うことは、「今、自分が親密な関係をつくっている(つくろうとしている)のは女性である○○さんだ」という事実を示すひとつの方法でしかない。そして、一人一人の人が自分の現実をそうやって口にすることが簡単になりさえすれば、「レズビアン」という言葉も、「同性愛」「異性愛」という分類も意味をもたなくなる。だが、今の社会で「自分が親密な関係をつくっているのは女性である」と言うことは容易ではない。その一は自分の日常すべてさえも破壊しかねないからだ。
(pp.21-22)
しかし、レズビアンは、男が妄想するポルノグラフィックな表象のカテゴリーであり、畢竟、レズビアンは、関係性なり生き方なり人物なりを表象するものではなく、男の性幻想の表れとしての「行為」でしかなくなる。
自分が女だから、女と「セックス」をするときには理解しやすいというのも、男性がつくってきたポルノグラフィの受け売りにすぎない。実在のレズビアンたちはその件に関して、まだほとんどなにも語っていないのだから。女だけでセックスをすることは、これまでずっと「変態の一種」とみなされて嫌悪され、一方では、ポルノグラフィの恰好の材料となっていた。その同じことが否定的な文脈ではなく肯定的な文脈で言いかえられただけなのだ。こうした言いかたを通じて異性愛者の女性が認めているのは、「レズビアン」という人間の存在ではなく、「セックス」のヴァリエーションとしての「レズビアン行為」でしかない。ポルノグラフィは、まさに「レズビアンという生きかた」あるいは「レズビアンという関係」ではなく、「レズビアン行為」のみを描いているのだから。
(pp.42-43)
さらに、異性愛という関係がほかのなによりも価値あるものであるとみなされている現状では、異性愛の文脈で語られる「快」の基準が、女と女の間の「快」の基準にも入りこんできてしまう。手をつなぐことよりもキスをすることのほうが、キスをすることよりも「セックス」のほうが、服を着てからだにふれることよりも服を脱いでからだにふれることのほうが、より親密な関係をあらわす行為であるというあまりに疑われることのない価値観は、(もちろん異性愛者をも縛ってはいるだろうが)女と女の間にももちこまれる。この点において、すでに女性は異性愛への移行を自然とする「成長の神話」に侵されてしまっている。それらの価値観にしたがうにせよ、それらの価値観に意識的に抵抗するにせよ。だが、女と女の間にある親密さとふれあいが異性愛の「セックス」の決まりきった手順にならって強制的に並べ直され、女性の間につくられる関係が異性愛に準じて「レズビアン」という枠にはめこまれることがなければ、女性は自分たちがしたいように親密さとふれあいを共有することができるのではないだろうか。〔同性愛─異性愛〕の枠そのものを超えて。
(p.186)
私自身は、すでに述べた通り、「女性間の同性愛」としてのレズビアニズムは個人のプライバシーであり、なんら政治的な意味をもたないが、それが社会のなかで無視と抑圧にさらされている事実は、プライバシーに関するレズビアンの権利が侵されているという点で社会的・政治的な意味をもつと考えている。レズビアンに対する無視と差別は、つまるところ女性に対する無視と差別の凝縮である。「レズビアンは存在しない」という強固な神話は、女性がもっている自律性と自立性を無視し、おとしめようとする社会の態度のきわめて明確なあらわれであるし、レズビアンを「行為」におとしめる意識は、女性全体を最終的に「性的な対象物」とみなす意識と密接にむすびついている。
(p.54)
レズビアンであることは、その人の「生きられる現実」の一つである。
それ以上でも以下でもない。
カムアウトが他人につきつけるのは、ただこの一点だけである。この人は自分とは違う現実を生きているのだ、ということが「受け入れ」られ、レズビアンが自分のプライバシーを侵害される危険に脅えていなくてもすむようになりさえすればいいのだ。
だが、同性愛をめぐる無知と偏見は単なる「受け入れ」すらをもむずかしくする。「レズビアンである」と言うことは、「私はあなたと違う現実を生きており、それについて差別されたり、詮索されたりすることを拒否する」という表明であるにもかかわらず、カムアウトはプライバシーへの侵害をいっそうひどくする危険をはらんでいる。ことに同質性を当然として生きている日本人の感性は、なんとかして「自分と違うもの」を自分の土俵にひきずりこもうとする。自分の知らないこと、自分に理解できないことが存在するという事実を認めず、それを受け入れようとせず、自分がもっているきわめて小さなものさしですべてを理解しようとするのである。
「自分はレズビアンである」と話すと、「私には理解できない」という反応を示す人は多い。「理解したい」と言ってくれる人もときおりいる。だが、レズビアンでない人にレズビアンが「理解」できるだろうか?逆に、レズビアンに異性愛者が「理解」できるだろうか?(さらに言えば、あるレズビアンにほかのレズビアンを完全に理解することができるだろうか?)女性に魅かれる理由やその感情、女性との間に生まれる感覚や関係を異性愛者は理解することができるだろうか?理解などできないし、してくれなくてよい、と断言するつもりはないけれども、「理解」はレズビアン自身が求めているものではない。私は、私がなぜ、どのように女性に魅かれるのかを理解してもらおうとカムアウトしているわけではない。当然、「認めてもらうこと」も必要ない。私は、この社会が「普通」としている異性愛の文脈で自分のプライバシーを読みかえられること、異性愛の規範をおしつけられることを拒否したい、自分のブライバシーを守りたい、ただそれだけのためにカムアウトしているのである。
(pp.209-210)
レズビアンであることは、さまざまな掛札さんの属性の一つにしか過ぎない。
私が「自分はレズビアンである」と表明するのは、私が「レズビアン」でも「女」でもない「私」になれるような状況、逆に言えば、「レズビアン」でもあり、「女」でもあると同時にほかのさまざまな特性をもった「私」になれるような状況をつくりだしたいからである。「レズビアン」や「女」という、本来、私の属性のひとつでしかないことがらに自分を自己同一視(identify)せずにすむ(させられずにすむ)状況こそが最終目標である。「レズビアン」と「異性愛者」、「女」と「男」をふくめ、そういった雑な分類名が人にとって意味をもたなくなりさえすればいい。だが、そのためには、今のところ、「レズビアン」であり、「女」であることがそうではない人のおかれている状況とどのように違うかを明確にしつづけなくてはならない。なぜなら、この社会では「異性愛者」であること、さらには「男」であることに大きな価値が付与されており、反対に「同性愛者」であること、「女」であることに強いマイナスの価値が付与されているのだから。
(pp.236-237)
上野千鶴子さんの女性を冒涜するような(としてしか捉えられない)発言に対する批判は手厳しい。
まあ、筆が滑るというのは、誰にでもあり得ることだろうが。
掛札さんが言論の表舞台から去った理由は、次のブログ記事から推察できる。
「LGBT」というレッテルを貼られて。
4.誰のための運動なのだろう?
女性が、男が作り上げてきた性幻想から自由になれたとは言いがたい現状が続くなか、掛札さんの叙述は現在でもなお輝きを失っていない。
目次
「レズビアン」とはだれか
ポルノの嘘、フェミニズムの誤解
結婚と家族と「レズビアン」
「母」という呪縛
「レズビアン」差別が見えない理由
「女と女」の可能性
教室の中の同性愛者
ひとつではない「快」を探す
カムアウト、そして、共生へ
いま、「レズビアン」であるということ