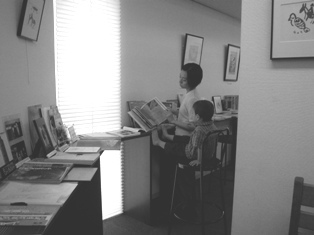2006年12月26日付の朝日新聞の“惜別”の欄。
論説委員でいらした大野博人さんが、11月23日に亡くなられた灰谷健次郎さんへの追悼の文章を寄せられていました。
大野さんは教師時代の灰谷さんの教え子でいらしたのです。
「あそびにいきたいよ、せんせい」───。
そう結ばれた文章が私の心にずっと残っていて、いつか「うの花忌」にお招きしたいと思っていました。
その願いが叶ったのは、2018年、第11回の「うの花忌」でした。
フランス人のジャーナリスト、クロード・ルブランさんが突然このミュージアムにいらしたのは、2021年だったでしょうか。
退職されて白馬村に住まいを移された大野さんを訪ねての帰りでした。
クロードさんが山田洋次さんの評伝を書き上げられたこと、フランスでの「男はつらいよ」の上映会に協力されていること、寅さんの絶大なファンでいらっしゃることを知りました。
ちょうどその日、小諸にあった「寅さん会館」の資料がここに持ち込まれたのです。
あまりにも偶然でしたけれど、クロードさんは、とても喜ばれて資料のひとつひとつをカメラに収められていました。
「寅さん会館」が閉館になったあと、行き場を失っていた大切な資料です。
寅さん映画の上映会を小諸と上田で長く続けていらしたグループの方々が保管されていたものです。
昨年、評伝『山田洋次が見てきた日本』の邦訳が刊行されました。
クロード・ルブラン著・大月書店、そして──、大野博人、大野朗子訳と記されているではありませんか。大野さん夫妻が訳されたんだ!。
大野さんはパリ支局長(2000年5月)、ヨーロッパ総局長(2007年9月)を歴任されていました。
クロードさんとの出会いがあったのですね。
今週末、6月28日(土)に『男はつらいよ 第47作 拝啓車寅次郎様』の上映会が行われます。
それに併せて、このミュージアムの一角に、「寅さんに会える部屋」を開設しました。
お知らせのチラシです。
企画展 寅さんに会える部屋 vol.1
日時:6月21日(土)~8月17日(土)まで開催。 11時~17時
休館日: 毎週火曜日・7月16日(水) 入場料300円
場所:〒386-0025 長野県上田市天神1-6-1 若菜館ビル3階
Editor's Museum (小宮山量平の編集室)
≪開催にあたり≫
戦後「理論社」を創業(1947年)、95歳で亡くなるまで生涯編集者であった小宮山量平の“めぐりあい”の歴史をたどることができるミュージアムを設立しました。(2005年)
その一角に山田洋次さんとの“めぐりあい”を物語るコーナーがあります。
1987年、モスクワへの旅を同行して以来、試写会に必ず父を呼んでくださった山田監督は、父の感想を心待ちにしてくださっていました。
父に会うのを楽しみに何度かこのミュージアムへもお越しくださいました。「寅さん」をこよなく愛していた父。
この場所で「寅さん」を甦らせることができたらきっと喜んでくれると思います。
エディターズミュージアム代表 荒井 きぬ枝
小諸市に「寅さん会館」がありましたが、15年前に惜しくも閉館してしまいました。
私たちコモロ寅さんプロジェクト(ココトラ)は寅さんを伝え残して行こうと上映会を行ったり、寅さんの写真を展示し、寅さんの想いを伝える活動をしています。
コモロ寅さんプロジェクト(ココトラ)代表 渡辺 広昭
<特別イベント>
*「かつくんのハーモニカ演奏」
今から9年前、東京柴又で「寅さんサミット」が開催され、“コモロ寅さんプロジェクト”もブースを広げました。その店先になんと監督が立ち寄ってくれたのです。
そしてメンバーのかつくんの「男はつらいよ」のハーモニカ演奏を聴いてくださったのです。翌年にも聴いていただく機会がありました。
そのかつくんの演奏を会場でぜひみんなにお届けしたいと思います。
予告:7月12日(土) 14:00
7月13日(日) 15:00 から会場内で演奏します。
*FMさくだいらで毎週金曜日の午後4時からの番組の紹介をします。
*「オルガニート男はつらいよ体験コーナー」(レインボークローバー提供)
・問い合せ先: 090-4180-6214(渡辺)
・メール: komoro.torasan@gmail.com
先月、また突然クロードさんが来てくださいました。
“寅さん談義”と、“山田作品談義”に花が咲きました。
(クロードさんは日本語が大変お上手です)
ミュージアムについて、「この場所、すきです」───と。
「寅さんに会える部屋」の期間中にまたお会いできたらな、と思っています。
2025.6.25 荒井 きぬ枝