




































(三) 水引の花 Mizuhikinohana
日本という国と正座する日本人の雨田博士には、ここ30年間にわたり万夜万乗の執筆がつづく。
衰えたその眼には、それでも初夜から昨夜までの筆跡をバックナンバー順に並べたインデックスが、次々と引き出されていた。
「ああ、これではもう幾ばくも無い、そんな気がする・・・・・! 」
吐息、そして溜め息に、ひと呼吸おいて静かに坂を上る阿部富造の影を泛かべると、ある雨の一夜が想い起こされた。
「 戦中、特に戦後、この異様な現象間によこたわる本性、そして戦争という実在の奥底にある非日常の世界性、博士は何故そのような試みに夢中になったのであろうか。博士は、戦後における日本人の生活意識が二重化され、玩具化されているという。これなどは博士独自の類をみないフラジリティ的史観ではあるが・・・・・ 」
やはり博士が気にかかる。そして斎場御嶽(せーふぁうたき)で宵闇の青い星空をながめる幽・キホーテの眼には、さも共鳴し合うごとく雨田博士が富造へと想いやる一筋の軌道が克明に泛かび起こされていた。
克明であるというのは、雨田虎哉の見聞が詳細にわたっているというだけではなく、取り扱っている情報の意味、すなわち「日本をどのように変えようとしたか」という主題を深く彫りこんでいるという意味もあった。
博士の眼は、コーン・パイプを咥(くわ)えたマッカーサーが厚木飛行場に到着するところから始まろうとしているが、すでに敗戦直後の混乱と錯綜は緩和されていた。が、ここから日本は、アメリカ指南の豪腕な「民主化」という敗戦処理が徹底して行われた。幽・キホーテは現在にいたる今も、GHQが日本にもたらした亡国のシナリオを知って驚愕しているのだ。そして日付を追って戦時体験者・雨田博士のツボをバランスよく心得た見聞と過不足ない適確な感想を読んでいくと、暗澹たる気分になってくる。
幽・キホーテはそのうえで、まるで2時間で一国スクラップの推移を描いた銀幕をみるごとく、珍しくも不可解な人間界の出来事に食い入るように自国の過激な変貌を見ている自身がいることに気づかされた。きっと琉球の御嶽だからそうさせるのだ。しかしだからと言って、ここでアメリカに惨敗した日本の惨めで不格好でペコペコした姿をじっと見続けさせられるのは、それはやはり痛切である。
「 だが、その日本の戦後を何とか回復させようと躍起になっていた日本人らしき日本人が生き生きとした活躍も、博士は遠慮容赦なく書き加えてくれている。ああ、あの一翼に、あらゆる万感が込められている・・・・・ 」
その一翼である音羽六号の飛翔を泛かばせながら、幽・キホーテは雨田博士の眼差しを追った。
「 雨田博士、阿部富造、この一点をどう見るかということに21世紀後半の日本の大半がのしかかってくるといってよい。その最初の一撃がこの御嶽によって私に放たれたわけだ・・・・・ 」
幽・キホーテは京都から放されて富士山を越えようとする一翼に、そして二人の男影に、じっと手を固く握り締めた。密かにその影にいた小生丸彦もまた同じく猫の手を固く拳(こぶし)にした。








枯葉でも一枚たゞようごとく小さな列島がある。
西洋の野心家らの眼にはそのように映っていた。
極東に隠れるように陰(かげ)り、かたくなに国を鎖(とざ)したこの小さな島の連なりを敷島(しきしま)という。
これが幕末に日光権現の力が弛緩(しかん)して、古き形を捨てようとする日本という国の夜明け前の姿である。
嘉永五年、そんな日本に迫りくる異国からの密かな一団があった。
「 あれは国ではなく、小島の村だ。あの島を補給基地として活用すれば、清国は近くなる。東海岸からインド洋経由で134日かかっていたものが、西海岸から太平洋経由でならわずか18日で行けることになるのだ。じつに七分の一、驚異的な時間短縮が見込まれる。ヨーロッパのアジア戦略に対抗するためにも、開港は是が非でも実現したい。もはやその力は知れている。分断された非力な小島の集合ではないか 」
餌を求めて飛び回る鴎かもめの群れをみすえながら、老司令官ぺリー58歳はそうつぶやいた。
大統領の親書を携えたこの艦隊は、1852年11月(嘉永五年)にアメリカ東海岸のバージニア州ノーフォークを出航した。フリゲート艦ミシシッピ号を旗艦とした四隻、黒い鎧(よろい)づくしに黒煙を吹く艦隊である。カナリア諸島・ケープタウン・シンガポール・香港・上海・琉球・小笠原諸島を経由して浦賀沖へとやって来た。
1853年7月8日(嘉永六年六月三日)、ペリー率いる米海軍東インド艦隊の黒船来航がこれである。
目的は開国の要求、ペリー代将はこのときフィルモア大統領から、琉球の占領もやむなしと言われていた。その年はアメリカ国独立宣言から77年の節目、記念すべ喜ばしさに加えアメリカ国が新たな希望を拓きより飛躍しようとする年であった。
7月4日がその記念日にあたることから数十発の空砲で祝した。
蟻(あり)が砂糖の山に群がるように浦賀浜にとりついた江戸の民衆は、突如と現れて空砲と黒煙を吹く、その船団の異様な大きさ、黒さ、怪しさにド肝を抜かれ、我先にと逃げ散った。ペリーの日本遠征記によると二度の来航で、百発以上の空砲を、祝砲、礼砲、号砲という名目で撃っている。結果、耳をつんざくような音に、江戸中が大混乱を巻き起こした。


「 アメリカは、このようにして日本の鎖された封建の正門へ黒船の大砲を翳(かざ)して強引にこれをこじ開けたのだ・・・・・ 」
翌1854年、ペリーはすでに香港で将軍家慶の死を知り、国政の混乱の隙を突こうと考えていた。
そして二度目の恐喝に屈した江戸幕府はアメリカの開国要求を受け入れた。
約一ヶ月にわたる協議の末、幕府は返答を出し、二つの不平等条約(長崎、下田、箱館、横浜などの開港や在留外国人の治外法権を認めるなど)を日本は締結させられて、ペリー艦隊は6月1日に優優と下田港を去った。
「 この黒船が開国へのトリガーであり、開国が明治維新へのトリガーとなる・・・・・ 」
産業革命期の世界の列強は、大量生産した工業品の輸出拡大の必要性から、インドを中心に東南アジアと中国大陸の清への市場拡大に急いでいた。後にそれは熾烈な植民地獲得競争となるが、競争にはイギリス優勢のもとフランスなどが先んじており、インドや東南アジアに拠点を持たないアメリカ合衆国は、清国を目指すうえで太平洋航路の確立が必要であった。また、欧米の国々は日本沿岸を含み世界中の海で「捕鯨」を盛んに行なっていた。
これは、夜間も稼動を続ける工場やオフィスのランプの灯火として、主にマッコウクジラの鯨油を使用していたからである。
「 太平洋で盛んに捕鯨を操業していたアメリカは、太平洋での航海・捕鯨の拠点(薪、水、食料の補給点)の必要に駆られていた 」
永らく閉ざされていたこの敷島から、三本マストの蒸気船「咸臨丸(かんりんまる)」百馬力で米国桑港(サンフランシスコ)へと船出し、初めて太平洋横断を果たしたのが1860年(安政七年)のことであった。
出港から到着まで、じつに37日を費やしている。洋行の目的は、日米修好通商条約の批准書を交換するためで、遣米使節団一行77名が、アメリカ軍艦ポーハタン号(黒船)にて太平洋を横断するに伴い、咸臨丸はポーハタン号の別船として浦賀より出港した。この渡航より八年後の明治、日本はアジアで最初の西洋的国民国家体制を有する近代国家として誕生することになる。
「 ご一新の、これが「ミカドの国」という小さな帝国であった。だが国名は、いかにも大きく「大日本帝国」と名付けられた・・・・・ 」
したがって名実とするために日本の新政府は西洋に手習い近代化を急いだ。

この小さな帝国に、ダグラス・マッカーサー は二度訪れている。
初めて訪れた1905年(明治三十八年)とは、それまで世界史の中で隠れ隠れしていた小さな島国が、あたかも神風を吹かすがごとく、大国ロシアとの日露戦争に勝利し、ポーツマス条約を締結させて、大日本帝国の名を世界の大国らの前に堂々と知らしめた年であった。
フィリピン植民地総督のアーサー・マッカーサーの来日の目的は、駐日アメリカ大使館付き駐在武官としてこの日露戦争を観戦することである。この時に「 父と共に私も副官として観戦した 」と後年に自身でほのめかしてはいるが、正しくはダグラスのみポーツマツ条約の締結後に遅れて来日した。来日の真相はいずれにしろ、ロシア帝国を破ったこの小国の想定外の変貌(へんぼう)が25歳のマッカーサーの眼にはどのように映ったのであろうか。またこの年の6月にはアルベルト・アインシュタイン(当時25歳)が特殊相対性理論を発表し光量子仮説を導入するなど、物理学の奇蹟の年を起した。
日本の近代には二つのエポックがあった。またそこに係わる大きな存在として、二つのメイド・イン・アメリカがある。
その一つは開国を強要した「黒船」であり、二つは終戦を決定づけた悪魔の「リトルボーイ」であった。対象である世界大戦の上に何らかの幻想を織りあげるとすれば、これら二つの唯物は、数奇な運命として日本の敗戦のそこに連なる。




「 阿部富造が、山王社北にある左右庵を訪ねてきたのは、或(あ)る晩秋の夜であった・・・・・! 」
秋はものうく熟(う)れきっている。やわらかな雨打(あまうち)、そんな夜であるから、門前は呆(ほう)けたように閑しずかである。20年ぶりにみる、記憶の風雪を止める小さな茅葺(かやぶき)の門はしっとりと濡れていた。
門前には「面会謝絶」の立札がある。濡れるにまかせて富造は茫然(ぼうぜん)と立ちつくした。
但し書きに「 やむなく門前に面会御猶予の立札をする騒ぎなり 」と添えられている。
それは誰にともなくつぶやいているのではなく、矛先(ほこさき)をぴたりと老人に向けていた。
「 軍人を捨てたら、私に何が残る。もう、疲れたよ 」
慷慨(こうがい)の士が、それらしくなく呻(うめ)きながらこう吐き捨てた。初めて聞く弱音であった。富造の遠い記憶の中に、この言葉だけは今も鮮明にある。国事に悲憤して泣いた落胆のそれは、蜘蛛(くも)の巣の糸が心にからみついた後味の悪さのように、どのように時を重ねようとも落ちることはなかった。
「 軍人として、君は卑怯(ひきょう)だよ・・・・・ 」
と、そのとき即座に答え返し、富造は彼の不甲斐なさを罵倒(ばとう)して詰(なじ)ったのだ。ただし腹に据えかねて侮辱したのではない。あのときは、あふれ出ようとする大粒の涙をはじき飛ばして、敢(あえ)てそのような促し方をした。死に臨んで潔(いさぎよ)くあるべきだという、軍人としての未練が厭(いとわ)しく感じられたからだ。
「 なにっ!・・・・・ 」
冷静な富造の侮辱に、精気を失いかけてはいても、目鼻をくしゃくしゃと寄せて相変わらずの怒声で仕返してきた。
しかしそれは一瞬、腸(はらわた)を噴き出して嘶(いなな)くような只(ただ)の一言でしかなかった。敗北を背負った軍人が、最後の力をふりしぼって空をかく声であった。
そうしてそのまゝ、つんのめるように前に倒れたが、その眼はまだうっすらと血走っていた。
一睡もせずに思い詰めた末の言動であったはずだ。
軍事裁判の前に自害する軍人の情報を得るたびに、今日は死ぬか明日は果てるかと気を揉むことに、疲れ過ぎていたのかもしれない。そこには武人として人の上に立ったからには、という自負と自責とがあった。
「 気の済むようにさせてくれ 」
と、律儀で強情な性(たち)であるからこそ、富造もまた常軌を逸したかに、冷たくそれを諌(いさ)めようとした。
互いに気性は知り尽くしている。
「 だってそうだろう。国民にこれ以上苦労をかけて済まないとは思わないのか。たしかに日本軍は敗北した。だが国家には回復の道もあろう。その事後処理という重大な任務を放棄し、屈辱を恐れて自害して果てた軍人と等しく、みずからの面目ばかり立てようとしているのではないか。そうした軍人の性(たち)でもって、置き去りにされる国民は一体どうなるというのか 」
と、真っ直ぐな正義は、真っ直ぐに切り崩すしかない。竹の剛のごとく死を賭(と)した正義は真っ直ぐである。睨(にら)んだ通りやはり苦(にが)り切った貌(かお)で貞次郎は首を振り、呻くような声を切れ切れに漏らした。
「 しょせん復員に帰した軍人に、仏の救いなどまやかし事さ。俺も軍人であったが、俺は生きて償いをしたい。お互い罰当たりを承知で軍人をしたのではないか。たしかに一度はお前と同じように自害の道を選ぼうとした。しかしそれは敵前逃亡、鬼が外から閂(かんぬき)をしたよ。どうだろう、惨めで辛い道になるのだが、もう一度、同じ道を二人して歩こうじゃないか・・・・・ 」
終戦直後の、あたりを憚(はばか)る押し殺した二人の会話には、言いようのない重苦しさがあった。詰(なじ)られた戦友はしばらく地べたに腰をお落としたまゝでいた。隔意のない間柄であるからこそ富造はあえて平然と無造作に応えたのであるが、戦友でもある親友はスィと立ち上がると、抉(えぐ)るような凄まじいばかりの号泣になった。
富造もまた棹(さお)立ちで水洟(みずばな)をすゝり上げながら泣いた。
高札は人を拒むものではない。しかし何とも皮肉な目をして富造を見下ろしていた。庇(ひさし)からの雨だれが、かすかな光をともなって立札に落ちて、しずくがその字面(じづら)を這(は)うように流れると、また雨垂れとなり、終戦時の地へとしたゝりながら富造の足元に落ちていた。
「 このまゝでは、たゞ、古い日本を信じて死んだ、ということになるな・・・・・ 」
と、言い遺(のこ)そうとしたので、肩をぽんと叩いてやったのだが、そのとき彼は妙に生臭い匂いをさせた。しかし初七日の夜に骨壷のある部屋に入ると線香の匂いに混ざって生臭さもあの世へと紛(まぎ)れたようであるから、恋しい人の清らかな名をそっと耳元に呼んであげた。




彼が生き永らえることの苦しさにはその名への呵責(かしゃく)もあったからだ。
許嫁(いいなずけ)の「妙子さん」20歳が無差別の東京大空襲で落命している。右腕をもがれながら身ぐるみ焼け爛(ただれ)て転がるようにもがきながら他界した。置き去りにした呵責は彼の胸を鎖させた。生前はその名さえ一言も語ることはなかった。
その古閑(こが)貞次郎は20年前に他界したのである。
「 古い日本・・・・・か 」
阿部富造は彼の臨終(いまわ)の言葉を改めて起こすと、ぐっさりと心につき刺さるようでどうにも気持ちがめいるのを感じた。それは言葉にも何もならない、大正、昭和、平成と継ぎ、やがて還暦を目前にした初老の心の襞(ひだ)にべっとりと貼り付いたまだらな感情の沈殿でもあった。
「 堪忍(かんにん)やで、本当に堪忍や。お前だけではない、私も古い日本の雨垂れなのかも知れない 」
富造はしばらく痛ましげな面持ちで高札を見廻していたがその高札の中に、野末を吹き渡る風のような海原(うなばら)に渦巻く潮騒(しおさい)のような音をきいた。否(いや)、訊(き)かされた。すると富造の古い五体は妙に軽くて意外だった。生前貞次郎は高札が古くなると真新しく立て替えていた。
「 読めなくてはこの世に何の役にも立つまい。古臭くてはこれがこゝに立つ瀬もあるまい 」
と、剽軽(ひょうきん)にさらりと言って、その、のんびりとした声音(こわね)が富造の耳底に今も棲(す)みついている。左右庵はこれまでに幾度となく訪れてきたが、雨の日の夜は数少なく、しずくが垂れながら地を洗っている。
そんな門前の立札をながめながら、それらが貞次郎の面影を静かに洗い鎮めるようで、確かこれが三度目の雨夜であることを覚えると、富造の古びた心を波のような懐かしさがやはり戦友であったときと同じように潤(うるお)した。
焼けただれた焦土の上に、やがて緑の草が生えようとするころに立てられた憤る高札である。だが永遠の憤慨のつもりでいても、これはもはや、無(む)の沈黙としか理解されない立札であった。
「 なあ貞次郎、そろそろ、意地もたいがいにして和睦(わぼく)をしようじゃないか 」
どこか空気にでも抗(あらが)うかに富造は力細く吐き捨てた。 狂うにはじつに多くのことを知り過ぎたのだ。たゞ遣瀬無(やるせな)くなる、それを堪(こらえ)るために富造は少し角度を穏やかに変えて高札をながめた。
立札がいう「騒ぎなり」とは、日本政府が社格制度を廃止させた騒動のことである。
昭和21年2月2日、神道(しんとう)指令により神社の国家管理が廃止されるのと同時に社格制度も廃止された。
「 神道指令とは昭和20年12月15日にGHQが日本政府に発した覚書の通称である・・・・・ 」
覚書は信教の自由の確立と軍国主義の排除、国家神道を廃止し政教分離を果たすために出されたものであり、「大東亜戦争」や「八紘一宇」の語の使用禁止や、国家神道、軍国主義など過激なる国家主義を連想するとされる用語の使用もこれによって禁止された。
この覚書「 国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件 」に従って、日本国の神社の性格が解体されたのである。
「 それまで山王日枝神社は、神祇官が祀(まつ)る神社の官弊(かんぺい)大社として一等に列格されていた・・・・・ 」
高札はこれを廃棄させられた側の憤慨の証であった。そこで貞次郎という不器用な男は高札を立て続けることに固執した。立札がなされてから、すでに半世紀が経っている。
「 この高札も、古い日本を信じて今も立っているというのか・・・・・ 」
富造の眼には、敗戦直下、許されぬ神の住まいを覗(のぞ)きみるような恐怖で息をつめて高札のあたりを見まわした古人(ふるひと)の自らが羨(うらやま)しいのである。しかし反面、老人は自分が戦中に何をしたかを考えなければならなかった。
それは胸倉の片隅に直径一尺ばかりの不発弾が、二つ三つ四つ転がっているような、何時(いつ)如何(いか)なるときも棘(とげ)に座らせられて居た堪(たま)れない燻(くすぶ)りである。
「 界隈を焼き焦がし草のない世界にしたのは軍人であった・・・・・ 」
当事者であるその軍人の眼でみても、この高札が、敗戦という大事件の中で人間が人間にもたらしたところの、屈折した遺恨の表現であることに変りはない。今や無の沈黙としか理解されないが、もはや貞次郎の手を離れても、尚(なお)、堂々と起立し憚(はばか)り続ける高札なのである。キリストの血に係る彼(か)の国による試みは、日本国の敗北というより、密かに産み落とされて揶揄(やゆ)された仇名(あだな)も「リトルボーイ」という少年の血に宿された惨劇と悲劇であった。
「 人間が殺されることに正義などなく、国を比べ較あわせて人が下す勝敗などに何の意義もなく価値もない。あるとすれば唯一、無防備の人民を無差別大量に撃殺すことを可能とした科学の敗北であったろう。彼の国では神は人間に叡智を与えたのであるというが、その科学という聖域をみずからが手で穢(けが)した・・・・・! 」
その多くがキリストを父としマリアを母とする子供らの手なのであった。
日本では「 天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ人ノ下ニ人ヲ造ラズト云ヘリ 」という明治維新の一節が有名である。
この「云ヘリ」とは、現代における「云われている」ということで、したがってこの言葉は福沢諭吉の言葉ではなく、アメリカ合衆国の独立宣言からの引用である。咸臨丸でアメリカに渡った福沢はこれを範として日本国民の行くべき道を指し示した。
しかし範とされた彼の国がその宣言で人の平等を説きながら、広島のリトルボーイで輝かしきその伝統の法灯を消した。長崎の不必要がその思いをさらに強固に証明させるのである。




中でも、「 全ての人間は平等に造られている 」と不可侵・不可譲の自然権として唱えている。
このことを憂い思う富造は、戦後の1946年に公布された日本国憲法の第十三条「すべて国民は、個人として尊重される」にも、その影響が見られることに、人民の下にあるばずの国家というものが全く危うく思われるのであった。
福沢諭吉は、江戸時代末期から明治時代初期にかけて、西欧文明が押し寄せてくるのに先立ち「 天ノ人ヲ生スルハ、億兆皆同一轍ニテ之ニ附與スルニ動カス可カラサルノ通義ヲ以テス。即チ通義トハ人ノ自カラ生命ヲ保シ自由ヲ求メ幸福ヲ祈ルノ類ニテ他ヨリ如何トモス可ラサルモノナリ。人間ニ政府ヲ立ル所以ハ、此通義ヲ固クスルタメノ趣旨ニテ、政府タランモノハ其臣民ニ満足ヲ得セシメ初テ眞ニ権威アルト云フヘシ。政府ノ処置此趣旨ニ戻ルトキハ、則チ之ヲ変革シ、或ハ倒シテ更ニ此大趣旨ニ基キ人ノ安全幸福ヲ保ツヘキ新政府ヲ立ルモ亦人民ノ通義ナリ。是レ余輩ノ弁論ヲ俟タスシテ明了ナルヘシ 」と、著書「西洋事情」で、「 千七百七十六年第七月四日亜米利加十三州独立ノ檄文 」と、して、アメリカ独立宣言の全文を和訳して紹介した。
このうち、冒頭の章句および思想は、後の著書「学問のすすめ」初編冒頭に引用され、日本国民に広く知られるところとなった。
「 日本には障(さわり)という言葉使いがある。その顕あらわれ方は、言霊(ことだま)の作用である。古代から日本では言語の裡(うち)に神が顕れた。つまりそこには日本の神の心がある。この神意は畏れ多い日本人の他は解らない。神の意志とは人間の意志では表せぬ日本国において、そのような障りがどこに向かうかは日本人の心のみが予感して判ることである・・・・・ 」
それはまことに小さく斬新な科学、直径75センチ、長さ3メートル、重さ4トンの人類未曾有の兵器である。
それが広島のリトルボーイ(少年)と、長崎のファットマン(豚男)であった。
この原爆で玉砕され、かくして莫大な障りを享受した日本国民は、被爆国の理性を芽生えさせて戦後を生きることになったが、新たなこの理性を真摯に享受した富造は、この一点で新たな日本人であることを誇りに思い続けている。
「 リトルボーイ・・・・・ 」
と、確かに俺はこの耳で聞き取った。
テニアン島ハゴイ基地からの打信音の中に・・と、語りかけるその古閑貞次郎の眼光は、人の心の奥底まで見透かすほど鋭かった。
「 こんな、こんな、こん畜生があるのかい 」
一瞬気圧(けお)されるのを感じた富造は、気後れしそうになる自分に活を入れながら震えるように聞いていた。
何よりもリトルボーイという奇妙なコード番号の新語が耳に斬新であった。
「 あの時、参謀本部が広島に敵機襲来の空襲警報を発令してさえいれば、多くの人命が救われた。なぜ、発令はなかったのだ! 」
と、こう語りながら烈(はげ)しく詰め寄る貞次郎の終戦直後の無念さが、富造によみがえり脳裏を痛烈にかすめるのだ。体は小柄(こがら)だし、ふっくらとした顔には温和な笑みを普段は泛かばせていたが、このとき貞次郎は貌(かお)を、十歳ほど老けた鬼の姿に変えていた。
この貌に富造は酷い障りを強く抱いた。
「 北マリアナ諸島の一つサイパンから南8キロにテニアン島がある。その島北部に諸島最大の飛行場を有するハゴイ基地があった。1944年(昭和19年)7月まで、この基地は約8500名が駐屯する日本軍の重要な軍事基地であった 」
その7月、北部チューロ海岸から米軍が上陸、日本軍を玉砕し8月には同島を占領した。
これが戦史に名高いテニアンの戦いである。

以後、飛行場は拡張され本格的な日本本土空襲を行う前線の基地となった。
この戦いは、日本の終戦をすでに決定づけていた一戦ということになる。
7月16日にはすでに、米国内でのトリニティ実験(プルトニューム原子爆弾の起爆実験)が行われ、成功した同日サンフランシスコ港から重巡洋艦インディアナポリスに同型原爆の二種類、リトルボーイとファットマンが積載され、日本本土への爆撃機の基地であるテニアン島へ向け出港をしている。 到着後、リトルボーイの組立が完了したのは7月31日であった。
昭和20年8月6日、真夜中、日本軍の諜報(ちょうほう)部隊はテニアン島を軍事拠点とする米軍部隊の無線情報を監視し、懸命なコール無線の傍受によってB29エノラ・ゲイという特殊任務を帯びた敵機部隊が広島に接近していることを察知した。しかしその諜報は、防衛に生かされることもなく空襲警報すら発令されなかった。古閑貞次郎26歳は、通信班を率いる中尉としてこの諜報の任務にあたっていた。
「 あの時、一翼の紫電改(しでんかい)すら広島の上空に無かった・・・・・! 」
確かに本土決戦に備えた当時、すでに零戦では米英軍の新鋭戦闘機に太刀打ちできなくなっていたし、ようやく完成した雷電(らいでん)は実戦配備が遅れ、空中戦の切り札として紫電改は残されてどこかに待機していたはずだ。
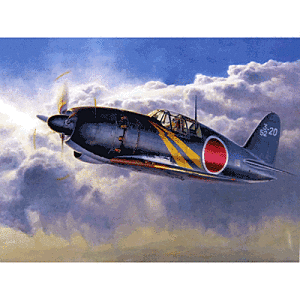
高度一万メートルの上空で交戦できる戦闘機は紫電改(紫電二一型)しか他はなかった。本機は遠方から見るとグラマン社の米海軍F6Fヘルキャットとよく似ており、誤認させる作戦は夜間の戦闘上有効でもあった。
一説では当時、日本国の敗戦を予期したソ連軍が北部から南下を開始したことで、参謀本部は混乱を極め適正な判断が疎(おろそ)かにされたというが、そうであれば益々貞次郎は不本意なわだかまりが消化できずにいた。ドイツが降伏したのは5月7日。その後に欧州戦線のソ連軍が満州方面に大挙して移動中との情報が入ったのであるから、その間約三ヶ月、軍議に暇(いとま)なきことが参謀の本分であろうから、と考える忠誠の貞次郎には理解不能なことであった。
「 俺達の懸命な諜報任務は一体何であったのか、あの有様は・・・・・ 」
貞次郎の吊りあがった細い眼が、らんらんと輝いていた。このとき富造は深くため息をついた。これは初老である阿部富造が未だ若く、戦後昭和21年にようやく再会を果たした折りの、古閑貞次郎との会話である。
以来、語る復員者と聞く復員者とにできた空白は一度も動こうとはしなかった。
しかしあの時、小刻みに震える貞次郎の肩を見ているうちに、富造はどうしょうもない無力感にとらわれたが、なぜ気力が萎(なえ)ていくのかが解らなかった。富造の無念や痛哭は終戦という結論では一切閉じれないのだ。


「 日露戦争から40年後、来日二度目のマッカーサーは、大日本帝国の凋落(ちょうらく)に立ち会うことになる・・・。この黙示録的な黒い影がふらふらとする時間の経過とは一体何か・・・・・ 」
1945年(昭和20年)、降伏文書の調印に先立つ8月31日に専用機「バターン号」で神奈川県の厚木海軍飛行場に到着した。厚木に降り立った最高司令官マッカーサーは、記者団に対して第一声を次の様に答えた。
「 メルボルンから東京までは長い道のりだった。長い長い困難な道だった。しかしこれで万事終わったようだ。各地域における日本軍の降伏は予定通り進捗し、外郭地区においても戦闘はほとんど終熄し、日本軍は続々降伏している。この地区(関東)においては日本兵多数が武装を解かれ、それぞれ復員をみた。日本側は非常に誠意を以てことに当たっているやうで、報復は不必要な流血の惨を見ることなく無事完了するであらうことを期待する・・・・・ 」
と、コーンパイプを燻くゆらしたのである。
このような因縁の交わりのもとで織りなす敗北と勝利のさまとは事実としての奇妙な奇跡であった。
「 いにしえより日本の四季は、朝の凛(りん)に夜の幽という・・・・・ 」
マッカーサーが初めて訪れた日露戦争の当時、日本には楚々(そそ)とした野趣の漂う日本人の長閑な凛とした生活があり、表には近代文明へと生き急ぐような変貌ぶりで、国勢の絶頂を幽(かそ)けく見せつける滞在期間があった。この絶頂から凋落までが40年、そのすべてが戦争に尽くされた何とも不毛の時間であったわけだ。
昭和20年(1945年)9月2日、東京湾の戦艦ミズーリ艦上で日本の降伏文書調印式が行われた際、嘉永七年(1854年)の開国要求を果たした折りの、ペリー艦隊の旗艦「ポーハタン」号に掲げられていた米国旗が本国より持ち込まれ、マッカーサーはその旗の前で調印式を行なった。
このセレモニーを演出してみせたマッカーサーの意図が、大戦の一切が不毛であったことを物語っている。富造にはこうした日本人に向けた決着の付けようが一つの慟哭の要因なのだ。日本の男児には馴染まないのである。


「 人間どうしが互いに理解しあうことが困難なのは、しかし、国家と国家とのつながりだけなのであろうか。同じ時代を生きた人間どうしの心にも、語りがたい体験の落差として、孤独の深淵(しんえん)は今もぽっかりと口を開いているではないか・・・・・ 」
マッカーサーやアインシュタインの孤独が不毛なものであるなら、大日本帝国の情熱もまた不毛なものであったかもしれない。にもかかわらず、どんなに徒労に終わった情熱でさえ、やはり人生の固有な一駒をなしているし、人間はどの時代に対しても、それぞれの夢を抱くことに変わりはない。敗戦には一言もないが、アメリカは日本人に潔い敗北の慟哭を自責させることをしなかった。
「 現代の日本と自由な交渉を持つアメリカを、戦後の解放の所産と見ることもできなくはないが、戦争が人間に与えた痕跡は、まことに複雑を極めたものであった。特に原爆の、その苦痛はあまりにも量り知れない。私は最期の沖縄も見た。文化とか心とかは合理や効率で分かち合えるものではない。心ここにあらずの米国と結び合う将来とは不安だ! 」
眼にペリー艦隊の旗艦「ポーハタン」号に掲げられていた星条旗が三度みたびはためく。無性にはためくのだ。無性に障るのだ。
人が末期(まつご)に見る色がどんなものかは知る由もないが、これに対し、死体とはまったく沈黙の世界である。ひたすら静謐(せいひつ)なのである。そこには人間を限りなく誤解させるほどの静けさがある。その人の死とは、冷然と人間界を無視して勝手に動いてゆくものではないであろうか。人間とは卑小であるから、と、済ますのでは悪意に翻弄された人間の心の傷が永遠に癒えることはない。そんなはずはない。富造は同世代の死者にたいして拘泥(こうでい)せずにはいられないのである。
たしかに人間は卑小かも知れぬ。だが富造には、還暦を過ぎて長寿になろうとするまでを生き永らえて享けた命のあることの意味として、仏の済度に洩(もれ)た衆生(しゅうじょう)を救うために現れる未来の仏も人間にはあるような気もする。そんな陰陽寮博士・富造の、花卒塔婆(はなそとば)とは、あらゆる死者たちに化粧を施し、哀しくも美しく弔うことであった。
「 神に丘惚れした男に板塔婆(いたとば)はなかろう。貞次郎には花そとば、どうだ此(こ)の花は、貴様には比叡山の野花と語り合って欲しい。あの世でもきっと俺の花形で居ろよ。なあ貞次郎よ!・・・・・ 」
高札の根元に富造はそっと水引(ミズヒキ)の赤い花穂の小さな花束を添えた。
「 待っていろ貞次郎・・・・・!。俺も間もなくそちらへ行く。きっとお前はあの姿で、あの坂にいるのであろう。あゝ、俺もそうだ。あの坂の頂きにまた二人して立とうじゃないか・・・・・! 」
富造が古閑貞次郎という男との最初の出逢いを想い起こそうとするのは、今日が彼の祥月であるからで、高札を眺め終えた初老・安倍富造は、茅葺きの門前で一礼を終えると、眼に刻み込まれた二人だけの、あの青春を描き起こした。













リトルボーイ 広島





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます