




































(六) 漏 電 Rouden
ウチナーンチュが時間を厳守する性格であることは今や常識であるという。
「 沖縄には琉球時間という特別な体内時計がセットされているというわよ・・・・・ 」
そんな話を修治は非常識な妻の沙樹子から聞かされていた。
沙樹子には何度か沖縄出身者の弁護を担当した体験がある。その体験によると非常識だそうだ。しかしこれは沙樹子が沖縄の人とは違う時計を常識と思い込んでいるふしがある。弁護士が弁護しずらかった琉球時間、その非常識、常識にかかわらず、今日まで時間厳守を貫いてきた性格上、修治は果たして柔軟に対応できるのか心配であった。相手も時間厳守の人である。
「 郷に入れは郷の時計に従える人が常識者なのだ 」
そうも思える許容はゆるやかに意識しているつもりだが、しかし相手に合わせることは不慣れでもある。うつ病になってここ数年間、意識して融通の利かぬ男でいようと自覚してきたのだ。そのために遠に携帯電話は捨てている。
30分経過した。たが名嘉真伸之は現れない。やはり琉球時間だけが見事鮮やかに修治の眼の前に現れていた。
一人の人間が二つの時間内に存在する沖縄の待ち時間とは、なるほどなかなか不可思議なものだ。最低1時間のロスは予見しておかないと貴方の場合とても癇癪(かんしゃく)を軽減するのは困難だからと、事前にそんなアドバイスを沙樹子からされている。
しかしその一時間が過ぎても名嘉真は一向に姿を現さない。コンピュータがわれわれの脳や心のはたらきにどこまで食い下がれるかという問題は、世界の錚々たる科学者がズラリと顔を揃えて、1950年代にまだサイバネティクスに人々が熱中していた当時から、先駆的な議論がされていた。そして人工知能(AI)の可能性が爆発した80年代は、比江島修治も片っ端からそうした動向を傍目で観察していたのだが、どうも成熟した問題を議論しているようには思えなかった。その積年の疑問について解答が何時与えられるのかと期待したくなるのだが、どうやらその期待は沖縄の体内時計に硬く拒まれて、あっけなく裏切られることになるようだ。
やがて二時間が過ぎようとしている。こうなると相手のイレギュラーに猶予する問題ではない。すると修治は、現代の日本が立ち会うべき時間の問題を沖縄が引き受けているだろうことだけは、存分に確信できた。
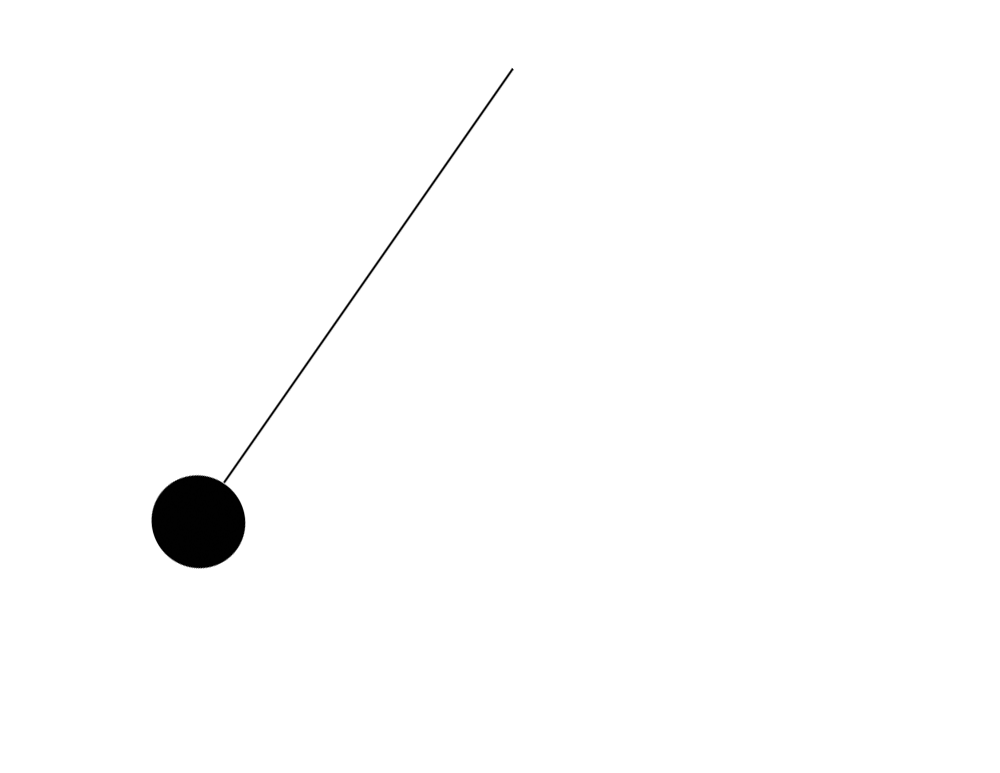
「 やはり琉球とは、日本における傑作の人種なのだ・・・・・。そして、恐るべき子供たちなのだ・・・・・ 」
絵画や書籍などの優れた作品には、観手や読み手側の常識や良識と、多々ぶつかるところがある。そこには人間が安住する世界を揺さぶるだけの力が宿されている。たとえば戦争はダメ、平和は大切だという常識性の価値観だけで咀嚼(そしゃく)できる作品であれば、誰も観ないし読まないであろう。傑作とか名作という類(たぐい)の産物は、挑発することに意義と価値がある。修治は名嘉真にある種の挑発を感じた。
「 ドストエフスキーは、青年に金貸しの老婆と妹を斧で打ち殺させて罪と罰にしたではないか・・・・・。僕を手招きで挑発している 」
と、非常識は時として、主張の根幹をなし、時代の閉塞を反映させるモノで、そう思えると比江島修治は、遅延で挑発してくる名嘉真の常識を超えて現れた非常識な時間に身震いするような快感を覚えた。修治の常識が地響きを立てたのだ。
「 どうやら沖縄の体内温度を、いわばその「一時しのぎ」という「かりそめ」にみる、そこに日本の弱点があるとみなした方がよさそうだ 」
だからこそ、世界の諸文化のなかで、あるいは日本文化のなかで、沖縄の文化は比類のない人の営みによる成果だという見方を挑発してまでも披露してくれているわけだ。それが修治には、日本人が琉球の面影の本質を読みとる感覚と才能のかなりの部分を失っているからだと思えた。現在の沖縄は問題を背負いながらも琉球と少しも変わらない姿でいるのだ。だから琉球は、ナイチャーのような「卑しい関心」をもつこと自体に容赦なく鉄槌をくだすのだ。そして琉球は脳の未来もコンピュータの未来もありえないという結論を用意する。沖縄が性格に内包させる体内時計は、明らかに小さなビックバンなのである。念の為に三時間待ってみたが、ついに名嘉真伸之は姿をみせなかった。
「 予測できない何か常識的なアクシデントがあったのであろう・・・・・ 」
そうポジティブに思うことにした。修治のそれは一つの発見である。
「 これは僕の時計と名嘉真の時計が違うという問題ではない。東京と沖縄の時差なのだ。日本国内には時差がないとするのは、そもそもが詭弁なのである。厳密にいえば1mm間隔にも時差は生じる。人はこういう厄介な問題は科学から省略させる。同じように沖縄と東京間に生じる時差は日本人が勝手に消却させたことによる違和感だ。そこには日本人の身勝手が沖縄に押し付けてある。僕は潔くこの時差を認めなければならない。そして僕の対応能力の未熟さを正さなければならない・・・・・ 」
ある結晶的な図形の性質を研究し、その図形を体験的な図形のように平面に並べることはできるのだが、修治は、自身の体験によるその並べ方は非周期的にならざるをえないという不本意な法則を沖縄に発見した。もともと曲亭馬琴で有名な「椿説弓張月」の椿説を解析し、日琉同祖論の根源を現在の沖縄に求めようとしたのがほかならぬ修治自身だったのだから、こういう発見があっても当然なのである。
「 たぶん、われわれ人間の心は、古典物理的構造の対象なるものが遂行する、何らかのアルゴリズムの特徴にすぎないというよりも、われわれの住んでいる世界を現実に支配している物理法則の、ある奇妙な驚くべき特徴に由来する性質を持つのであろう・・・・・ 」
が、このことは容易には見えてはこない。一杯のコーヒーで三時間も窓際にポツリと居座り、ダイワロイネットホテル18階のレストランから見渡せる那覇新港の上空にある白い夏雲の動きをしばらくながめていた修治は、琉球とその心について新しく学ぶべきことが、自身の知覚する「時間の流れ」に密接な関係があるらしいと思えるようになっていた。その「琉球でうごめく時間の流れ」には、きっと日本人の本質としての量子と重力がからんで関与しているはずで、それが今、修治の脳と心を支配していることを、微妙な発光で白雲を揺すり動かす琉球の空にそう感じていた。そして欝(うつ)を晴らそうと脳内を刺戟する処方の光りにゆるやかな爽快感を覚えた。
「 8月29日午後3時。これは反古(ほご)か、常識なら仕方ない・・・・・。三年前の約束なのだ・・・・・ 」
修治はもう一度、那覇市街のパロラマを一望した。そしてまた東の方にある雲の流れに眼をあてると、美妙な輝きと絶妙の彫琢があるにもかかわらず、平然と流れ動く雲の歯車が、不思議なほど青い空の真実を傷つけていないことを感じさせてくれた。それは不束な夏の青さが雲の白い動きをうけてその精神を受胎しているような構図でふわふわと描き出されていて、空も雲もじつにフラジャイルなのであった。





人生はところどころ辻褄があわないものだ。60年にわたって生き継いだせいもあるし、そのような辻褄のあわないところに自分の身をおくことが、そもそも修治の生き方だったようにも思われる。しかも50歳代の最後といえば、だいたいの男は自分の限界がどんよりのしかかってくる時期である。いまさら好看(きれい)ごとで済ませるものなんてないということも、分かりきっていた。そして分かりきったと安易に思えば、そこから先は行ったり来たりで、さも修治は、土壁の前に立ちながら左官が鏝(コテ)を右往左往させているばかりの男なのだ。自身の意に反して相貌は正直なことをいう。60歳を過ぎてみると、前に憚る相貌のそこを修治はなかなか承知できなくなっていた。
そこで一つの決心は、携帯電話を使用しないことにした。つまり電話が紐でつながれていた時代に我が身を置いてみることにした。常識は時代が作り出している。人はその時代の常識に動かされている。しかし昭和までは辛うじてそうではなかった。修治は自身の常識を取り戻したいのである。一度、時代を相手に訴訟を起こしたいが弁護できるか、との問いに、すかさず沙樹子から大笑いされた。そういうことは人類史上判例がないという。あるとすれば日本神話のアマテラスとスサノウを沙樹子は例えたが、スサノウの控訴は問答無用と棄却された。
宿泊予定のホテルは9階がフロントである。最上階の18Fにいた修治はチエックインを済ませるために下の階に降りた。
「 予約しておいた比江島だが・・・・・ 」
名前を名乗り、そしてチエックカードを手にとってみて、いよいよ虚無を抱きはじめたとき、フロントの女性はそんなことにはおかまいなしに、しかしその笑顔は驚くほど新鮮ではあったのだが、渋々怖々と、一枚の伝言を差し出した。
「 あの~ッ、一応お預かりはしたのですが、先ほど・・・・・ 」
と、差し出した嘉利吉(かりゆし)の清楚で白い琉球紬七分丈の彼女は、まだ若かった岸田今日子が演じたジャンヌ・ダルクのような少し捻れた禍々(まがまが)しい笑みをした。受け取ると、たしかに禍々しくもなりそうな文面を短く二行連ねたいかにも奇妙な伝言であった。何しろ岸田今日子似の白い細指から受け取ったそれは何というのか、ビーナスめく魔女の鏡台の匂いでもこっそり嗅ぐようなものだった。
その伝言の内容は真逆にして想えば、それは沖縄の真夏の夜陰に出る幽霊にでもふさわしく、ふと修治はニコライ・ゴーゴリのごとく外套の襟を立てたくなったのだ。まぎれもなく名嘉真伸之からの言伝であった。
人ごみに蝶の消えたる盂蘭盆会 明日の陽は靴の底なり昆布橋
「 もともと琉球は地球の土につながっている。その地球である琉球に新たな人間たちが生まれてくるときは、月の作用が女性たちになんらかのものをもたらして、その新たな人間がよく育つようにするはずだ。そして新たな琉球の人間を迎えることになる女性たちはきっと月になっていく。それが証拠に、琉球の地球は毎年、盂蘭盆会が近づくたびに、地球のすぐ内側にある琉球にとても月に似た部分をつくっているものなのだ。だから盂蘭盆会のころ琉球の人はいつも月と一体になる・・・・・ 」
と以前、名嘉真はそう語ったのだが、琉球の人々は、これを舞踊し、これを感知することを現在も試みるのである。超感覚的知覚とでもいうべきものがこの世にあり得るだろうことは、堅物の科学者以外はだれも否定していない。修治でさえ、そんなことを否定したら科学の未知の領域がなくなるとさえ考えてきた。そう思う修治は、ただひたすら血走った目で暗号めいた書付を何度か口ずさんでみた。
「 沖縄は、そうか旧盆なのか・・・・・ 」
わずか二行の俳句で言伝しようとする名嘉真のメモ書きは、奇怪で非常識な人生を歩んで、他人に迷惑をかけつづけた俳人たちの日々でも拾ったような、それでもって我が身が忙しいからと捨て台詞のような名文なのであるのだから、真実それが沖縄の旧盆というものなのだ。
旧盆という沖縄の常識も知らずに、約束を無理強いをした修治の方が迂闊なのであった。
「 三年先の旧暦を意識して相互の都合を見通した約束などではなかった 」
沖縄の日常は現在でも旧暦で成立する。その年行事でも春の清明祭(シーミー)と旧盆とは特別に意識されている。おしなべて人々は旧暦7月13日(ウンケー)は必ずお墓に行き、先祖をあの世からお迎えして、家まで連れてくる。14日(ナカヌヒー)はお中元を持ち、親戚を一軒々々回って歩く。15日(ウークイ)は迎えた先祖を、またあの世へとお送りする。この三日間だけは何事があろうと絶対に妥協しないのだ。
そうした沖縄の民俗文化は、大きく言えば信仰にもとづいて形づくられている。
ここには御嶽(うたき)という神聖な空間がある。御嶽は本土のように神社などの建造物がなく樹木がこんもり茂った場所で、御嶽での祭りは「神女」が中心となり、信仰の際には女性が大きな役割をもつ。ウナイ神という言葉があるが、これは男性にとっての姉妹を意味し、ウナイ神信仰は、兄弟に対して霊的に守護するということの表れで、女性の役割が重要視される。
それらの主体者となるノロ(祝女)は琉球王国時代に制度化されたもので、王国が崩壊してからも村の祭りを担ってきた。また、ユタ(呪術職能者)も圧倒的に女性が多い。ユタは公的な祭りに関わるというより、個人的な吉兆を判断する。このように沖縄の信仰には大きく女性の霊力が中心をなしている。沖縄とは神話を超えて、日本で唯一アマテスの現存するエリアなのだ。
名嘉真はその盆行事の蘇生にあたっては沖縄の情熱や狂気に与(くみ)せず、あたかも写経などするようにその感情を殺して俳句仕立てにしているが、修治はそこに「ヒラウコー」の幽かに揺れる赤い火を想い起こした。沖縄がかかえこんだ琉球の世界というものが、われわれ日本人の存在がついに落着すべき行方であって、そのことを名嘉真伸之がとっくの昔から見据えていたということだ。





「 未来があるということは、どんな風土にもつねに未完成がつきまとう・・・・・ 」
この世にはアマデウス・モーツァルトのように、あえて未完成を標榜する名曲もあるが、そうではなくとも、どんな風土にも未完成というものが忍びこんでいる。名嘉真が伝言とした二つの俳句は、三年前に修治の目の前で披露してくれたものであった。これは沖縄生まれの名嘉真らしく最も自伝性が濃い作品といってよい。それなのに名嘉真は、三年間、句集にすることをまるで反故にするかのようにほったらかしにしていたようだ。修治はその仕上がりを心待ちにしていた。
名嘉真伸之の話によると、こうした俳句は明治が終わるころに生まれた伸之の母るつ美が、沖縄の家庭を守る火の神ヒヌカンに着せられた芭蕉布の一枚一枚と、るつ美の子守役でもあった「サシおば~」の生きた琉球への眼差しを通して、時代とともにしだいにめざめてきた名嘉真の俳句なのである。そうであるから修治には、琉球女性の心身が育まれる俳句というふうにもうけとれた。
思えば三年前、当時は旬の話題がクールビズだったころに、琉球紬のことを持ち出したところ、名嘉真が「 うん、あれこそは琉球女の本格的な教養絵画ですよね 」と言ったものだった。そして加えて琉球紬や芭蕉布が琉球精神の修成をたどる作風であることを強調した。
たしかに伝統的な琉球の着物は女性の心身なのである。それは今日の、かりゆいファッションが現代女性の関心の大きな部分を占めていることでもわかる。たしかに伝来の琉球衣裳は、和服や洋服よりもずっと心身を感じさせてくれる動機に満ちている。そうであるから琉球の着物にはいくらでも妖精や魔物が、そして神々の想像力や吉凶の出来事が棲みこんでいる。いや、綺麗に染みこんでいる。それらは琉球ができることを身をもって伝えてくれた日本希有の文化遺産なのであった。








琉球が着物の柄や形を素朴に乱舞させて幽かで艶やかな女の妍を表現するという方法であり、また琉球紬のような着物や染物が文化の腑に落ちるというための方法であるとき、比江島修治には、いわばそれらが腑に落ちるも腑に落ちないも、基地問題こそが逆にそのすべての生命を引き取って沖縄の人生を着て、この人生に帯をしめていくという残酷な黙示録だったことが見えるのであった。
「 しかし、毒と薬はうらはらなのである。同じものが薬にも毒にもなりえるのだ。似て非なるものではない。同じく戦争と平和も裏腹なのであり、似て非なるものではなく、同じ意識が戦争にも平和にもなりえるのである。日本憲法の九条の件も、護憲にしろ改憲にしろ、平和のための護憲か、平和のための改憲か、いずれも意識の方向次第で戦争にも平和にもなりえるではないか・・・・・ 」
そう考えると修治は、戦後の沖縄は、その生体はさまざまな生化学反応をしてかろうじて生命を維持している。沖縄に生きるということは「 生化学している 」ということだ。これらの反応はすべてが相互に連関していて、言ってみれば平和と戦争の複合的なインタースコア状態にある。だから何か一つの反応が不首尾になると、その他の反応に大小の影響が出る。沖縄をこうした生化学反応を実験室とするフラスコ形式の中で進めようとすると、そこには「 酸や塩基を加えて100度で1時間加熱する 」といった苛酷な条件をつくる必要がある。そうしないと反応はまずおこらない。基地を抱え込む沖縄とは、まさにこの過酷なフラスコ型の巨大な壺の中にあるのだ。
修治はさもジャンヌ・ダルクを演じた怪しげな岸田今日子のごとく貌(かお)させてキープした15階の部屋へと上がっていった。
「 明日の陽は靴の底なり昆布橋 」・・・・・「 昆布(こんぶ)か・・・・・ 」
ホテルは沖縄の新しいビジネス拠点「新都心」のランドマークとして2011年10月にオープンした。その晩秋に修治は一度このホテルを訪れているが、案内したのが名嘉真なのであった。白を基調とした真新しい部屋のソファーに深く腰を沈めてみると、眼を閉じた修治の脳裏には三年前の光景がくるくると回りはじめた。名嘉真の句の一つにその光景がある。
「 龍田丸・・・・・! 」
修治のまぶたには海原を渡り琉球の港をめざす古い一隻の帆船が浮かんでいた。
三年前、今日と同じように旧52高地の光景を見終えた修治は、おもろまち駅から乗車して次の古島(ふるじま)駅で降りた。
ゆいレールの相対式ホーム二面二線を有する高架駅である。国道330号の上に建つ。すると修治は次に330号線を真北へ、たゞひたすらに眼差した。現代の内地に暮らす日本人は、戦後も遠くなったとばかりにさも能天気だけれど、戦後の沖縄とは戦時のページを繰るのがもどかしいほど愉快なのだ。やはり沖縄には、唯一ここだけの不機嫌な愉快さがある。それは生命化学の複雑なしくみを解きほぐして行くような愉快さなのだ。
唐船(とうしん)が来たと叫んでも、若狭町村の瀬名波しなほのおじいさんは一目散に走らない人なのだが、当時、 たゞ血奔るごとくあった修治の、その眼には、しだいにサンゴ礁の連なる紺碧の金武湾(きんわん)が広がってきた。 江戸の当時、この金武湾を目指して南海の白波を越える一隻の北前船があった。
「 その沖縄の港界隈は真昼間である。美しい遠浅の海岸には、しかし暗黒の波濤が揺れていた・・・・・ 」
たゞ、ジッとその黒く泡立つ静かな波音に修治は耳をあてた。
「 昆布(こんぶ)の北側、桟橋ポイントに、漏電地がある。そして前方に航路、その景色を確かめる必要がある・・・・・ 」
漏電地帯(リーキジ・エリア)、そう思えると修治は、闇間に浮き上がる航路の彼方をギッとみつめた。真上には太陽が輝いている。
「 この航路の景色に、一つ枕をつけよ、とは・・・・・! 」
いつも通りの彼女らしいおどけた文言である。修治はふゝとニヒルに笑った。
「 この海に一首、歌を詠むとすれば、枕にはやはり(夜干玉ぬばたま)・・・・・、これしかない 」
そう固定していゝ。置き替える言葉は他にない。すると修治の瞳孔が開いてきた。こうなると妙に1938火野葦平の『麦と兵隊』が重なってくる。修治は最初これを読むのがキツかった。火野のモノなら『糞尿譚』のほうがお気にいりで、しかし沖縄にいる修治は『革命前後』を遺して服毒自殺した火野の生涯像が気になってくる。沖縄の自然は申し分のない天然作品、だからこそここには病気的・猟奇的な日本という一面も、民度風土という琉球の一面もあるのだ。悪しく語れば、それは天才的な日本人の創り上げた地中海型の神話的作品。この沖縄の10作を見らずとも1作くらい読むだけで戦後日本の歪が浮き彫りとなる。
この沖縄の性格には闇としての一面があり、内的生活と暴力的生活、殺害の欲望と創造の欲望とが、それぞれ同居する。いずれこうした矛盾が日本国内全土で露呈するだろう。すでに沖縄とは対極にある東京はすでにこれを露呈する。現在の沖縄には日本とアメリカがある。今日、その日本とアメリカはなかなか区別がつかない近親憎悪者なのだ。それらは似て非なるもの、なのではない。似ていて、かつ非なるものなのだ。日米関係が持つ薬と毒とは現代文明が見た同床異夢なのだ。いわば「ときどき薬、ときどき毒」なのである。そして内地は薬、沖縄は毒こそを与えられてきた。だが副作用のない薬はなく、量に無関係な毒もない。結核に効く抗生物質ストレプトマイシンは難聴という副作用をもたらし、整腸剤キノホルムはスモン病を併発させた。
では、或る薬がおこす副作用を日本国が抑えられないかといえばそうでもなく、たとえばキノホルムの投与と同時にビタミンB12を補うと、これがアルツハイマーの特効薬になることが最近わかってきたことに例えても、沖縄の現状が本来の日本回帰への回復薬になる可能性は十二分にある。沖縄の日差しは修治に未だそれほど眩しすぎた。アメリカと日本政府によってばらまかれた沖縄の毒と薬は、島民の意識が二分されたように裏腹なのである。昔から日本では「色白は七難を隠す」と言われてきたように、なぜか顔色や肌色を白っぽくしたいという美醜観が強くはたらいてきた。この人種固有の黄色肌を国策的・人為的に変更してまで美白を求めるのは、つまり日本人は色白人種に一等憧れているということにほかならない。修治はこういう白人アメリカ主義を好まない。うつ病をくれた東京がそのことを教えてくれた。




「 何だ、この妙な痺(いた)さは・・・・・? 」
ふと背筋、指先がビリッとした。にわかに痺しびれは地より昇る。しだいに刺し上がる。修治はジロリと己(おのれ)の足元をみた。そこには、ふらふらと修治を揺する影がある。
ハタと気づくと周囲に闇と影があるのだ。そして修治の影は泛うき立って揺れた。しかし闇間にモノ影が泛くはずはない。すると影は幻想であろうか。いや真昼間だ。影の方が正しい。ならばやはり闇の方が幻覚だ。しかし修治の前にはたしかに闇がある。そして暗黒の航路はその闇の足元から彼方へと伸びていた。
これは不思議だ。たしかめようと影を探した。すると瞬時、全身に電流(カ―ラント)がビッと奔った。
「 俺は、今、感電(ショート)しているのだ!。俺は燃えそうだ! 」
針のごとく全身の毛が闇によだつと、堪(たま)らず修治の眼は放電スパークをしはじめた。
「 これは・・・。やはり彼女のいう通りだ。こゝの埠頭(ふとう)は・・・・・、漏電(リーキジ)している! 」
堪こらえ切れずに足は地を叩たたいて飛び跳ねた。修治は天願桟橋(てんがんさんばし)に立っていた。
「 天願桟橋が占める土地のうち、約半分は私有地である。このため年間一千万円を超える賃借料が地主に支払われている・・・これが漏電の対価か・・・・・!。ここは夢で人類が滅亡すると予言した場所なのだが、この体たらく。やはりここは人をだまして資本を稼ぐ日本国でありアメリカ国なのだ。俺にはこの国籍が分からない・・・・・ 」
桟橋を奔はしりながら修治はそう閃ひらめいた。
漏電(リーキジ)はこの断線(デスコネ)が原因なのだ。借地料を支払う見返りとして電線(ワイヤー)は切られた。修治は逃げないと感電(ショック)で火傷(ヒート)死する。保安柵まで修治は奔った。跳ねては転び、起きては転びして修治はようよう逃げのびた。
「 借地料は平成20年度に一千四百万円、地権者数は9名。これは桟橋部分だけではなく全敷地31千㎡の借地料。この施設地全域が漏電しているのだ。施設内の無断立入は不法浸入罪。しかし、だから敷地内には投光照明が備えられているのではない。この桟橋には密かに暗躍するモノ影がある。どうやら天への願い事の多くは夜陰の闇中で祈られている・・・・・ 」
そう思えると、これは離人症的な光景、あらかじめの喪失感、世界腐食感覚などをもって、よくもわるくもここに接触不可能領域みたいなものが流出し始めていた。地権者の大半が保身された借地料を基に沖縄を疎開するごとく東京に移転した。そこにあるものは資本主義自己肯定とウルトラ保守のための屁理屈ばかりがこびりついている。
沖縄県うるま市にある天願桟橋は長さ640m、幅約22m、最大2万トン級までの船が同時に接岸可能なのだ。閃く密かな船がある。修治は、この桟橋から闇の航路で結ばれている彼方に、怪しげな北太平洋の米領ジョンストン島を眼に描き出した。
「 沖縄本島には、ホワイト・ビーチ地区という揚陸・補給施設で、かつアメリカ海軍艦船が使用する基地があるが、天願桟橋は、ホワイト・ビーチ地区では揚陸できない、弾薬などの危険物の揚陸施設として使用されている・・・!。この天願桟橋は、米軍の沖縄占領と同時に海兵隊基地として使用を開始、そしてベトナム戦争激化に伴い拡張された・・・・・ 」
640mとは小さな細橋であるが、現実は、じつに甚大な暗黒を秘めているのだ。
修治の眼に泛かぶジョンストン環礁(Johnston Atoll)は、アメリカ合衆国領の北太平洋の環礁である。ハワイ諸島のオアフ島からは西に約1500㎞、ミッドウェー島からは南に約1000㎞の位置にある。





「 この紺碧の波濤には、あの枯葉剤Agent Orangeを載せた、暗黒の航路が泛かんでくる・・・・・ 」
ジョンストン島はかつてアメリカ軍の空港や港湾施設があり、数百名の居住者がおりホノルルなどからのコンチネンタル航空の定期便も就航していたが、2004年にアメリカ軍が撤収して以降、各施設は閉鎖され、現在は滑走路跡地やその他の施設の跡地が残るものゝ、すでに無人島となっている。しかしこの無人島ゆえに怪しく密やかなのだ。
「 ぴ~ゃらぴゃらり、ぴゃらりり~、ぴゃらり、ぴゃりこ、ぴゃたうら~・・・・・ 」
眼をつむり、小首を下げると彼女の笛の音が聞こえた。阿部秋子が吹くそれは、野仏のように無邪気で可愛い音色である。秋子は京都の狸坂多聞院(たぬきざかたもんいん)から姑洗(こせん)E陽律の笛を送り届けている。たゞしずかに黙祷、聴き終えると修治は左眼をギョロりと太陽に向けた。 秋子とは阿部美智代の妹である。この姉妹は修治の妻沙樹子とは縁戚関係にあった。
「 これが数々の戦争空間の形骸か・・・。アメリカと日本の関係、それは幕末の黒船に始まるのだ。そしてリトルボーイの投下で被爆し太平洋戦争は閉じた。だが日本と沖縄を結ぶ電線は断線したのだ。以来、沖縄は漏電をしつゞけている。大戦後、沖縄はベトナム戦争の最前線基地とされた。そして現在、沖縄は未だそのベトナム戦争で使われた兵器危険物を密かに蓄え、暗黒の航路で人知れず米領ジョンストン島と結ばれているのだ・・・・・ 」
比江島修治の眼には、輝く太陽の白光に重なるようにして左三巴みつどもえ紋のフィジャイグムン旗が哀しげにはためいた。それは誇らしい琉球王国の古旗である。そこには昆布を積んだ北前船・龍田丸がみえた。
「 日本人がどう思おうと、米国の基地利用が続けば、戦争の火種に日本は晒さらされる。戦争の脅威から沖縄が逃れられることはない。きっと沖縄はそうなる・・・・・ 」
と、かって阿部秋一郎は眼を皓ひからせていった。まったくその通りだった。ふと修治は亡き秋一郎が遺した大宝恵(おおぼえ)に記された赤いラインを想い起こした。現状の沖縄をみて感じることは、日本人の暴走をとめたアメリカの話ではない。近代および現代資本主義国家の歪みは成熟していない資本論から起こるというふうに読むべき現代黙示録十巻の光景であった。

















琉球の着物 1





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます