キャロットでは創業三十年代後半になろうと言うところを、平均勤続年数が9〜10年と言う少し平均や中央分布から乖離した数字が出ています。
創業25年くらいであるならば平均勤続年数が9〜10年と言うのはありえる数字ですが、37年で9〜10年は少しおかしい。
当て推量レベルの推測をしますと、このまま永遠にキャロットソフトウェアが続くにしてもこの数字は変わらないのではないでしょうか。
即ち、いつの時代に入っても、キャロットソフトウェアに入社した人は、平均で9〜10年辺りで退職を決意するということです。
それをなさしめる要因はなんであろうか、と言うことを考えた時、金銭的な問題、健康面での問題など物理的な側面の他に、心理的な側面において「この会社ではもうやっていけない」とモチベーションがゼロになったりマイナスになったりした時に退職するのではないでしょうか。
このモチベーションについて少し丁寧に見ていきましょう。
古い本ですが、モチベーション入門(田尾雅夫)を引っ張り出して検証して見ましょう。
F・ハーズバーグの二要因説が次のものとして紹介されています。
同前70ページより:
衛生要因:
1.賃金
2.さまざまな付加給付
3.作業条件
4.経営方針
5.上司や同僚、部下などとの人間関係
動機づけ要因(仕事に内在するモチベーションを維持・上昇させる要素):
1.達成
2.承認
3.仕事そのもの
4.責任
5.昇進
6.成長
これらをキャロットソフトウェアに適用してみるとどうなるでしょうか。
以下は私個人の意見を適合させた結果となりますが、この会社は年間10人ペースで採用したと概算する場合、8割弱の人間が辞めていく環境なので、辞めた人間の内の一人として私が書くことは、当たらずとも遠からずではないかなと考えます。
衛生要因:
1.賃金→安い
男性Sさんに聞いたが、同期女性Hさんとのボーナスにかなり色がついた結果で差が出ていて(男性Sさんの方が低い)、かなり落ち込んでいた。
そもそも評価制度が機能していない。色がつくのは上長の気分次第だと思われる。
2.さまざまな付加給付→ない。一度だけ、社員全員に10万円が配られたことがありました。でも今のネットの評価を見てるとそれ以降は全くやっていないっぽい。
3.作業条件→衛生環境は良く、危険性もないが、とにかくストレスの嵐である。
4.経営方針→ない。あるいは「金が稼げれば良い」。ちなみに仮想などの思想が無かった2000年台前半のコンピュータ業界の中で、樋口さんと言うオタク気質の古株の社員が仮想化を提案したところ「何の役に立つってんだよ」と言う一言で蹴った実績あり。つまり眼の前の金を稼ぐことが第一思想で、コンピュータの先の何たるかを追うと言う経営体制・経営思想ではない。
5.上司や同僚、部下などとの人間関係→ツンドラが如く大地さえも凍てつく極北の寒風吹きすさぶ環境・・・
とは言いつつも仲いい人はOFFは仲が良かった。
OFFはサバンナ程度だが、ONになるとツンドラモードになる。
動機づけ要因(仕事に内在するモチベーションを維持・上昇させる要素):
1.達成→ない。プロジェクトの打ち上げやった記憶がなく・・・どこら辺が仕事の終わりだったんでしょう。
いや、社内全体の飲みはやっていたからあれがそうだったのかな・・・
これはキャロットソフトウェアのみならず、ソフトウェア業界全般において言えることではないかと思います。
(特に新規開発ではなく保守開発の場合)
2.承認
→ない。賞賛されることなし。人間面での対応の前に社内での評価制度がそもそもなし。
3.仕事そのもの
→仕事そのものに充実感はあるかもしれない。かなり忙しい。息をつく暇が基本的にない。
4.責任
→責任範囲が不明瞭。とにかく上からの圧迫で重圧を感じる。
それでもみんなそれなりに一生懸命働いていた(が、辞めていった)。
5.昇進
→まれにある。上司の気分次第(席が空いているかどうかも重要)。
Mさんが主任に昇進した時、役職に近いTさん(偉い)が辞めて、窓際の偉い人専用の広い席が一つ空いたので、
そこを埋める形でMさんがその席に座ったが、あのタイミングを見る限りはそういう順番待ちもあるように思う。
尚、私が辞めた後に聞いた話だと、Sさんがその後に主任に昇進されたと聞いた。
空き席の有無が関与したのかどうかはこのケースだと分からない。
6.成長
→ない。ビジネス面では結論を先に言うだとか、プログラムのここをこうするとかは鍛えられるのですが、それでは報告文章の「敷衍と要約」などの訓練は行いますか?報告書の作成練習はさせますか?プログラムは体系的に効率的に組んで、理論としてはこういう風に作っているので盤石です、メンテナンス性能もありますなどと言える体制を組んでいますか?私はそうではないと思います。
そうしたスキルが個人に蓄積されません=組織からの成長を促されるような組織体系づくりがない。
思えば研修についても「分からなかったら聞いて」と言う放置スタイルでした(みんなそう)。
創業25年くらいであるならば平均勤続年数が9〜10年と言うのはありえる数字ですが、37年で9〜10年は少しおかしい。
当て推量レベルの推測をしますと、このまま永遠にキャロットソフトウェアが続くにしてもこの数字は変わらないのではないでしょうか。
即ち、いつの時代に入っても、キャロットソフトウェアに入社した人は、平均で9〜10年辺りで退職を決意するということです。
それをなさしめる要因はなんであろうか、と言うことを考えた時、金銭的な問題、健康面での問題など物理的な側面の他に、心理的な側面において「この会社ではもうやっていけない」とモチベーションがゼロになったりマイナスになったりした時に退職するのではないでしょうか。
このモチベーションについて少し丁寧に見ていきましょう。
古い本ですが、モチベーション入門(田尾雅夫)を引っ張り出して検証して見ましょう。
F・ハーズバーグの二要因説が次のものとして紹介されています。
同前70ページより:
衛生要因:
1.賃金
2.さまざまな付加給付
3.作業条件
4.経営方針
5.上司や同僚、部下などとの人間関係
動機づけ要因(仕事に内在するモチベーションを維持・上昇させる要素):
1.達成
2.承認
3.仕事そのもの
4.責任
5.昇進
6.成長
これらをキャロットソフトウェアに適用してみるとどうなるでしょうか。
以下は私個人の意見を適合させた結果となりますが、この会社は年間10人ペースで採用したと概算する場合、8割弱の人間が辞めていく環境なので、辞めた人間の内の一人として私が書くことは、当たらずとも遠からずではないかなと考えます。
衛生要因:
1.賃金→安い
男性Sさんに聞いたが、同期女性Hさんとのボーナスにかなり色がついた結果で差が出ていて(男性Sさんの方が低い)、かなり落ち込んでいた。
そもそも評価制度が機能していない。色がつくのは上長の気分次第だと思われる。
2.さまざまな付加給付→ない。一度だけ、社員全員に10万円が配られたことがありました。でも今のネットの評価を見てるとそれ以降は全くやっていないっぽい。
3.作業条件→衛生環境は良く、危険性もないが、とにかくストレスの嵐である。
4.経営方針→ない。あるいは「金が稼げれば良い」。ちなみに仮想などの思想が無かった2000年台前半のコンピュータ業界の中で、樋口さんと言うオタク気質の古株の社員が仮想化を提案したところ「何の役に立つってんだよ」と言う一言で蹴った実績あり。つまり眼の前の金を稼ぐことが第一思想で、コンピュータの先の何たるかを追うと言う経営体制・経営思想ではない。
5.上司や同僚、部下などとの人間関係→ツンドラが如く大地さえも凍てつく極北の寒風吹きすさぶ環境・・・
とは言いつつも仲いい人はOFFは仲が良かった。
OFFはサバンナ程度だが、ONになるとツンドラモードになる。
動機づけ要因(仕事に内在するモチベーションを維持・上昇させる要素):
1.達成→ない。プロジェクトの打ち上げやった記憶がなく・・・どこら辺が仕事の終わりだったんでしょう。
いや、社内全体の飲みはやっていたからあれがそうだったのかな・・・
これはキャロットソフトウェアのみならず、ソフトウェア業界全般において言えることではないかと思います。
(特に新規開発ではなく保守開発の場合)
2.承認
→ない。賞賛されることなし。人間面での対応の前に社内での評価制度がそもそもなし。
3.仕事そのもの
→仕事そのものに充実感はあるかもしれない。かなり忙しい。息をつく暇が基本的にない。
4.責任
→責任範囲が不明瞭。とにかく上からの圧迫で重圧を感じる。
それでもみんなそれなりに一生懸命働いていた(が、辞めていった)。
5.昇進
→まれにある。上司の気分次第(席が空いているかどうかも重要)。
Mさんが主任に昇進した時、役職に近いTさん(偉い)が辞めて、窓際の偉い人専用の広い席が一つ空いたので、
そこを埋める形でMさんがその席に座ったが、あのタイミングを見る限りはそういう順番待ちもあるように思う。
尚、私が辞めた後に聞いた話だと、Sさんがその後に主任に昇進されたと聞いた。
空き席の有無が関与したのかどうかはこのケースだと分からない。
6.成長
→ない。ビジネス面では結論を先に言うだとか、プログラムのここをこうするとかは鍛えられるのですが、それでは報告文章の「敷衍と要約」などの訓練は行いますか?報告書の作成練習はさせますか?プログラムは体系的に効率的に組んで、理論としてはこういう風に作っているので盤石です、メンテナンス性能もありますなどと言える体制を組んでいますか?私はそうではないと思います。
そうしたスキルが個人に蓄積されません=組織からの成長を促されるような組織体系づくりがない。
思えば研修についても「分からなかったら聞いて」と言う放置スタイルでした(みんなそう)。










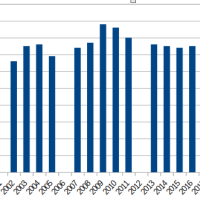
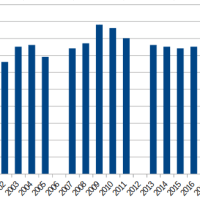
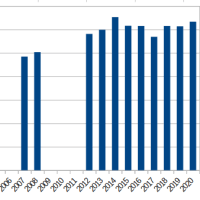
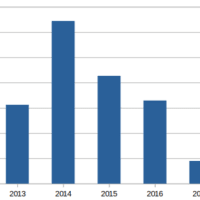
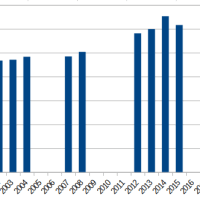
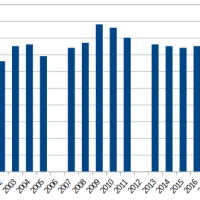
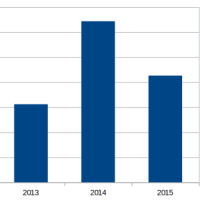
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます