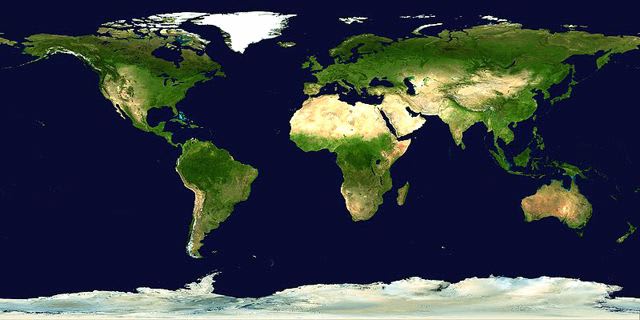
File:Whole world - land and oceans.jpg Wikimedia Commons
宇宙から日本を眺めると、ある奇妙なことに気がつく。それは、日本列島が世界の雛形になっていることだ。世界と日本が地勢的な相同関係にあり、日本は世界のミニチュアなのである。本州をユーラシア大陸、アフリカ大陸は九州だとすると、位相学的には、四国をオーストラリア大陸と見なすことが出来る。しかも、陸の外縁だけではなく、日本で最も大きな湖・琵琶湖は、世界最大の湖であるカスピ海に、日本の最高峰である富士山は、世界で最も高い山・エベレスト(チョモランマ)に対応している。イギリス人は、ヨーロッパ大陸とブリテン島を隔てるドーバー海峡を難攻不落の天然の濠に見立て、それを、ヨーロッパ大陸の動向からイギリスの独自性を守る為に、神が天地創造以来為し給うた特別な計らいと信じる向きもあると聞く。もちろん、隷属状態にあったエジプトから脱出するモーセたち一行を追っ手から守った「紅海が二つに割れた奇跡」を意識しているのである。そして、「花綵(はなづな=花の首飾り)の島々」とも謳われる、日本列島を中心とした弧状の地域であるこの「ヤポネシア弧」も、まるで誰かがわざと悪戯したみたいに、世界の縮図になっているのだ。この事実の元ネタは、「天津金木(あまつかなぎ)@竹内文書」と呼ばれる秘教的古神道の、日本と世界との相応関係を記した『五大州対応図(外八洲内八洲史観)』にあるらしいのだが、真偽の程はともかく、そう言われて見れば、瀬戸内海が地中海に、隠岐はイギリスに、能登半島はスカンジナビア半島に、紀伊半島がアラビア半島に、伊勢湾がペルシャ湾に見えてくるから不思議なものである。それぞれ日本地図と世界地図を見比べて遊んで頂きたい。ちなみに、私の「見立て」は、先住民の人権が蹂躙されて強引に同化された歴史をもつ北海道が北アメリカ大陸、北方四島はアメリカの喉元に刺さった棘・キューバであり、サハリン(樺太)を南アメリカ大陸に、台湾を南極大陸と見なして、とどめは、「本土」の一方的な思惑で踏みつけにされる沖縄が、日本列島の中にある「日本」である。もとよりこれは、「見立て」という「お遊び」であって、この手の話を真に受けて「オカルトの森」に迷わぬよう、話半分に聞いて「面白がる」というのが、大人の風儀というものである。
ホモ・サピエンスと呼ばれる知性的な存在にとって、本当に恐ろしいことはランダムな事況であり、理解の手がかりのない未知の事態の出来がそれだ。エネルギーや物質の代謝、果ては愛や情報の交換などの、絶えざる流入と退出の過程そのものが定常状態である生物にとっては、立ちすくむこと、固化すること、情況を読み込めずに外界から取り残される停滞状況は死に等しい。武道においては、対峙する事況のなかで、常に先手を取って主導権を維持することが勝利であり、現状に頑になること、状況に居着くことは敗勢の徴候である。アメリカがイラン・イラク・北朝鮮の三国を名指しして「悪の枢軸」呼ばわりしたのも、国連(第二次世界大戦の勝者である諸国連合)主導の湾岸戦争時とは異なり、単独行動主義で未知の事況に突っ込んで行く不安を既知の文脈のなかで払拭しようとしたからであって、その「見立て」にさしたる論拠があったわけではない。抽出しようとする構造が相同な事由であるならば、譬え話というものがどのようなものにでも応用出来るように、わけのわからない未知の状況に対する時も、とりあえず既知の情報を組み合わせて仮説をたて、とにもかくにも、その方向性で先へ進んで行くためのガイドラインが、「モデル」という譬え話の機能なのである。これは、「そっくり同じだ」という繰り返しの感覚が、そこにランダムネスでない一定の法則性やルールの存在を感じさせ、人間に安心感を与えるからであって、それが比喩の役割であり、わかりにくい事況を、あえてわかりやすい別のモデルと対比することで、人をわかったような気にさせるのである。未知をとりあえず既知の文脈にはめ込んで、わけのわからないものの取っ付きにくさを解錠し、立ちすくませることなく先に踏み出す勇気を、ヒトに与えるのだ。そして事態はしばしば進んで行くなかで変化し、事は『下手の考え、休むに似たり』とか、『案ずるより、生むが易し』とか言われるように推移するのであって、結局、『道を知ることと、実際にその道を歩んで行くことは違う』のである。知性的なホモ・サピエンスにとって、信用とは過去の「繰り返し」であり、もどってくること、一方通行でないこと、底なしでないこと、回帰性や再現性があることが理解の決め手であり、繰り返しの実績が信頼や確信の基礎となる。それゆえ、人類の規範的なルールや社会の基本構造が埋め込まれている基礎的資料である完全記号・完全テキストから作業仮説を引き出して行く行為が、ヒトの信用創造に他ならない。
完全記号・完全テキストというものは多様な読みを許し、そこから様々な意味合いを引き出してゆけるものだ。したがってある読解が唯一の正解ということではなく、その解釈を、専らその読み手自身の文脈に負うているのである。紀元1世紀のローマ帝国キリスト教迫害時代に、信徒を励ます目的で書かれた文書とされる『ヨハネの黙示録』も謎が謎を呼び、絶えず、読み手独自の読解を魅惑し続けて来た終末論的テキストである。21世紀のアジアの日本の私がそれを読み解くとすれば、次ぎのようになる。
『ヨハネの黙示録』の第2章は、キリスト教会の四分類に当てられている。最初の「エペソにある教会の御使い」に宛てられた部分にはこうある。『わたしは、あなたのわざと労苦と忍耐とを知っている。また、あなたが、悪い者たちをゆるしておくことができず、使徒と自称してはいるが、その実、使徒でない者たちをためしてみて、にせ者であると見抜いたことも、知っている。... しかしこういうことはある、あなたはニコライ宗の人々のわざを憎んでおり、わたしもそれを憎んでいる』。これは、東方正教会とローマ・カトリック教会の関係に相応する。しかも、奇しくもニコラウスという名の教皇は、そのいずれもが、教皇権の拡大に関与しているのである。そして、『あなたは忍耐をし続け、わたしの名のために忍び通して、弱り果てることがなかった。しかし、あなたに対して責むべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった』というのは、オーソドックス教会が国教会ゆえに、その世俗国家の提灯持ちに過ぎない御用宗教に陥りがちな瑕疵を、よく指摘しているのである。
二番目の「スミルナにある教会の御使い」宛のメッセージにある『わたしは、あなたの苦難や、貧しさを知っている(しかし実際は、あなたは富んでいるのだ)。また、ユダヤ人と自称してはいるが、その実ユダヤ人でなくてサタンの会堂に属する者たちにそしられていることも、わたしは知っている』という箇所は、カトリック教会とプロテスタント教会の関係性と符合する。一般にカトリック教会は、貧しい者の宗派と見なされているからである(しかしバチカン法王庁は壮麗でさえある)。また、WASPの国のアメリカ人はユダヤ人(ユダヤ教キリスト派)というよりも、実際にイエスを鞭打ち、茨の冠を被せては侮辱し、もっとも残酷な刑罰である十字架刑に処して「神の子」を殺した「ローマ人」にそっくりであると言える。古代ローマ人が転生して蘇ったとしたら、小躍りしてアメリカ市民権を得るであろうし、その物質享楽的な「パンとサーカス」の現代アメリカ生活に適応するに、何ら不都合を感じさせないであろうからである。そして『あなたがたは十日の間、苦難にあうであろう』というのは、統合の中心的存在である教皇が空位になる際の、カトリック信者の精神的危機を予言しているのである。
三番目の「ペルガモにある教会の御使い」に宛てられた箇所にはこうある。『鋭いもろ刃のつるぎを持っているかたが、次ぎのように言われる。わたしはあなたの住んでいる所を知っている。そこにはサタンの座がある』。これはアメリカのことである。『あなたがたの中には、現にバラムの教えを奉じている者がある。バラムはバラクに教え込み、イスラエルの子らの前に、つまずきになるものを置かせて、偶像にささげたものを食べさせ、また不品行をさせたのである』。相対主義的な多種多様な価値観を許す合衆国に住むアメリカ人を一つにまとめて行こうとすれば、「星条旗」と「自由の女神」の偶像の力に頼るほかあるまい。国家分裂の危機に際して、ますます星条旗が打ち振られ、はためき、林立するであろうことは想像に難くない。『同じように、あなたがたの中には、ニコライ宗の教えを奉じている者もいる。だから、悔い改めなさい。そうしないと、わたしはすぐにあなたがたのところに行き、わたしの口のつるぎをもって彼らと戦おう』。つまるところ、EUという諸国連合の中に浮いた陸の孤島・バチカン市国に住む「普遍教会教皇権至上主義者」と、アメリカ諸国連合(U.S.A.)の中のコロンビア特別区(ワシントンD.C.)に住む「連邦大統領権至上主義者」は、言っていることは違っても、やっていること(目的)は同じである(旧教勢力が世界をキリスト教一色に染めようとしたのも、人類すべてがキリスト教徒となって「神殺しの罪=神のひとり子イエスが全人類の原罪を贖って死んだのだという贖罪意識」を告白すれば、実質的に「神殺しの告発者」が地球上からいなくなり、自分たちの「神殺しの事実」を、人類史から事実上「なかったことにする」ことが出来るから。『一億総懺悔論』と同じ理屈。ユダヤ教殺しの「最終的解決」の目的もその一点にあり、イスラム教殺しの「十字軍」もまた同様。正教勢力が科学的唯物論で、新教勢力が無神論的ヒューマニズムによって『それ』を「忘れることにした」のも同様の企み)。その根城(ホワイトハウスは、後者の別荘のようなものである)の建築スタイルに隠しようもなく現れているのは、いわば、西方教会文明の昼の顔と夜の顔、グッド・コップとバッド・コップの自作自演の猿芝居を演じる二人三脚の珍道中である。南北両アメリカ大陸を征服して原文明原文化を蹂躙しておきながら、我が物顔であり、神殺しの罪で塀の中にいる犯罪者のくせをして、さも裁判官・検察官気取りで、われわれ塀の外の娑婆の人間に向かってしたり顔でいちいち説教たれる、底なしの勘違い振りが両者に共通しているのである。
そして、四番目の「テアテラにある教会の御使い」に書き送られた部分は、私がいうところのプログレッシブ教会に当たる。実は、プログレッシブ教会の萌芽はアングリカン・チャーチ(イギリス聖公会)に見られるのであるが、それは、アングリカン・チャーチが国教会というオーソドキシーと、カトリック(公同的)という普遍性と、加えて近代性というプロテスタンティズムを併せ持っているからである。いわゆる無教会主義者の集会は(これは近代国家コミュニティそのものである)、必然的にその三つの要素を併せ持ったものにならざるを得ないが、しかしながら、真のプログレッシブ教会にとっては、それはまだ過半である。それらは「メディア教会」であるプログレッシブ教会の、「オフ会」の仮の姿でしかないからであり、その実身は「オンライン」上にある。『また、テアテラにいるほかの人たちで、まだあの女の教えを受けておらず、サタンの、いわゆる「深み」を知らないあなたがたに言う。わたしは別にほかの重荷を、あなたがたに負わせることはしない。ただ、わたしが来る時まで、自分の持っているものを堅く保っていなさい。勝利を得る者、わたしのわざを最後まで持ち続ける者には、諸国民を支配する権威を授ける』というのは、儒教圏のキリスト教徒となる者のことを指している。サタンの、いわゆる「深み」であるキリスト殺しには関与していないからであって、神殺しの罪のうちにある者の魔除けである「聖体」を拝領する必要がない、部外者だからである。
同様にして、第3章にある「サルデスにある教会」がユダヤ教徒、「ヒラデルヒアにある教会」がイスラム教徒にあたり、以上で、一神教の「啓典の民」の分類は終了である。一神教以外の、残りの相対主義的な人々のことを言っているのが、最後の「ラオデキアにある教会」である。『わたしはあなたのわざを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。むしろ、冷たいか熱いかであってほしい。このように、熱くもなく、冷たくもなく、なまぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、なんの不自由もないと言っているが、実は、あなた自身がみじめな者、あわれむべき者、貧しい者、目の見えない者、裸な者であることに気がついていない。そこで、あなたに勧める。富む者となるために、わたしから火で精錬された金を買い、また、あなたの裸の恥をさらさないため身に着けるように、白い衣を買いなさい。また、見えるようになるため、目にぬる目薬を買いなさい。すべてわたしの愛している者を、わたしはしかったり、懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい』とは、誠に現代人の無神論的ヒューマニスト振りを言い得て妙である。
実は、私の最初のカテキズム(公教要理)の際に、神父様と最も見解が相違したのが、この「黙示録」の解釈と(私とすれば、終始教えを請う者としての謙抑的な態度は失わなかったつもりであるが、私の神秘体験の告白に続いた私独自の読解には、神父様はかなり激高されたものである。当然と言えば当然過ぎるくらい当然な話ではあるが、その頃の私は「うぶ」であった)「使徒言行録」の中の、以下の部分の解釈であった。
『そのころ、弟子の数が増えてくるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちから、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちの寡婦らが、日々の配給で、おろそかにされがちだと、苦情を申し立てた。そこで、12使徒は弟子全体を呼び集めて言った。「わたしたちが神の言葉を差し置いて、食卓のことに携わるのは面白くない。そこで、兄弟たちよ、あなたがたの中から、御霊と知恵とに満ちた、評判のよい人たち七人を捜し出して欲しい。その人たちにこの仕事をまかせ、わたしたちは、もっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしよう」。この提案は会衆一同の賛成するところとなった。そして信仰と聖霊とに満ちた人ステパノ、それからピリポ、プロコロ、ニカルノ、テモン、パルメナ、およびアンテオケの改宗者ニコラオを選び出して、使徒たちの前に立たせた。すると、使徒たちは祈って手を彼らの上においた。こうして神の言葉は、ますますひろまり、エルサレムにおける弟子の数が非常に増えていき、祭司たちも多数、信仰を受け入れるようになった』(使徒言行録第6章1節~7節)
私が思うに、ここは、預言者宗教と教団宗教とのギャップ、その立ち位置の違いから来る宿命的な乖離が露になった箇所である。「食卓のこと」とは、人間が集団をつくる時に必然的に付随して来る、組織内の物質的再配分の問題のことであって、預言者宗教が専ら与る、御言葉の再配分のことではない。この「食卓のこと」が教団内部から12使徒のところへ持ち上げられた時、ペテロにはまず、ユダのことが念頭にあったのである。イエスご自身の教団において、会計を任されていたのは、ペテロらと同等同格に立つ12使徒のうちのひとり、後に「裏切り者のユダ」と呼ばれることになるその人であった。しかも、それを選んだのはイエスご本人であり、主は後に自ら、『あなた達12人を選んだのは、このわたしではなかったのか。ところが、そのうち一人は悪魔だ!』(ヨハネによる福音書第6章70節)と嘆かれることになったのである。わずか三・四年に満たないとされるイエスの宣教活動期間においても、大勢の人間が集団を組めば、そこには不可避的に「食卓のこと(会計の問題)」が浮上してくる。つまり、「カエサルのもの」をどのように再配分するかという現実的な問題が起こって来るのである。イエスの教えに従う人が増えて行く段階では、神の御言葉の御用を務めるイエス(=宣教者)の利害と、教団の会計を任されたユダ(=司牧者)の利害とは一致している。しかしながら、イエスがエルサレムに上り、いよいよ神の御言葉の最終的な御用を果たさんとするとき、この世的な、つまり、ユダヤ人の信じるメシア的な革命運動による解放ではなく、霊的な、すなわち、全人類の精神的な解放を目指したキリスト的な覚醒運動であることが、よりはっきりすると(キリスト的な目論みからすれば、全人類が精神的に覚醒し、「カエサル的なもの」への隷属状態から解放されると、それは同時に、イスラエルのメシア的解放にもなるわけである)、当然のように、神につかえるものとカエサルにつかえるものとの関係性は、決定的な危機を迎えるのである。
ヨハネによる福音書第6章66節~67節にはこうある。『このはげしい言葉のために、多くの弟子が離れていって、もはやイエスと一緒に歩かなくなった。するとイエスが12人の弟子に言われた、「まさか、あなた達まで離れようと思っているのではあるまいね」』。イエスの宣教活動が、人類の魂の解放を目指したグローバルな、キリスト教的宗教運動であることの性格を鮮明にすると、どんどん信者は減って行く。つまり、イエスをメシアに目した古代イスラエルのローカルな、現世的革命運動・社会改造運動の勝ち馬に乗ろうとしていた人から順次離れて行き、最後まで付き従って行くのは、失うもののない人、すなわち貧しい人々である。そして、それは同時に、会計係の懐具合も寂しくなる一方であることをも意味したのである。実質的に教団会計を取り仕切っていたユダにしてみれば、自分が鉛筆舐め舐め苦労して築き上げて来たもの(=人々がシステムの移行期的な混乱を生き延びる為の互恵的な共同体・アジール)をイエスが壊そうとしているように感じられたであったろうとしても無理はない。そして、ついに、あの「ナルドの香油」事件において、キリスト者とメシア主義者の利益相反は決定的となり、両者の対立は不可避となって、ユダの裏切りとイエスの捕縛に至るのである。
『ベタニヤで癩病人シモンの家におられるとき、食卓についておられると、一人の女が混ぜ物のない、非常に高価なナルドの香油のはいった石膏の壷を持って来て、その壷をこわし、香油をすっかりイエスの頭に注ぎかけた。数人の者はこれを見て、こう言って互いに憤慨した、「香油を、なぜこんなもったいないことをしたのだろう。この香油は300デナリ(15万円)以上にも売れて、貧乏な人に施しが出来たのに」。そして女に向かっていきり立った。イエスは言われた、「構わずにおきなさい。なぜいじめるのか。わたしに良いことをしてくれたのだ。貧乏な人はいつもあなた達と一緒にいるから、したい時に慈善をすることが出来る。だがわたしはいつも一緒にいるわけではない。この婦人はできるかぎりのことをした。前もってわたしの体に油をぬって、葬る準備をしてくれたのである。アーメン、わたしは言う、世界中どこでも今後福音の説かれる所では、この婦人のしたことも、その記念のために一緒に語りつたえられるであろう」』(マルコによる福音書第14章3節~9節)
ここにこそ、すべての教団宗教と預言者宗教の間にある、あるいは祭司と預言者の間にある、または教会と神秘主義者の間に存在し続ける、相克のエッセンスが込められている。それゆえペテロたち12使徒は、主の『その人は、ああ、かわいそうだ! 生まれなかった方がよっぽど仕合わせであった』(マルコによる福音書第14章21節)という言葉を、しかも、その人を『選んだのは、このわたしではなかったのか』(ヨハネによる福音書第6章70節)というイエスの懊悩をも知っていたので、『そこで、兄弟たちよ、あなたがたの中から、御霊と知恵とに満ちた、評判のよい人たち七人を捜し出して欲しい。その人たちにこの仕事をまかせ、わたしたちは、もっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしよう』(使徒言行録第6章3節~4節)ということになるのである。ユダの欠員を埋めた、イエスなき後の使徒時代のキリスト教団の12使徒は、教団宗教ではなく、イエス復活の「奇跡」に直接立ち会った、神秘主義的な預言者宗教者の立場に立つものであることを、ここにおいて明確に宣言しているのだ。つまり、ペテロを筆頭とする12使徒は、七人の「評判の良い人」によって司牧された七つの教会、すなわち、人類の七つの集団の上に君臨する12の星の冠のようなものであって、「黙示録」と「使徒言行録」の記述を素直に読み込めば、人類の歴史は、ローマン・カトリック教会が「使徒座」を独占して収まるようなものでは、端からないと言えるのである。
もし、人類の集団がある属性にしたがって大きく分類されるとすれば、必然的にそれは「(七つの)教会」と呼ばれることになろう。なぜならば、人間を大集団へと組織化してゆく行動原理の根底には、必ず「旨とする教え=宗旨」という規範的なもの(=行動規範=協調性=同質性)があるからである。それゆえ、『ヨハネの黙示録』にある七つの教会に宛てたメッセージから、構造的に相同なある意味を引き出して、つまり、「使徒言行録」にある「食卓のこと(物質的再配分)」のことをまかされた七人の代表者によって司牧される集団としてそれを「見立て」、それをモデルとして、そこからある教訓を引き出したとしても、事実関係や史実としてはどうであれ、論理的によく整合し生産的であるならば、それはそれとして、一向に構わないということになるであろう。そこで、それぞれの「教会」の「長(集団維持に最終責任を持つ者)」を仮定して、ある組織原理的な問いを立ててみたい。もし今、あなたがたの教団にこの「ナルドの香油」問題が持ち上がった時、あなたがたは果たして、「もっぱら祈りと神の御言葉の御用に当たる」ことを選び、たとえそれが「食卓のこと(集団を日々維持してゆく組織原理)」に反する行いであったとしても、今日の糧を求める大勢の貧しい人たちのためでなく、神のひとり子のために、「高価な香油」をこぼすことの方を言祝ぐことが出来るだろうか。もし、あなたがたが人々の中から互選で選ばれた「七人の評判のよい人」の仲間であるとしたら、それはそのような振る舞いは、委託された職務への裏切り行為となるであろうし、またたとえ、あなたがたが神の子から選ばれた「12使徒」の仲間だとしても、「そのうちの一人はサタン」なのである。神の御言葉の成就と神の教えに従う人間の集団(教団)の利益相反が決定的となり、いよいよ主の贖罪の日が近づいて、主自らが近しい者の裏切りをはっきりと予言された時、12人の使徒たちは、皆が皆「まさかわたしではないでしょう!」(マルコによる福音書第14章19節)と互いに疑心暗鬼に陥り、ユダ自身を含めて、弟子達は誰一人として、裏切り者(サタン)が誰であるかを指摘することが出来なかったのである。誰もが皆、神の御子に牧される〈こども〉だったからだ。唯一人ユダだけが、〈夫〉であるイエスとともに、「家計(教団の食卓のこと)」に責任を持つ〈妻〉(=女房役)だったと言えるが、〈妻〉といえども、〈夫〉に対しては〈こども〉である。〈こども〉とは〈親〉に甘えるものだから。そして、この甘えが悪魔を呼び込むのである。それゆえ、普段から、「神のもの(御言葉=霊)は神に」、「カエサルのもの(食卓のこと=肉)はカエサルに」と、この両者をはっきり区別しておいた方がよい。少なくとも、この二つを混同した(イエスとカエサルを同衾させる立ち位置にあった)ユダにはならなくて済むであろうからである。ここに「ペテロの学び(教訓)」がある。最後の審判とは、集団で類別される革命的救済(党派性)というよりも、個人の魂の選別であることには(それは、教会の長もその例外ではない)あなたがたも同意されるであろう。最後の審判においては、すなわち、人類の集団や組織の解体局面においては、個人の救済と組織の延命は利益相反するのである。ユダが救われたのなら、イエスの復活はなかったということである。「ユダ」が大手を振っているところでは、キリストの再臨は決して「見られない」ということである。最後の審判とは、人類が種として成熟するための、エディプス的切断だ。それは、〈おとな〉と〈こども〉が仕分けされ、〈こども〉が淘汰されてゆく過程である。つまり、『幼年期の終わり』ということなのである。












































