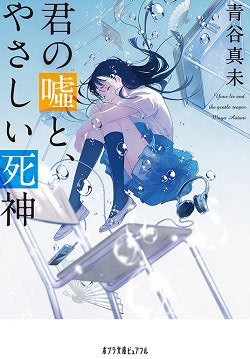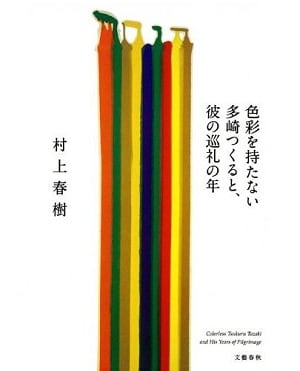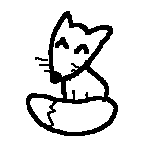「壁」を意識することは「内部」と「外部」の同質性に気づくこと

「壁」 安倍公房(著) 新潮社 新潮文庫 1969年発行
収録作品
<序> 石川淳
S・カルマ氏の犯罪
赤い繭
洪水
魔法のチョーク
事業
バベルの塔の狸
<解説> 佐々木基一
先に紹介した「読書嫌いのための図書室案内」で「赤い繭」が登場する
高校の教科書に載っているらしい
「壁」は読んだはずだが・・なにせ40年以上前の話である
文庫本があるはずだと探し始めたがみつからない
何年か前に文庫本をまとめて処分した中にいれてしまったのだろうか
1時間以上探して廊下に押し出した息子のマンガ本の棚の最下段でやっと発見する
我が家にあったのは1972年9月第5刷で読んだのは当然それ以降
ちょうど「読書嫌いのための図書室案内」の主人公と同じ年齢の頃だ
ぱらぱらとめくり思い起こすなどできない話で読み直すはめになる
今の文庫より活字が小さく紙は黄変しとてとても読みづらかったが
読書が新鮮な体験であった頃の懐かしい匂いが蘇ってきた
と同時に村上春樹の「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」を想起する
村上のいくつかの作品に登場する「穴」のイメージが「壁」に重なる
「壁」を読んでから半世紀近く「主観性」という壁の中で生きてきた
世界を見ているようで「間主観性」という鏡に映る自分とその世界を受け入れてきた
「外」は自己感覚世界の「内」にしかない
しかし「内」なるものは紛れもなく(であれば良いが)世界に所属する「外」に晒されているはずだ
読んだ当時は「意味不明」ながら社会の不条理や矛盾と自己の透明性(という思い込み)の狭間で
いかにして生きて行くかなどと悩んでいたかもしれない
歳を重ねてから青春時代に読んだ本を読み返すのは
なかなか楽しい体験であると気づかされる
「読書嫌いのための図書室案内」では安倍公房の「箱男」と「砂の女」も題名だけ出てくる
「砂の女」は読んだ後、部屋中ざらざらと砂の手触りがして
口の中にまでその感覚が残るぞわぞわする作品だった
文字通り「文学体験」をした貴重な一冊だった
なので安倍公房の新刊「箱男」が出ると知り発売を待って買ったのを覚えている
我が家にあるのは1973年発行の初版本である


新潮社の「純文学書下ろし特別作品」は箱入りで重々しく
大江健三郎、倉橋由美子等々の作品も発売されると買っていた
これが本棚にあるだけで文学少年(青年)であるのだという気分に酔っていた
そういえば村上春樹の「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」も
この書下ろし作品として発表されている
体験が新鮮さを欠く歳となって
昔日の体験をよみがえらせてくれる原点回帰的読書も
なかなか捨てたものではないなと感慨深い
ふと手に取った「読書嫌いのための図書室案内」がそのきっかけを作ってくれたわけで
好き嫌いなくいろんな本を読むことで得られる出会いや発見の楽しさを思い出させてくれた
だから本屋に行かなければね

「壁」 安倍公房(著) 新潮社 新潮文庫 1969年発行
収録作品
<序> 石川淳
S・カルマ氏の犯罪
赤い繭
洪水
魔法のチョーク
事業
バベルの塔の狸
<解説> 佐々木基一
先に紹介した「読書嫌いのための図書室案内」で「赤い繭」が登場する
高校の教科書に載っているらしい
「壁」は読んだはずだが・・なにせ40年以上前の話である
文庫本があるはずだと探し始めたがみつからない
何年か前に文庫本をまとめて処分した中にいれてしまったのだろうか
1時間以上探して廊下に押し出した息子のマンガ本の棚の最下段でやっと発見する
我が家にあったのは1972年9月第5刷で読んだのは当然それ以降
ちょうど「読書嫌いのための図書室案内」の主人公と同じ年齢の頃だ
ぱらぱらとめくり思い起こすなどできない話で読み直すはめになる
今の文庫より活字が小さく紙は黄変しとてとても読みづらかったが
読書が新鮮な体験であった頃の懐かしい匂いが蘇ってきた
と同時に村上春樹の「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」を想起する
村上のいくつかの作品に登場する「穴」のイメージが「壁」に重なる
「壁」を読んでから半世紀近く「主観性」という壁の中で生きてきた
世界を見ているようで「間主観性」という鏡に映る自分とその世界を受け入れてきた
「外」は自己感覚世界の「内」にしかない
しかし「内」なるものは紛れもなく(であれば良いが)世界に所属する「外」に晒されているはずだ
読んだ当時は「意味不明」ながら社会の不条理や矛盾と自己の透明性(という思い込み)の狭間で
いかにして生きて行くかなどと悩んでいたかもしれない
歳を重ねてから青春時代に読んだ本を読み返すのは
なかなか楽しい体験であると気づかされる
「読書嫌いのための図書室案内」では安倍公房の「箱男」と「砂の女」も題名だけ出てくる
「砂の女」は読んだ後、部屋中ざらざらと砂の手触りがして
口の中にまでその感覚が残るぞわぞわする作品だった
文字通り「文学体験」をした貴重な一冊だった
なので安倍公房の新刊「箱男」が出ると知り発売を待って買ったのを覚えている
我が家にあるのは1973年発行の初版本である


新潮社の「純文学書下ろし特別作品」は箱入りで重々しく
大江健三郎、倉橋由美子等々の作品も発売されると買っていた
これが本棚にあるだけで文学少年(青年)であるのだという気分に酔っていた
そういえば村上春樹の「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」も
この書下ろし作品として発表されている
体験が新鮮さを欠く歳となって
昔日の体験をよみがえらせてくれる原点回帰的読書も
なかなか捨てたものではないなと感慨深い
ふと手に取った「読書嫌いのための図書室案内」がそのきっかけを作ってくれたわけで
好き嫌いなくいろんな本を読むことで得られる出会いや発見の楽しさを思い出させてくれた
だから本屋に行かなければね