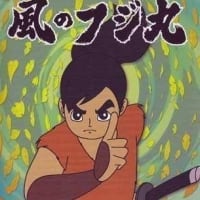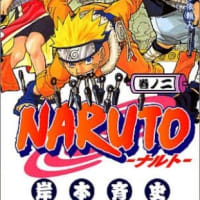先日ラジオをつけていたら、古い昭和歌謡曲が流れてきた。
昔の音源を流しているんだろう・・・と思って聴き流していたら、・・あれ?
歌っている人が、歌い終わった後に、番組のパーソナリティとトークをしている。
ってことは、これ・・・生ということになる。
ああ、そうか、昔の歌手が久々にラジオに呼ばれて懐メロを歌ってるんだろう・・・と思った。
と思ってなおも聞き流していたら、どうも若そうだ。声につやがあるし、若々しい。
古い昭和の歌手が、若返って現代で歌っている・・・そんな感じ。
どうやら、若いシンガーが、昭和の古い歌謡曲を歌っているようだった。
昭和歌謡をカバーするシンガーは、多い。
だが・・・この歌手は・・・単にカバーするだけでなく、歌い方まで、昭和歌謡の歌手たちのような発声と歌い方で歌っている。
妙に原曲を崩すこともないので、そこには昭和歌謡に対する敬意もちゃんと感じる。
おお・・・。
なにやら、昔・・シャネルズが顔を黒く塗って人前に現れ、ドゥワップを歌い始めたのを見た時に感じたような楽しさを、この東京大衆歌謡楽団には感じた。
これは面白い!
そう思って、この歌手のいるユニット「東京大衆歌謡楽団」を検索してみたら、あらら・・・やはり皆若い!
しかも、歌い方だけなく、ヘアスタイル、服装まで、昔の昭和歌謡を再現している。
編成は、ボーカル、アコーディオン、ウッドベース・・が基本のようだ。
昭和初期から中期に青春時代を過ごしたご年配の世代の方が聴いたら、今の時代にこの選曲、サウンド、そして歌い方まで昭和を再現してるスタイルに涙ものなのではないか。
ユーチューブでは、多数の動画がアップされている。
主に路上でのライブの映像が多い。
案の定、年配の方が多数足をとめて、このユニットのパフォーマンスに見入っている。皆、嬉しそうだ。
年配の方々にとっては、若いミュージシャンの路上パフォーマンスのために立ち止まることなど、普段はあまりないであろう。
それがどうだ。
やっと自分らの楽しめる音楽の路上パフォーマーが出てきてくれた・・とばかりに、一緒に歌ったり、手拍子したり。
だが、年配の客に混ざって、若い人も足をとめている。若い人にとっては、新鮮なのだろう。
なにより、このユニットが醸し出す、あたりの雰囲気がいい。見ている人の笑顔、笑顔。
私は、はっきり言って、こういう歌い方が主流だった時代の生まれではなく、ポップスやロックやフォークなどが日本のヒットチャートをにぎわす時代に、多感な時代を過ごしている。
なので、こういう歌い方で歌われてた時代の曲には、古臭さを感じていた。
そして、明らかに発声方法が違うことに、少し距離感を感じていた。
だが、今・・・若い人がこういうスタイルで音楽をやってるのを聞いて、けっこう新鮮に思えた。
今、こういう歌い方で歌うシンガーって、少なくても若いシンガーにはいない。だから、なおさら。
聴いた感じでは、決して奇をてらってこういうスタイルでやってるというわけでもなく、むしろ本格的だ。
こういうユニットが出てくるとはねえ・・。
もしも、昭和の往年の歌手が、こういう曲を歌をこういうサウンドや歌い方で歌ってたら、私は「懐メロ」として受け取るだけだったかもしれない。
だが、若いミュージシャンが、サウンドも、容姿も、選曲も、歌い方も、こういうスタイルでやると、それは「懐メロ」という感覚にならない。
現役の新しい音楽なのだ。それまで「懐メロ」としてあった音楽が、ここでは現役の楽曲として、世の中に、新曲であるかのように再登場してきてるのだ。なにより、その躍動感ゆえに。
その躍動感は、やはり彼らの若さからくるものであろう。こればかりは、若さの特権なのかもしれない。
だからこそ、古い楽曲が、まるで今のポップスのような躍動感を持つのだろう。
ボーカリストが直立で背筋をのばして高らかに歌う様は、昔の歌手もおそらくこんな感じだったのかな・・と、昔を知らない私に想像させてくれるが、ボーカリストが曲の節々に細かくリズムを取ってる様は、現代の音楽のノリを知ってるからではないだろうか。
例えば、直立不動で歌ってたことで知られる東海林太郎さんなどは、こんな細かいリズムの取り方はしなかったと思うし。ボーカリストが無意識のうちにとってしまう細かいリズムは、やはり現代出身ならではという気がする。
もっとも、だからといって、それがのどかな昭和楽曲の良さを壊してるわけではなく、むしろそれらの曲を、現代に生き返らせている「良さ」に繋がっているとも思える。
年配の人たちが喜んでおひねりを入れていく。すると、ボーカリストの深々としたおじぎが返る。このへんには、古き良き時代の礼儀正しい昭和歌謡歌手の仕草までも再現している。
「サンキュー」とか「みんな~!あ~りがとう~~~!!」ではなく、「どうもありがとうございます。」なのだ。
ラジオでのトークを聞いた感じでは、レパートリーは戦前・戦後などの古い昭和歌謡なのだが、案外このスタイルで新しめの曲をカバーしたら一体どうなるんだろう・・とも思った。
例えば、藤山一郎さんが、最近のポップスを歌ったらどうなるか・・という感じで。
プロフィールを見てみたら、このユニットのメンバーは、もともとは民族音楽を中心としたバンド活動をしていたそうだ。
また、ボーカリストは、こういう音楽をやるために、ちゃんとした声楽を学んだそうだ。どうりで本格的なわけだ。
普段ロックやポップスなどを歌っているシンガーが、バリエーションとして昭和歌謡を自己流にカバーするのとは根本的に違う。
ロックなどに私が目覚めたころ、ラジオなどで昭和初期・中期の歌謡曲を聴く機会があると、その歌い方がどうも気取って歌っているように聴こえ、むしろ少し苦手に感じていた私。
だが、そういう歌い方がチャートの主流じゃなくなってしまってみると、かえってこういう歌い方が面白く感じてしまった。
そして、古臭いと思っていたはずの戦前戦後の昭和歌謡のメロディの良さに改めて目を向けさせてくれた気はする。
年配の方に受けるのは当然としても、若い人たちにこのユニットがどんどん受け入れられていったら、面白いなあ。
そして若い人に、「なんだ、古い日本の曲やスタイルって、こんなに良かったんだね」・・とでも思ってもらえるようになれば、彼らは日本音楽の功労者にだってなれるかもしれない。
かつて一世を風靡したこのスタイル、絶滅してしまうのは惜しい。
こういうスタイルも、継承され、残っていったっていいよね。
だから、こういうスタイルのユニットが若い世代から出てくると、けっこう貴重ではないか。
おそらくこのユニットは、全国のご年配の方に好かれるだろう。実際、そうらしい。
若くて新しいユニットとしては、斬新なスタイルなので、幅広い世代に少しずつでも広めていってほしい気はする。
それにしても、容姿のほうも・・・いやはや本格的だなあ。
こういうユニットがいきなり今のチャートに登場してきたら、楽しいかもしれない。
若い人は、こういう音楽を聴いて、どう感じるのだろう。
古すぎて、もはや新しい???
ユーチューブの動画では、残念ながらウッドベースの音がよく聴こえない。
なので、一度、生で見てみたいユニットだ。
結成してパフォーマンスを始めたら、すぐに音楽関係者から引き合いが来たらしいが、分かる気がする。
私がもしレコード会社の人間だったとしても、こういうパフォーマンスを見せられたら、ほっておくわけにはいかないと思うだろう。
それにしても・・・参った。
彼らのライブ映像をあれこれ見てからというもの、戦前戦後間もない頃あたりの昭和歌謡のメロディが頭の中をまわりまくっている。
そして、つい口ずさんでしまっている私。
東京大衆歌謡楽団。
これからの活躍に、大いに期待して見守りたい。
メンバーの皆さん、心から応援しています。