「小林流必勝置碁【三子局】」を読んだ。
年初に打ってもらった指導碁が3子の手合いだったので、今の実力では3子は無理とは思いつつも、少し勉強しておこうと思ったのだ。
これまで置碁に関する本は、この小林光一九段も含め、何冊も目を通した。
軽く復習しておこうというところだが、内容についてはすっかり忘れてしまっている。
毎度のことだがいつも新鮮である。
小林九段の必勝置碁の本に限らず、置碁に関する本は、大抵は30手か40手くらいで「黒勝勢」と書かれていることが殆ど。
それで本当に勝ち切れたら世話はない。
本に出てくる通りに打ったのに勝てないじゃないか、なんてことは良くある。
あくまで置碁の布石の勉強であって、そっから先は実戦や他の勉強で地力を付けようと考えて読むべきだろう。
そんな中、今回久しぶりにこの本を読んで特に印象に残ったのがこの場面。
白1は出切ったところだが、「下手の実力を試す意味」と書かれていて、「黒がうまく応じればそれまでです」とある。

まず頭に浮かんだのは黒1とカケる手。
しかし、これは失敗。「黒1、3などと三子を逃げると、白も2、4と動き出して、だんだんわけが分からなくなります」とのこと。
まだまだ未熟だなあ、自分。

黒1とアテ、白2に黒3とカケるのが軽い手、と書かれていた。
「次に白イなら黒ロと下り、白ハ、黒ニと締めつけます。白はこの四子を後手で取ってみてもどうということはありません。」

ところで、この本の後半には三子局の実戦譜の解説が掲載されている。
その実戦譜については、以前の日記にも書いたことがある。
・上手の石は死なないの図-秀栄・林文子三子局
・道知下手ごなしの名局
6局掲載されている中には、本因坊秀哉名人と16歳の木谷實初段の碁と、本因坊秀哉名人と15歳の呉清源三段の碁も含まれている。
木谷初段は中押し勝ちで「二子局、三子局の名手といわれる秀哉名人も、この碁は完敗に終わった」と書かれている。
呉三段は「名人の威圧感で手が縮んだのでしょうか」と書かれるような手もあるものの、「終局では十一目の大差」となった。
私は年初から、PCソフトの「囲碁古典棋譜全集」の並べ易そうな棋譜を選び、何局か並べているのだが、「二子局、三子局の名手」である秀哉名人が二子局、三子局で勝った対局をまだ見かけない。
並べた棋譜が少ないが、瀬越憲作、岩本薫、梶原武雄を相手にすべて負けている。それに今回の木谷實と呉清源。
秀哉名人は本当に強かったのかな、などと思ったりした。
しかし、木谷實初段の碁の解説には「木谷先生は正確無比な手順でとどめをさしました。当時初段ということですが、実力はとてもそんなものではありません」とあり、また、下手が「うっかり応じると大逆転の恐れがあります」とも書かれていた。
秀哉名人が強いことには違いはないが、これらの対局は相手が悪かったということなのだろう、と思い直した。
年初に打ってもらった指導碁が3子の手合いだったので、今の実力では3子は無理とは思いつつも、少し勉強しておこうと思ったのだ。
これまで置碁に関する本は、この小林光一九段も含め、何冊も目を通した。
軽く復習しておこうというところだが、内容についてはすっかり忘れてしまっている。
毎度のことだがいつも新鮮である。
小林九段の必勝置碁の本に限らず、置碁に関する本は、大抵は30手か40手くらいで「黒勝勢」と書かれていることが殆ど。
それで本当に勝ち切れたら世話はない。
本に出てくる通りに打ったのに勝てないじゃないか、なんてことは良くある。
あくまで置碁の布石の勉強であって、そっから先は実戦や他の勉強で地力を付けようと考えて読むべきだろう。
そんな中、今回久しぶりにこの本を読んで特に印象に残ったのがこの場面。
白1は出切ったところだが、「下手の実力を試す意味」と書かれていて、「黒がうまく応じればそれまでです」とある。

まず頭に浮かんだのは黒1とカケる手。
しかし、これは失敗。「黒1、3などと三子を逃げると、白も2、4と動き出して、だんだんわけが分からなくなります」とのこと。
まだまだ未熟だなあ、自分。

黒1とアテ、白2に黒3とカケるのが軽い手、と書かれていた。
「次に白イなら黒ロと下り、白ハ、黒ニと締めつけます。白はこの四子を後手で取ってみてもどうということはありません。」

ところで、この本の後半には三子局の実戦譜の解説が掲載されている。
その実戦譜については、以前の日記にも書いたことがある。
・上手の石は死なないの図-秀栄・林文子三子局
・道知下手ごなしの名局
6局掲載されている中には、本因坊秀哉名人と16歳の木谷實初段の碁と、本因坊秀哉名人と15歳の呉清源三段の碁も含まれている。
木谷初段は中押し勝ちで「二子局、三子局の名手といわれる秀哉名人も、この碁は完敗に終わった」と書かれている。
呉三段は「名人の威圧感で手が縮んだのでしょうか」と書かれるような手もあるものの、「終局では十一目の大差」となった。
私は年初から、PCソフトの「囲碁古典棋譜全集」の並べ易そうな棋譜を選び、何局か並べているのだが、「二子局、三子局の名手」である秀哉名人が二子局、三子局で勝った対局をまだ見かけない。
並べた棋譜が少ないが、瀬越憲作、岩本薫、梶原武雄を相手にすべて負けている。それに今回の木谷實と呉清源。
秀哉名人は本当に強かったのかな、などと思ったりした。
しかし、木谷實初段の碁の解説には「木谷先生は正確無比な手順でとどめをさしました。当時初段ということですが、実力はとてもそんなものではありません」とあり、また、下手が「うっかり応じると大逆転の恐れがあります」とも書かれていた。
秀哉名人が強いことには違いはないが、これらの対局は相手が悪かったということなのだろう、と思い直した。















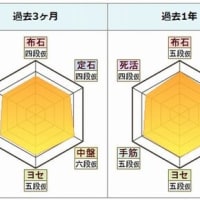









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます