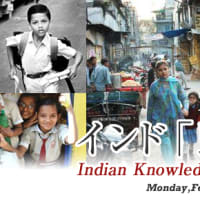風が大草原をわたる。白く波打つ海原のように見えるのは、満開のそばの花だ。オーストラリア南端のタスマニア島にある広大な畑は今年3月、日本と半年違いの開花期を迎えていた。
タスマニアは北海道くらいの大きさのハート形の島。その北部の農村で、そば栽培が根づいている。
仕掛け人は千葉県習志野市にある白鳥製粉の社長、白鳥理一郎(59)だ。現地でのパートナーである製粉業者、ブレントン・ヘーズルウッドや地元農民の間では「リック」と呼ばれる。
白鳥は、ここで日本と正反対の季節に栽培したそばを日本に輸入するという、ニッチ戦略を展開している。
そばは、主に夏に植えて秋に収穫し、冬にかけて新そばが出回る。角張った実から黒くて固い皮をむくと、甘皮が表れる。甘皮の緑が鮮やかな時は香りが瑞々(みずみず)しく、水を加えると粘りも強い。「打って良し、食べて良し」の新そばの特徴だ。
ところが、新そばの風味はせいぜい翌春までしか続かない。冷水でキリリとしめて食べる夏場は、実はそば自体の魅力は落ちかけている時期なのだ。
「粉が悪い」。毎年夏になると、東京・浅草でそば屋の老舗(しにせ)「並木藪蕎麦(そば)」を営んでいた故・堀田平七郎から苦情を言われた。
「夏は端境期だと言っても通じない。粉屋はそば屋の歴史が始まって以来、同じ言い訳ばかりしているではないか。研究課題として取り組みなさい」と叱咤(しった)された。そば屋の歴史は16世紀末の大阪城築城のころに始まったとされる。「400年来の難題解決を宿題にもらった気がした」
1982年、先代社長の父、利重が亡くなった。
白鳥が粉作りへの思いを一段と深めていたころだった。製粉技術に優れたドイツに留学し、「製粉マイスター」の資格を取っていた。社長を継ぎ、「宿題」に向き合った。
まだ大学生だった70年、南オーストラリア州の片田舎に留学したことがあった。その時、住み込み先の農場まで会いに来た父の言葉を忘れてはいなかった。
「豪州でそばが栽培できれば、日本の端境期に新そばを出荷できるのだが」
豪州での栽培実験は、父が地元に依頼して失敗したと聞いていた。問い合わせてみると、現地の農家が、南半球なのに日本と同じ7~9月に種まきをしていたとわかった。
「父の考えが間違っていたわけでない。自分の手で品質の高いそば栽培を目指そう」と思い立った。自分の構想を「サザンクロス(南十字星)計画」と名づけ、84年、具体化に着手した。
豪州の気象や地理を徹底的に調べ上げ、タスマニアが適地として目星をつけた。南緯40度から43度。北半球で言えば、北海道南部や東北北部の緯度にあたる。夏も25度くらいで涼しく、気象条件も近い。乾燥した大陸部より雨に恵まれ、そばの生育に適している。
それでは、どんな品種を植えればいいのか。専門家を訪ね歩いた。
そばは原産地とされる中国から世界に伝わり、欧州やロシアでもパンやケーキに焼いたりして食べる文化がある。その研究の世界的な権威は、東欧にいた。
以前、そばの国際会議で出会ったスロベニアのイワン・クレフト(68)だ。彼が教授を務めるリュブリャナ大学を訪ねると、地道な取り組みを勧められた。「実際に大量栽培する前に、十分な基礎データを現地で集めなさい。そうすれば、サザンクロスはいつか輝く」
何人もの紹介をへてタスマニアの農場主に手紙を書き、種子を送って栽培実験を依頼。85年には、ひとり現地に乗り込み、タスマニア州政府の農務省に支援を要請した。日本のそば食文化について英語で書いた論文も配って歩いた。
帰国後まもなく、同州の農務大臣から手紙が届いた。「州政府が栽培実験をする。私あてに種子を送ってほしい」
12月に種をまき、3月に収穫。味覚を試す実験が始まった。ところが、うまく実がつかない。品種のせいか。土壌のせいか。クレフトに知らせると心配して、タスマニアまでやってきた。
「いくつものそばの品種を植えて実験をする時は、畑を2kmほど離し、ネットで覆って隔離しないと、正確なデータがとれない」。クレフトはそう説明し、「がっかりするな」と励ました。
そばは雌しべが別の株の雄しべの花粉を受粉して結実する「他家受粉」の植物。同じ株の雄しべから受粉するコメ、ムギなど「自家受粉」の場合とはまた違うやり方が必要だったのだ。
試行錯誤の末、87年の試食会でついに堀田のOKが出た。白鳥は88年、品種を絞り込み、商用の栽培に入った。
作付けは年々拡大し、今では11軒の大規模農場が計150haで栽培する。
農場主のひとり、フィル・スペンサー(57)は半ズボン姿でトラクターに乗り、畑を走り回っていた。小麦や豆、牧草などに加えて昨年末、そば栽培を始めた。7haの畑で化学肥料を使わず、有機栽培をしている。
「リックがコツを教えてくれ、買い付けてくれるから、相場を気にしなくていい。安心して作れるんだ」。腰の高さにまで育ったそば畑を見渡して言った。
タスマニアでの1ha当たりの収穫量は1.5t前後。日本より作付け規模が大きいから効率がよく、単位収穫量は日本より5割ほど多いという。豪州は、今や日本向けそばで中国、米国、カナダに次ぐ供給国になった。
シドニー在住の作家、雁屋哲は原作を担当する漫画『美味(おい)しんぼ』で、「真夏のソバ」と題し、白鳥を紹介した。
雁屋は語る。「日本の食材を外国で作ることを考えつく人はいる。だが、本当に作りに行く勇気と度胸がすごい。そばは荒れ地でも育って手間がいらず、農民は感謝している。豪州の日本料理店にも出荷され、豪州人の間にもそば食文化が広まった」
東京・上野の老舗「上野藪蕎麦」。店主の鵜飼良平(72)と白鳥、来日したクレフトの3人が4月末、タスマニア産の新そばを味わった。ざるにのった手打ちそばはつるんとした食感に、ほんのりと甘さが漂った。
「これだと思ったら突っ込んでいく、やんちゃ坊主。開拓者魂があり、豪州が合っている」。鵜飼は白鳥をそう評する。
「赤道を超えた栽培協力」は、一層すそ野を広げつつある。
昨年、日本のそばが不作に陥った。福島県の会津地方では、今年まくタネの不足が心配された。白鳥は支援を頼まれ、昨年末、タスマニアに会津のタネ2tを空輸して作付け。会津に送るタネを4月に収穫した。
「タスマニアを増産や研究開発の拠点に育てたい。そばを通じた草の根外交ですよ」。稼いだ資金でタスマニアにソメイヨシノの苗木を植え、1000本に達した。やはり日本と半年違いの9月から10月に満開になる。
白鳥理一(しらとり・りいちろう)
1951年、千葉県生まれ。
70~71年、ロータリークラブの交換留学で南オーストラリア州に。
75年に立教大学を卒業後、ドイツ国立製粉学校に入学。
78年に帰国。白鳥製粉専務取締役に。
82年、社長に就任。
88年、タスマニアで、そば栽培スタートを祝う記念式典を開く。
2002年、豪日交流基金賞受賞。