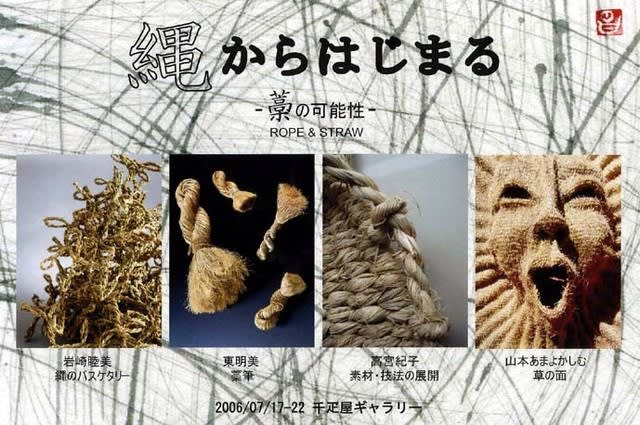◆写真1 楮

◆写真 2

◆写真 3

◆写真 4

◆写真 5

◆写真 6
2007年7月10日発行のART&CRAFT FORUM 45号に掲載した記事を改めて下記します。
編む植物図鑑④『紙を作る植物』 高宮紀子
2007年7月10日発行のART&CRAFT FORUM 45号に掲載した記事を改めて下記します。
編む植物図鑑④『紙を作る植物』 高宮紀子
作る作業が行き詰ったり、壁があると思った時には、書くのがいいと私は思っています。紙に書いて考える、そして考えたものを繋げたり、分析したものをまた紙に書く。書くことで壁が無くなったり、自分を客観的に見ることができます。これも作るという作業の一つです。家庭でもペーパーレスという時代になりましたが、完全に紙なしの生活は私にとってはちょっと無理。
情報のやりとりという点でも、紙というのは人間の文化にとても深く関係しています。情報を記録するため、世界にはいろいろな方法があります。先日、武蔵野美術大学で沖縄の民具の展覧会があり、期間中わら算の講習がありました。わらを束にして結んで数や種類を記したというものです。結び方にはルールがあって、実際に当事者がいなくても検証が可能です。結ぶだけだから書くものもいりません。
記すということが一番簡単なのは、石や葉などの表面に直接ひっかいてキズをつけることです。原始的な方法ですが、簡単です。次は、ちょっと痛々しいですが動物の皮も利用しました。
その次は樹皮のジンピ繊維を叩いて伸ばすというもの。樹木によっては薄く伸びて、つなげることもできます。模様なども入れて、日用品や衣料などにも使います。でも、その労力を考えるととても貴重で、使い捨てなんていうのはとても無理。次は植物のセルロースを重ねていくという方法。パピルスはあまりにも有名です。茎を縦に切って、直角に並べて層を作って圧力を加えると表面がなめらかで平らな面ができます。
そして最後に、ばらばらにした繊維を水の力でからめて面を作るという紙漉きの方法
です。
紙漉きができる植物で、まず思いつくのがコウゾです。写真1はまだ小さい苗なので、葉も小さいですが、クワ科の植物らしく、葉の切り込みが不規則です。このジンピ繊維を取って、つまり皮を剥いで、その内側の繊維を使います。外側の茶色い皮をつけたままま乾燥しているのが写真2です。先日、小川町へ紙漉きの体験に行った時に、見つけました。
写真3はミツマタ。これも同じ所でみかけたものでまだ蕾です。黄色い花が下向きに咲きます。これも皮をはいで使います。
偶然にも本コウゾで紙を漉かせてもらったのですが、紙漉きというのはつくづく水との関係が深い、と思いました。紙を漉くとき、水を貯めたり、捨てたりするのですが、これがむつかしい。できあがりの紙に必ず、影響します。リズミカルなぽちゃぽちゃという水の音を聞いていると、繊維がそろう一瞬がわかるそうです。ミツマタはジンチョウゲ科の植物です。庭木のジンチョウゲの皮をはぐと繊維が強いということがよくわかります。ただ、枝の分岐同士の距離が短いので、長くはとれませんが。写真4がミツマタのジンピ繊維。紙料として売られています。
以前、ある研究所から紙料の植物リストを送ってもらったことがあります。私のHPでかごの植物図鑑を掲載しているのですが、その参考になればと送って下さったもので、すごく詳しく驚きに満ちていました。考古学的な物証の研究をされているので、とても興味深かったのですが、見れば私が使う繊維植物と同じです。繊維があるものはすべて紙にすることができる、ということがわかりました。竹、藁、麻などはいうまでもなく、編む繊維植物である草本、木本にいたるまで、共通していました。
紙を作るのは、植物ばかりではありません。コットンペーペーという言葉を聞いた方があると思います。綿の繊維からも紙を作るのですが、工場で作られていたのは、なんと、中古の綿の衣類が材料でした。
平塚市美術館でかご展に参加したときに来日したスコットランドのアナ・キングさんがやっているのはキノコの紙。ある種のキノコがいいようで、たまたま宿泊地の庭にあったからと、採ってきてくれました。(写真5の右下の赤いもの。)下にひいた紙はキノコの紙の作り方ですが、どのキノコがいいのか、まだ試していません。でも、じゃがいもをすってミキサーに入れ、紙を作ったぐらいのシンプルさではないかと思います。
紙を作る技術は、ばらばらの繊維にして、または繊維の性質を利用し、以下に平らにするか、という技術です。これに比べ、編むという技術は、ばらばらの繊維を繋げていかに連続した線材や面にするか、という技術です。ばらばらの繊維からいろいろな方法が可能です。例えば撚るという方法がありますが、撚りながらできるのは、縄、ループ、結びという形があり、一つではありません。
写真6は私が作りました。素材はスギの樹皮です。スギの樹皮は厚いのですが、それを薄く剥いだり、叩いて柔らかくすることができます。この作品は一枚のスギの皮の硬いところを残して、他を叩いて柔らかくしたもの。下の柔らかいところは紙になりそうです。スギはクラスの参加者の皆さんと採りに行きました。
今年のかごクラスの参加者は面白い実験をする方が多い。Mさんは洗濯機で紙バンドを洗ったり、ビニールを熱で溶かしたりしています。またSさんはCDを螺旋状に切って、ダブルにつながった螺旋を作ってきました。Fさんはシュロの繊維を煮てきた。KさんはPPバンドから新たな物質を作り出し、Nさんはゴムを解いた。その他にも驚くものがたくさんあります。実験ですが、実験だけに終わりません。これによって新しい個性的の自分だけの素材をみつけることができるのです。