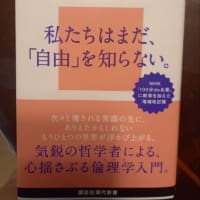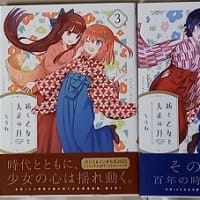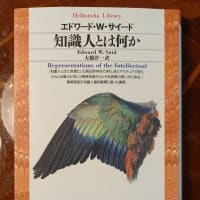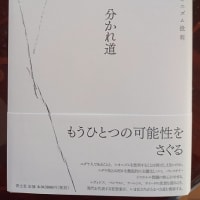ハンナ・アーレントの『全体主義の起源』三部作の第二巻目「帝国主義」を読みました。
19世紀後半から20世紀を迎えたあたりまでの約40年ぐらいを、アーレントは「帝国主義の時代」と定義。
ここでも、一般に広く使われる「帝国主義」という語句と比べて、アーレントが使うこの言葉は…
かなり狭い意味で使われています。
もっとも、多くの人が「〇〇主義」という言葉の定義を、乱雑に扱い過ぎていると思いますが。
帝国主義に限らず。
とにかく「〇〇主義」に関しては、そもそも定義をよく知らないのに使われることが多い。
一例をあげれば「共産主義」と「社会主義」の違い、ということをわかっていないのにも関わらず…
やたらと「共産圏では」なんていう言い方、よく使われますよね。
いままで人類の歴史上に「社会主義」国家と一応言われる、また自称する国はたくさんあったけれど…
「共産主義」社会の構築に成功した国家なんて、一つもあった試しがないのに。
それなのに「あの国は共産主義だから」とか「共産主義の国では」と言う人、よくいますよね。
まあ、今はそういう話ではないので、共産主義と社会主義の違いについては措いておきます。
知らないけれどどうしても気になる、という方は、この機会にウィキでも良いので調べて見て下さい。
とりあえずこの稿では『全体主義の起源2 帝国主義』のレビューを書く、ということで。
まず、ものすごくざっと、本の大きな流れを述べてしまいます。
第二巻では帝国主義の時代、それが成立した過程とその実際について、アーレントは縷々述べています。
彼女が主に扱っている「帝国主義」国家は、イギリスとフランスです。とくにイギリスの帝国主義。
イギリスなどが海外に植民地を拡大し、自国内で飽和した資本や労働力を、そこに送り込んだ。
ついでに、この本で盛んに使われる「モッブ」という言葉で表される種類の人々…
これは主としてブルジョア・小市民の社会から吐き出された、はみ出し者、はぐれ者のことですが…
そうした、本国の社会で行き場を失い、厄介者扱いされた人間の行き場所にもなった、という。
そうやってどんどん拡大膨張し、海外植民地から富を発生させた国が「帝国主義国家」ということです。
当然、先住民からの搾取を伴って。
そして西ヨーロッパ諸国の帝国主義的発展に乗り遅れた、つまり海外領土をあまり得られなかったのが…
ロシア帝国と、オーストリア帝国という、君主制の国だったというわけです。
これらの国は、海の向こうに進出できなかった代わりとして、大陸の内部で拡張政策をとろうとした。
つまり、周辺のいろいろな民族集団を統合、併呑して勢力を拡大しようとした。
その理念になったのが、ロシアで起こった汎スラブ主義、オーストリアで起きた汎ゲルマン主義だった。
英仏のように海外領土をどんどん拡げて経済にその恩恵を反映させられなかった代わりに…
汎スラブ主義や汎ゲルマン主義は、理念的、観念的な傾向が強くなって行った。
そしてスラブ人、あるいはゲルマン人こそ、全人類の長となるべく定められた人種だと。
やがて遠い未来には、世界を平定して、真の平和な世界を作る使命を帯びているのだと。
いわゆる「選民思想」です。
そうやってどんどん、イデオロギー的な色彩を帯びたものになっていった。
ただ、汎ロシア、汎ゲルマンだったころは、思想の基盤は「人種の優等性とその使命」でした。
それが、ロシアの場合は社会主義革命が起きた後、より強力なマルクス主義のイデオロギーを得て…
オーストリアの場合は、第一次大戦で君主制が崩壊した後、ダーウィニズムの「優性思想」を得て…
そして結果的に、ロシアからはスターリンが出て、そしてオーストリアからはヒトラーが出て…
(ヒトラーはもともとドイツ帝国の出身ではなく、オーストリア・ハンガリー帝国の出身です)
それぞれの人物が独裁的な力を持って、二つの「全体主義」国家の成立に至った、と。
汎スラブ主義を土壌としてスターリニズムが出現し、汎ゲルマン主義を土壌としてナチズムが生まれた。
そういう流れを、非常に詳しく描写したのが、この第二巻の内容でした。
以上、内容紹介としては、ものすごーくざっとでしかないですが…。
最初に第三巻から読み始めたのは、第一巻の序文で…
アーレントの大学時代の師である哲学者、カール・ヤスパースがそう勧めていたからで…
どうせ三巻から始めたのだから、遡ってよもうということで、次に第二巻を読んだのですが…
それは正解だったと思います。
そして第二巻も大変示唆に富んでいて、すごく勉強にはなりました。
ただ、途中とても引っかかって、読むのが辛い感じになるパートがありました。
それは、イギリスのアフリカ進出に関して記述した部分です。
アフリカにもとから暮らしていた黒い肌を持った人々に対する、著者の偏見というか…
おそらく自覚はしていない、でも明確な差別意識。
そして、アフリカ大陸にもとからあった文明・文化に対する無知や、思い込み、決めつけが…
21世紀の今読むと、いちいち気になって仕方なかったのです。
この本が執筆されたのは、1940年代の後半ですから、時代の制約で、もちろん仕方ないのです。
脱・欧米中心主義の思潮に大きな影響を与えた文化人類学の名著にして、構造主義のお手本となった…
レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』という著作さえ、まだ世に出ていない時点なのですから。
この本が書かれた米国でも、黒人の公民権運動がようやく始まるのは、この10年後ぐらいのことで…
当時、黒人は白人と同じトイレに入れず、バスに乗っても白人と同じ座席には座れず…
そういう場所には「ホワイト・オンリー」などと書かれていたのですから。
スポーツでさえも一緒にできず、野球のメジャーリーグで最初の黒人選手ジャッキー・ロビンソンが…
ドジャースからデビューしたのは、この本が執筆されている途中、という時代ですから。
ハンナ・アーレントが、いかに進歩的な知識人であっても、時代の制約からは逃れられないのです。
すべて書物というのは、それが書かれた「場所」と「時代」を考慮に入れて評価しないといけません。
ケプラーもガリレオも出ていない時代の本を、天動説を語っているからと馬鹿にするのはおかしい。
という理屈は重々わかっているのですけれど…
むき出しの差別意識とか、無知を見せつけられると、やはり「ああ……」となってしまうんですよね。
大昔の本ならきっちり割り切れるのですが、ほぼ現代の作品、という意識が働いてしまうと…。
うーん。これは読者側の、私の問題であるのは間違いないのですけれど。
でも、そういうわけで、この『全体主義の起源2 帝国主義』は…
まずこの点から、第三巻よりも星をひとつ減らさざるを得ないようです。
もう一点、最終章でアーレントは「人権」について、難民と無国籍者の権利、という観点から論じています。
(難民となったユダヤ人、またイスラエル建国によって新たに難民となったパレスチナ人を第一に想定)
これに関しては、私には、アーレントが「人権」という概念をやや矮小化して…
というかあまりに狭い概念として(またしても、ですが)捉え過ぎて議論しているように思えました。
人権から、人間の理想主義的規範という一面を取り去って、現実世界での「適用」の一面…
リアリティとしての社会関係の中での権利、という一面に押し込めている…
という態度から発生した、少し視野の狭い議論になっている気がしたのです。
そしてこの巻の最後の最後の文章は、難民というものを論じて、それを生み出した世界が彼らを…
未開部族や文明に無縁の野蛮人と本質的には同じ生活状態に突き落とすことによって、あたかも自分自身のうちから野蛮人を生み出しているかのようである。
と、またしても、現代では通用しない文言で締めくくられているのです。
西欧、北米人の価値観では計れない豊穣さが、白人到来前の…
彼女が「未開部族」や「野蛮人」と呼ぶ人々の生活・文化・社会に…
かつてあったことには思い至らないのだなと。仕方ないとはいえ、そういうところを読んだとき…
書かれた時代の文脈で理解しなくてはいけない、と分かってはいても、げんなりしてしまうのですよ。
申し訳ないけれど、この人権の章に、現代人としてはいろいろ納得いかないというところ、そして…
作品としての古さを、やはり感じざるを得ないということで、さらに星をひとつ減じて…
この巻は星5個がフルマークとすると★★★の3個とさせてもらいます。
次は、第一巻めの「反ユダヤ主義」について書かれたものを読んでみようかと思っています。