ココディ大学のアルー教授に、私は自分の意見を開陳する。王殺しというのは極端な風習ですけどね、優秀な指導者を確保するという意味では、ちゃんと理由がありますよね。この間はエブリエ族の世代方式を知って、たいへん感心したのですよ。アフリカにはアフリカの社会が、伝統の中で培ってきた統治の知恵が、ちゃんと存在している。社会の出来るだけ多くの人々が意思決定に参加でき、それでいて社会がしっかりした指導者の意思において活力を発揮できる、そして不適当な指導者については政権交代が行われる、そうした仕組みがちゃんとある。
それなのに、欧米諸国が民主主義だ、選挙だといって、ヨーロッパで出来上がった統治の知恵をアフリカに押しつけるのはどうだろうか。アフリカなりの民主主義はあるし、アフリカなりの政権の選び方があるのではないか。そういう疑問が湧いてきているのです、と話す。
「そうですね、選挙だけが民主主義の方式だという欧米の考え方を、アフリカにそのまま持ってくれば、木に竹を接いだようなことになりかねないですよね。」
アルー教授も、私の疑問に賛同する。
「アフリカでは、やはりいい統治が長く続くことが大事なのです。だから、ちゃんと統治が行われていれば、それでずっと末長くやってほしい。安定が続くことこそが人々の希望です。それなのに、数年ごとに政権交代をするべきかどうかを問わなければならない、という制度になっているのは、実のところ無理があります。」
そう言ったって、アフリカの伝統社会のやり方では、やみくもに指導者が長く権力に居座ることになるじゃないか、というとそうでもない。良い統治が損なわれた場合、その場で指導者は退陣を余儀なくされる。数年先の選挙を待たないと政権が変わらない、という欧米民主主義よりも、手っ取り早い。そういう見方もできる。
「それから、アフリカ社会は本質的にはコンセンサス(全員承諾原則)なのです。投票により多数決で決める、などということは伝統にはない。村の寄り合いで、誰もかれも参加して、延々と議論する。大事なことは、そこに全ての人々が参加しているということです。とことんまで議論して、皆が渋々でも納得するところまでこぎつけます。ところが、選挙というのは、選挙に負けた勢力は、政治に参加できないという制度です。あるいは、多数決という原理は、アフリカにあてはめると、少数部族が常に排除されるということを意味するわけです。そういうのは、コンセンサスが政治の本質、という土壌にはそぐわない。」
アルー教授は、続ける。
「アフリカには、大統領制が一般的ですけれどね、これが正しいのかどうか。」
疑問を持っていると語る。
「大統領を選ぶというのは、全国民が投票を行って、たった一人の指導者を選び、その指導者が全権を握るという方式でしょう。そうすると、選挙に負けた人々は、意思決定から排除される。何とか挽回するために、武力に訴え、国の分裂を呼ぶ。かえってアフリカの政治を不安定にしているきらいがあります。」
でも、そうは言っても他にどういう制度がありますかねえ、と私は聞く。
「そうですね、むしろ議院内閣制のような方式、つまり議会に決定権限がより強く委ねられる制度のほうが、コンセンサス重視の社会には合っていますよ。大統領がいるといっても、イタリアのように、実権は総理大臣が握るという制度です。」
そういえば、アフリカに日本のような議院内閣制をとる国がほとんどないのは、なぜだろうか不思議である。またアフリカというと、私たちには、大統領が独裁政権をしくもの、という印象が強い。それで、アフリカの人たちは遅れているから、民主主義を教えても、結局そういう政権のあり方に堕落してしまうのだ、と思いこんでいる。しかし、この見方は、原因と結果を転倒してしまっているのかもしれない。
アフリカはもともとコンセンサス社会で、むしろ独裁などという文化の希薄なところだった。しかし、そうした伝統的な政治・社会文化を生かさないで、欧米型の政治制度を導入し、無理に大統領を作った。そういう、木に竹を接いだ制度を維持するために、独裁型の大統領が数多く生まれてしまった。つまり、本来は一人の人間に権力が集中するような社会の仕組みでなかったのに、憲法で大統領一人に強力な権限を与えてしまった。決定権から排除された人々の不満を抑え、その権限を維持しようとすると、その大統領は独裁に傾いてしまう。そういうことなのかもしれない。
それなのに、欧米諸国が民主主義だ、選挙だといって、ヨーロッパで出来上がった統治の知恵をアフリカに押しつけるのはどうだろうか。アフリカなりの民主主義はあるし、アフリカなりの政権の選び方があるのではないか。そういう疑問が湧いてきているのです、と話す。
「そうですね、選挙だけが民主主義の方式だという欧米の考え方を、アフリカにそのまま持ってくれば、木に竹を接いだようなことになりかねないですよね。」
アルー教授も、私の疑問に賛同する。
「アフリカでは、やはりいい統治が長く続くことが大事なのです。だから、ちゃんと統治が行われていれば、それでずっと末長くやってほしい。安定が続くことこそが人々の希望です。それなのに、数年ごとに政権交代をするべきかどうかを問わなければならない、という制度になっているのは、実のところ無理があります。」
そう言ったって、アフリカの伝統社会のやり方では、やみくもに指導者が長く権力に居座ることになるじゃないか、というとそうでもない。良い統治が損なわれた場合、その場で指導者は退陣を余儀なくされる。数年先の選挙を待たないと政権が変わらない、という欧米民主主義よりも、手っ取り早い。そういう見方もできる。
「それから、アフリカ社会は本質的にはコンセンサス(全員承諾原則)なのです。投票により多数決で決める、などということは伝統にはない。村の寄り合いで、誰もかれも参加して、延々と議論する。大事なことは、そこに全ての人々が参加しているということです。とことんまで議論して、皆が渋々でも納得するところまでこぎつけます。ところが、選挙というのは、選挙に負けた勢力は、政治に参加できないという制度です。あるいは、多数決という原理は、アフリカにあてはめると、少数部族が常に排除されるということを意味するわけです。そういうのは、コンセンサスが政治の本質、という土壌にはそぐわない。」
アルー教授は、続ける。
「アフリカには、大統領制が一般的ですけれどね、これが正しいのかどうか。」
疑問を持っていると語る。
「大統領を選ぶというのは、全国民が投票を行って、たった一人の指導者を選び、その指導者が全権を握るという方式でしょう。そうすると、選挙に負けた人々は、意思決定から排除される。何とか挽回するために、武力に訴え、国の分裂を呼ぶ。かえってアフリカの政治を不安定にしているきらいがあります。」
でも、そうは言っても他にどういう制度がありますかねえ、と私は聞く。
「そうですね、むしろ議院内閣制のような方式、つまり議会に決定権限がより強く委ねられる制度のほうが、コンセンサス重視の社会には合っていますよ。大統領がいるといっても、イタリアのように、実権は総理大臣が握るという制度です。」
そういえば、アフリカに日本のような議院内閣制をとる国がほとんどないのは、なぜだろうか不思議である。またアフリカというと、私たちには、大統領が独裁政権をしくもの、という印象が強い。それで、アフリカの人たちは遅れているから、民主主義を教えても、結局そういう政権のあり方に堕落してしまうのだ、と思いこんでいる。しかし、この見方は、原因と結果を転倒してしまっているのかもしれない。
アフリカはもともとコンセンサス社会で、むしろ独裁などという文化の希薄なところだった。しかし、そうした伝統的な政治・社会文化を生かさないで、欧米型の政治制度を導入し、無理に大統領を作った。そういう、木に竹を接いだ制度を維持するために、独裁型の大統領が数多く生まれてしまった。つまり、本来は一人の人間に権力が集中するような社会の仕組みでなかったのに、憲法で大統領一人に強力な権限を与えてしまった。決定権から排除された人々の不満を抑え、その権限を維持しようとすると、その大統領は独裁に傾いてしまう。そういうことなのかもしれない。



















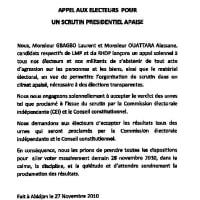
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます