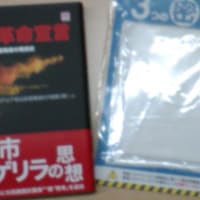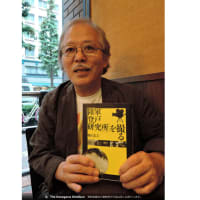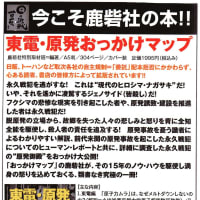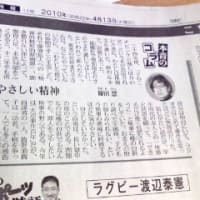前回、話がまたヘンな方に向かってしまった。抽象的にすぎるのだけれども、人間社会が自由自治を目指し、その構成員である個々人が自主、自立、自律などを獲得していくためにはどうすればいいのか、ということを考えていたつもりであった。その一つのオルタナティブとしてル・グィンの小説を取り上げてみたものの、そこから、名誉なるものを考えていたら迷走してしまったので話をもどすことにする。
ここで、社会が先か個人が先かという「ニワトリ=タマゴ」論は避けておこう。また、社会とはなにかというソモソモ論にも踏み込まないようにしたい。こんな問題、社会学者が考えたって結論に到達できるわけがないのだから、ここで「だれだれがかく語りき」的なことを記しても意味がない。しかしアナキズムの場合、国家という支配機関(暴力装置)を否定する以上、そのよりどころを社会なる曖昧模糊としたものに求めてしまうのは自明だろう。そして、社会なるものを無批判に信仰するわけではないにしても、例えばその成長とか熟成とか進化などに期待するオプティミスティックな側面が強いのも事実えだる。そうでもなければ、ル・グィンは『所有せざる人々』など書けなかったはずだ。ここで彼女がアナキストであったなどと述べているわけではなく、彼女もアナキストに通じる楽観を共有していたのだろうという意である。
再びアナキズムに似た用語を取り上げると、ニヒリズムというものがある。これもまた、よくわからない考えだ。『ニヒリズム』(渡辺二郎著、東大出版会)を若いころに読んだことがあったけれど、どんな内容だったのか全部忘れちゃった。そのためかなりいい加減なことを述べることになるが、ニヒリズムって要は「この世のなかに信頼(信仰)しうるのもはないのだから、すべてはカスであると全否定するところからなにもかも始めなければならない」ということではなかったろうか(間違っていたらご教示いただけると助かります)。
小生はハイデッカーを読んでないので偉そうなことを述べる資格はないのだろうけれど、しかし一方で思うに、この世の現実を否定するとはどういうことなのだろうか(そんなことハイデッカーが述べている?)。そこで最初に突然もどると、『保守と大東亜戦争』(中島岳志著、集英社新書)によると、1944年になり特攻隊の攻撃が始まったとき、竹山道雄の隣りで林健太郎が「ニヒリズムだ」とつぶやいたというエピソードが紹介されている。
当然ながら、林はニヒリズムという語を否定の意味合いにおいて使っており、竹山もそれに深く共感したことだろう。青年たちが国の命令によって自殺攻撃をしなければならないのだから。そこまでは理解できるのだけれども、小生はその箇所を読んでいてつまらない隘路に陥ってしまった。つまり林は、ニヒリズムというものを死ぬことを賛美する思想として皮肉に表現したのではないのだろうか、とも読める。もしくは、くだらない作戦を立てて青年を死に追いやる軍部のあり方が、人の死をないがしろにしたものだ、とも読める。さらには、青年を死に駆り立てる日本など、その全体が根底から腐っている、とも読める。そのなかでどういう解釈が真っ当なのだろうかと考え始めたら、よくわかんなくなってしまったというわけだ。
そこで先ほどのニヒリズムの定義で正しいのかどうか、意味深いものなのかどうかにはまったく自信を持てないのだけれども、しかし、林の伝でいくと、東アジア反日武装戦線なんてまさに日本に対する一種のニヒリズムである。日本人が天皇制を頂点とする日本総体を否定する行動であり、発想であったからだ。ここで行動と記したのは、運動といえるほどの広がりをもてなかったからである。そこで、林のような戦前派と反日武装戦線のような戦後派の区別を持ち出したとしても、さほどの豊穣さが生れるとは思えない。ニヒリズムとはなにか、ニヒリズムとアナキズムとの共通と相違を考えているところなので、世代間のちがいを持ち出してもしょうがないからだ。
前掲書によると、林は後年次のように述べているそうだ。
「…今日戦前の日本軍部の中国への武力進出を弁護する人は、それが十九世紀までに西洋人の行ったことと同じであるからそれは正しいと主張しているように見えるが、これほど倫理性を欠いた態度はないであろう」
この一点だけにフォーカスをしぼってしまえば、林健太郎と東アジア反日武装戦線なる真逆の立場なのに、その主張は一致しているようにみえる。しかし、アナルコ保守主義において、やはり林とは訣別せざるをえないということをこのあと考えてみたい。ちなみに、全共闘が東大を占拠していた当時、林健太郎は東大の文学部長だったのかな。つまりは、全共闘の敵であり学生の側から激しい糾弾を受けることになった。しかし、小生は全共闘世代ではないうえ彼らにシンパシーもないので、そうした面からは距離を置いて考えることにしよう。
ここで、社会が先か個人が先かという「ニワトリ=タマゴ」論は避けておこう。また、社会とはなにかというソモソモ論にも踏み込まないようにしたい。こんな問題、社会学者が考えたって結論に到達できるわけがないのだから、ここで「だれだれがかく語りき」的なことを記しても意味がない。しかしアナキズムの場合、国家という支配機関(暴力装置)を否定する以上、そのよりどころを社会なる曖昧模糊としたものに求めてしまうのは自明だろう。そして、社会なるものを無批判に信仰するわけではないにしても、例えばその成長とか熟成とか進化などに期待するオプティミスティックな側面が強いのも事実えだる。そうでもなければ、ル・グィンは『所有せざる人々』など書けなかったはずだ。ここで彼女がアナキストであったなどと述べているわけではなく、彼女もアナキストに通じる楽観を共有していたのだろうという意である。
再びアナキズムに似た用語を取り上げると、ニヒリズムというものがある。これもまた、よくわからない考えだ。『ニヒリズム』(渡辺二郎著、東大出版会)を若いころに読んだことがあったけれど、どんな内容だったのか全部忘れちゃった。そのためかなりいい加減なことを述べることになるが、ニヒリズムって要は「この世のなかに信頼(信仰)しうるのもはないのだから、すべてはカスであると全否定するところからなにもかも始めなければならない」ということではなかったろうか(間違っていたらご教示いただけると助かります)。
小生はハイデッカーを読んでないので偉そうなことを述べる資格はないのだろうけれど、しかし一方で思うに、この世の現実を否定するとはどういうことなのだろうか(そんなことハイデッカーが述べている?)。そこで最初に突然もどると、『保守と大東亜戦争』(中島岳志著、集英社新書)によると、1944年になり特攻隊の攻撃が始まったとき、竹山道雄の隣りで林健太郎が「ニヒリズムだ」とつぶやいたというエピソードが紹介されている。
当然ながら、林はニヒリズムという語を否定の意味合いにおいて使っており、竹山もそれに深く共感したことだろう。青年たちが国の命令によって自殺攻撃をしなければならないのだから。そこまでは理解できるのだけれども、小生はその箇所を読んでいてつまらない隘路に陥ってしまった。つまり林は、ニヒリズムというものを死ぬことを賛美する思想として皮肉に表現したのではないのだろうか、とも読める。もしくは、くだらない作戦を立てて青年を死に追いやる軍部のあり方が、人の死をないがしろにしたものだ、とも読める。さらには、青年を死に駆り立てる日本など、その全体が根底から腐っている、とも読める。そのなかでどういう解釈が真っ当なのだろうかと考え始めたら、よくわかんなくなってしまったというわけだ。
そこで先ほどのニヒリズムの定義で正しいのかどうか、意味深いものなのかどうかにはまったく自信を持てないのだけれども、しかし、林の伝でいくと、東アジア反日武装戦線なんてまさに日本に対する一種のニヒリズムである。日本人が天皇制を頂点とする日本総体を否定する行動であり、発想であったからだ。ここで行動と記したのは、運動といえるほどの広がりをもてなかったからである。そこで、林のような戦前派と反日武装戦線のような戦後派の区別を持ち出したとしても、さほどの豊穣さが生れるとは思えない。ニヒリズムとはなにか、ニヒリズムとアナキズムとの共通と相違を考えているところなので、世代間のちがいを持ち出してもしょうがないからだ。
前掲書によると、林は後年次のように述べているそうだ。
「…今日戦前の日本軍部の中国への武力進出を弁護する人は、それが十九世紀までに西洋人の行ったことと同じであるからそれは正しいと主張しているように見えるが、これほど倫理性を欠いた態度はないであろう」
この一点だけにフォーカスをしぼってしまえば、林健太郎と東アジア反日武装戦線なる真逆の立場なのに、その主張は一致しているようにみえる。しかし、アナルコ保守主義において、やはり林とは訣別せざるをえないということをこのあと考えてみたい。ちなみに、全共闘が東大を占拠していた当時、林健太郎は東大の文学部長だったのかな。つまりは、全共闘の敵であり学生の側から激しい糾弾を受けることになった。しかし、小生は全共闘世代ではないうえ彼らにシンパシーもないので、そうした面からは距離を置いて考えることにしよう。