本書の著者・河村啓三さんはある殺人事件で死刑判決を受け、現在大阪拘置所に在監の身となっている。本書には死刑囚の立場から、執行のある日の拘置所の雰囲気、拘置所の日常生活と同囚への想い、看守や裁判の裏側、そして事件への反省の念と拘置所内で仏門に入られたことなどが綴られている。
まず目を引くのは、その言葉遣いの面白さだ。拘置所を「モンキーハウス」と呼び、自身の独房を「囹圄(れいご)」、お金を「金貲(きんし)」と称している。それは言葉をもてあそんでいるのではなく、視点をずらすことによって、厳しい日常のなかに少しでも生きがいを見出そうとする営為の現われなのだろう。
死刑囚の生きがい? 一般的にははなはだ矛盾した表現のように聞こえるかもしれない。ところが当たり前のことであるが、死刑囚だろうが日本最長寿のおじいさんだろうが、だれもが死にたくはないのだ。そして生きていくには、どんなにささいなことでもいいから生きがいを求めるのが、われわれ凡俗の姿である。
一方、現在日本で三万人以上の自殺者が出ているように、死刑囚のなかにも、おのれの起こした犯行の罪深さや拘禁ノイローゼにとらわれ、自殺願望をいだく人もいる。そういう人を処刑することは、はたして刑足りうるのだろうか。本書で著者も指摘しているが、これは国家によるただの自殺幇助に過ぎないように思えてしまう。
ところが獄吏というのは難儀な商売だ。死刑囚が自殺を企てた場合は必死になって救出しなければならないのに、法務省からの命令が届けば同じ死刑囚を処刑台に引っ立てていく。生殺与奪の権が国家権力にあることを示すために死刑制度が存続しているので、死刑囚は勝手に死ぬことも許されていない。
本書の著者は、あくまでも生きたい派である。そのため、ささいな生きがいを求める。たとえば、季節の移り変わりや、獄窓から見える小動物の姿に心がとらわれ、来世を信じ、同囚や看守とのやりとりに濃密な人間世界を感じる。看守の大半は小生同様の人間のクズだと勝手に思っているが、なかには尊敬できる人もいるようだ。そういうまともな人との触れ合いこそが、死刑囚に半生を振り返らせるきっかけになることが、本書を通してよくわかる。
著者は次のように述べる。「人間というのは自分を認識するためには他人が必要である」。現在死刑囚として収監されている人に本当に反省してもらうには、まともな人間と付き合い、犯してしまった事件と真正面から向き合うことが必要だろう。その作業を放棄させ、殺してしまうことだけで行刑を事務的に処理するのは、保身第一のお役所仕事と批判してもし足りない。
読んでいてもっともつらいのは、著者の家族を襲った災難である。著者が死刑判決を受けると、心労のあまり父親はガンとなり、姉は心身を患い、残された母親はその後しばらくして脳梗塞で倒れながらも、獄中の息子のことを思い、意識朦朧のなか自ら119番通報をして息絶えたそうだ。ひとつの悲劇がさらに悲劇を生んでいく。小生には痛ましいという月並みの表現しかできないが、それを獄中で手をこまねくしかなかった著者の苛立ちは想像もつかない。
くだらない日常をくだらなく生きている小生には、死ぬために生きている著者の放つ「一瞬一瞬を精いっぱい頑張りたい。そしてあとは黙って耐え忍ぶ」という言葉は、耳を撻(う)つ。しかしそれは、死刑囚の言葉だからこそわが耳を撻つのであって、安っぽい自己啓発とは立っている地平がそもそも違うのだ。一瞬、一呼吸を大事に生きることの大切さを、素朴に伝えてくれる。
著者は笑顔を心がけているらしい。「辛くとも笑顔を見せることが大切」で、「笑顔は人を安心させる」そうだ。これは不自由な獄中で、居丈高な看守や自棄気味の同囚と付き合っている著者ならではの発見なのだろう。著者が殺人事件を起こし逮捕されてから約二〇年。その間の、死と対峙し続ける生活と思索とが、こうした境地に赴かせたのだろう。こういう人をいまさらあえて殺さなければならない理由は、少なくとも小生のなかには見つからない。それどころか、やはり死刑制度は廃止すべきだという思いを強くさせる。
河村さんには(ほかの死刑囚にも)少しでも長く、元気で生き抜いてほしい。そして、正面から事件と向き合ってほしい、と切に考えさせられた。
最後に、二〇〇七年に実際に殺人被害にあわれたかたは六〇〇人台で、そのうち心中事件がもっとも多いそうだ。殺されている人の数は年々減少傾向にあり、体感治安の悪化とは正反対にある。この逆転現象の背景には、マスコミの煽り報道があることは言うまでもない。私たちは眉に唾をして事件報道を受け止めないと、だまされていることに気が付かないのだ。
本書は「死刑廃止のための大道寺幸子基金第三回死刑囚表現展」に応募し奨励賞となった作品を大幅に加筆・訂正したものであること、また著者が死刑囚となるまでの経過は前著『こんな僕でも生きてていいの』(インパクト出版会)をご参照いただきたいことを付言しておく。
まず目を引くのは、その言葉遣いの面白さだ。拘置所を「モンキーハウス」と呼び、自身の独房を「囹圄(れいご)」、お金を「金貲(きんし)」と称している。それは言葉をもてあそんでいるのではなく、視点をずらすことによって、厳しい日常のなかに少しでも生きがいを見出そうとする営為の現われなのだろう。
死刑囚の生きがい? 一般的にははなはだ矛盾した表現のように聞こえるかもしれない。ところが当たり前のことであるが、死刑囚だろうが日本最長寿のおじいさんだろうが、だれもが死にたくはないのだ。そして生きていくには、どんなにささいなことでもいいから生きがいを求めるのが、われわれ凡俗の姿である。
一方、現在日本で三万人以上の自殺者が出ているように、死刑囚のなかにも、おのれの起こした犯行の罪深さや拘禁ノイローゼにとらわれ、自殺願望をいだく人もいる。そういう人を処刑することは、はたして刑足りうるのだろうか。本書で著者も指摘しているが、これは国家によるただの自殺幇助に過ぎないように思えてしまう。
ところが獄吏というのは難儀な商売だ。死刑囚が自殺を企てた場合は必死になって救出しなければならないのに、法務省からの命令が届けば同じ死刑囚を処刑台に引っ立てていく。生殺与奪の権が国家権力にあることを示すために死刑制度が存続しているので、死刑囚は勝手に死ぬことも許されていない。
本書の著者は、あくまでも生きたい派である。そのため、ささいな生きがいを求める。たとえば、季節の移り変わりや、獄窓から見える小動物の姿に心がとらわれ、来世を信じ、同囚や看守とのやりとりに濃密な人間世界を感じる。看守の大半は小生同様の人間のクズだと勝手に思っているが、なかには尊敬できる人もいるようだ。そういうまともな人との触れ合いこそが、死刑囚に半生を振り返らせるきっかけになることが、本書を通してよくわかる。
著者は次のように述べる。「人間というのは自分を認識するためには他人が必要である」。現在死刑囚として収監されている人に本当に反省してもらうには、まともな人間と付き合い、犯してしまった事件と真正面から向き合うことが必要だろう。その作業を放棄させ、殺してしまうことだけで行刑を事務的に処理するのは、保身第一のお役所仕事と批判してもし足りない。
読んでいてもっともつらいのは、著者の家族を襲った災難である。著者が死刑判決を受けると、心労のあまり父親はガンとなり、姉は心身を患い、残された母親はその後しばらくして脳梗塞で倒れながらも、獄中の息子のことを思い、意識朦朧のなか自ら119番通報をして息絶えたそうだ。ひとつの悲劇がさらに悲劇を生んでいく。小生には痛ましいという月並みの表現しかできないが、それを獄中で手をこまねくしかなかった著者の苛立ちは想像もつかない。
くだらない日常をくだらなく生きている小生には、死ぬために生きている著者の放つ「一瞬一瞬を精いっぱい頑張りたい。そしてあとは黙って耐え忍ぶ」という言葉は、耳を撻(う)つ。しかしそれは、死刑囚の言葉だからこそわが耳を撻つのであって、安っぽい自己啓発とは立っている地平がそもそも違うのだ。一瞬、一呼吸を大事に生きることの大切さを、素朴に伝えてくれる。
著者は笑顔を心がけているらしい。「辛くとも笑顔を見せることが大切」で、「笑顔は人を安心させる」そうだ。これは不自由な獄中で、居丈高な看守や自棄気味の同囚と付き合っている著者ならではの発見なのだろう。著者が殺人事件を起こし逮捕されてから約二〇年。その間の、死と対峙し続ける生活と思索とが、こうした境地に赴かせたのだろう。こういう人をいまさらあえて殺さなければならない理由は、少なくとも小生のなかには見つからない。それどころか、やはり死刑制度は廃止すべきだという思いを強くさせる。
河村さんには(ほかの死刑囚にも)少しでも長く、元気で生き抜いてほしい。そして、正面から事件と向き合ってほしい、と切に考えさせられた。
最後に、二〇〇七年に実際に殺人被害にあわれたかたは六〇〇人台で、そのうち心中事件がもっとも多いそうだ。殺されている人の数は年々減少傾向にあり、体感治安の悪化とは正反対にある。この逆転現象の背景には、マスコミの煽り報道があることは言うまでもない。私たちは眉に唾をして事件報道を受け止めないと、だまされていることに気が付かないのだ。
本書は「死刑廃止のための大道寺幸子基金第三回死刑囚表現展」に応募し奨励賞となった作品を大幅に加筆・訂正したものであること、また著者が死刑囚となるまでの経過は前著『こんな僕でも生きてていいの』(インパクト出版会)をご参照いただきたいことを付言しておく。
 | 生きる―大阪拘置所・死刑囚房から河村 啓三インパクト出版会このアイテムの詳細を見る |















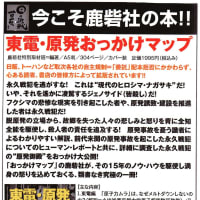




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます