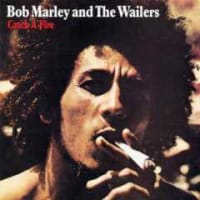モーツァルトには全部で23曲のピアノコンチェルトを書いているが、第1番から4番は他人の編曲であるのでオリジナルは23曲、但し、第27番まで存在する。このうち、第11番以降がウィーンで書かれたもので10年間で17曲、特に14番から25番は3年間に11曲作られている。如何に、モーツァルトがピアノという楽器とオケとの相性や協調に関して高い価値と、多大なる興味を持っていたかということが分かる。後世においての一番人気はなんといっても前回記事を書いた「第20番」であるが、その次はというと色々と好き嫌いが分かれるところであり、この23番、25番、「戴冠式」と題された26番、最後のピアノ協奏曲となった27番あたりが2番人気を争っているらしく、レコードの売上もそんな順番だが、たしかにこれ以外でも、21、22、24番はどれも「モーツァルトらしさ」が十二分の堪能できる楽曲である。
以前はモーツァルトというと、自分的には、室内音楽、それも弦楽四重奏曲の14~19番、所謂、ハイドンセットが一番好みであった。しかしこれらの楽曲はモーツァルトファンならいざ知らず、一般的にそんなに演奏機会の多い曲ではなかった。それに弦楽四重奏曲というジャンルでは、この後にベートーヴェンが控えていて、彼もまた、大フーガに至る道のりとしての、第10番から第16番というのは傑作である。この重々しいベートーヴェンの弦楽四重奏曲集を聴いてしまうと、モーツァルトはものすごく軽い。しかし、結果論を大事にするベートーヴェンに比べて、モーツァルトには、挑戦とか新境地とかという熟語が当てはまる。しかし、そういうことを繰り返しつつも、良く構成を分析すると、色々な試みがそのほかの曲や、後世の他人の曲に別の形で現れていたりする、やはりこの時代に彼は重要な「音楽研究」を後世の教科書として残したのだということがいえて、これはある意味でバッハが音階を整理したことに通じるものがある。モーツァルトは、理論としてバッハをものすごく尊敬し、同時期の実践者としてハイドンを尊敬していた。だから、このハイドンセットから大きく音楽が変わった時代でもある。この直後、1785年に20番、1786年に書かれたのがこの「第23番イ長調」である。
この楽曲はピアノ協奏曲の中でもとても分かり易い曲、古典派の典型的な形式であり、そしてモーツァルトらしい旋律である。曲の構成も単純で楽器の編成も至って普通である。特に第1楽章はまさに型どおりのソナタ形式(協奏ソナタ形式で、オケが提示した主題をピアノが繰り返すというパターン)、またオーボエ使わずにクラリネットを使用しているが、実は、この後に書かれた、「クラリネット五重奏曲」、「クラリネット協奏曲」は何れもイ長調で書かれていて、この3曲は冒頭が似ているが、この辺りにはモーツァルトのクラリネットという楽器への拘りが感じられる。また、第1楽章の展開部では提示部の主題ではなく、新しく導入された主題が用いられているが、これは後世への問題提起とも取れる。
この第23番が好きな人は多く、多分、その方たちは本当に「モーツァルト」を聴きこんだ、モーツァルトフリークだと思う。私は勿論、モーツァルト好きだがモーツァルトファンではないので、やはり第20番とか第25番の方が色々憶測を巡らすことが出来て好きなのである。
こちらから試聴できます