最近買った「トリガーポイントと筋肉連鎖」という本に、面白い記述を見つけた。
頭蓋の屈曲と伸展により各文節が歯車のように動き、姿勢や骨の歪みに影響を与えるという。
私は以前、解剖学的な骨の変位と第一次呼吸機序による頭蓋の病変とは関係が無いと習った事がある。
例えば仙骨の動きで言えば、第一次呼吸機序の仙骨の動く軸と解剖学的変位を起こす軸は違うとされ、解剖学的には仙骨が屈曲していても頭蓋ー仙骨の動きでは伸展を起こしている事がある。
頭蓋の動きは微妙な物で、確かに頭蓋の動きは骨の動きに影響を与えるが、目に見えて姿勢を変化させるほど影響を与えるとは思えない。
私自身は、頭蓋が全身の関節に影響を与えるとしても、あくまでも関節の遊びの範囲内での動きと考えている。
頭蓋の全身への影響に関する記述の中で一番違和感を感じたのは後頭骨の病変と頸椎のカーブとの関係である。
「後頭骨が伸展位にあるとき、頸椎は前彎が強まる」と書かれている。
後頭骨が伸展位ということは後方に変位するということである。
その時にギアのように連鎖が起こり頸椎に前彎が起こると書かれているが、臨床上、後頭骨が伸展位(解剖学上の屈曲位)にあるときはストレートネックの人が多く、逆に後頭骨が屈曲位(解剖学上の伸展位)にあるときは過剰前彎が多い。
これはクロスシンドロームで説明されている通りで、その方が遥かに納得がいくと思う。
頭蓋の動きはあくまでも流体モデルの中で処理するべき考えてあって、それを解剖学的動きにまで広げるべきではないと思う。
この本にはいろんな筋膜連鎖のモデルが紹介されているが、姿勢に関してはやはりクロスシンドローム、運動的な筋膜連鎖に関してはアナトミートレインの考え方が妥当ではないだろうか。
頭蓋の屈曲と伸展により各文節が歯車のように動き、姿勢や骨の歪みに影響を与えるという。
私は以前、解剖学的な骨の変位と第一次呼吸機序による頭蓋の病変とは関係が無いと習った事がある。
例えば仙骨の動きで言えば、第一次呼吸機序の仙骨の動く軸と解剖学的変位を起こす軸は違うとされ、解剖学的には仙骨が屈曲していても頭蓋ー仙骨の動きでは伸展を起こしている事がある。
頭蓋の動きは微妙な物で、確かに頭蓋の動きは骨の動きに影響を与えるが、目に見えて姿勢を変化させるほど影響を与えるとは思えない。
私自身は、頭蓋が全身の関節に影響を与えるとしても、あくまでも関節の遊びの範囲内での動きと考えている。
頭蓋の全身への影響に関する記述の中で一番違和感を感じたのは後頭骨の病変と頸椎のカーブとの関係である。
「後頭骨が伸展位にあるとき、頸椎は前彎が強まる」と書かれている。
後頭骨が伸展位ということは後方に変位するということである。
その時にギアのように連鎖が起こり頸椎に前彎が起こると書かれているが、臨床上、後頭骨が伸展位(解剖学上の屈曲位)にあるときはストレートネックの人が多く、逆に後頭骨が屈曲位(解剖学上の伸展位)にあるときは過剰前彎が多い。
これはクロスシンドロームで説明されている通りで、その方が遥かに納得がいくと思う。
頭蓋の動きはあくまでも流体モデルの中で処理するべき考えてあって、それを解剖学的動きにまで広げるべきではないと思う。
この本にはいろんな筋膜連鎖のモデルが紹介されているが、姿勢に関してはやはりクロスシンドローム、運動的な筋膜連鎖に関してはアナトミートレインの考え方が妥当ではないだろうか。











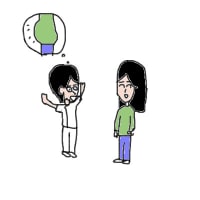
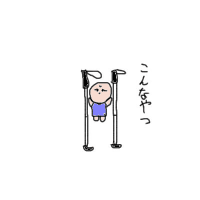
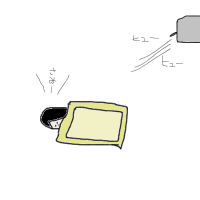


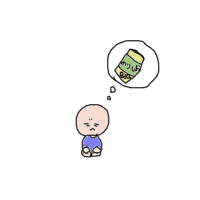
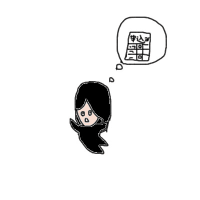
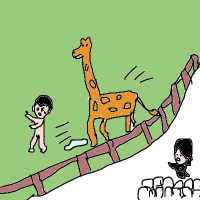

コメントの整理をしている時に間違えて消してしまいました。
オステオパシーでいう「伸展」は解剖学的な変位を表す「伸展」(屈曲制限)と頭蓋仙骨系の「伸展位相」の意味と両方使います。
この本の場合は「伸展位相」という意味で使われており、解剖学的な動きで言えば、逆になります。
朝、寝ぼけてましたから何書いたかあんまり覚えてませんしw
何にしても、「頭蓋の屈曲と伸展により各文節が歯車のように動き、姿勢や骨の歪みに影響を与える」とは何と不自由な体なんでしょう
クロスシンドロームやアナトミートレインもそうですが、そんなに単純な制御系で説明出来るのは節足動物まででしょう。
第一、単純制御はオステオパシーの概念に反していると思いますけどねぇ。
そんなのは我々カイロプラスチックに任せてオステオパスはもっと別な道を進んで下さい
自分は本職ではないのですが人の身体に興味があるということもあり本を少しずつ読んでおります。先生が書かれている「クロスシンドローム」という言葉にとても興味があるのですがこのクロスシンドロームについて勉強する上で何かお勧めの書籍はありますか?初めてのメッセージでいきなりの図々しさ申し訳ありません。
クロスシンドロームについては、エンタプライズから出されている「オーソペディックマッサージ」に比較的詳しく描かれています。
下位交差症候群に関しては79-80Pあたり
上位交差症候群に関しては163-164pあたりです。
8400円の本ですからちょっと高いですけど、基礎的な事が多く、いろいろと役に立つ本だと思います。
一度読んでみて下さい。
お返事ありがとうございます。さっそく購入してみたいと思います。これからもお邪魔させて頂きます。。