今回の不況は構造的なものであり、今後大きな好景気や経済発展は戦争や大規模災害でもない限り望めないだろう。
我々は経済が低成長がデフォルトである社会を生きていかなくてはならないのだ。
もはや社会には潜在的に(これまでの意味での)仕事がない。
そんな中で障害者は福祉サービス部門のサービスの受け手としての役割を期待されている。
そのため「あえて障害者を自立させないというパラドックス」が存在する。
このパラドックスのため障害者の雇用はなかなか促進されない構造がある。
主に知的障害の方が通う作業所などの賃金は時給にして100円台だそうである。
製造業の企業の下請けなどをやっていると東南アジアや中国などとのグローバルでの競争を強いられるからどうしてもそうなってしまう。
(100円ショップで売られている商品の安さなどは異常である。しかしそれは第3国の低賃金、低保障の労働の上に成り立っていることを忘れてはならない。そしてそれは回り回って私たちの首をしめている。閑話休題__・)
かといってよくあるようなクッキーや手すきの葉書、名刺の政策などでは商品性が低く収入が得られない。
作業所を支援するカンパ目的の物品販売の案内がよくまわってくるところをみると実際に事業として成り立っているところは少ないようだ。
ねば塾などの例外はあるにしても・・・。
しかも、現行の応益負担(!?)原則の現行の自立支援法下では作業所に利用料を支払って通うようになってしまったため自己負担分が負担となりこれまでのように通えなくなったり、賃金がモチベーションになっていたのに逆に支出の方が多くなるなどの逆転がおきている。
そしてさらに問題なのは、これらの福祉就労から一般就労の間には広くて深い溝である。
コミュニケーションに困難をかかええていたり、能力の片寄りのある発達障害の人、何度も傷つき社会参加へのエネルギーを失ってしまった依存症の方が、それぞれの能力に応じて働ける職場というのはなかなかない。
一般就労と作業所や授産施設といったモデルだけでは限界がある。
また症状の安定しなかったり無理できない精神障害者も大変だ。
働かない人と働けない人の区別は傍目には難しい。
だから働けない人は偏見に苦しむのだ。
多様な働き方ひいては多様な生き方が容認されない社会では、「働かざるもの食うべからず」といわれ毎日コンスタントに働き賃金を得るというプレッシャーが与えられる。
ただでさえ厳しい労働市場の中で障害をかかえながら仕事をえるのは大変だ。
精神障害はわかりにくい障害であるからオープンで行けば「大丈夫かな?」と思われて雇ってもらえず、クローズドで就職すれば仕事の内容や量が能力を超えていても「つらい、休みたい」となかなか言えず無理をして調子を崩してしまう。
就労訓練をおこなってから、職場に入るモデルもあるが構造化された単純作業自体が減ってしまい仕事が無い。
変わって今主流となってきているIPSモデルでは障害者が自分でやりたい仕事を見つけてきて、ジョブコーチが入り仕事のやり方や働き方などを一緒に考えて就労を継続するモデルである。
それでも障害をもつ人が単独で職場に入った場合、周囲に障害のことが理解されず、また理解されたとしても周りと同じように働きたいと言うプレッシャーから自分を追いつめてしまう場合もある。
結局、社会に居場所をみつけられずにこころに傷を残してやめてしまい引きこもってしまうこともあるだろう。
障害者雇用促進法に基づき常用労働者数56人以上規模の企業では1.8%以上の障害者(具体的には身体障害者手帳か精神保健福祉手帳)、特殊法人や公務員は2.1%以上雇用しなければならないという法律がある。
障害者雇用対策
法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされており、その納付金を障害者雇用の推進のための資金として用いている。
しかしポーズとしては障害者の雇用を募集していても実際に雇うとなると厳しく納付金を払うことを選ぶ企業も多いようだ。
しかし過去に法定雇用率の平均が基準値を上回った例はない。(基準値は改訂で引き上げられてきて入るのもあるが)
これは突き詰めれば障害者は就労の場から排除されており、サービスの受けてとしておとなしくしていろということである。
企業にもっと障害者を雇いましょうと恫喝したり、補助金をだすようなことは対症療法にすぎない
障害者の雇用は、障害者にとっても企業にとってもメリットがなければ障害者の雇用は推進されない。
それでは、どのような仕組みをつくれば障害者の雇用が推進され、サービスの受給者であるという役割を担いながら社会参加が推進されるのだろうか。
まず障害者手帳を 社会参加サポートカードと名称変更し、障害に応じて今以上にきめこまかく配慮をおこなうべきであろう。
そして障害年金は社会参加手当てと名称を変更し積極的に支給し、彼らの生活保障は全面的に国が責任を負うべきである。
苦労しながらも生存権を主張し、支援者の仕事をつくり、堂々と社会参加して生きていくことをまず仕事として認めるきであろう。
その過程でフリーライダーが紛れてきてもよいではないか。
今だって役場や企業内の失業者だって沢山いるのだし(雇用された状態のまま雇用調整助成金で救済されている。)、その後に「生存手当て」としてベーシックインカムに拡大するのが狙いなのだから。
障害者の基本的な生活保障がなされればその分、企業福祉の負担が減り障害者雇用も促進されるだろう。
基礎的な所得の支給を保障した上で、それぞれの能力特性、障害特性にあった仕事をおこなえばよいのである。
精神保健福祉士や作業療法士などはまさにそのマッチング、ジョブコーチング、 キャリアカウンセリング のスペシャリストとしてどんどん活躍してもらえばよい。
支援者もサービスの受給者としての障害者がいることで仕事も得られ、障害者も能力に応じて仕事、役割を得ることができ社会参加が促進される。
これも広い意味でのワークシェアリングである。
障害や欠点は見方を変えれば特徴や個性、長所になりうる。
障害をかかえているからこそ見えること、出来ることもあるだろう。
出来ないことに焦点をあてるよりも、そういった価値転換がはかれないものだろうか。
支援者や周囲の人が障害をもちながらも生きている人から教わることは多いだろう。
多様な人を受け入れることができ、障害者がはたらきやすい職場はそうでない人にとっても働きやすい職場となる。
それは多様なものをみとめる文化へとかわることである。
硬直化し行き詰りつつある今の日本の雇用体制を打ち壊す突破口になるだろう。
参考リンク
Railでいこう! 知識経済に乗れない人たち
我々は経済が低成長がデフォルトである社会を生きていかなくてはならないのだ。
もはや社会には潜在的に(これまでの意味での)仕事がない。
そんな中で障害者は福祉サービス部門のサービスの受け手としての役割を期待されている。
そのため「あえて障害者を自立させないというパラドックス」が存在する。
このパラドックスのため障害者の雇用はなかなか促進されない構造がある。
主に知的障害の方が通う作業所などの賃金は時給にして100円台だそうである。
製造業の企業の下請けなどをやっていると東南アジアや中国などとのグローバルでの競争を強いられるからどうしてもそうなってしまう。
(100円ショップで売られている商品の安さなどは異常である。しかしそれは第3国の低賃金、低保障の労働の上に成り立っていることを忘れてはならない。そしてそれは回り回って私たちの首をしめている。閑話休題__・)
かといってよくあるようなクッキーや手すきの葉書、名刺の政策などでは商品性が低く収入が得られない。
作業所を支援するカンパ目的の物品販売の案内がよくまわってくるところをみると実際に事業として成り立っているところは少ないようだ。
ねば塾などの例外はあるにしても・・・。
しかも、現行の応益負担(!?)原則の現行の自立支援法下では作業所に利用料を支払って通うようになってしまったため自己負担分が負担となりこれまでのように通えなくなったり、賃金がモチベーションになっていたのに逆に支出の方が多くなるなどの逆転がおきている。
そしてさらに問題なのは、これらの福祉就労から一般就労の間には広くて深い溝である。
コミュニケーションに困難をかかええていたり、能力の片寄りのある発達障害の人、何度も傷つき社会参加へのエネルギーを失ってしまった依存症の方が、それぞれの能力に応じて働ける職場というのはなかなかない。
一般就労と作業所や授産施設といったモデルだけでは限界がある。
また症状の安定しなかったり無理できない精神障害者も大変だ。
働かない人と働けない人の区別は傍目には難しい。
だから働けない人は偏見に苦しむのだ。
多様な働き方ひいては多様な生き方が容認されない社会では、「働かざるもの食うべからず」といわれ毎日コンスタントに働き賃金を得るというプレッシャーが与えられる。
ただでさえ厳しい労働市場の中で障害をかかえながら仕事をえるのは大変だ。
精神障害はわかりにくい障害であるからオープンで行けば「大丈夫かな?」と思われて雇ってもらえず、クローズドで就職すれば仕事の内容や量が能力を超えていても「つらい、休みたい」となかなか言えず無理をして調子を崩してしまう。
就労訓練をおこなってから、職場に入るモデルもあるが構造化された単純作業自体が減ってしまい仕事が無い。
変わって今主流となってきているIPSモデルでは障害者が自分でやりたい仕事を見つけてきて、ジョブコーチが入り仕事のやり方や働き方などを一緒に考えて就労を継続するモデルである。
それでも障害をもつ人が単独で職場に入った場合、周囲に障害のことが理解されず、また理解されたとしても周りと同じように働きたいと言うプレッシャーから自分を追いつめてしまう場合もある。
結局、社会に居場所をみつけられずにこころに傷を残してやめてしまい引きこもってしまうこともあるだろう。
障害者雇用促進法に基づき常用労働者数56人以上規模の企業では1.8%以上の障害者(具体的には身体障害者手帳か精神保健福祉手帳)、特殊法人や公務員は2.1%以上雇用しなければならないという法律がある。
障害者雇用対策
法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされており、その納付金を障害者雇用の推進のための資金として用いている。
しかしポーズとしては障害者の雇用を募集していても実際に雇うとなると厳しく納付金を払うことを選ぶ企業も多いようだ。
しかし過去に法定雇用率の平均が基準値を上回った例はない。(基準値は改訂で引き上げられてきて入るのもあるが)
これは突き詰めれば障害者は就労の場から排除されており、サービスの受けてとしておとなしくしていろということである。
企業にもっと障害者を雇いましょうと恫喝したり、補助金をだすようなことは対症療法にすぎない
障害者の雇用は、障害者にとっても企業にとってもメリットがなければ障害者の雇用は推進されない。
それでは、どのような仕組みをつくれば障害者の雇用が推進され、サービスの受給者であるという役割を担いながら社会参加が推進されるのだろうか。
まず障害者手帳を 社会参加サポートカードと名称変更し、障害に応じて今以上にきめこまかく配慮をおこなうべきであろう。
そして障害年金は社会参加手当てと名称を変更し積極的に支給し、彼らの生活保障は全面的に国が責任を負うべきである。
苦労しながらも生存権を主張し、支援者の仕事をつくり、堂々と社会参加して生きていくことをまず仕事として認めるきであろう。
その過程でフリーライダーが紛れてきてもよいではないか。
今だって役場や企業内の失業者だって沢山いるのだし(雇用された状態のまま雇用調整助成金で救済されている。)、その後に「生存手当て」としてベーシックインカムに拡大するのが狙いなのだから。
障害者の基本的な生活保障がなされればその分、企業福祉の負担が減り障害者雇用も促進されるだろう。
基礎的な所得の支給を保障した上で、それぞれの能力特性、障害特性にあった仕事をおこなえばよいのである。
精神保健福祉士や作業療法士などはまさにそのマッチング、ジョブコーチング、 キャリアカウンセリング のスペシャリストとしてどんどん活躍してもらえばよい。
支援者もサービスの受給者としての障害者がいることで仕事も得られ、障害者も能力に応じて仕事、役割を得ることができ社会参加が促進される。
これも広い意味でのワークシェアリングである。
障害や欠点は見方を変えれば特徴や個性、長所になりうる。
障害をかかえているからこそ見えること、出来ることもあるだろう。
出来ないことに焦点をあてるよりも、そういった価値転換がはかれないものだろうか。
支援者や周囲の人が障害をもちながらも生きている人から教わることは多いだろう。
多様な人を受け入れることができ、障害者がはたらきやすい職場はそうでない人にとっても働きやすい職場となる。
それは多様なものをみとめる文化へとかわることである。
硬直化し行き詰りつつある今の日本の雇用体制を打ち壊す突破口になるだろう。
参考リンク
Railでいこう! 知識経済に乗れない人たち










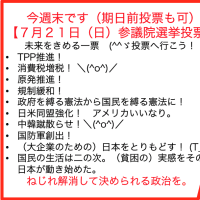
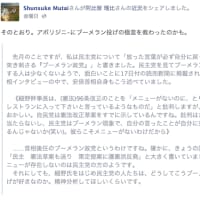




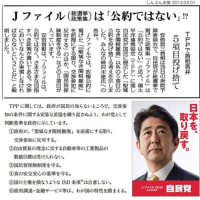

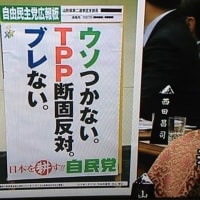

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます