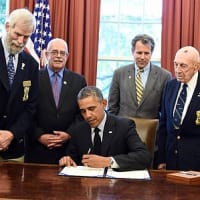【書籍】『大韓民国の物語』日本語版~読売新聞書評、「ニューライト・李榮薫教授は勇気ある韓国人」[05/07]
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1241636175/
■日本紙書評で「強い愛国心込められて」
(写真)
http://data.orunson.kr/img/photo/0905/06/1241588139.jpg
2007年5月、図書出版・キパラン(代表=アン・ビョンフン)が発行した李榮薫(イ・ヨンフン)教授の『大韓民国の物語(大韓民国話)』を、日本の『文藝春秋』が日本語版で発行した。書名は韓国の書名と同じ『大韓民国の物語』。
『大韓民国の物語』は2006年2月に発売された『解放前後史の再認識』を、著者の李榮薫教授が「少し分かりやすく、読みやすく」ともう一度書いた本だ。最初の原稿はEBSラジオ放送の要請を受け、特別講義形態で一般人に公開されたが、一週間の講義内容を修正・補完し、三倍になる量で完成された本として発行した。
『大韓民国の物語』は、韓国近現代史を全面再解釈している。
結局歴史は解釈のみ。激動の20世紀を経た大韓民国近現代史で我々は、『民族主義』という感情に縛られた歴史だけを語り、解釈して来たのは事実。著者は我々を縛りつけた民族主義を解体して分別し、利己心を本性とする人間個体を歴史叙述の単位にしなければならないと主張する。朝鮮王朝が敗亡した原因、植民地収奪論、親日派清算問題、日本軍慰安婦問題など、現代史の重要な問題と争点なども新しい視覚で解いている。
日本の読売新聞は去る5月3日付けの文化面で、李榮薫教授の『大韓民国の物語』の書評を囲み記事で比重をかけて扱った。筆者は韓国思想研究者である小倉紀蔵氏。
小倉氏は書評の初節をこんな風に始めている。「真に勇気のある韓国人がここにいる、という感じだ」と・・・。
小倉氏は、「これまでは歴史について韓国人がどんなに声高に語っていても、つねに『民族』に遠慮している」と前提して、「韓国でニューライトの論客として有名な李榮薫教授がこの本で、『歴史の主体は民族ではなく個人であると明確に語る』」と驚いている。
また、「李教授が韓国の近現代史を、伝統文明と外来文明が衝突し接合する『文明史の大転換過程』と把(とら)え、善と悪の二項対立式の歴史観を拒絶する」と紹介した。歴史を見る目が単純でなく複合的というのだ。
実は李榮薫教授はこの本で、民族史観と民族主義を猛烈に攻撃している。しかし彼を反民族主義者と思ってはいけない。李教授は単に民族だけが歴史の唯一無二する単位であると思うのは偏狭だと言っているだけだ。小倉氏の指摘どおり、彼が『民族』を単位にした歴史の代案として提示したのは、『個人』を単位にした歴史だ。
小倉氏は書評を通じてこの本に対し、「歴史を直視できぬまま歴史から自由になれていない韓国人に、「過去の歴史の亡霊」から解放されよと発言する、強靱(きょうじん)な愛国の書」であると評価している。
過去から自由でない韓国人が、この書評に対してどの位自由であるかを知りたい。
ソース:ニューデイリー(韓国語)
http://www.newdaily.co.kr/articles/view/26056
『大韓民国の物語』 李榮薫著 永島広紀訳
民族主義からの脱却
真に勇気のある韓国人がここにいる、という感じだ。これまでは歴史について韓国人がどんなに声高に語っていても、つねに「民族」に遠慮している。「民族」をこわがっている。「民族」の代表者になってしまっている。「個人」の意見を堂々と語っていない。そんな印象を受けていたからだ。もっと自由に語ってもいいはずなのに、できなかった。
本書の著者は、韓国でニューライトの論客としてあまりにも著名な歴史家である。だが、民族主義者ではない。歴史の主体は民族ではなく個人であると明確に語る。その視点から見ると、これまでの韓国史は嘘(うそ)だらけだった。偽善の知性としての歴史学者たちが、実証を経ずにでたらめな説を述べ、歴史教科書に書き、そしてそれが韓国人の誤った集団記憶となってしまったというのだ。
韓国人は5000年前からひとつの民族でありひとつの共同体だった。日本は植民地支配を通して朝鮮人の土地・財貨・食料などを無慈悲に収奪した。解放後に親日派を粛清できなかったことが、今日の韓国の不正義の淵源(えんげん)だ。これらはすべて間違った認識だと、著者は次々に切り捨てる。すべてを根本的なひとつの要因によって説明しようとする道徳主義的な民族絶対主義から抜け出さなくては、韓国は決して先進国にはなれないという。
韓国の近現代史を、伝統文明と外来文明が衝突し接合する「文明史の大転換過程」と把(とら)え、善と悪の二項対立式の歴史観を拒絶する。歴史を見る目が単純でなく複合的なのだ。
「植民地時代に韓国は近代化し発展した」と説き韓国人の猛烈な反発と批判を受けても、実証への信頼があるから全く動じない。とはいえその主張は日本の支配の美化ではなく、日本の「右」を勇気づけるものでもない。歴史を直視できぬまま歴史から自由になれていない韓国人に、「過去の歴史の亡霊」から解放されよと発言する、強靱(きょうじん)な愛国の書なのである。永島広紀訳。
◇イ・ヨンフン=1951年生まれ。ソウル大学校経済学部教授。主な著書に『朝鮮後期社会経済史』など。
文芸春秋 1857円
評・小倉紀蔵(韓国思想研究家)
(2009年5月4日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/book/review/20090504bk06.htm
『大韓民国の物語 韓国の「国史」教科書を書き換えよ』 李 榮薫著 (文芸春秋・1950円)
●偏狭な歴史観が理解を阻む 立石 泰則 ノンフィクション作家
韓国と北朝鮮は隣国であるにもかかわらず、多くの日本人にとって「遠い国」である。たしかに昨今の韓流ブームで韓国に対する理解が進み、好感を持つ日本人が増えたとはいえ、本質的な問題解決には道はまだ険しい。
両国民の相互理解を阻んでいるもののひとつは、戦前の日本による朝鮮統治、つまり「加害者」と「被害者」という意識に囚(とら)われすぎて自然体で向き合うことが難しいことである。朝鮮の植民地化に対し多くの日本人が「負い目」を感じ、多くの韓国人は「無慈悲で暴力的な日本人」像から逃れられないでいるからだ。
それは、ある意味、両国の歴史教育の「成果」でもある。
例えば、一般の韓国人は《日本の朝鮮統治は収奪以外のなにものでもなかった》と国史の教科書で教えられ、そう信じている。また物理的な収奪以外にも《約650万名の朝鮮人を戦線へ、工場へ、炭坑へ強制連行し、賃金も与えず、奴隷のように酷使した。(中略)朝鮮の娘たちを動員し、日本軍の慰安婦とした》といった記述も、教科書にはある。
しかしそれらは、緻密(ちみつ)な実証に基づく韓国の経済史家の著者にとって執筆者が書いた「物語」にすぎず、《過去50年の間、民族主義の歴史学が、20世紀の韓国史の道筋をどれほど深刻に歪(ゆが)めてきたか》と鋭く批判する。
著者にとって20世紀の韓国史で重要なのは、日本からの独立だけでなく《文明史における一大転換》、つまり《中華文明圏から離脱し、西欧文明圏に編入された》ことである。人間の本性は「自由」であり、それを認める西欧文明圏への編入は、新しい時代の到来であった。そしてその大転換を直接強要したのが、日本(の植民地化)だったという。
だからといって、著者はいわゆる親日家ではない。むしろ徹底した日本帝国主義(植民地政策)の批判者である。彼の批判の目は、朝鮮統治における日本の「同化政策」が「自由な存在」である人間の本性を否定する点に向けられている。《自由がない者は屍(しかばね)と変わりません》という言葉に日本の朝鮮統治批判と朝鮮独立の正当性の主張が端的に表されている。
偏狭なナショナリズムに基づく歴史観が、いかに国の発展を阻害するか‐‐このことは、本書を読むと、日本も対岸の火事ですまされないことがよく分かる。
=2009/03/22付 西日本新聞朝刊=
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/book/review/20090323/20090323_0001.shtml
『大韓民国の物語・韓国の「国史」教科書を書き換えよ』
鈴木琢磨書評=今、日本にとどく 韓国保守知識人の「自国の歴史」への思い
おもしろいなあ。萎縮していた脳みそのシワがびよーんと伸びる。「大韓民国の物語」を読んでの、それが実感である。コチコチに凍っていた「韓国の歴史」がぽかぽか春の日差しに融けだしたような。初めての体験。
著者の李榮薫さんはソウル大経済学部の教授。「朝鮮後期土地所有の基本構造と農民経営」で博士号をとっている。なにやら難しそうであるけれど、その文章に触れれば、この博士が専門バカでないことはすぐわかる。
いったい、それがいかなるものかは知らないけれど、経歴には1977年から芝谷書堂で漢学5年課程を修了
とある。いいなあ。教養人である。それもとっびっきり上等の。
知的でユーモラス、わが民族を愛しながらも決して溺れず、あくまで視野は広く、自らの言葉で、やわらかく歴史を語る、その手ダレ感は司馬遼太郎さんをほうふつさせる。司馬さんの歴史エッセーにどこか通じる。実際に本を手にとって、じっくり味わっていただきたいから、引用はほんのちょっとだけ。
〈大韓民国は「歴史問題」で風邪をひいています。かからなくてもいい風邪に意味もなくかかっているのです。だから余計に体と心が痛いのかも知れません。風邪の原因は誤った歴史観です。歴史観は明るく健康なものにすれば、風邪はたちどころに治るでしょう〉
すべてがここに集約されている。博士はかなり重症で、ほおっておけば肺炎になるやもしれない自国の「歴史問題」なる風邪を退治したい、その純粋な一念で、ドクターよろしく、患者に語りかける。その風邪は、たちが悪いせいか、玄界灘をこえて日本にも広がっているらしく、このたび、翻訳というかたちでドクターが往診にきてくれたのである。まことに慶賀にたえないことである。
ついつい日本人としては遠慮がちに小声でしか言えなかった「事実」を、のびやかに堂々と開陳されてくださっているのは痛快である。たとえば、日本の植民地の「遺産」について。1960年代までは南よりも北が経済的に進んでいたといわれる。それは、彼ら平壌政府が宣伝するような社会主義の生産力のためではなく、北のエリアが植民地の物質的遺産が豊富だったから、と看破している。そして、そうした、ある意味メードイン・ジャパンの生産力への過信が金日成をして、朝鮮戦争へと突き進ませたのだ、とも論じる。
それにしても、ようやく、との感を禁じえない。これほどの実力をそなえた韓国保守知識人の思いすら、日本ではほとんど知られていなかった。読まれることはなかった。隣人理解はまだまだである。最後に永島広紀さんの翻訳文のうまさを特記しておきたい。
(すずき たくま 毎日新聞編集委員)
http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=48124&thread=10
歴史からの自由を説く韓国人による韓国論が生れた
『大韓民国の物語』 (李榮薫 著/永島広紀 訳)
鄭 大均Taikin Tei|首都大学東京教授
2009.02.20 00:00
■ 収奪論の神話性
『大韓民国の物語――韓国の「国史」教科書を書き換えよ』は少なくとも三つの理由で、三種類の日本の読者にきわめて有益である。
第一に、隣国に政治的な疑念を抱いている読者にとって。国家が半世紀以上も前の親日派を調査し、その名簿と行状を公開するといったニュースや韓国の北朝鮮に対する宥和政策のニュースに接して、解(げ)せないという感覚をもつ人々のことである。進歩派というよりは保守派の日本人に広く共有される感情や態度で、中には専門家といわれる人々も含まれるだろう。だが、ソウル大学経済学部教授の李榮薫(イ ヨンフン)氏が書いた本書を読むと、こうした疑念は、韓国人自身にも共有されていることがよく分かる。
李氏によると、韓国の政治は過去の亡霊から早く自由にならなければならないのであり、これ以上、死者が生者の足を引っぱるようなことをしてはならない。そもそも、世にいう「植民地収奪論」といったものは実証的な議論なのだろうかともいう。
生産された米のほぼ半分が日本に渡っていったのは事実です。しかしながら、米が搬出される経路は奪われていったのではなく、輸出という市場経済のルートを通じてでした。(中略)収奪と輸出はまったく異なります。収奪は朝鮮側に飢饉のほかには何も残しませんが、輸出は輸出した農民と地主に輸出にともなう所得を残します。米が輸出されたのは総督府が強制したからではなく、日本内地の米価が三〇パーセント程度高かったからです。ですから、輸出を行えば、農民と地主はより多くの所得を得ることになります。その結果、朝鮮の総所得が増え、全体的な経済が成長しました。
植民地収奪論はおおむね一九六〇年代以降、韓国の民族主義が高揚する過程で作られた神話に過ぎない。
李榮薫氏は一九五一年生の韓国経済史の専門家。古い土地台帳を資料に実証的な歴史研究をするとともに、今日のニューライト運動の中心にいる人物で、北朝鮮に宥和的な左派民族主義者にも自己陶酔的な右派民族主義者にも批判的である。
本書に接した読者は、韓国人がみな北の王朝に宥和的であるとか韓国人が日本を怨嗟(えんさ)の目で眺めているという印象が、実は自身の韓国や韓国人に対する先入観やステレオタイプの思考の産物であり、いま韓国は、北朝鮮との関係においても、日本との関係においても、重要な岐路にあるのだということに気がつくはずである。
■ ヨン様派やカン様派への贈りもの
第二に、本書は隣国に比較的最近、親近感を抱きはじめた読者にとっても有益である。ここには若い学生もいれば、熟年の女性もいるだろうし、筆者が「ヨン様派」や「カン様派」と呼ぶ関心層もいるであろう。
ヨン様派が「冬ソナ」や「チャングム」といった韓国のポップカルチャーとの出会いを通して隣国に関心を寄せはじめた読者であるとするなら、カン様派とは、例の姜尚中東大教授の著書やテレビでの尊顔に接して隣国に関心を寄せはじめた読者のことで、前者がリアリズム志向なら、後者はバーチャル志向という重要な違いはあるが、いずれも日本人の劣化過程で生れた現象であり、隣国になにかしらの幻想を抱きやすいという共通性もある。
こういう読者に李氏の本が益するところは大であろう。といっても、これは大部の本でもなければ、生硬な本でもない。二〇〇六年六月、李榮薫氏は韓国のEBSラジオに出演、『解放前後史の再認識』(本の世界社刊)という本の解説番組を一週間にわたって担当した。
本書はそのときの放送原稿に加筆・修正してできあがったもので、話し言葉的に記されていると同時に、自伝的な語りがあり、流行歌や文学作品の一節が紹介されていたりする。
筆者に印象的だったのは、詩人・徐廷柱の「親父はだった」から始まる「自画像」(一九三七年)という詩に触れたくだりで、次のようにいう。
この偉大なる抒情詩人は父親がの出身でした。詩人はの身分を恥じました。そこで「世の中は行けども行けども恥ばかりなり」と詠いました。ところで李朝時代におけるの売買文書を見ると「寿介(スゲ)」というちょっと粋な名前がしばしば目につきますが、実際には「犬っころ(スケ)」という語の当て字でした。詩人は自分をその犬っころに喩えています。「舌が垂れ下がった病犬のように息せき切りながら我は来たり」と。私はいまだかつて、このように自身の卑しい身分をある時代の痛みにまで昇華させて詠う高潔なる精神に触れたことはありません。この詩人はしばしば親日派と罵られていますが、私はこの詩の一篇だけでも彼を愛してやみません。
最後に本書は、韓国にはとりたてて関心を寄せるわけではないが、自分は欧米やその他の地域の政治や歴史や文化などについてはよく知っていると自負するインテリ読者にもお薦めの一冊である。
そんなインテリが、たとえばアジアや欧米のどこかの国で、韓国のインテリに会ったとする。そんなとき韓国人は「植民地時代」を、善良な韓国人が無慈悲にも日本人に土地や食料や労働力を収奪される物語として語るかもしれないが、それになんと応えるのだろうか。たまには疑念を表明するものもいるのだろうが、おそらくは同調してしまうものの方がずっと多いに違いない。
それに触れた箇所があるわけではないが、そんな日本人の態度は韓国人にとってもマイナスが大きいのだということを本書は教えてくれる。それは要するに思考停止の植民地認識であり、植民地体験からなにも学んでいないに等しいというだけではなく、韓国人にとっては、死者が生き返り、再び生者の足を引っぱりはじめることを意味するからである。
■ 説得力の源泉
著者も記しているように、『大韓民国の物語――韓国の「国史」教科書を書き換えよ』と題する本書はいつの日か、体系的に書きなおされるべき韓国近現代史のための水先案内といった性格の本に過ぎない。にもかかわらず、李氏の本が他の本よりも陰翳(いんえい)に富み、奥行きがあるように見えるのはなぜか。
それは李氏が韓国の知識人たちがよくやるように、外来思想で事象や対象を眺め、当世流行の図式を描き出して満足するかわりに、対象に向き合い、モノゴトを考えているからではないのか。当世流行の韓国論の多くは、そんな意味ではバーチャルなものばかりだ。あの言語道断の北朝鮮の王朝に宥和的な議論を展開する韓国論、つまり金大中や池明観や姜萬吉や和田春樹や高崎宗司や姜尚中といった面々の議論がそれだ。だからそんな韓国論を読んでも、他人事(ひとごと)のような気がする。彼らの物語のなかに生きた自分を位置づけることができないからである。
本書の前半に記されているのが日本統治にかかわる問題であるとしたら、後半に記されているのはアメリカや北朝鮮との関係の問題で、そのいずれにおいても、李榮薫氏は自分の国がなにものであるのかを真摯(しんし)に問い続ける。自国のナショナル・アイデンティティを問う作業は、自国の歴史をどのように統合するかの問題であると同時に、他国や他文化との共有性の問題であり、だからここには日本もアメリカも北朝鮮も中国も登場するが、私が知る限り、李榮薫氏ほど自国のアイデンティティについての説明責任を明瞭に果たした韓国人はいない。
しかしこのことは李榮薫氏という人物が日本に阿諛(あゆ)迎合するような人間であることを意味しない。訳者の永島広紀氏はあとがきで次のように記している。「実証を伴わない観念的な思考を極度に排する態度を崩すことなく、それでいてかつての『日帝』の所業に対する筆致は厳しい。その意味では日本にとっては最も手強い相手の一人であるのかも知れません」。同感である。
http://hon.bunshun.jp/articles/-/299
李栄薫・ソウル大学教授:「私たちが植民地時代について知っている韓国人の集団的記憶は多くの場合、作られたもので、教育されたものだ」
「私が植民地時代のイメージを修正するようになった個人的動機は、1990年、日本の『土地調査事業共同研究』のために全国を巡回し、土地台帳など原資料を収拾したことだった。慶南・金海市地域には、大量に原資料が残っていた。それらの資料を参考を検証して、教科書とは余りにも異なる内容に驚いた。
『土地申告をやらせて、無知な農民たちの未申告地を容赦なく奪った』と教科書の記述にはあるが、実際はまるで異なり、未申告地が発生しないよう綿密な行政指導をしており、土地搾取が発生することがないよう、繰り返し、指導と啓蒙を進めていた。
農民たちも自身の土地が測量され、地籍簿に記載されたのを見て喜び、積極的に協力した。その結果、墓や雑種地を中心に0.05%程度の未申告地が残ったに過ぎない。それを知った時、私が持っていた植民地朝鮮のイメージは、架空の創作物に過ぎないものであったことを自覚した」
日韓併合の「よこせ」神話の実体
http://ameblo.jp/myaimistrue/entry-10209245860.html
【韓国】ソウル大・李教授「日本による収奪論は反日教育で作られた神話」
ソウル大学の李栄薫教授~『日帝の650万人動員説は誇大』
【韓国】「日帝、米収奪なかった」~乱闘場になった「教科書フォーラム」
話題の新刊「解放前後史の再認識」
官僚とメディア 魚住昭 著
私がまだ共同通信の記者をやめる直前の『沈黙のファイル』の取材で、同僚と一緒に太平洋戦争開戦前夜の参謀本部作戦課の内情を調べたことがある。作戦課は陸軍大学校出身の超エリート参謀二十数人からなる陸軍の中枢機関で、国防方針に基づいて作戦計画を立案し、約四百万人の軍隊を意のままに動かした。
その作戦課の元参謀たちに「勝ち目がないと分かっていながら、なぜ対米戦争を始めたのか」と聞いて回ったら、ある元参謀がこう答えた。
「あなた方は我々の戦争責任を言うけれど、新聞の責任はどうなんだ。あのとき新聞の論調は我々が弱腰になることを許さなかった。我々だって新聞にたたかれたくないから強気に出る。すると新聞はさらに強気になって戦争を煽る。その繰り返しで戦争に突き進んだんだ」
この言葉は私にとってかなり衝撃的だった。というのも、私はそれまで新聞は軍部の圧力に屈して戦争に協力させられたのだと思い込んでいたからだ。それが事実でなかったとしたら、私たちが教えられた日本のジャーナリズム史は虚構だったということになる。(P126)
~
佐々木によれば、新聞の親軍的記事はすべてが強制ないし暗黙の強制によるものではなかった。誘導の効果はいくらかあったかもしれないが、もともと親軍的な記者、軍にシンパシーを抱く記者、誘導を受け容れる素地のある記者はいくらもいた。それは軍に批判的な記者や記事が存在したことと同様にまぎれもない事実だった。
彼ら新聞記者たちは政官界の随所に濃密な人間関係を設けて食い込み、情報を物々交換することで、あるいは情報を通貨のように利用することで密着度を高めながら、実態としては情報提供者・情報幕僚として振る舞い、時としては政治ブローカーのごとき役割をも果たしていたという。
まったくその通りだったろうと私はかなりの確信を持って言うことができる。なぜかというと、戦後の記者である私自身が検察庁に「濃密な人間関係を設けて食い込み、情報を物々交換することで、あるいは情報を通貨のように利用することで密着度を高めながら、実態としては情報提供者・情報幕僚として振る舞」っていたからだ。
たしかに政官財界の腐敗を摘発する検察と、日本を破局に陥れた旧陸軍は違う。しかし、それは戦後の我々が陸軍を罪悪視しているだけであって、戦前・戦中の「親軍的な記者」たちにとって陸軍は今の地検特捜部のような「正義の味方」だったのだろう。(P127・P128)
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/08414aebd4f1e1c57273678da46d1962
身近な植物がなぜ叩かれる?~『大麻ヒステリー』
武田 邦彦著(評:加藤 亨延)
光文社新書、740円(税別)
大麻が、日本人にとって身近な植物だと聞いて、驚かれる方も多いだろう。神社の鈴縄やしめ縄は大麻から作られているし、七味唐辛子に含まれる「麻の実」は大麻の実である。この他にも蚊帳、産着、下駄の鼻緒、畳の縦糸と、我々の伝統文化と大麻との関係は、枚挙にいとまがない。
著者によれば〈大麻は、日本の風土にあっていて、農薬などが少なくて済み、成長が早く、広い用途に使うことができ、持続性社会を考えるなら最適な作物の一つ〉であった。有史以来、日本の伝統・文化と多くの接点を持ち、生活に溶け込んでいた植物にも関わらず、戦後、我々は大麻に対し一貫して否定的な印象を持ち続けてきた。本書では、このような“現代の禁忌”である大麻問題を、様々な例を挙げつつ、肯定しようと試みている。
そもそも「麻薬」と「大麻」を混同している人も多いのではないか。「麻薬」という言葉は、旧字体では「痲薬」と記し、「痲」の字は「しびれる」という意味を持つ。一方で、「大麻」の「麻」は植物の「アサ」を指す。つまり「痲」と「麻」は同じ意味ではない。1949年に、漢字が旧字体から新字体に移行され、「痲」と「麻」が同じ漢字になった結果、このような混同が起きたのだ。
言葉の問題に限らず、大麻が禁忌たる“最大の障壁”、精神的作用にも著者は言及する。精神的作用とは、多幸感や開放感と表現される。具体的には、頭がボーっとしつつも、少しの物音にもパッと反応する鋭利な感覚が混在し、箸が転んだだけで笑い出してしまうほど、感情が大袈裟になるといえば、理解できるだろうか。大麻の種類によって、これら引き起こされる作用の程度も異なるという。
大麻の主成分は、主に二種類の化学物質によって構成されている。1つは精神的作用をもたらすテトラヒドロカンナビノール(THC)。もう1つはカンナビジオール(CBD)という、THCの精神的作用を打ち消す働きをするものだ。つまり、THCとCBDの含有割合によって、精神的作用に強弱がつく。
国産は精神的作用が低いらしいが
インド大麻はTHCの割合が多く精神的作用が高いが、一方で、日本固有の大麻にはTHCが少なく(もしくは、ほとんど含まれず)、CBDが多い。よって、精神的作用が低い(もしくは、全くない)らしい。
しかし、現行の大麻取締法では、THCの有無に限らず、全ての大麻が取り締まりの対象となる。これに対し著者は、THCの含有量によって規制すべきと提案している。
それでは、精神的作用をもたらす大麻は人体に有害なのか? 著者はWHO(世界保健機構)が1970年にまとめた「健康および心理に対するアルコール、インド麻、ニコチン、痲薬摂取の結果の相対的な評価」というレポートの一部を根拠に、大麻の有害性を否定している。
〈奇形の発生、衝動的な行動、大麻を吸っているうちに吸う量が増えるというような、激しい障害や習慣性はないこと、さらには痲薬につきものの禁断症状などは認められない〉
〈大麻がきっかけになって、ヘロインなどの痲薬につながる(評者注:ハードドラッグへの入り口になる)ことはない〉
さらに、著者は科学的根拠だけでなく、現行の大麻取締法の出自を探りながら、その施行自体に疑問を呈していく。
大麻取締法のキッカケはGHQ(連合国軍総司令部)の戦後占領政策にあり、その大元は、1920年にアメリカで制定された禁酒法だという。
そもそも、禁酒法の制定の裏には、ドイツなどから新たにアメリカに渡ってきたカソリック系住民に対する、プロテスタント系住民の感情的な反発があった。また、第一次大戦による対独感情の悪化も影響していた。
結局、禁酒法は13年後の1933年に廃止されることになるのだが、今度は酒の販売や製造を取り締まっていた捜査員の再就職問題が浮上してきた。同法の施行下では、大規模な酒店から小さな酒屋まで監視の目を光らせるため、多くの人員を要していたからである。
その頃になると、カソリックに代わり、メキシコなどから多くのヒスパニック系移民がアメリカに渡ってきた。白人にはもともと大麻を吸う習慣はなかったが、彼らヒスパニック系移民は、ニコチン・タバコより習慣性がなく価格も低かった大麻を、安タバコとして吸っていた。もともと、彼らが街に進出してくることを快く思わない白人の感情に、禁酒法廃止による捜査員の失業対策が加わり、大麻課税法が成立していくのである。
大麻課税法においては、建前上は法外な税金を支払えば大麻を扱うことが可能となっていたが、実際には「大麻に課税したことを示す証明書」は一度も発行されていない。つまり、実質、大麻課税法は“大麻禁止法”の意味合いを持っていた。
さらに当時、大麻は重要な繊維資源だったが、デュポンの研究員だったカロザースがナイロンを発明し、石油化学産業が勃興する。彼ら石油化学産業関係者にとっても、大麻課税法の成立を後押しすることは、繊維産業のライバルを蹴落とす意味でも好都合だったのだ。
これら、さまざまな思惑が入り混じった大麻課税法制定から10年の時を経て、第二次大戦の戦勝国となったアメリカが、GHQの中心国として日本に上陸する。日本の大麻の精神的作用が低いことは、既に説明した。それにも関わらず、アメリカ本国の大麻課税法の影響を受け、新たな規制が日本国内にも作られていくことになる。
以上のように、著者は大麻擁護の論陣を張っていくが、こうした主張は本書に限ったことではない。新書でいえば『大麻入門』のように、大麻解禁を訴える他の本の多くも、同じような説明を展開している。大麻の神道における位置づけにはじまり、大麻由来のプラスチックなど産業用大麻の重要性を挙げながら、大麻を肯定していく。しかし精査してみると、論の運び方が無理やりだったり記述に誤りがある場合も少なくない。残念ながら、本書も前轍を踏んでしまっている。
強引な大麻擁護論は逆効果
例えば著者は、〈1961年の国際条約(麻薬単一条約)で、マリファナ(評者注:大麻)をアヘンやヘロインなど本当の痲薬と同じ取り扱いにしました〉と述べているにも関わらず、そのすぐ後の文章で、〈オランダ、デンマーク、イタリアでは(評者注:大麻が)公に使用が認められています〉と言い切っている。これは完全な誤りだ。
そもそも、オランダは麻薬単一条約のメンバーである。ゆえに大麻を完全に合法化することはできない。大麻所持は罪であることに変わりはないが、基準量以下だった場合、起訴が猶予されるというだけだ。それを「公に使用が認められている」と言い換えては、大変な無理が生じるし、上記WHOのくだり等、他の箇所における引用さえも説得力が薄れてしまう。このような強引なアプローチをしていては、大麻擁護論の信頼性を失わせるだけでなく、今まで示してきたレポートなども、ただの断章取義と捉えられる可能性がある。
一方で、他書と異なる点があるとすれば、それは、著者が“色”のついた大麻像ではなく、ありのままの大麻の姿を伝えようと努めていることである。
大麻擁護本は往々にして、本文中に多くの科学的・人文社会学的根拠を列挙していても、結局は、その著者が望む嗜好品としての大麻像が見え隠れする。もちろん、“嗜好品”というのは、彼らが目指す究極的な大麻のあり方かもしれない。しかし、行間にその欲望が垣間見えた時点で、大麻に抵抗感を持っている読者は心を閉ざしてしまうことだろう。
大麻擁護論者は、ゆがめられた大麻観を改めるために、大麻議論をさらに深めていきたいはずだ。その彼らが、個人的趣向を含ませて、客観性を欠いた擁護論を展開しては、結局は十把一絡げに大麻を規制する日本の現行法の姿勢と何ら変わりはない。
本書は現在の大麻問題に一石を投じようと試みてはいるものの、肯定の決め手となる議論は提示できなかった。しかし、社会の発展は何事も安易に決めつけず、常に「なぜ?」と問いかけることからはじまっていく。大学生の大麻問題が騒がれる昨今、大学教授という立場の教育者が大麻を肯定する意味では、新鮮さを感じさせる一冊である。
(文/加藤 亨延、企画・編集/須藤 輝&連結社)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20090818/202682/
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1241636175/
■日本紙書評で「強い愛国心込められて」
(写真)
http://data.orunson.kr/img/photo/0905/06/1241588139.jpg
2007年5月、図書出版・キパラン(代表=アン・ビョンフン)が発行した李榮薫(イ・ヨンフン)教授の『大韓民国の物語(大韓民国話)』を、日本の『文藝春秋』が日本語版で発行した。書名は韓国の書名と同じ『大韓民国の物語』。
『大韓民国の物語』は2006年2月に発売された『解放前後史の再認識』を、著者の李榮薫教授が「少し分かりやすく、読みやすく」ともう一度書いた本だ。最初の原稿はEBSラジオ放送の要請を受け、特別講義形態で一般人に公開されたが、一週間の講義内容を修正・補完し、三倍になる量で完成された本として発行した。
『大韓民国の物語』は、韓国近現代史を全面再解釈している。
結局歴史は解釈のみ。激動の20世紀を経た大韓民国近現代史で我々は、『民族主義』という感情に縛られた歴史だけを語り、解釈して来たのは事実。著者は我々を縛りつけた民族主義を解体して分別し、利己心を本性とする人間個体を歴史叙述の単位にしなければならないと主張する。朝鮮王朝が敗亡した原因、植民地収奪論、親日派清算問題、日本軍慰安婦問題など、現代史の重要な問題と争点なども新しい視覚で解いている。
日本の読売新聞は去る5月3日付けの文化面で、李榮薫教授の『大韓民国の物語』の書評を囲み記事で比重をかけて扱った。筆者は韓国思想研究者である小倉紀蔵氏。
小倉氏は書評の初節をこんな風に始めている。「真に勇気のある韓国人がここにいる、という感じだ」と・・・。
小倉氏は、「これまでは歴史について韓国人がどんなに声高に語っていても、つねに『民族』に遠慮している」と前提して、「韓国でニューライトの論客として有名な李榮薫教授がこの本で、『歴史の主体は民族ではなく個人であると明確に語る』」と驚いている。
また、「李教授が韓国の近現代史を、伝統文明と外来文明が衝突し接合する『文明史の大転換過程』と把(とら)え、善と悪の二項対立式の歴史観を拒絶する」と紹介した。歴史を見る目が単純でなく複合的というのだ。
実は李榮薫教授はこの本で、民族史観と民族主義を猛烈に攻撃している。しかし彼を反民族主義者と思ってはいけない。李教授は単に民族だけが歴史の唯一無二する単位であると思うのは偏狭だと言っているだけだ。小倉氏の指摘どおり、彼が『民族』を単位にした歴史の代案として提示したのは、『個人』を単位にした歴史だ。
小倉氏は書評を通じてこの本に対し、「歴史を直視できぬまま歴史から自由になれていない韓国人に、「過去の歴史の亡霊」から解放されよと発言する、強靱(きょうじん)な愛国の書」であると評価している。
過去から自由でない韓国人が、この書評に対してどの位自由であるかを知りたい。
ソース:ニューデイリー(韓国語)
http://www.newdaily.co.kr/articles/view/26056
『大韓民国の物語』 李榮薫著 永島広紀訳
民族主義からの脱却
真に勇気のある韓国人がここにいる、という感じだ。これまでは歴史について韓国人がどんなに声高に語っていても、つねに「民族」に遠慮している。「民族」をこわがっている。「民族」の代表者になってしまっている。「個人」の意見を堂々と語っていない。そんな印象を受けていたからだ。もっと自由に語ってもいいはずなのに、できなかった。
本書の著者は、韓国でニューライトの論客としてあまりにも著名な歴史家である。だが、民族主義者ではない。歴史の主体は民族ではなく個人であると明確に語る。その視点から見ると、これまでの韓国史は嘘(うそ)だらけだった。偽善の知性としての歴史学者たちが、実証を経ずにでたらめな説を述べ、歴史教科書に書き、そしてそれが韓国人の誤った集団記憶となってしまったというのだ。
韓国人は5000年前からひとつの民族でありひとつの共同体だった。日本は植民地支配を通して朝鮮人の土地・財貨・食料などを無慈悲に収奪した。解放後に親日派を粛清できなかったことが、今日の韓国の不正義の淵源(えんげん)だ。これらはすべて間違った認識だと、著者は次々に切り捨てる。すべてを根本的なひとつの要因によって説明しようとする道徳主義的な民族絶対主義から抜け出さなくては、韓国は決して先進国にはなれないという。
韓国の近現代史を、伝統文明と外来文明が衝突し接合する「文明史の大転換過程」と把(とら)え、善と悪の二項対立式の歴史観を拒絶する。歴史を見る目が単純でなく複合的なのだ。
「植民地時代に韓国は近代化し発展した」と説き韓国人の猛烈な反発と批判を受けても、実証への信頼があるから全く動じない。とはいえその主張は日本の支配の美化ではなく、日本の「右」を勇気づけるものでもない。歴史を直視できぬまま歴史から自由になれていない韓国人に、「過去の歴史の亡霊」から解放されよと発言する、強靱(きょうじん)な愛国の書なのである。永島広紀訳。
◇イ・ヨンフン=1951年生まれ。ソウル大学校経済学部教授。主な著書に『朝鮮後期社会経済史』など。
文芸春秋 1857円
評・小倉紀蔵(韓国思想研究家)
(2009年5月4日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/book/review/20090504bk06.htm
『大韓民国の物語 韓国の「国史」教科書を書き換えよ』 李 榮薫著 (文芸春秋・1950円)
●偏狭な歴史観が理解を阻む 立石 泰則 ノンフィクション作家
韓国と北朝鮮は隣国であるにもかかわらず、多くの日本人にとって「遠い国」である。たしかに昨今の韓流ブームで韓国に対する理解が進み、好感を持つ日本人が増えたとはいえ、本質的な問題解決には道はまだ険しい。
両国民の相互理解を阻んでいるもののひとつは、戦前の日本による朝鮮統治、つまり「加害者」と「被害者」という意識に囚(とら)われすぎて自然体で向き合うことが難しいことである。朝鮮の植民地化に対し多くの日本人が「負い目」を感じ、多くの韓国人は「無慈悲で暴力的な日本人」像から逃れられないでいるからだ。
それは、ある意味、両国の歴史教育の「成果」でもある。
例えば、一般の韓国人は《日本の朝鮮統治は収奪以外のなにものでもなかった》と国史の教科書で教えられ、そう信じている。また物理的な収奪以外にも《約650万名の朝鮮人を戦線へ、工場へ、炭坑へ強制連行し、賃金も与えず、奴隷のように酷使した。(中略)朝鮮の娘たちを動員し、日本軍の慰安婦とした》といった記述も、教科書にはある。
しかしそれらは、緻密(ちみつ)な実証に基づく韓国の経済史家の著者にとって執筆者が書いた「物語」にすぎず、《過去50年の間、民族主義の歴史学が、20世紀の韓国史の道筋をどれほど深刻に歪(ゆが)めてきたか》と鋭く批判する。
著者にとって20世紀の韓国史で重要なのは、日本からの独立だけでなく《文明史における一大転換》、つまり《中華文明圏から離脱し、西欧文明圏に編入された》ことである。人間の本性は「自由」であり、それを認める西欧文明圏への編入は、新しい時代の到来であった。そしてその大転換を直接強要したのが、日本(の植民地化)だったという。
だからといって、著者はいわゆる親日家ではない。むしろ徹底した日本帝国主義(植民地政策)の批判者である。彼の批判の目は、朝鮮統治における日本の「同化政策」が「自由な存在」である人間の本性を否定する点に向けられている。《自由がない者は屍(しかばね)と変わりません》という言葉に日本の朝鮮統治批判と朝鮮独立の正当性の主張が端的に表されている。
偏狭なナショナリズムに基づく歴史観が、いかに国の発展を阻害するか‐‐このことは、本書を読むと、日本も対岸の火事ですまされないことがよく分かる。
=2009/03/22付 西日本新聞朝刊=
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/book/review/20090323/20090323_0001.shtml
『大韓民国の物語・韓国の「国史」教科書を書き換えよ』
鈴木琢磨書評=今、日本にとどく 韓国保守知識人の「自国の歴史」への思い
おもしろいなあ。萎縮していた脳みそのシワがびよーんと伸びる。「大韓民国の物語」を読んでの、それが実感である。コチコチに凍っていた「韓国の歴史」がぽかぽか春の日差しに融けだしたような。初めての体験。
著者の李榮薫さんはソウル大経済学部の教授。「朝鮮後期土地所有の基本構造と農民経営」で博士号をとっている。なにやら難しそうであるけれど、その文章に触れれば、この博士が専門バカでないことはすぐわかる。
いったい、それがいかなるものかは知らないけれど、経歴には1977年から芝谷書堂で漢学5年課程を修了
とある。いいなあ。教養人である。それもとっびっきり上等の。
知的でユーモラス、わが民族を愛しながらも決して溺れず、あくまで視野は広く、自らの言葉で、やわらかく歴史を語る、その手ダレ感は司馬遼太郎さんをほうふつさせる。司馬さんの歴史エッセーにどこか通じる。実際に本を手にとって、じっくり味わっていただきたいから、引用はほんのちょっとだけ。
〈大韓民国は「歴史問題」で風邪をひいています。かからなくてもいい風邪に意味もなくかかっているのです。だから余計に体と心が痛いのかも知れません。風邪の原因は誤った歴史観です。歴史観は明るく健康なものにすれば、風邪はたちどころに治るでしょう〉
すべてがここに集約されている。博士はかなり重症で、ほおっておけば肺炎になるやもしれない自国の「歴史問題」なる風邪を退治したい、その純粋な一念で、ドクターよろしく、患者に語りかける。その風邪は、たちが悪いせいか、玄界灘をこえて日本にも広がっているらしく、このたび、翻訳というかたちでドクターが往診にきてくれたのである。まことに慶賀にたえないことである。
ついつい日本人としては遠慮がちに小声でしか言えなかった「事実」を、のびやかに堂々と開陳されてくださっているのは痛快である。たとえば、日本の植民地の「遺産」について。1960年代までは南よりも北が経済的に進んでいたといわれる。それは、彼ら平壌政府が宣伝するような社会主義の生産力のためではなく、北のエリアが植民地の物質的遺産が豊富だったから、と看破している。そして、そうした、ある意味メードイン・ジャパンの生産力への過信が金日成をして、朝鮮戦争へと突き進ませたのだ、とも論じる。
それにしても、ようやく、との感を禁じえない。これほどの実力をそなえた韓国保守知識人の思いすら、日本ではほとんど知られていなかった。読まれることはなかった。隣人理解はまだまだである。最後に永島広紀さんの翻訳文のうまさを特記しておきたい。
(すずき たくま 毎日新聞編集委員)
http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=48124&thread=10
歴史からの自由を説く韓国人による韓国論が生れた
『大韓民国の物語』 (李榮薫 著/永島広紀 訳)
鄭 大均Taikin Tei|首都大学東京教授
2009.02.20 00:00
■ 収奪論の神話性
『大韓民国の物語――韓国の「国史」教科書を書き換えよ』は少なくとも三つの理由で、三種類の日本の読者にきわめて有益である。
第一に、隣国に政治的な疑念を抱いている読者にとって。国家が半世紀以上も前の親日派を調査し、その名簿と行状を公開するといったニュースや韓国の北朝鮮に対する宥和政策のニュースに接して、解(げ)せないという感覚をもつ人々のことである。進歩派というよりは保守派の日本人に広く共有される感情や態度で、中には専門家といわれる人々も含まれるだろう。だが、ソウル大学経済学部教授の李榮薫(イ ヨンフン)氏が書いた本書を読むと、こうした疑念は、韓国人自身にも共有されていることがよく分かる。
李氏によると、韓国の政治は過去の亡霊から早く自由にならなければならないのであり、これ以上、死者が生者の足を引っぱるようなことをしてはならない。そもそも、世にいう「植民地収奪論」といったものは実証的な議論なのだろうかともいう。
生産された米のほぼ半分が日本に渡っていったのは事実です。しかしながら、米が搬出される経路は奪われていったのではなく、輸出という市場経済のルートを通じてでした。(中略)収奪と輸出はまったく異なります。収奪は朝鮮側に飢饉のほかには何も残しませんが、輸出は輸出した農民と地主に輸出にともなう所得を残します。米が輸出されたのは総督府が強制したからではなく、日本内地の米価が三〇パーセント程度高かったからです。ですから、輸出を行えば、農民と地主はより多くの所得を得ることになります。その結果、朝鮮の総所得が増え、全体的な経済が成長しました。
植民地収奪論はおおむね一九六〇年代以降、韓国の民族主義が高揚する過程で作られた神話に過ぎない。
李榮薫氏は一九五一年生の韓国経済史の専門家。古い土地台帳を資料に実証的な歴史研究をするとともに、今日のニューライト運動の中心にいる人物で、北朝鮮に宥和的な左派民族主義者にも自己陶酔的な右派民族主義者にも批判的である。
本書に接した読者は、韓国人がみな北の王朝に宥和的であるとか韓国人が日本を怨嗟(えんさ)の目で眺めているという印象が、実は自身の韓国や韓国人に対する先入観やステレオタイプの思考の産物であり、いま韓国は、北朝鮮との関係においても、日本との関係においても、重要な岐路にあるのだということに気がつくはずである。
■ ヨン様派やカン様派への贈りもの
第二に、本書は隣国に比較的最近、親近感を抱きはじめた読者にとっても有益である。ここには若い学生もいれば、熟年の女性もいるだろうし、筆者が「ヨン様派」や「カン様派」と呼ぶ関心層もいるであろう。
ヨン様派が「冬ソナ」や「チャングム」といった韓国のポップカルチャーとの出会いを通して隣国に関心を寄せはじめた読者であるとするなら、カン様派とは、例の姜尚中東大教授の著書やテレビでの尊顔に接して隣国に関心を寄せはじめた読者のことで、前者がリアリズム志向なら、後者はバーチャル志向という重要な違いはあるが、いずれも日本人の劣化過程で生れた現象であり、隣国になにかしらの幻想を抱きやすいという共通性もある。
こういう読者に李氏の本が益するところは大であろう。といっても、これは大部の本でもなければ、生硬な本でもない。二〇〇六年六月、李榮薫氏は韓国のEBSラジオに出演、『解放前後史の再認識』(本の世界社刊)という本の解説番組を一週間にわたって担当した。
本書はそのときの放送原稿に加筆・修正してできあがったもので、話し言葉的に記されていると同時に、自伝的な語りがあり、流行歌や文学作品の一節が紹介されていたりする。
筆者に印象的だったのは、詩人・徐廷柱の「親父はだった」から始まる「自画像」(一九三七年)という詩に触れたくだりで、次のようにいう。
この偉大なる抒情詩人は父親がの出身でした。詩人はの身分を恥じました。そこで「世の中は行けども行けども恥ばかりなり」と詠いました。ところで李朝時代におけるの売買文書を見ると「寿介(スゲ)」というちょっと粋な名前がしばしば目につきますが、実際には「犬っころ(スケ)」という語の当て字でした。詩人は自分をその犬っころに喩えています。「舌が垂れ下がった病犬のように息せき切りながら我は来たり」と。私はいまだかつて、このように自身の卑しい身分をある時代の痛みにまで昇華させて詠う高潔なる精神に触れたことはありません。この詩人はしばしば親日派と罵られていますが、私はこの詩の一篇だけでも彼を愛してやみません。
最後に本書は、韓国にはとりたてて関心を寄せるわけではないが、自分は欧米やその他の地域の政治や歴史や文化などについてはよく知っていると自負するインテリ読者にもお薦めの一冊である。
そんなインテリが、たとえばアジアや欧米のどこかの国で、韓国のインテリに会ったとする。そんなとき韓国人は「植民地時代」を、善良な韓国人が無慈悲にも日本人に土地や食料や労働力を収奪される物語として語るかもしれないが、それになんと応えるのだろうか。たまには疑念を表明するものもいるのだろうが、おそらくは同調してしまうものの方がずっと多いに違いない。
それに触れた箇所があるわけではないが、そんな日本人の態度は韓国人にとってもマイナスが大きいのだということを本書は教えてくれる。それは要するに思考停止の植民地認識であり、植民地体験からなにも学んでいないに等しいというだけではなく、韓国人にとっては、死者が生き返り、再び生者の足を引っぱりはじめることを意味するからである。
■ 説得力の源泉
著者も記しているように、『大韓民国の物語――韓国の「国史」教科書を書き換えよ』と題する本書はいつの日か、体系的に書きなおされるべき韓国近現代史のための水先案内といった性格の本に過ぎない。にもかかわらず、李氏の本が他の本よりも陰翳(いんえい)に富み、奥行きがあるように見えるのはなぜか。
それは李氏が韓国の知識人たちがよくやるように、外来思想で事象や対象を眺め、当世流行の図式を描き出して満足するかわりに、対象に向き合い、モノゴトを考えているからではないのか。当世流行の韓国論の多くは、そんな意味ではバーチャルなものばかりだ。あの言語道断の北朝鮮の王朝に宥和的な議論を展開する韓国論、つまり金大中や池明観や姜萬吉や和田春樹や高崎宗司や姜尚中といった面々の議論がそれだ。だからそんな韓国論を読んでも、他人事(ひとごと)のような気がする。彼らの物語のなかに生きた自分を位置づけることができないからである。
本書の前半に記されているのが日本統治にかかわる問題であるとしたら、後半に記されているのはアメリカや北朝鮮との関係の問題で、そのいずれにおいても、李榮薫氏は自分の国がなにものであるのかを真摯(しんし)に問い続ける。自国のナショナル・アイデンティティを問う作業は、自国の歴史をどのように統合するかの問題であると同時に、他国や他文化との共有性の問題であり、だからここには日本もアメリカも北朝鮮も中国も登場するが、私が知る限り、李榮薫氏ほど自国のアイデンティティについての説明責任を明瞭に果たした韓国人はいない。
しかしこのことは李榮薫氏という人物が日本に阿諛(あゆ)迎合するような人間であることを意味しない。訳者の永島広紀氏はあとがきで次のように記している。「実証を伴わない観念的な思考を極度に排する態度を崩すことなく、それでいてかつての『日帝』の所業に対する筆致は厳しい。その意味では日本にとっては最も手強い相手の一人であるのかも知れません」。同感である。
http://hon.bunshun.jp/articles/-/299
李栄薫・ソウル大学教授:「私たちが植民地時代について知っている韓国人の集団的記憶は多くの場合、作られたもので、教育されたものだ」
「私が植民地時代のイメージを修正するようになった個人的動機は、1990年、日本の『土地調査事業共同研究』のために全国を巡回し、土地台帳など原資料を収拾したことだった。慶南・金海市地域には、大量に原資料が残っていた。それらの資料を参考を検証して、教科書とは余りにも異なる内容に驚いた。
『土地申告をやらせて、無知な農民たちの未申告地を容赦なく奪った』と教科書の記述にはあるが、実際はまるで異なり、未申告地が発生しないよう綿密な行政指導をしており、土地搾取が発生することがないよう、繰り返し、指導と啓蒙を進めていた。
農民たちも自身の土地が測量され、地籍簿に記載されたのを見て喜び、積極的に協力した。その結果、墓や雑種地を中心に0.05%程度の未申告地が残ったに過ぎない。それを知った時、私が持っていた植民地朝鮮のイメージは、架空の創作物に過ぎないものであったことを自覚した」
日韓併合の「よこせ」神話の実体
http://ameblo.jp/myaimistrue/entry-10209245860.html
【韓国】ソウル大・李教授「日本による収奪論は反日教育で作られた神話」
ソウル大学の李栄薫教授~『日帝の650万人動員説は誇大』
【韓国】「日帝、米収奪なかった」~乱闘場になった「教科書フォーラム」
話題の新刊「解放前後史の再認識」
官僚とメディア 魚住昭 著
私がまだ共同通信の記者をやめる直前の『沈黙のファイル』の取材で、同僚と一緒に太平洋戦争開戦前夜の参謀本部作戦課の内情を調べたことがある。作戦課は陸軍大学校出身の超エリート参謀二十数人からなる陸軍の中枢機関で、国防方針に基づいて作戦計画を立案し、約四百万人の軍隊を意のままに動かした。
その作戦課の元参謀たちに「勝ち目がないと分かっていながら、なぜ対米戦争を始めたのか」と聞いて回ったら、ある元参謀がこう答えた。
「あなた方は我々の戦争責任を言うけれど、新聞の責任はどうなんだ。あのとき新聞の論調は我々が弱腰になることを許さなかった。我々だって新聞にたたかれたくないから強気に出る。すると新聞はさらに強気になって戦争を煽る。その繰り返しで戦争に突き進んだんだ」
この言葉は私にとってかなり衝撃的だった。というのも、私はそれまで新聞は軍部の圧力に屈して戦争に協力させられたのだと思い込んでいたからだ。それが事実でなかったとしたら、私たちが教えられた日本のジャーナリズム史は虚構だったということになる。(P126)
~
佐々木によれば、新聞の親軍的記事はすべてが強制ないし暗黙の強制によるものではなかった。誘導の効果はいくらかあったかもしれないが、もともと親軍的な記者、軍にシンパシーを抱く記者、誘導を受け容れる素地のある記者はいくらもいた。それは軍に批判的な記者や記事が存在したことと同様にまぎれもない事実だった。
彼ら新聞記者たちは政官界の随所に濃密な人間関係を設けて食い込み、情報を物々交換することで、あるいは情報を通貨のように利用することで密着度を高めながら、実態としては情報提供者・情報幕僚として振る舞い、時としては政治ブローカーのごとき役割をも果たしていたという。
まったくその通りだったろうと私はかなりの確信を持って言うことができる。なぜかというと、戦後の記者である私自身が検察庁に「濃密な人間関係を設けて食い込み、情報を物々交換することで、あるいは情報を通貨のように利用することで密着度を高めながら、実態としては情報提供者・情報幕僚として振る舞」っていたからだ。
たしかに政官財界の腐敗を摘発する検察と、日本を破局に陥れた旧陸軍は違う。しかし、それは戦後の我々が陸軍を罪悪視しているだけであって、戦前・戦中の「親軍的な記者」たちにとって陸軍は今の地検特捜部のような「正義の味方」だったのだろう。(P127・P128)
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/08414aebd4f1e1c57273678da46d1962
身近な植物がなぜ叩かれる?~『大麻ヒステリー』
武田 邦彦著(評:加藤 亨延)
光文社新書、740円(税別)
大麻が、日本人にとって身近な植物だと聞いて、驚かれる方も多いだろう。神社の鈴縄やしめ縄は大麻から作られているし、七味唐辛子に含まれる「麻の実」は大麻の実である。この他にも蚊帳、産着、下駄の鼻緒、畳の縦糸と、我々の伝統文化と大麻との関係は、枚挙にいとまがない。
著者によれば〈大麻は、日本の風土にあっていて、農薬などが少なくて済み、成長が早く、広い用途に使うことができ、持続性社会を考えるなら最適な作物の一つ〉であった。有史以来、日本の伝統・文化と多くの接点を持ち、生活に溶け込んでいた植物にも関わらず、戦後、我々は大麻に対し一貫して否定的な印象を持ち続けてきた。本書では、このような“現代の禁忌”である大麻問題を、様々な例を挙げつつ、肯定しようと試みている。
そもそも「麻薬」と「大麻」を混同している人も多いのではないか。「麻薬」という言葉は、旧字体では「痲薬」と記し、「痲」の字は「しびれる」という意味を持つ。一方で、「大麻」の「麻」は植物の「アサ」を指す。つまり「痲」と「麻」は同じ意味ではない。1949年に、漢字が旧字体から新字体に移行され、「痲」と「麻」が同じ漢字になった結果、このような混同が起きたのだ。
言葉の問題に限らず、大麻が禁忌たる“最大の障壁”、精神的作用にも著者は言及する。精神的作用とは、多幸感や開放感と表現される。具体的には、頭がボーっとしつつも、少しの物音にもパッと反応する鋭利な感覚が混在し、箸が転んだだけで笑い出してしまうほど、感情が大袈裟になるといえば、理解できるだろうか。大麻の種類によって、これら引き起こされる作用の程度も異なるという。
大麻の主成分は、主に二種類の化学物質によって構成されている。1つは精神的作用をもたらすテトラヒドロカンナビノール(THC)。もう1つはカンナビジオール(CBD)という、THCの精神的作用を打ち消す働きをするものだ。つまり、THCとCBDの含有割合によって、精神的作用に強弱がつく。
国産は精神的作用が低いらしいが
インド大麻はTHCの割合が多く精神的作用が高いが、一方で、日本固有の大麻にはTHCが少なく(もしくは、ほとんど含まれず)、CBDが多い。よって、精神的作用が低い(もしくは、全くない)らしい。
しかし、現行の大麻取締法では、THCの有無に限らず、全ての大麻が取り締まりの対象となる。これに対し著者は、THCの含有量によって規制すべきと提案している。
それでは、精神的作用をもたらす大麻は人体に有害なのか? 著者はWHO(世界保健機構)が1970年にまとめた「健康および心理に対するアルコール、インド麻、ニコチン、痲薬摂取の結果の相対的な評価」というレポートの一部を根拠に、大麻の有害性を否定している。
〈奇形の発生、衝動的な行動、大麻を吸っているうちに吸う量が増えるというような、激しい障害や習慣性はないこと、さらには痲薬につきものの禁断症状などは認められない〉
〈大麻がきっかけになって、ヘロインなどの痲薬につながる(評者注:ハードドラッグへの入り口になる)ことはない〉
さらに、著者は科学的根拠だけでなく、現行の大麻取締法の出自を探りながら、その施行自体に疑問を呈していく。
大麻取締法のキッカケはGHQ(連合国軍総司令部)の戦後占領政策にあり、その大元は、1920年にアメリカで制定された禁酒法だという。
そもそも、禁酒法の制定の裏には、ドイツなどから新たにアメリカに渡ってきたカソリック系住民に対する、プロテスタント系住民の感情的な反発があった。また、第一次大戦による対独感情の悪化も影響していた。
結局、禁酒法は13年後の1933年に廃止されることになるのだが、今度は酒の販売や製造を取り締まっていた捜査員の再就職問題が浮上してきた。同法の施行下では、大規模な酒店から小さな酒屋まで監視の目を光らせるため、多くの人員を要していたからである。
その頃になると、カソリックに代わり、メキシコなどから多くのヒスパニック系移民がアメリカに渡ってきた。白人にはもともと大麻を吸う習慣はなかったが、彼らヒスパニック系移民は、ニコチン・タバコより習慣性がなく価格も低かった大麻を、安タバコとして吸っていた。もともと、彼らが街に進出してくることを快く思わない白人の感情に、禁酒法廃止による捜査員の失業対策が加わり、大麻課税法が成立していくのである。
大麻課税法においては、建前上は法外な税金を支払えば大麻を扱うことが可能となっていたが、実際には「大麻に課税したことを示す証明書」は一度も発行されていない。つまり、実質、大麻課税法は“大麻禁止法”の意味合いを持っていた。
さらに当時、大麻は重要な繊維資源だったが、デュポンの研究員だったカロザースがナイロンを発明し、石油化学産業が勃興する。彼ら石油化学産業関係者にとっても、大麻課税法の成立を後押しすることは、繊維産業のライバルを蹴落とす意味でも好都合だったのだ。
これら、さまざまな思惑が入り混じった大麻課税法制定から10年の時を経て、第二次大戦の戦勝国となったアメリカが、GHQの中心国として日本に上陸する。日本の大麻の精神的作用が低いことは、既に説明した。それにも関わらず、アメリカ本国の大麻課税法の影響を受け、新たな規制が日本国内にも作られていくことになる。
以上のように、著者は大麻擁護の論陣を張っていくが、こうした主張は本書に限ったことではない。新書でいえば『大麻入門』のように、大麻解禁を訴える他の本の多くも、同じような説明を展開している。大麻の神道における位置づけにはじまり、大麻由来のプラスチックなど産業用大麻の重要性を挙げながら、大麻を肯定していく。しかし精査してみると、論の運び方が無理やりだったり記述に誤りがある場合も少なくない。残念ながら、本書も前轍を踏んでしまっている。
強引な大麻擁護論は逆効果
例えば著者は、〈1961年の国際条約(麻薬単一条約)で、マリファナ(評者注:大麻)をアヘンやヘロインなど本当の痲薬と同じ取り扱いにしました〉と述べているにも関わらず、そのすぐ後の文章で、〈オランダ、デンマーク、イタリアでは(評者注:大麻が)公に使用が認められています〉と言い切っている。これは完全な誤りだ。
そもそも、オランダは麻薬単一条約のメンバーである。ゆえに大麻を完全に合法化することはできない。大麻所持は罪であることに変わりはないが、基準量以下だった場合、起訴が猶予されるというだけだ。それを「公に使用が認められている」と言い換えては、大変な無理が生じるし、上記WHOのくだり等、他の箇所における引用さえも説得力が薄れてしまう。このような強引なアプローチをしていては、大麻擁護論の信頼性を失わせるだけでなく、今まで示してきたレポートなども、ただの断章取義と捉えられる可能性がある。
一方で、他書と異なる点があるとすれば、それは、著者が“色”のついた大麻像ではなく、ありのままの大麻の姿を伝えようと努めていることである。
大麻擁護本は往々にして、本文中に多くの科学的・人文社会学的根拠を列挙していても、結局は、その著者が望む嗜好品としての大麻像が見え隠れする。もちろん、“嗜好品”というのは、彼らが目指す究極的な大麻のあり方かもしれない。しかし、行間にその欲望が垣間見えた時点で、大麻に抵抗感を持っている読者は心を閉ざしてしまうことだろう。
大麻擁護論者は、ゆがめられた大麻観を改めるために、大麻議論をさらに深めていきたいはずだ。その彼らが、個人的趣向を含ませて、客観性を欠いた擁護論を展開しては、結局は十把一絡げに大麻を規制する日本の現行法の姿勢と何ら変わりはない。
本書は現在の大麻問題に一石を投じようと試みてはいるものの、肯定の決め手となる議論は提示できなかった。しかし、社会の発展は何事も安易に決めつけず、常に「なぜ?」と問いかけることからはじまっていく。大学生の大麻問題が騒がれる昨今、大学教授という立場の教育者が大麻を肯定する意味では、新鮮さを感じさせる一冊である。
(文/加藤 亨延、企画・編集/須藤 輝&連結社)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20090818/202682/