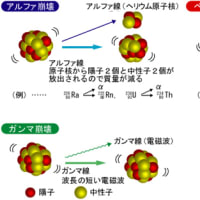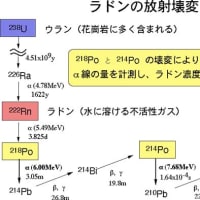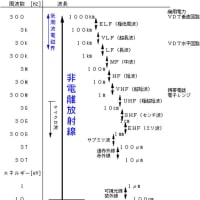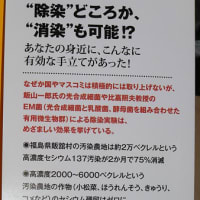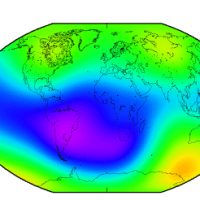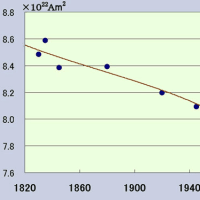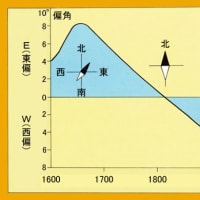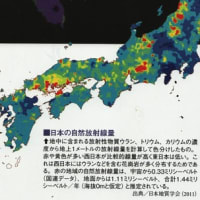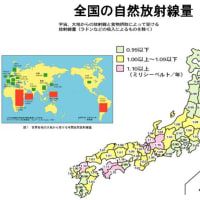既報にて、今までの再生可能なエネルギーに係る投稿を整理しました。
本件、ブログテーマとは直接関係しないかもしれませんが、別紙の観点に着目して新規に提案されている技術を都度、調べています。
今回は、軽薄短小な技術を象徴していると想われた圧電体を用いて環境に発生している無尽蔵な振動を大規模な電気に変換する「振動発電」に係る記載を調べました。
ウィキペディア「振動発電」 <<本文を読む>>
(一部抽出しました。)
「概要
振動による圧力を圧電素子によって電力に変換する。発電能力が低いため実用性のある装置の開発には至っておらず概ね研究段階である。また発電設備の製造に必要なエネルギーを、その後の発電で取り戻せるかどうかも不明である。
具体例
リモコン・・・ボタンを押す振動を電力に変換する。・・・
雨力発電・・・傘に圧電素子の一種であるポリフッ化ビニリデン(PVDF)膜を組み込み雨が当たる振動を電力に変換し、LEDを点灯させる。電池不要で夜間の歩行者の安全性向上に繋がるものと期待されている。
発電床・・・圧電素子を敷き詰めた板状の振動発電装置。人力で駆動するものを人通りの多い場所に設置し、東京駅等で実験が行われた。 2007年に首都高速五色桜大橋を通過する自動車の振動によりイルミネーションの電力の一部を発電する実験が行われた。・・・」
*圧電素子
<圧電素子の例>
工業的には、PZTと呼ばれるPb(鉛)、Zr(シルコニウム)チタニウム(Ti)からなる金属からなる複合の酸化物で構成されているようです。素子の作動原理も引用しました。

(google画像検索から引用) (google画像検索から引用)
経済広報センター『経済広報』(2010年3月号)
「実用化進む 振動が生み出すエネルギー」
「人が歩く際に生じる振動や自動車、自転車などの振動エネルギーを利用し発電する技術の開発と実用化に様々な企業が乗り出している。
首都高速道路は、2007年12月から中央環状線の荒川に架かる五色桜大橋のイルミネーションの電力の一部を、首都高を走る自動車の振動エネルギーで賄っている。美しいイルミネーションが、自動車の振動から生まれた。
また、東日本旅客鉄道研究開発センターフロンティアサービス研究所は、「発電床」の開発をジェイアール東日本コンサルタンツなどと共同で進めている。JR東京駅の改札や階段などの床に「発電床」を設置し、乗客がそこを通過する際に生まれる力を自動改札や電光表示器などの電力の一部に利用する実証実験を行っている。
NECエレクトロニクスと音力発電は、家電用リモコンのボタンを指で押すことで発電する「振動力発電」技術と、NECエレクトロニクスが独自に開発した電源制御技術の組み合わせにより、電池が不要なリモコンを試作した。2011年までに実用化を図るという。
オムロンは2008年11月に、日常的に存在する環境振動で発電する「環境振動発電デバイス」の試作に成功した。既に研究されていた振動発電デバイスは、高い振動を必要とするが、同社の精密メカ技術と高絶縁耐圧化技術を応用し、微小な振動からエネルギーを得ることで、小型化、耐久性の向上、実用レベルの発電性能を確保している。2011年の実用化に向け、さらなる取り組みを続けている。」
⇒現状の発電単価がどのくらいになっているか?また、その耐久性がどのくらいか?今後明らかになると思われます。
無尽蔵な振動を経済的に適材適所に利用することを期待します。