魂魄の宰相 第六巻
※ 以下、校正はして居無いので、誤字脱字、事実関係に誤りを見付けたらご一報下さい。
前書き
読者は、改革が如何に強く風当たりを受けるかと言うことを、この一篇で如実に悟らされるであろう。尤も道徳や倫理などは人の目先の欲望の前では無力であることは、改革を錦の御旗として掲げ、その実、結果として、何一つ既得権を排除出来無かったばかりか、政府の無駄を社会の格差に摩り替えた何処かの国の現実で思い知らされていることではあるのだが。
いずれにせよ、『周知のこと』から如何に自分の考えを纏め上げていくかと言うことが、書を読む姿勢といえる。一人一人が、「人間社会は如何在るべきか」ということを考え、最善の方向に進める努力無しに、わが国の此の行き詰った状況を変えることが出来ないのは自明である。倫理や道徳は無力だが、然し、これを無視して人間社会が成り立たないことも事実である。
我々は、生れ落ちたと同時に国を決められて仕舞う。自分の意思に拘らず。国籍を変えるには必死の努力もいるだろう。為政者が我々の生き様の決定権を持っているということは現実であり、それ故、其の選択は熟慮の上で為されることを願っています。
平成十八年七月某日 〇〇的窮浪人 於草庵
第六章 一人前の男の真骨頂は、容貌で決まるものでは無い
一、本音は改めない
王安石は心広く冷静無私で、真に道徳的で、だから損得に拘らず、如何でもいい習慣に左右される人では無く、彼は醜男であっても少しも臆すとこは無なかった。 魏泰《東軒筆録》巻十二では: 嘗て、呂恵卿は王荊公のことを語って曰: 「公の顔はどす黒かったので、薬草を用いて荒い流した方が良い」 荊公は曰: 「私の顔が黒いのは、後天的なもので無い」 呂曰: 「たとえそうであっても、薬草で取り除くことは出来よう」 応えて、荊公曰: 「生れつきの物であるので、如何して薬草で取り除くことが出来よう!」
呂恵卿と曾布は仲が悪くて、曾布は魏泰の姉婿であったことから魏泰は呂恵卿に対してあらん限りの反発をしていたので、上に掲げた記述は呂恵卿を陥れる意図があってのことかも知れず、荊公へのご機嫌取りを誹ったこのことが真実であったならば、彼の二人が付き合い始めた頃のことと考えられ、当時、呂恵卿は未だ少年であったが故に非常に容貌に関心を持つ年頃だったので、恐らく王安石の顔色がどす黒過ぎたので、王安石の顔には黒班があるからだと考えた呂恵卿が薬草を使っての美顔を奨めたのだが、黒班では無く元々の顔黒がそんなことでは直る訳が無いと王安石が言ったにも拘らず、呂恵卿が薬草で王安石の美顔を成せるとしつこく言い張るので、そのことで呂恵卿を笑い者にしようと、孔子の「桓魋が如何しようとも、天性の有徳は、私に与えられたものである」との言葉を引用して、「薬草を用いたとしても、生まれつきの顔黒が直るべくも無い」と茶化したのだ。
この言葉は冗談めいてはいたが、王安石が「色が黒いことを徳である」と言い換えたその意味は、彼が色黒で良いと言う事では無く、色黒は両親から頂いたことで、天性のもので、もしも白粉で顔を白くしたならば、生まれつきのことを汚すことになるばかりか、見掛けで飾り繕うことは、彼の性根にあわ無かったのだ。
信条を変える事無く生涯通した王安石の一徹さは、読書にも顕れ、屡耳にしたことではあるが、寝食をも忘れ何日もの徹夜続きで読書に熱中し、更には度支補佐役人の任時に全く数ヶ月もの間入浴し無かったので、十日間に一回しか入浴しなかったので、身体を洗うことを同僚数人と約束させられ、更に、同僚は王安石の衣服がぼろぼろであったので、まっさらな衣服を用意してあげ、王安石が風呂から出てくるのを、息を殺して待ち構え、王安石が風呂から上がると、新しい衣服を着せたのだが、このことは王安石の性格が些事に拘らず、又、如何に読書に熱中していたかということを如実に顕すものであったのだ。
王安石には宰相と成ってもその無頓着さは依然として変わることが無かったという逸話があった: 荊公と禹玉が煕寧年間同時期相府にいて、朝廷の日中仕事をしていた時、突然荊公の短着の上に虱がいたのだが、公はそんなこととは露知らずにいたことを禹玉は笑うことも出来ずに知らない振りをしていたのだが、朝廷から退却後、そのことを指差して虱を払いのけるように公に知らせた禹玉曰: 「未だほっとしてはいけ無い、虱を大切に身に着けていては」 公曰: 「何のことか?」 禹玉は笑って曰: 「屡虱が着いていたのを私は見たよ」 荊公も顔を綻ばし笑い飛ばしたのだ。
王安石は相に成った後にも恐らく、依然として入浴はすることは無く、絶えず身体に虱が涌いていたと想像出来、皇帝の御前に居並ぶのは大人物ばかりであるにも拘らず、図らずも皇帝を面前にして醜態を晒したのだが、彼らは王安石のお惚けを面白がったが、皆この事を大げさに騒ぎ立てずにいてくれたのだが、王安石の小さい礼節に拘泥しない風格と器の大きさを稀有な眼で見るしか無かったのだ。
王安石の偉そうに見え無い容貌、衛生を重んじ無く清潔だとは言い難いなど、見方に拠っては、全てが欠点だと言えたので、この面では呂恵卿が、王安石がこのように生き様を改め無いことを非難しているのに分があり、単純に頑固な気性と片付けられないことであると考えるのが普通であろう。
王安石は、人の文章には其の人の人格が顕れるとの孔子の考えに同調し、其の考えは文学の面にも反映するとし、文学と道学とはどちらも同様に大切なものだとし、其の結びつきを強めるべきであるということを強く訴えるようになった。然し、個人の教養を高める面では、その人の人格が深く関わり、上品で礼儀正しいことを美と認めたのだが、言うは易いが行うは難く、常人は人格を疎かにして文ばかり飾り勝ちで、本当は人格を磨くことが先決なのに、文を良く見せかけることに固執した結果、人格形成を疎かにした美文が罷り通り、空々しい偽りが見抜かれて仕舞うのだが、人格と文を同時に磨いていくということは並大抵のことでは無く、「右往左往する無かれ」という意を汲んで、先ずは人格形成に重心を置く事で決着を就けたのだ。
「誠実な人は永遠に変わることが無い森羅万象の本質である天道に従う」と、儒家は「誠実」ということに特に拘り、誠実であれば事物の本質を見抜くことが出来るので、少し位のことで動揺することも無いとしたのだ。これを受けて、王安石は自分の本分を守る為には常日頃からの地道の努力が必要であるのであって、「古来より民衆は誠実を守るろうとして来た」のであり、このことを自明のこととし、自ら守り通すべきことなのに、如何して相手に誠実であることを望むのか? きちっと入浴し清潔を保つようにと生活様式を改めることは、王安石にとって容易く出来ることでは無かった。このことは本質的に誠実とは関係無いことであるのだが、喩として彼の生き様を顕し、同時に、道徳的なことや教養の面でも彼が信条を変えない誠実さの表れでもあったと言えなくも無い。
王安石は、誠実さを求めることに対して、君子と小人とでは基準が違うとした: 君子、小人の置かれた立場を考えると、小人は野放図で道理が通ら無い前言は後で翻すことは出来無くなって仕舞いがちであり、言葉に信頼性と道理があって、言葉に責任を持っているのが君子であるとした。
皆にとって君子と小人見分けるのは難しいことではあるが、王安石は君子か小人かを選別するのに義と利で判定する古い基準を適用する手法は最早陳腐化して仕舞い、その基準で選別しようとしても、君子と小人とを確実に選別していくことは難しく、自身を基準にすることにも問題があり、全く利己的な私利を最も大切に考えるのが小人であることに間違い無いが、君子は利を重いとすれば利に振り回されるとして、利を言うべきで無いとする事が上辺だけを飾る理屈になり兼ねず、自分の利を図るので無く国の為に家の為になろうということに利を求める者もいるので、そうであれば広い意味では全く矛盾無く無私な君子の義利を果たしていると言えるので、其の者自身も境界の限界を何処に置いて良いか判然とせず、無論、小人の王安石も自身の基準で判別することを戸惑って仕舞うのは当然で、更には、恣意的に君子か小人かを分別することも出来るので、彼に信頼を置けるか、或いは野放図で出鱈目な人物か、はたまた、心に表裏の在る無しの判断をし、更に、言行一致言行不一致か、前後で言論を翻し辻褄があわ無いかをも観ることによって、見分けが出来るのではないのか。
王安石は守旧派の力を見極める為に彼らの本質をどう見るかということが分からないでいたが、彼の掲げた基準を適用して守旧派を値踏みしてみると、圧倒的多数が小人と区分け出来、守旧派の指導的人物の司馬光とても、小人共の上に担がれて伝統の道徳の手本として品行方正な人だと崇められているということは、疑いも無く小人の部類に入れることが出来たのだ。
司馬光《致三省咨目》の中で免役法を批判し、「貧民の防御の術を無くし、安心して生活が出来無くして仕舞った」という一節がある。 然も「公家も人民の力を得られず」とし、其の上更に「上級層には十分便を気遣い、下層階級の者達は愁え苦しんでいる」と、まるで彼は貧民の立場の上に立って話をして、国家と全体の立場を考慮した問題提起だとし、免役法が貧しい庶民の暮らしに過重な負担をかけ、国家利益をも損ない兼ねないと愁え、一握りの金持ちばかりに美味い汁を飲ませるようなもので、人手が欲しい時には人は急に集められるものでは無いのにと非難し、司馬光が身を翻して、自分の一貫した立場をさっさと捨てて、下層部の人民の代表になったかのような言動を吐いたことには、矛盾は無いのか? 実はこのようなこととは全く逆な立場を露呈した事実として、司馬光は元祐元年の正月の初三日に真っ先に提出した《乞罷免役銭依旧差役札子》の中で再度尻尾を出していた: 往日の労役の時には、上層の家は一応労役に応じる振りはしていたが、満期になった後の数年は軍の代わりに家産を治めることで労役に出ないように画策したのだ; 労役に出るか出無いかは金の在る無し次第なので、往時に比べて現状は毎年お金を出す額も次第に多くなり、弊害も大きくなって来たのだ。
この時、司馬光は迂闊にも免役に拠って齎される上層部への危害について大いに談じたのであり、この事実に拠って彼は本心を露呈して仕舞ったのだ: 前言から何日も経ってないにも拘らず上層部の利益を損なうことは出来ないので、十七日に至って前言を翻す書簡を子の刻に発表したのにも拘らず、更に其の後日の彼の更なる糾弾が「彼の免役法は下層部に金の工面で苦労させ、上層部に有利な便を齎した」と言う矛盾したものとなり、数日前に行った「其の糾弾の直前の言」と全く矛盾する発言を平然と為した態度は明らかに「野放図で出鱈目で筋道が無い」のであり、発言の度に前言と矛盾する言動を為したことは、如何にも小人の為せる業として認められ、司馬光の人格が疑られる所業であったと言わざるを得無い。
王安石は、君子が「何かを身に付けることに依って志の助けとなる」と言うものだということは揺ぎ無い事実であり、「財産や地位に惑わされなければ、貧賎にあっても確固としていられ、権威や武力でも屈服させ得無いのだ」と言っていたのだ。彼は自分の生き様は雅にこの精神の描写と思っている。
王安石の「内心を重厚に外面に隙を創るという思想」に未だ道家の匂いが残っていたのは、《庄子・徳充》などの編中では、「上辺は如何ってことは無いが内面が輝くに至った人や聖人と言われる人は其の多くが全て神のお陰を蒙っており」と記していることからしても、王安石は庄子の書を熟知しており、これに対して恐らく熱心に熟読していたと見て取れ、彼は上辺が醜くてつたないことを気にも掛けず、内在する道徳的な精神だけを強調する態度からして、庄子の影響を受けては無いとは言い切れ無いのであった。
王安石が重視するのは己の本領であり、更に仏教からも影響を受けたと雖も『性』あってこその仏陀だと思っていたのだが、各宗派が特に『性』というものを重視するのは其の殆どが禅宗からの影響であったが、本領が「元々『性』に邪気の無い仏陀から」としている為、禅宗が「本領衲僧」をすることを強調しているので、修行する必要が無くて、彫り刻む必要は無くて、誰(で)もが仏陀性を元来備えているということを、必ず常に肝に銘じ守らなければならないのに、禅宗の本領を重視することを見失い、そこで儒家の強調する伝統に比べて、更に「深い思想に内包される豊かさを守る必要は無い」とすこし迷ったが、道家の外見の重厚さに比べて内面が軽くなっていたのを考えると、精神が形に拘るので無く、更に具体的な内容があることを重視するとの考えに至ったのだ。
二、一生慎ましい
王安石は自分を飾る事無く、教養を身に付ける為に弛まず研鑽をし、衣食に拘らず、禁欲を堅持して質素な生活を維持し続けた。
父が亡くなったのが余りに早かったので、王安石の若い頃の生活は貧困を極めたが、二人の兄の力だけでは生計を立てることが出来無かったので、一家の生計の重圧は主に彼の肩の上に架かっていた。そこで彼の前半生は、全て家族を養うことのみに費やされることになり、下層部の中央役人の俸禄が余りに薄く、尚且つ、京城の物価も非常に高かったので、一家数十人を養っていくことが出来無かった為に、長い間地方で勤めることを余儀なくされていたのだ。
王安石の天性は、親しきものに孝を尽くすので、年を取った母に対して極めて親孝行をして、兄弟姉妹への慈しみも非常に強く、守旧派などの反対派でさえ感心したほどであった。言伝えに依ると彼は俸禄を受け取ると、其の儘家計に入れて仕舞うので、必要な額を兄弟達が貰うことにしており、例え彼らが全部使い果たしても、全く騒がず黙っていたのだ。王安石はまた非常に清廉潔白で、一文たりとも妄りに使うことを惜しむ性格だった。このような情況下では、彼は無論贅を極める生活などする筈が無く、ごく慎ましい暮らしをしていたのだ。
王安石の慎ましさ決して人目を気に掛けてのものでは無く、全く内心から発すものであった。彼には心ならずも非常に多くの欲求があったが、ただ長期に亘って教養を摘んでいたことに拠って無理やり表に出さないように押さえ込むことが出来、ぎりぎり欲が出無い限界に踏み止まったのだ。もし信念を持って無かったならば、このような生き様を万事について生涯続けることは無理なことだ。彼が中年になると、兄弟は次々と中科挙の最終合格者となり、其の上、朝廷に召される者も出て、皆が生計を立てる能力を身に付けるようになり、何人かの妹もすべて嫁に行って、彼の負担は過去のように重いものでは無くなって、彼の職務からの収入も次第に高額になって来たので、十分余裕を持って生計を立てられるようになったのだが、彼は依然として節約する習慣を改め無いで、木綿の着物を着て、菜食で、暮らし振りは万事に控えめであったのだ。特に彼が相になった後には、紛い無く最高権力者の重臣となったので、他に比べるものが無いほどの高貴で権勢を強く持ったのだが、贅を尽くして当然であったにも拘らず、彼の暮らし振りは依然として元の儘であった。彼が執政に任じた後に、のろ鹿の心臓の肉が好きだと言ったのを後で夫人が耳にして、如何してこのようなことを言ったのかと訝ったのは、王安石が何でも良く食べ生涯一度も食べ物の好き嫌いなど言ったことが無いことを彼女が知っていた為で、どのように調理すれば、のろ鹿の心臓の肉を美味しく食べるのかと言うことを知る為に、彼に何処にでも付いて歩くお付の者達に、のろ鹿の心臓の肉の彼の好きな食べ方を聞いてみると、毎回の食事で彼は野菜や他の料理には手を付けず、のろ鹿の心臓肉のみ余すところ無く食べたと聞くに及んで空かさず夫人は、のろ鹿の心臓肉は食卓のどの場所に置かれていたかと訊くに及び、王安石の直前に置かれていたことを知り、得心を得たのだ。詰まり、矢張り、王安石には食べ物の嗜好などは無く、食卓で自分の真近にあるものだけを食べる癖があっただけだったのだ。事実、婦人が野菜を直前に置くと、王安石はのろ鹿の心臓肉には目もくれずに、野菜だけをがつがつと食べ始めたのであった。
王安石は宰相として十年近く勤めたにも拘らず、財を貯めることは無かった。定年退職後は、彼は紅寧府城東門外の蒋山の粗中心の白塘と言う地名に居を構えたのであるが、風雨を凌ぐだけというほど非常に粗末で、驚くことには塀さえ無く、全く長年の宰相をした人の住む家のようでは無く、その棲家の近辺には人家も見当たらず、実は荒れ野原に家があったのだ。然し、王安石は非常に風情を重んじる人だったので、彼は多くの花木を栽培し、更に用水路を開けて放水して、窪地を造って、池に変え、大して費用も掛けずに、荒地のあばら家を自然の儘の趣のある美しい田園の佇まいに造り替えて仕舞ったのだ。彼が新居を 「半山園」と呼んだのは、此処が丁度蒋山の東の城門までの道程の真ん中にあったからであった。
邵伯温が「洛河の中の名教(名を惜しむ)を崇め尊ぶ習慣は、公家と雖も敢えて家勢を増すことを潔いとせず、貧富に拠って人の価値を諮らず、財貨の利を惜しむこと無い」と熱く語っている。然し、このように名教を崇めて、仁義道徳ばかり言うのは口ばかりで、実際には、公家や富豪は物欲や利を求め、錦で着飾り玉食をし、贅を尽くした豪邸に住み、広大で奥行きの深い静かな花園を庭園として購入したのだ。木綿の着物を纏って一杯の粥汁を啜る邵雍さえ、大勢の高官高位の人の助けに依って「窓からは瀍河の渓流が響き、縁台からは鮮明に彼の嵩山を望む」といった「ゆったりした住まい」を提供されたのだ。双方を比べてみると、王安石の生活は確かにとても貧乏臭かったので、蘇軾が「野人」と呼んだのも頷ける。
厳祐七年(1084)春、重篤な病気になった後の王安石は郷里と近くの小さい数(何)百畝の田畑も面倒見切れず、気前良く寺院に寄付して、自分の住む城内に別に小さい敷地を借りて居住することになったので、彼は一介の庶民層となったのだ。
王安石の定年退職後は、生活は更に簡素になり、彼は何時も腹が空いたときに食べようと袋に餅の十個も入れて、驢馬に乗って外に出かけ、終日松の木の下にある石に座っていたり、或いは田野の農家で休んでいたりしたのだが、偶には田野の農民が食事を献上することに出会っても、遠慮せずに有難く好意を受けたのだ。最初は神宗皇帝に頂いた御馬に乗って出かけていのだが、其の馬が死んで仕舞うと、彼は驢馬に乗って出かけるようになったのだ。ある人が彼を心配して、彼に人が担ぐ籠に乗るように奨めたのだが、彼は厳しい表情で曰: 「古い時代の高爵や貴族達ならいざ知らず、人は鳥獣に代わるものではない。 彼が籠に乗りたがらなかったのは、単に節約の為だけで無く、更に重要なのは人の尊厳を守ることで、人は動物では無いとの考えのもとに、人に自分を担がせて歩かせることが出来無かったのだ。
王安石の慎ましさは当時有名である上に、神宗皇帝は彼の家が貧しいことを知っていたので、彼が定年退職した後も何度も人を遣わし、お金を贈る手筈をしていたのだが、彼は皇帝と両親の為に功徳を修めようと人を介して全てを寺院に贈呈したのだ。このような彼の品格ある生活態度は、彼の若い頃の貧しかったことと関係があったのだが、更に大きく関係したのは彼が積み上げた教養だ。このような品格の形成は仏教と関係があると言うことが出来、儒家も食事は菜食と飲用水だけと言うけれども、その中には享楽を認めるところもあり、孔子も決して闇雲に慎ましさを求めることは無く、恵まれた環境のときは出来る範囲で美味いものも食べるほうが良いのだとし、細切り肉を厭わないことは宜しいことでは無いとしたのだが、仏教は最低限でも生活出来れば多くを望無いことを良とし、最低限の簡素な生活を維持するように奨めていたのだ。仏教は食事を 「空腹を満たす瘡」と教え、食事をする目的は楽しみの為では無くて、ただ生命を維持するだけのもので、肉体の存在と比べて解脱の自覚を持つことこそ大切なことで、極端を極めれば、解脱との交換の為には肉体をも提供して命を捧げることも厭わないとしたのだ。禅宗の第一世代の祖師の偉大なる迦葉は行脚僧の第一と称されて、行脚僧の行は、若い頃の釈迦牟尼の成道の修行方式を真似た修行で、苦行を積むことで知られており、後代の禅宗は粗この伝統を受け継いで、貪り求め無い生活を享受して、常に山林に居住して、都会での生活を避けていたのだ。
王安石の生活の方法は確かに禅宗のものと似ていて、江寧で喪に服した時期には、彼は 「まるで行脚僧のような生活だ」 と噂され、多くの人は彼が余りに忠実に苦行を積んでいると思った程だ。彼の晩年の生活は全く行脚僧と寸分の違いも認められず、ただ僧衣を着て無いだけの違いであった。
三、天性は誠実で率直だ
王安石の気性は誠実で率直であり、一生改めることは無かった。彼は完成された政治家だが、気性はさっぱりしていて、人には誠実に接し、強引に纏めたり、陰で画策したりと、陰謀詭計をもてあそぶことは無かったのであり、古今の政治家の中にあって、全く珍しい人であった。
王安石の若い頃は、中央政府の要職を求めること無く地方官になることを強く希望したのは、勿論様々な要因あってのことだったのだが、最も主要な要因は一家を支えるのに都合良かった為で、宰臣の文彦博はこのことに納得出来ずに「殿中補佐官の王安石は、未だ古い制度であった科挙の最終合格者として第四位で科挙試験に合格して、官職に就くことを求めた。安石は如何って言うことの無い職ばかりを歴任されたが決して文句を言うことは無く、朝廷も特別な計らいをしようと令召を試みたのだが、それを辞したのは家が貧しかったからである。しかも文官の職、文人の職に安住することを安石は堅持しようとしたのだ」と首を傾げた。文彦博は、安石が「家が貧しいことを何時も口実にするだけである」と言ったのだが、「本当は深謀深慮があって控えめにしている」と踏んで、彼は王安石のような人物を推薦することで朝廷内の互いに競い争う風を抑えようと考えたのだ。若し、王安石が時代の状況を理解し、安逸な暮らしを捨て敢えて逆境に立ち向かうような「話の分かる御仁」であったならば、これを良い機会として自分は欲が無く謙虚であることをそれと無く宣伝したか、或いは文彦博に対し彼の知遇を受けた恩に感謝する配慮をし、この元老の重臣と親密な関係を造る為に、人知れず接近しただろうに。然し、王安石は要領良く立ち振る舞う人では無く、上書してくれたことを恩に感じることも無く、まだ文彦博が実相を仔細に調べて無いことを責めて、彼は《乞免就試状》中で指摘した: 臣の老母が年老いているのを心配し、万が一のときも臣は葬式すら出せず、弟や妹の婚姻のことや、家が貧しく食い扶持も沢山で、都で暮らすなど出来ようが無い。今自身で述べたことから分かるように、敢えて試す勇気も出無い。……臣は分に適わず、又、冷静に考えて臣自身も遠慮する。令臣には弔事や慶事も無いが扶養に追われ、辞退することに躊躇することも無く、冷静に断るのだ。現時点では家を遣り繰りして如何稼ぐかで精一杯で、辞退することしか余地は無く、本当は、辞退は真意で無いのだ。
王安石はどうしても本当の話を言い出さなければならなくて、自分の「本心は所得を只増やしたいだけだと指摘して、 政権にある大臣の情けを受け取ら無かったことは勇気のいることだとした。彼は利害を省みず、真実に拘った彼の率直で誠意がある行いは常人が真似出来るものでは無かった。彼は詩《舒州被召試不赴偶書》を書いていた: 的外れなことをしても目的は達せず、虚名を笑い自己嫌悪に落ちる。膏の土壌が余りにはっきりと匂いを出している中で、ただ蚯蚓だけが清廉で在り得るか。
この詩の中で、王安石は自笑し自己嫌悪に落ち、事実も分かって無い政務担当者が為そうとしていることと王安石の目的が一致して無かったので人知れず自嘲をしたのだ。王安石は確かに大げさの所作で人に接するで 、人に由っては気分を悪くすることがあったのだが、多くの人の称賛と支持をも勝ち取ったのだ。
王安石は丞相と成った後も、変わること無く誠実で率直な風格を崩さ無かった。《邵氏聞見録》を範とした銭景諶の《答兗守趙度支書》に拠れば、銭景諶は王安石と夏真っ盛りの時に私邸で面会したことがあって、王安石と僧の智縁は床に横になっていたが、身を肌蹴て安石の旁にいた安石の最も親しい一人である智縁は銭景諶にも帽子と衣服を脱いで談じるように促した。銭景は王安石の門下生だとも言える人で、王安石が主なる試験管であった時に彼を合格させ、更に、それから彼を抜擢し推薦したので、安石に対しては知遇を受けた恩があったので、銭景諶が旧習に捉われることなぞ思いも付かず安心して心を許したのであったが、銭景諶は新法には傾倒し無かったので、王安石は彼の自身を枉げ無い行動は恩を仇で返し礼を欠くことだとし、その非礼を他の人にも知らせようと本に書いて仕舞ったので、後世に朱熹の類の輩から王安石を攻撃する一つの材料とされて仕舞ったのだ。朱熹が、王安石が「やって良いことと悪いこと」や「道徳性命」を分から無かったからなどとは勿論考えもしなかったのは、二者が互いに紙一重のことだからであった。 朱熹の挙げた論評は、「道について述べたこととして『やって良いことと悪いこと』を目盛りで計ることが出来る」とするなら、それは銭景諶が身を以って体験したこととして、「如何して僧が横になった儘、顧客に衣服を肌蹴るように」ということに如何応えるのか? 朱熹からすると、王安石は誠実でも率直でも無く、逆に「仏陀の古い言葉の妙道には、『礼儀作法の事績を太い跡にする』と言うものがあるが」と言うことが出来、これらの安石の行いは朱熹の目線で言うところの大逆無道と言うことであったのだ。
他人が如何観ようが、王安石は動くところが無く、彼の誠実で率直な個性は一生改め無いで、晩年には尚一層堅いものとなった。言い伝えに拠ると彼が江寧府知事の職を辞去した後に、私邸に夫人の呉氏が借りて未だ返していなかった役所の一張の藤床があったのだが、府中の群官が引き取りに来た時、其の日も王安石が裸足で藤床に上がっていて、暫く仰向けに寝ていたので、左右の侍従は言葉を掛けることすら出来無かったが、夫人の顔を見ると、急いで人に藤床を返すように命じたのだ。
王安石は裸足で籐床に横になったことは、全く大宰相であった者としての態度に似つかわしく無い行為であって、生まれもって清廉な夫人に対しても申し訳なく、きっぱりと籐床を返還したので、漸く面目を立てることが出来たのだ。こうしたのは王安石の故意に拠るものだったのかも知れず、彼は業と夫人に嫌悪させ、そのくせ直に籐床を返還することで、人が公の者が美味い汁を吸うと断罪することから免れようとしたのかも知れない。呉夫人も間違っても利得に預かろうなどと微塵も考える人では無く、お上の藤床を貪り捕ろうなどとは夢にも思わず、彼女は返そうにも返す術が分から無かったので、若しかしたら矢張り業とこのようにしたのかも知れない。 王安石が政治から身を引いた後に、地位や財産を持たない弱い小役人達が彼の庇護を失ったと思って、何か口実を探して嫌がらせに来たとも考えられる。若しも誰かの指図が無ければ、小役人達が如何して一張りの何の値打ちも無い藤床を取り戻しに来るだろうかと考え、呉夫人は業と返さ無いで、この人(其の誰か)が大胆に強取に来るかどうかを観て、結局どれだけ大きい器量かを測ったとも考えられる。王安石はこのような考え方にも理解を示し、問題を穏便に解決するため、夫人に口実を作る機会を与えた上で、些細なことで人と衝突することをも免れるようにしたのかも知れない。王安石は人と接するときには確かに威張ることが無かったばかりか、小人が少しぐらい彼を欺いても許していたのだった。彼が解任された後に、呉夫人を弟の弟が訪ねて来て見回すと、家が手狭だったので寺に間借りしたのだが、このことを聞いた太守の葉が弟に出て行くよう画策したにも拘らず皆口実を探して退却して来るので、彼は怒り心頭に達し罵ったのだが、それでも使いの者は少しも抗せずに帰って来て仕舞うので、補佐官の李琮が大いに怒り、牒州の如何にも役人然とした公差を送って逮捕しに来たので、弟は王安石の家の中まで(へ)逃げるほかなくて、結果、公差は大胆にも王安石の家人に食って掛った。外のがやがやとした騒ぎを耳にして、王安石は何の事かと出て来たのにも拘らず、公差が依然として騒動を止めなかったので、王安石は彼らを一喝するしか無かった。葉等の者達は自分らの非を認め、慇懃にも罪を詫びに来たのだが、呉夫人が彼ら小人の行為を激しく非難したが、王安石は何と彼らを咎めることは無かった。其の時丁度神宗派の一行が王安石を見舞いに来ていたので、この件を知ることになり、この情況を皇帝に報告したので、神宗は物凄く怒って、王安石に礼を失した葉ら三人を免職し、呂嘉を召して江寧の府知事になるように任命して、更に王安を心配し、彼を長江下流地域の刑獄に任命したのだが王安石には江寧に居住して、自分の最寄りの所で暮らすように配慮したのだ。
王安石が友達に対して誠実で率直であるのは当然で、何と彼は政敵に対しても同様に振舞ったのだ。彼と蘇軾の兄弟との相互の誤解は大きいものであったが、併し彼の晩年の時に、江寧で蘇軾と遭遇したとき何事も無く互いに平然としていた。朱弁《曲洧旧聞》の記録によると: 蘇東坡は金陵を通り黄河を渡り切ったのだが、荊公は野良着で驢馬に跨って舟に出会ったのだが、蘇東坡は拱手もせず礼を摂らずに言った:「軾は野良着を纏う大丞相に今日会って恐れ多い!」 荊公か笑って言う: 「我等にどのように礼を摂ると言うのか!」
礼儀作法の面では王安石と蘇軾とは煩く無く自由で良いと言う同じ考えをしており、王安石は蘇軾が何度も新法と彼本人を皮肉ったことに意に介さず、蘇東坡に対して誠を以って遇したので、蘇東坡は暫し感動を受けた様子で、詩と禅についての議論のみならず談義は弾み、終には、最寄りの土地に田を買って、近くで学びたいと思った程だったのだ。
王安石は真面目一本槍では無く、更に洒脱な面も持ち合わせていた。彼はいつも他の人と冗談を言って、他の人が彼に冗談を言っても気にかけなかった。彼の親しい友人の劉が天性を公言するのが滑稽で、いつも彼と冗談を言っており、他の人が彼らのやり取りを我慢して聞いているなぞと言うことを理解出来ず、少しも気に掛け無かった。
王安石の性格は確かに平凡で役に立たない学者と違い、彼の率直さ.彼の洒脱なところは、総てが真面目くさった顔つきをしている役に立たない学者連には今まで見られなかった人格で、朱熹はこのことで彼を目障りであるとしたのか。併し、朱熹はとても見る眼を持っていたので、王安石のこの性格と仏教.道家への彼の影響とは関係があったことを見抜いていた。彼は礼儀作法の事績を確りと遺した儘、見事に道を仏教が取り入れることを成功させ、もちろん出来無いことは改め無いで通したのだが、敢えて中途半端に電池を取り替えるような愚は避けたのだ。 仏教は元々俗世間の儀礼を余り重視し無かったが、禅宗がこれを始めた。後世に於いて、禅宗は更に仏陀を愛し祖を罵ることを強調して、徹底的に偶像崇拝を打ち破って、ただ自分が自分の主人公であり得るとし、外在する神としての仏陀を相手にしないことを核心として、更に皇帝すら優位に置くことも無かった。この種類の自由な精神には伝統をも破壊する大きな力があって、仏教界の内部で教えることとしていた戒律を、人を通じて(通って)得させることを重視することさえにも不満の意を表していたのだが、況してや俗世間の学者であれば尚更のことだったろうか? 王安石への称賛は更に増えたが、彼は丞相という高い地位にあったので、明確に賛成する意思を表せるべくも無かったが、心中極めて賞賛し、彼は晩年にことあるごとに納得いくまでこのことを著書に著したのだ。
【魂魄の宰相 第七巻】に続く










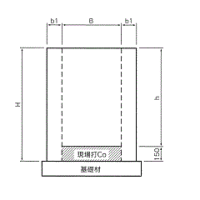









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます