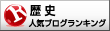陸尺というのは駕篭舁き(かごかき)のことである。
ただし、この名称は通常の駕籠舁きには使用されず、将軍や大名の駕籠を担ぐ者のみを指し示す。
通常の駕籠舁きは、舁夫だとか、俗称の雲助などと呼ばれていた。
身分の違いには厳格だった江戸時代だから、こういった名称にも敏感だったのだろう。
なぜ陸尺(六尺)と言うかについては、定説はないのだが、主に四説ある。
①力者からの転化。
②乗り物の棒は一丈二尺、これを二人で担ぐから六尺。
③乗り物の寸法が六尺。
④六尺以上の身長の者をよしとするため。
幕府の職名によると、六尺は若年寄→同朋頭→同朋の配下に風呂六尺と表六尺、裏六尺があるが、これは雑役夫のことであり、ここで取り上げている六尺とは異なる。
将軍や世子等の駕籠舁きは、若年寄→目付→駕籠頭の配下の駕篭之者という名称で表されている。三田村鳶魚によると、一般にはおかご衆と呼ばれていた。
駕籠者の員数は、家康の頃には駕籠頭一名、輿夫三十一名であったが、その後は人数を増やし、頭三名、輿夫百五十名となった。報酬は、頭が年六十俵、駕籠者が二十俵二人扶持とされた。他の六尺が十五俵一人扶持であるから、それよりは高給取りであり、台所番などと同じ禄である。
組屋敷ははじめ、本郷湯島にあったが、その後、追加や移転を繰り返した。
本所四ツ目前、谷中七面前、四谷鮫ケ橋などがその例であるが、現在も地名に残る巣鴨近くの駕籠町は、その名残である。
陸尺は、今で言うハイヤーのドライバーのようなものだから、さぞマナーもよかったのだろうと思うとそうでもなかったようだ。
本来、将軍を乗せた駕籠はゆっくり進むものだが、御目付けがゆっくり行け、と命じても陸尺はすぐに走り始める。
例外としては曇天の日だった。
雨が降ると、濡れ手当てが出るため、雨が降るのを待って、わざとゆっくり進むのだった。
大名の陸尺は、江戸抱えの一季契約の者、日雇いの者が多かったから、なおさらがさつである。
他の陸尺と争うように走り、混雑の中でも飛ばして危険だったため、何度も注意が出ている。
陸尺の服装は、通常は法被で、布地は将軍、御三家、喜連川は特に黒絹を着て脇差を差した。そのほかは木綿の法被であった。大礼服も紅のさめた退色と取り決めがある。
立派な乗り物を担ぐ陸尺らしい、それなりの格好であったが、腰から下は甚だ見苦しい。
法被をまくり、尻丸出しであったからだ。
現代の感覚からしても、おかしいが、当時も問題視していた人もいる。
荻生徂徠の流れを引く江戸中期の儒学者・太宰春台は、
陸尺は輿の前後にありながら、人体の中でも最も不浄な尻を顕にして貴人に示す。特に輿の者は、尻を輿中の面前にさらす。輿中の人が汚らわしいと思わないのは、まことに奇妙だ。嘔吐すべき習慣だ。
と嘆いている。
考えるまでもなく、指摘通りであり、非常に奇妙である。
名称までいちいち神経質に一般の駕篭舁きとは変え、ドレスコードまで規定しているのに、下半身に関しては、取り決めがない。
立派な輿であっても、前後を担ぐのが褌姿では無礼なのではないだろうか。
しかし、太宰のような指摘はむしろ例外的であって、あまり問題視されていた気配はない。
これはひとつには、駕篭舁きの一般的な服装に対する共通の認識が、褌姿であったという点があり、他方には、駕篭之者の身分が微妙なものであったいう点があると思う。
現に輿前の陸尺が放屁したとしても、お咎めなかったというから、駕籠之者の扱われ方としては馬のように単なる労働力としてしか見られていなかったのかもしれない。
参考資料:江戸のうつりかわり3(芳賀昇編)柏書房
歴史読本スペシャル28 新人物往来社
江戸武家事典(稲垣史生編)青蛙房
↓ よろしかったら、クリックお願いします!!

人気ブログランキングへ

にほんブログ村
ただし、この名称は通常の駕籠舁きには使用されず、将軍や大名の駕籠を担ぐ者のみを指し示す。
通常の駕籠舁きは、舁夫だとか、俗称の雲助などと呼ばれていた。
身分の違いには厳格だった江戸時代だから、こういった名称にも敏感だったのだろう。
なぜ陸尺(六尺)と言うかについては、定説はないのだが、主に四説ある。
①力者からの転化。
②乗り物の棒は一丈二尺、これを二人で担ぐから六尺。
③乗り物の寸法が六尺。
④六尺以上の身長の者をよしとするため。
幕府の職名によると、六尺は若年寄→同朋頭→同朋の配下に風呂六尺と表六尺、裏六尺があるが、これは雑役夫のことであり、ここで取り上げている六尺とは異なる。
将軍や世子等の駕籠舁きは、若年寄→目付→駕籠頭の配下の駕篭之者という名称で表されている。三田村鳶魚によると、一般にはおかご衆と呼ばれていた。
駕籠者の員数は、家康の頃には駕籠頭一名、輿夫三十一名であったが、その後は人数を増やし、頭三名、輿夫百五十名となった。報酬は、頭が年六十俵、駕籠者が二十俵二人扶持とされた。他の六尺が十五俵一人扶持であるから、それよりは高給取りであり、台所番などと同じ禄である。
組屋敷ははじめ、本郷湯島にあったが、その後、追加や移転を繰り返した。
本所四ツ目前、谷中七面前、四谷鮫ケ橋などがその例であるが、現在も地名に残る巣鴨近くの駕籠町は、その名残である。
陸尺は、今で言うハイヤーのドライバーのようなものだから、さぞマナーもよかったのだろうと思うとそうでもなかったようだ。
本来、将軍を乗せた駕籠はゆっくり進むものだが、御目付けがゆっくり行け、と命じても陸尺はすぐに走り始める。
例外としては曇天の日だった。
雨が降ると、濡れ手当てが出るため、雨が降るのを待って、わざとゆっくり進むのだった。
大名の陸尺は、江戸抱えの一季契約の者、日雇いの者が多かったから、なおさらがさつである。
他の陸尺と争うように走り、混雑の中でも飛ばして危険だったため、何度も注意が出ている。
陸尺の服装は、通常は法被で、布地は将軍、御三家、喜連川は特に黒絹を着て脇差を差した。そのほかは木綿の法被であった。大礼服も紅のさめた退色と取り決めがある。
立派な乗り物を担ぐ陸尺らしい、それなりの格好であったが、腰から下は甚だ見苦しい。
法被をまくり、尻丸出しであったからだ。
現代の感覚からしても、おかしいが、当時も問題視していた人もいる。
荻生徂徠の流れを引く江戸中期の儒学者・太宰春台は、
陸尺は輿の前後にありながら、人体の中でも最も不浄な尻を顕にして貴人に示す。特に輿の者は、尻を輿中の面前にさらす。輿中の人が汚らわしいと思わないのは、まことに奇妙だ。嘔吐すべき習慣だ。
と嘆いている。
考えるまでもなく、指摘通りであり、非常に奇妙である。
名称までいちいち神経質に一般の駕篭舁きとは変え、ドレスコードまで規定しているのに、下半身に関しては、取り決めがない。
立派な輿であっても、前後を担ぐのが褌姿では無礼なのではないだろうか。
しかし、太宰のような指摘はむしろ例外的であって、あまり問題視されていた気配はない。
これはひとつには、駕篭舁きの一般的な服装に対する共通の認識が、褌姿であったという点があり、他方には、駕篭之者の身分が微妙なものであったいう点があると思う。
現に輿前の陸尺が放屁したとしても、お咎めなかったというから、駕籠之者の扱われ方としては馬のように単なる労働力としてしか見られていなかったのかもしれない。
参考資料:江戸のうつりかわり3(芳賀昇編)柏書房
歴史読本スペシャル28 新人物往来社
江戸武家事典(稲垣史生編)青蛙房
↓ よろしかったら、クリックお願いします!!

人気ブログランキングへ
にほんブログ村