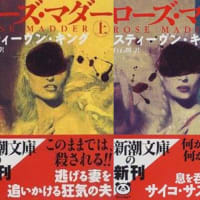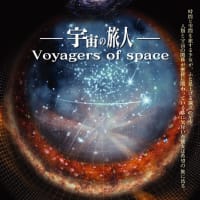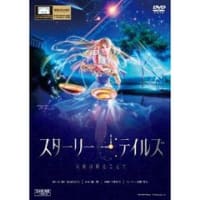著者:石持浅海(いしもちあさみ) 光文社文庫刊 定価:495円(税別)
初版刊行 :2008年 5月20日(入手版)
文庫裏の紹介文:
大時化の海の遭難事故によって、信頼の強い絆で結ばれた六人の仲間。
そのなかの一人、米村美月が、青酸カリを呷って自殺した。
遺された五人は、彼女の自殺に不自然な点を見つけ、美月の死に
隠された謎について、推理を始める。
お互いを信じること、信じぬくことを、たった一つのルールとして…。
メロスの友の懊悩を描く、美しき「本格」の論理。
読み終わった時に。
少なからず、僕は戸惑いを覚えていた。
それは。
この作品で取り上げられた事件に関する”動機”について。
最後のページを読み終えて尚、すとんと胸の中に落ちるものが
得られなかった故である。
標題のセリヌンティウスとは、太宰治の「走れメロス」にて
メロスの身代わりとなって牢獄に囚われた友人の名である。
本書では、登場人物がメロス、セリヌンティウス、そして
ディオニス(メロスに死刑を命じた王)に仮託されて、
物語が紐解かれていく。
死刑は受け入れるものの、妹の結婚式に出席はしたい。
そのために、友人に一時の身代わりを委託するメロス。
突然もたらされたその運命を従容と受け入れ、メロスを信じ
待ち続けるセリヌンティウス。
両者の友情を審判するものとして君臨するディオニス王。
誰がどの役目を担うことになるのかは、推理小説の書評の
モラルとしてここでは明かすまい。
ただ。
これだけは言っておきたい。
本書の解説で、杉江松恋は
「本書は、人間を信じるということを書いた作品である」
と、総括する。
なるほど、メロスはその友セリヌンティウスとの友情を信じ、
一歩間違えば死を蒙る運命をさえ仮託した。
そして。
セリヌンティウスも、又。
何年もメロスと会っていなかったにも関わらず。
メロスは帰ってくるものと信じ切り、その身を獄へと繋がれた。
人同士が、互いに深いところで絆を持ち、信じ合える奇跡。
その奇跡の種が大地に落ち、やがて芽吹き、根を張っていく。
その様をこそ、作者は描きたかったのだろうか。
とはいえ。
人と人との繋がりが、どこまで深甚な領域に行き着けるものなのか。
自らの命を賭してまで、とさえ思えるほどの。
そんな繋がりを、登場人物の間に現出させるために。
作者は、スキューバ・ダイビングを用いる。
ガイドの失敗によって、荒れ狂う海に放り出された6人は。
その九死に一生を得た体験を通じて、正に命友とも言える繋がりを
お互いに持つことになる。
それは。
社会や学校という頚城(くびき)とは、一切関係の無い。
ダイビングという趣味の世界の中で生まれた繋がりだけに、
何の利害も無く、只管(ひたすら)に純粋な紐帯となっていく。
そこまでは、いい。
そもそも、浮上したら荒れ狂う海というシチュエーションで、
客を置いてボートを探しに行くというガイドの存在に疑問は
持ってしまうとはいえ、だ(笑)。
#普通のガイドなら、そんなときは絶対に離れない。
信頼できるボートの船頭なら、流れを追って来てくれる。
それを信じて、固まって救助を待つのが常道だからである。
問題は、その後。
それほどの絆で結ばれた6人。
その絆を刹那ではなく、永遠のものとしたい。
その思いから生まれた行動が、この物語の深い動機となる。
だけど。
はっきり言おう。
僕は、この犯人(あえて、そう言おう)に全く感情移入が
出来なかった。
それほどまでの深い紐帯で結ばれた仲間とはいえ。
その視線の先にあるものが異なることは、当然有りうる。
それは、いい。
だけど。
だからといって、あれがその絆を深めるために取った行動
足りえるとは、とても思えない。
自分の行動が仲間の絆を強固にすることを信じて、犯人は哀しい
行動に出た。
だけど、その哀しい行動を仲間が乗り越えた先には、きっと
この絆はより強く美しいものに生まれ変わることが出来る筈。
そんな、犯人の動機に全くシンクロ出来なかった僕は。
作者よりも、余程のペシミストなのだろうか。
それとも、作者が余程のオプチュミストなのか。
(そうありたい、と思って書いているということも有りだけどね)
どちらにせよ。
自分なら、そんなことは絶対にしない。
でも、そういう人もいるんだ。
そうとすら思えなかった本書は。
僕に取っては、作者の精神的な自慰行為の産物にしか思えなかったのだ。
美しい題名だけに。
残念に、思う。
(この稿、了)
初版刊行 :2008年 5月20日(入手版)
文庫裏の紹介文:
大時化の海の遭難事故によって、信頼の強い絆で結ばれた六人の仲間。
そのなかの一人、米村美月が、青酸カリを呷って自殺した。
遺された五人は、彼女の自殺に不自然な点を見つけ、美月の死に
隠された謎について、推理を始める。
お互いを信じること、信じぬくことを、たった一つのルールとして…。
メロスの友の懊悩を描く、美しき「本格」の論理。
読み終わった時に。
少なからず、僕は戸惑いを覚えていた。
それは。
この作品で取り上げられた事件に関する”動機”について。
最後のページを読み終えて尚、すとんと胸の中に落ちるものが
得られなかった故である。
標題のセリヌンティウスとは、太宰治の「走れメロス」にて
メロスの身代わりとなって牢獄に囚われた友人の名である。
本書では、登場人物がメロス、セリヌンティウス、そして
ディオニス(メロスに死刑を命じた王)に仮託されて、
物語が紐解かれていく。
死刑は受け入れるものの、妹の結婚式に出席はしたい。
そのために、友人に一時の身代わりを委託するメロス。
突然もたらされたその運命を従容と受け入れ、メロスを信じ
待ち続けるセリヌンティウス。
両者の友情を審判するものとして君臨するディオニス王。
誰がどの役目を担うことになるのかは、推理小説の書評の
モラルとしてここでは明かすまい。
ただ。
これだけは言っておきたい。
本書の解説で、杉江松恋は
「本書は、人間を信じるということを書いた作品である」
と、総括する。
なるほど、メロスはその友セリヌンティウスとの友情を信じ、
一歩間違えば死を蒙る運命をさえ仮託した。
そして。
セリヌンティウスも、又。
何年もメロスと会っていなかったにも関わらず。
メロスは帰ってくるものと信じ切り、その身を獄へと繋がれた。
人同士が、互いに深いところで絆を持ち、信じ合える奇跡。
その奇跡の種が大地に落ち、やがて芽吹き、根を張っていく。
その様をこそ、作者は描きたかったのだろうか。
とはいえ。
人と人との繋がりが、どこまで深甚な領域に行き着けるものなのか。
自らの命を賭してまで、とさえ思えるほどの。
そんな繋がりを、登場人物の間に現出させるために。
作者は、スキューバ・ダイビングを用いる。
ガイドの失敗によって、荒れ狂う海に放り出された6人は。
その九死に一生を得た体験を通じて、正に命友とも言える繋がりを
お互いに持つことになる。
それは。
社会や学校という頚城(くびき)とは、一切関係の無い。
ダイビングという趣味の世界の中で生まれた繋がりだけに、
何の利害も無く、只管(ひたすら)に純粋な紐帯となっていく。
そこまでは、いい。
そもそも、浮上したら荒れ狂う海というシチュエーションで、
客を置いてボートを探しに行くというガイドの存在に疑問は
持ってしまうとはいえ、だ(笑)。
#普通のガイドなら、そんなときは絶対に離れない。
信頼できるボートの船頭なら、流れを追って来てくれる。
それを信じて、固まって救助を待つのが常道だからである。
問題は、その後。
それほどの絆で結ばれた6人。
その絆を刹那ではなく、永遠のものとしたい。
その思いから生まれた行動が、この物語の深い動機となる。
だけど。
はっきり言おう。
僕は、この犯人(あえて、そう言おう)に全く感情移入が
出来なかった。
それほどまでの深い紐帯で結ばれた仲間とはいえ。
その視線の先にあるものが異なることは、当然有りうる。
それは、いい。
だけど。
だからといって、あれがその絆を深めるために取った行動
足りえるとは、とても思えない。
自分の行動が仲間の絆を強固にすることを信じて、犯人は哀しい
行動に出た。
だけど、その哀しい行動を仲間が乗り越えた先には、きっと
この絆はより強く美しいものに生まれ変わることが出来る筈。
そんな、犯人の動機に全くシンクロ出来なかった僕は。
作者よりも、余程のペシミストなのだろうか。
それとも、作者が余程のオプチュミストなのか。
(そうありたい、と思って書いているということも有りだけどね)
どちらにせよ。
自分なら、そんなことは絶対にしない。
でも、そういう人もいるんだ。
そうとすら思えなかった本書は。
僕に取っては、作者の精神的な自慰行為の産物にしか思えなかったのだ。
美しい題名だけに。
残念に、思う。
(この稿、了)
 | セリヌンティウスの舟 (光文社文庫)石持浅海光文社このアイテムの詳細を見る |