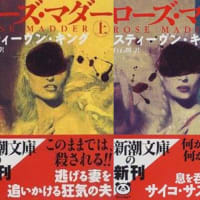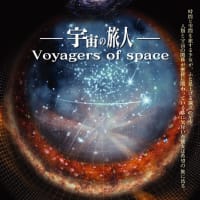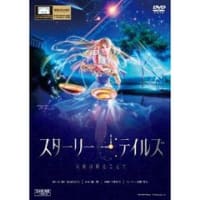記:津村記久子(作家)
2009年12月15日(火)日本経済新聞 夕刊 7面らいふより
コラムタイトル:プロムナード
サブタイトル:「働く私はみにくい」
とかく。
この世は、先入観で満ち満ちていることを。
折に触れて示唆され、愕然とすることがある。
今回のコラムを読んだときも又、そうだった。
冒頭で、作家である作者は。
何が苦手と言って、小説のタイトルを考えるのが苦手だ。
と、そう語る。
それは、分かる。
タイトルは、謂わば小説の顔である。
インパクトを重視した、直接的なものがよいのか。
それとも。
一見何のことか分からないけれど、魅力的な言葉を打ち出して。
読後に、おお。このタイトルは、この寓意だったのか!と読者に
思わせることを狙うのか。
また、サブタイトルはつけるのか? 等など。
作品は謂わば、作者の子どもともよく言われることでもあり。
その子どもに、どのような名前=タイトルを授けるのか?という
ことは。
親としての大いなる歓びでもあり、また大いなるプレッシャーでも
あるのだから。
問題は、その後だった。
作者は、そのタイトル決めについて。
作品を生み出した後に、あれこれと思い悩む、と語る。
ここに、僕は吃驚してしまった。
物語を創造する、ということは。
そこに盛り込まれた主題をとことんまで煮詰め、昇華し、分解して
いくことだ、と僕は思っている。
ふと思いついた情景や台詞をコアとして生み出される可能性もある
ショートショート等であれば、まだしも。
ある程度の長さの小説を、破綻するなく起承転結を纏め上げていく
そのためには。
作者の中では、意識的、無意識的かは兎も角。
これを自分はもっとも語りたいんだ!
そういった主題についての思いが凝縮されていく過程の中で。
その作品のタイトルについては、自ずから決まっていくものなの
だろう。
そう。
僕は、思い込んでいたのだ。
そりゃあ。
最終的な推敲の中で、タイトルもまた変化することは有るとしても。
最後まで、タイトルを決めずに作品を仕上げてしまう。
そうしたことは、僕の想像の埒外だったのである。
そうした作者が、珍しく先行して思いついたタイトル。
それが、このコラムのサブタイトルである。
すなわち、「働く私はみにくい」。
だが。
このタイトルに見合う物語を、まだ生み出せていない。
作者は、そうも語る。
この「ネガティブなインパクト」だけを狙い、「露悪的」で
すらあるタイトル。
それに相応しい物語とは、どのようなものになるのだろう?
働く私を。
自己肯定したいのか?
自嘲したいのか?
あるいは、その双方なのか?
様々な展開が考えられるが、まだそれは曖昧模糊として、
作者の中でさえ形造られてはいない。
煮詰まった作者は、このサブタイトルをもってネットで検索を
かける。
その結果から、思わぬ方向性のヒントを得ようとするかのように。
その中で。
作者は、フィリピンの「醜い少女」という神話と遭遇する。
実文もとても短いので、リンク先のpdfを読んでいただければと
思うが、以下に拙い大意を載せよう。
『ある村に、とても優しい両親の元、その愛を受けて育った一人の
少女がいた。
少女もまた、その愛を受けるに相応しい優しい心根の持ち主で
あったが、容姿に恵まれていなかった。
村の少女達は、そんな少女の容姿をいつも侮蔑し、嘲っていた。
ある日、とうとうその仕打ちに耐えられなくなった少女は、
神に泣きながら救いを求めた。
神は少女の願いを受け入れ、少女を椰子の木に変えた。
今では彼女は皆から必要とされ、その良さを認められるように
なった。
やっと少女は、幸せになれたのだ。」
この少女の物語を目にして。
ラストに同意できるだろうか。
作者は、一旦は否定的に受け止めたが、やがて肯定に転じた。
少女は、人間という枠を超えて、純粋に”働く存在”へと昇華した。
そのことを以って、是と受け止めた故である。
僕は、と言えば…。
素直に首肯できなかった。
確かに少女は、自らの存在を他者に必要と認識され、受け入れて貰える
ものへと変わることが出来た。
だけど、それは。
少女の求めていた結末だったのだろうか?
少女は、愛する両親との生活の中で、その喜びを享受したかったのでは
ないのか?
また、少女を不意に喪った両親の嘆きはどうなるのか?
そうした点を考慮して、尚。
これ以上、現世には留まれないと思うほどに、少女の心を塗りこめた
絶望の色は深かったのだろうか。
確かに、少女は椰子の木として、その幹も、その葉も。
人々の生活に役立つ存在へと生まれ変わった。
だが、それは少女が必要とされたのではない。
椰子の木だから、必要とされたのだ。
少女の絶望が深ければ深いほどに。
この現世で、少女として必要とされる存在となって、
生の歓びを噛み締めて欲しかった…。
了見の狭い僕としては、どうにもやりきれない後味を遺した物語と
なってしまったが故に。
その結末に、同意出来なかった次第である。
ともあれ。
作者が、この寓話をここで紹介した真意が何処に在るかだが。
作者の持つ闇も又。
少女と同様に深く、哀しいものであり。
現世の有り様では幸せになることは出来ないと、そう考えて
いるのだろうか。
僕もまた、我侭で強欲、かつ楽天的な一個の人間として。
幸せになりたいという欲求は、勿論持っているのだけれど。
人としての存在の在り様を捨ててまで、それらを求めたい。
そこまでのパッションは、幸か不幸か僕の中には無い。
ということは。
間違いなく。
僕は、幸せなのである。
ブラウニングの言うとおり。
”神は天にいまし、世はすべてこともなし。”である。
(この稿、了)
2009年12月15日(火)日本経済新聞 夕刊 7面らいふより
コラムタイトル:プロムナード
サブタイトル:「働く私はみにくい」
とかく。
この世は、先入観で満ち満ちていることを。
折に触れて示唆され、愕然とすることがある。
今回のコラムを読んだときも又、そうだった。
冒頭で、作家である作者は。
何が苦手と言って、小説のタイトルを考えるのが苦手だ。
と、そう語る。
それは、分かる。
タイトルは、謂わば小説の顔である。
インパクトを重視した、直接的なものがよいのか。
それとも。
一見何のことか分からないけれど、魅力的な言葉を打ち出して。
読後に、おお。このタイトルは、この寓意だったのか!と読者に
思わせることを狙うのか。
また、サブタイトルはつけるのか? 等など。
作品は謂わば、作者の子どもともよく言われることでもあり。
その子どもに、どのような名前=タイトルを授けるのか?という
ことは。
親としての大いなる歓びでもあり、また大いなるプレッシャーでも
あるのだから。
問題は、その後だった。
作者は、そのタイトル決めについて。
作品を生み出した後に、あれこれと思い悩む、と語る。
ここに、僕は吃驚してしまった。
物語を創造する、ということは。
そこに盛り込まれた主題をとことんまで煮詰め、昇華し、分解して
いくことだ、と僕は思っている。
ふと思いついた情景や台詞をコアとして生み出される可能性もある
ショートショート等であれば、まだしも。
ある程度の長さの小説を、破綻するなく起承転結を纏め上げていく
そのためには。
作者の中では、意識的、無意識的かは兎も角。
これを自分はもっとも語りたいんだ!
そういった主題についての思いが凝縮されていく過程の中で。
その作品のタイトルについては、自ずから決まっていくものなの
だろう。
そう。
僕は、思い込んでいたのだ。
そりゃあ。
最終的な推敲の中で、タイトルもまた変化することは有るとしても。
最後まで、タイトルを決めずに作品を仕上げてしまう。
そうしたことは、僕の想像の埒外だったのである。
そうした作者が、珍しく先行して思いついたタイトル。
それが、このコラムのサブタイトルである。
すなわち、「働く私はみにくい」。
だが。
このタイトルに見合う物語を、まだ生み出せていない。
作者は、そうも語る。
この「ネガティブなインパクト」だけを狙い、「露悪的」で
すらあるタイトル。
それに相応しい物語とは、どのようなものになるのだろう?
働く私を。
自己肯定したいのか?
自嘲したいのか?
あるいは、その双方なのか?
様々な展開が考えられるが、まだそれは曖昧模糊として、
作者の中でさえ形造られてはいない。
煮詰まった作者は、このサブタイトルをもってネットで検索を
かける。
その結果から、思わぬ方向性のヒントを得ようとするかのように。
その中で。
作者は、フィリピンの「醜い少女」という神話と遭遇する。
実文もとても短いので、リンク先のpdfを読んでいただければと
思うが、以下に拙い大意を載せよう。
『ある村に、とても優しい両親の元、その愛を受けて育った一人の
少女がいた。
少女もまた、その愛を受けるに相応しい優しい心根の持ち主で
あったが、容姿に恵まれていなかった。
村の少女達は、そんな少女の容姿をいつも侮蔑し、嘲っていた。
ある日、とうとうその仕打ちに耐えられなくなった少女は、
神に泣きながら救いを求めた。
神は少女の願いを受け入れ、少女を椰子の木に変えた。
今では彼女は皆から必要とされ、その良さを認められるように
なった。
やっと少女は、幸せになれたのだ。」
この少女の物語を目にして。
ラストに同意できるだろうか。
作者は、一旦は否定的に受け止めたが、やがて肯定に転じた。
少女は、人間という枠を超えて、純粋に”働く存在”へと昇華した。
そのことを以って、是と受け止めた故である。
僕は、と言えば…。
素直に首肯できなかった。
確かに少女は、自らの存在を他者に必要と認識され、受け入れて貰える
ものへと変わることが出来た。
だけど、それは。
少女の求めていた結末だったのだろうか?
少女は、愛する両親との生活の中で、その喜びを享受したかったのでは
ないのか?
また、少女を不意に喪った両親の嘆きはどうなるのか?
そうした点を考慮して、尚。
これ以上、現世には留まれないと思うほどに、少女の心を塗りこめた
絶望の色は深かったのだろうか。
確かに、少女は椰子の木として、その幹も、その葉も。
人々の生活に役立つ存在へと生まれ変わった。
だが、それは少女が必要とされたのではない。
椰子の木だから、必要とされたのだ。
少女の絶望が深ければ深いほどに。
この現世で、少女として必要とされる存在となって、
生の歓びを噛み締めて欲しかった…。
了見の狭い僕としては、どうにもやりきれない後味を遺した物語と
なってしまったが故に。
その結末に、同意出来なかった次第である。
ともあれ。
作者が、この寓話をここで紹介した真意が何処に在るかだが。
作者の持つ闇も又。
少女と同様に深く、哀しいものであり。
現世の有り様では幸せになることは出来ないと、そう考えて
いるのだろうか。
僕もまた、我侭で強欲、かつ楽天的な一個の人間として。
幸せになりたいという欲求は、勿論持っているのだけれど。
人としての存在の在り様を捨ててまで、それらを求めたい。
そこまでのパッションは、幸か不幸か僕の中には無い。
ということは。
間違いなく。
僕は、幸せなのである。
ブラウニングの言うとおり。
”神は天にいまし、世はすべてこともなし。”である。
(この稿、了)
 | ミュージック・ブレス・ユー!!津村 記久子角川グループパブリッシングこのアイテムの詳細を見る |