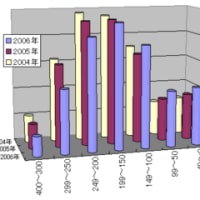夏休みに入り、家庭学習の時間が増えてくることと思います。
お通いの塾から出題される各種の宿題などをこなすのはもちろん、弱点の補強のための自主学習なども計画されているでしょう。
(そんな余裕はない!とお感じの方もあるかもしれません。そいういった場合、その大量の宿題が、お子さんにとって必要不可欠なものであるかどうかは、吟味が必要かもしれません…。)
家庭で勉強をする場合は、どうしても集中が途切れがち。
私自身のことをふりかえっても、冷蔵庫が開く音を聞いただけで、気持ちがそちらに取られたものです。
ならば、むしろ「区切り」をきちんと設定してあげることが有効です。
「○○までやる」という、見通しを立ててあげることで、「終わりの状態」「完成の状態」がわかりますので、勉強にもリズムが出てくると思います。
では、その「区切り」ですが、ここにも工夫が必要。
学習の内容によって、少々、変えたほうがいいでしょう。
-----「量」で区切る----------------------------------------
ほとんどの問題を熟知していて、「解く」ことで正確性をあげていくような勉強は、「量」で区切るといいでしょう。
例えば、計算問題であったり、一行文章題や、国語の読解の基礎問題、理科・社会の知識系一問一答など。
なお、漢字などの暗記作業を「量」でこなそうとする無駄が出る場合があります。
例えば、暗記のために「漢字を10回書く」といったような作業をする場合。
10回書けば覚えるのではありません。3回でおぼえるものもあるでしょうし、20回書いても覚えられないものは覚えられません。
-----「質」で区切る----------------------------------------
上記の漢字などの知識については、明らかに「質」で区切らないといけません。覚えたかどうかが大事なのであって、何回書いたかは問題ではない。
同じように記述式の問題なども「質」=「内容」(文の内容+表現方法の的確さ)で消化しなければなりません。
また、算数の問題や、理科の計算問題で複雑なものについては、途中の考えを図示するなど、たくさんこなさなくても、1問をきちんと解くほうが、実力の伸長に貢献する場合があります。
-----「時間」で区切る----------------------------------------
今までのふたつは、実力そのものは伸ばせますが、「テストに対応する力」(実戦力)は伸ばすのが難しい。
そこで、「時間」で区切る方法の登場です。
例えば、計算問題をするときに、10問解くというようなきめ方をせず、10分間する、つまり「決めた時間の間に、何問でもいいので、解き続ける」のです。
テストでは早さと正確さが求められますから、毎回、同程度の問題に挑戦し、何問解けたか、正答率はどれぐらいかを記録していけばいいのです。
算数の一行文章題や、理科・社会の一問一答などで効果的です。
実際に家庭で学習されるときは、上記の方法をいつ適用するか迷うときがあるかもしれませんが、そういったやり方があることを意識していただくことで、勉強のクオリティも変化するのではないでしょうか。
お通いの塾から出題される各種の宿題などをこなすのはもちろん、弱点の補強のための自主学習なども計画されているでしょう。
(そんな余裕はない!とお感じの方もあるかもしれません。そいういった場合、その大量の宿題が、お子さんにとって必要不可欠なものであるかどうかは、吟味が必要かもしれません…。)
家庭で勉強をする場合は、どうしても集中が途切れがち。
私自身のことをふりかえっても、冷蔵庫が開く音を聞いただけで、気持ちがそちらに取られたものです。
ならば、むしろ「区切り」をきちんと設定してあげることが有効です。
「○○までやる」という、見通しを立ててあげることで、「終わりの状態」「完成の状態」がわかりますので、勉強にもリズムが出てくると思います。
では、その「区切り」ですが、ここにも工夫が必要。
学習の内容によって、少々、変えたほうがいいでしょう。
-----「量」で区切る----------------------------------------
ほとんどの問題を熟知していて、「解く」ことで正確性をあげていくような勉強は、「量」で区切るといいでしょう。
例えば、計算問題であったり、一行文章題や、国語の読解の基礎問題、理科・社会の知識系一問一答など。
なお、漢字などの暗記作業を「量」でこなそうとする無駄が出る場合があります。
例えば、暗記のために「漢字を10回書く」といったような作業をする場合。
10回書けば覚えるのではありません。3回でおぼえるものもあるでしょうし、20回書いても覚えられないものは覚えられません。
-----「質」で区切る----------------------------------------
上記の漢字などの知識については、明らかに「質」で区切らないといけません。覚えたかどうかが大事なのであって、何回書いたかは問題ではない。
同じように記述式の問題なども「質」=「内容」(文の内容+表現方法の的確さ)で消化しなければなりません。
また、算数の問題や、理科の計算問題で複雑なものについては、途中の考えを図示するなど、たくさんこなさなくても、1問をきちんと解くほうが、実力の伸長に貢献する場合があります。
-----「時間」で区切る----------------------------------------
今までのふたつは、実力そのものは伸ばせますが、「テストに対応する力」(実戦力)は伸ばすのが難しい。
そこで、「時間」で区切る方法の登場です。
例えば、計算問題をするときに、10問解くというようなきめ方をせず、10分間する、つまり「決めた時間の間に、何問でもいいので、解き続ける」のです。
テストでは早さと正確さが求められますから、毎回、同程度の問題に挑戦し、何問解けたか、正答率はどれぐらいかを記録していけばいいのです。
算数の一行文章題や、理科・社会の一問一答などで効果的です。
実際に家庭で学習されるときは、上記の方法をいつ適用するか迷うときがあるかもしれませんが、そういったやり方があることを意識していただくことで、勉強のクオリティも変化するのではないでしょうか。