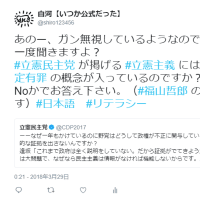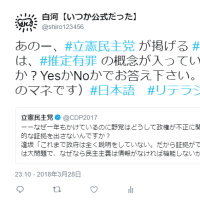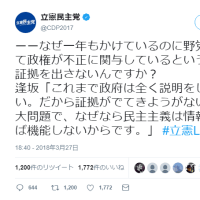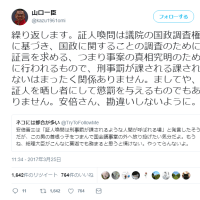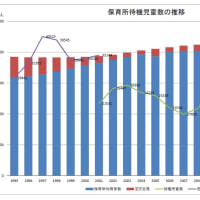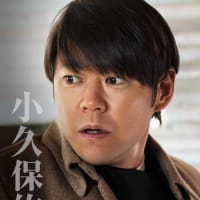国民投票法案について調べてみると、意外と憲法第九九条が重要な要素として働いていることに気づく。
日本国憲法 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、 裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
この条文は「公務員の憲法尊重擁護義務」と言われることが多い。今まで、弁護士やら「自称リベラル」の人々は、 この条文が、あたかも個人としての自由権より優先する「義務(縛り)」として働くかのように、 さまざまな場面で、自衛官などの「公務員」や、政治家などの「公務員」を叩いてきた。
立川反戦ビラ事件無罪判決と表現の自由 より 弁護士 内田雅敏氏の発言
>内田 はい。公務員の政治的行為の制限に対する国の態度は極めて恣意的です。昨年10月15日に、陸上自衛隊の幹部が、 元防衛庁長官で当時自民党憲法改正案起草委員会座長だった中谷元衆議員議員の依頼を受けて、勤務時間中に憲法改正草案を作り提出しました。草案には、自衛隊を「自衛軍」として憲法に明記すべきであり、 現行憲法上許されていない集団的自衛権の行使について憲法改正することによって、これを可能にすべきだと主張するなど, 公務員の憲法尊重擁護義務(憲法99条)に反する行為をしています。これは自民党の憲法改正草案大綱に盛り込まれました。
こう言っておきながら、
>内田 社会保険庁の職員が、日曜日に「赤旗」を配ったことが、 国家公務員法の政治的行為の制限条項違反として起訴されました。あるいは東京板橋の高校の卒業式の開始前に同校OBが「日の丸・君が代」の強制に反対である旨の発言をしたことに関して、 威力業務妨害罪で起訴されたりしています。卒業式が始まる前に 「君が代のとき皆さん方が立つと座っている先生が処分されるから、立たないで下さい」と呼びかけたのであり、 卒業式そのものには全くといっていいほど支障はありませんでした。昨年末には、東京の葛飾区で、 共産党の都議会報告書を配っていた人を住民が取り押さえ警察に突き出して、これも起訴されています。これらの動きは、 底が通じ合っています。本当に大変な社会になってしまったのだろうという気がします。
こちらでは、「公務員にも自由権がある」と声高らかに謳っているのが、理解不能である。
<追録>自民党 「憲法改正草案大綱(たたき台)」の正体と、その撤回について- 本質をどう見るか より 弁護士 坂本修氏の発言
>さらに、小泉本部長という布陣の持つ重大性を痛感します。憲法99条は、国務大臣らに憲法擁護義務を明記しています。 小泉首相は、首相として、もっとも重い憲法擁護義務を持っているのです。それなのに、 現憲法の3原則(あるいは5原則)のすべてを侵害し、憲法原理を逆立ちさせるための改憲策動組織のトップに小泉首相が座るというのは、 決定的違憲行為です。涜職という言葉がありますが、 小泉首相は戦後総理の誰一人もやらなかった明白かつ重大な涜職行為を犯しているといわなければなりません。
では、国会議員ならいいのだろうか。
で、考えてほしいのだが、国会議員も含めた「すべての公務員」が、すべからく、さまざまな自由権に優先して、この憲法九九条を守らなければならないとするのが「正しい法理」ならば、憲法九六条に規定された「憲法改正の手続き」など、実行できるのだろうか?当然、無理であろう(※)。したがって、そのような法理など、憲法九六条の行使を不可能にするという意味で、ムチャクチャな拡大解釈に過ぎないのだ。公務員であろうと政治家であろうと首相であろうと、一私人としての「自由権」の方が優先されるというのは、左側の人が泣いて喜んだ、小泉前首相の靖国参拝が傍論で違憲と判断された、 例の大阪高裁の判決でも明確に指摘されている。
日本国憲法 第96条 この憲法の改正は、 各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
>a 内閣総理大臣その他の国務大臣の地位にある者であっても, 私人として憲法上信教の自由が保障されていることは言うまでもないから,
同様に考えると、信教の自由だけでなく、「思想の自由」とか「良心の自由」と言われる、この憲法第一九条で保証されている自由権も、当然「私人」としては保障されているだろう。
日本国憲法 第19条 思想及び良心の自由は、 これを侵してはならない。
憲法九九条が、憲法一九条に定められた思想の自由を上回る「強制力」を持つとして、公務員や政治家たちの「思想・言論の自由」を叩いてきた「自称リベラル」や「自称人権派」の連中うち、自分自身も公務員である者は、今回の国民投票法案の審議において、「公務員は国民投票運動をすることができない」という縛りをかけられて、そこかしこで必死にあえいでいる。自業自得であろう。どちらも「公務員は、ある種の自由権に制限がかけられる」という点では論理的に一貫しているのだから。
(衆議院を通過した)国民投票法案(「日本国憲法の改正手続に関する法律」) 第百三条
国若しくは地方公共団体の公務員若しくは特定独立行政法人 (独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。第百十一条において同じ。) 若しくは
特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。 第百十一条において同じ。)の役員若しくは職員又は公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号に規定する公庫の役職員は、 その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、 国民投票運動をすることができない。
自分の身に火の粉がかかってきて、ようやくわかった公務員も多いのではないか。憲法九九条に規定されている「憲法尊重擁護義務」とは、あくまでも実際の行動における努力目標に過ぎないのであって、一個人としての「内心の自由、思想の自由」を縛りつける拘束力など、持ちはしないのだと。
だからと言って、私はこの条項を撤廃せよと主張するつもりもない。公務員の立場利用を禁じること自体は、私人としての内心の自由の尊重とは別次元の問題だからだ。この法案を、この角度から日々叩き続けている連中は、この二点を分けて論ずるべきであろう。わざとごちゃ混ぜにして論じても、バレバレだよ。
--------------------------
※ この不条理に対し、「国会議員だけは別」という、これまた不思議な「解釈改憲」が、アレな人の一部によって繰り広げられている。何度も言うが、「自分たちの解釈改憲だけは正しい」と思える、その傲慢さは、どこからやって来るのだろうか?? それだけ他の国民をバカにできる傲慢さは、どういう種類の精神年齢の低さからやって来るのだろうかね?
[PR] 美容整形